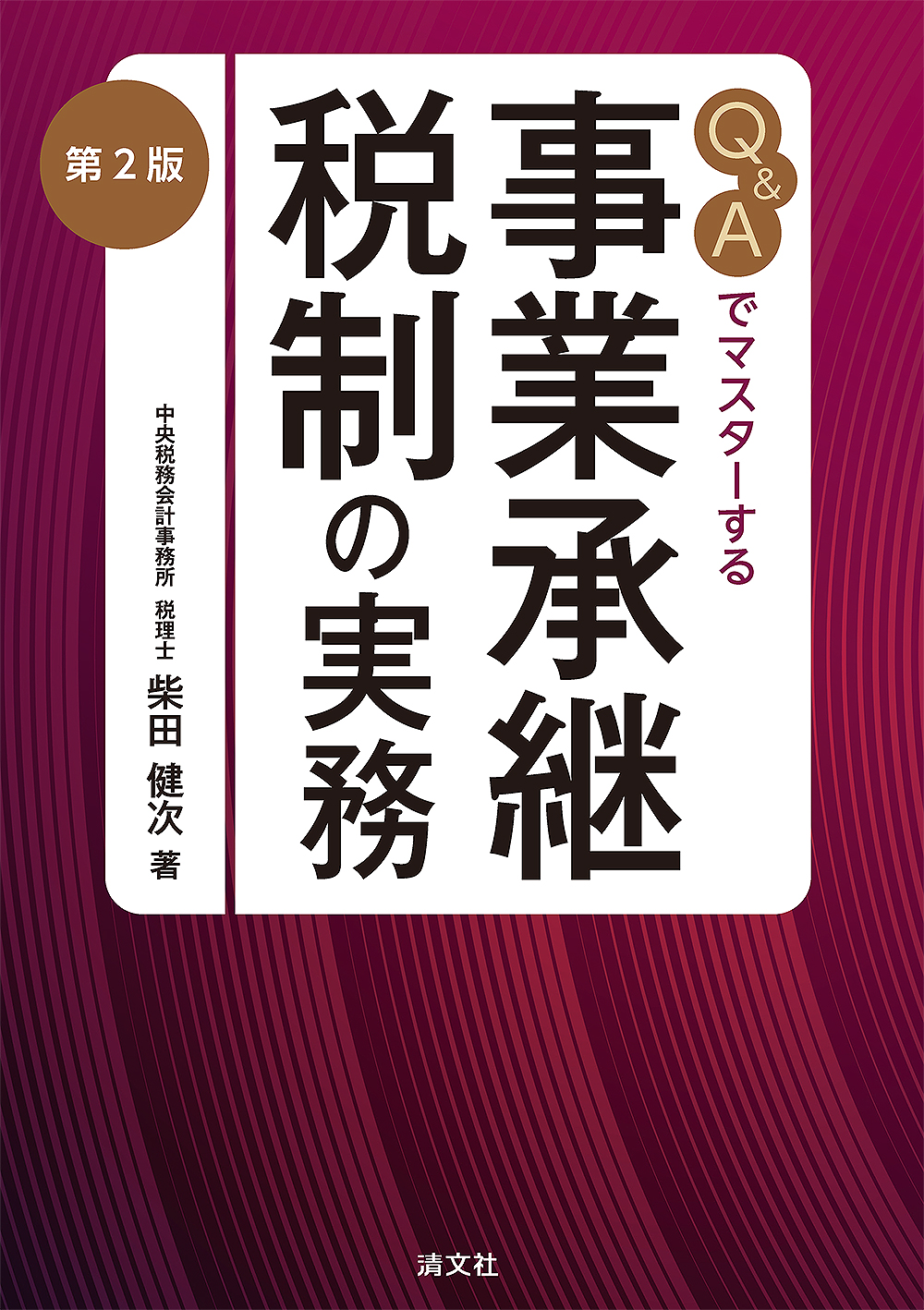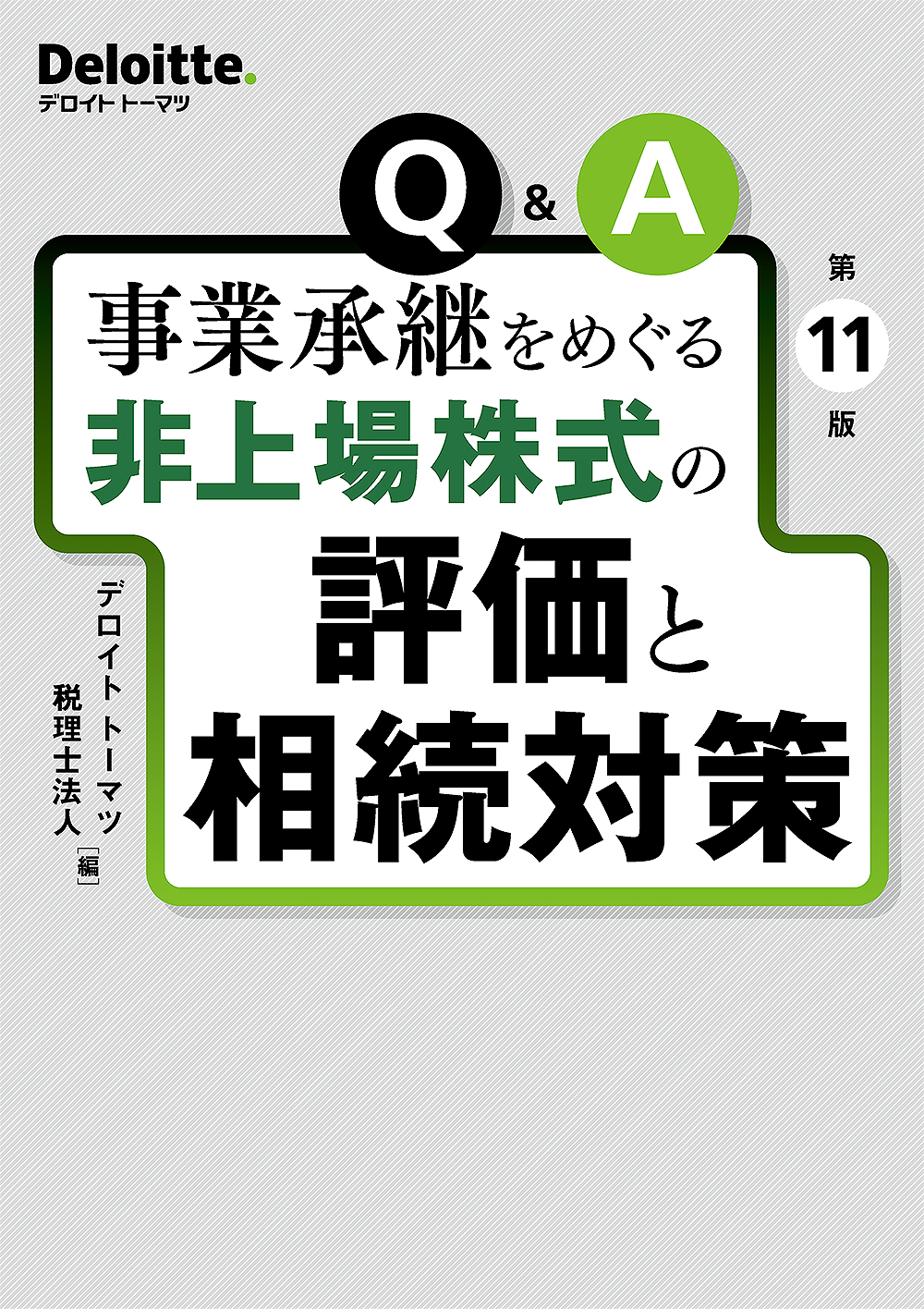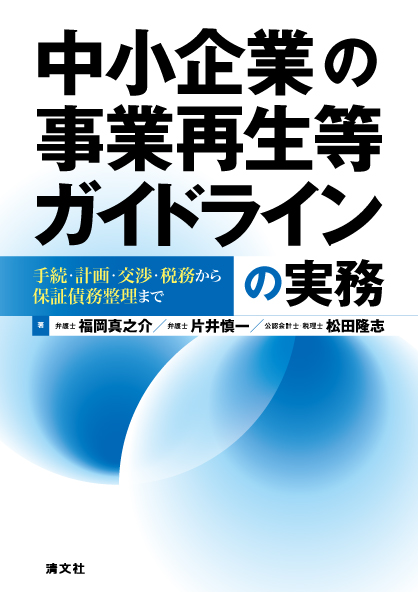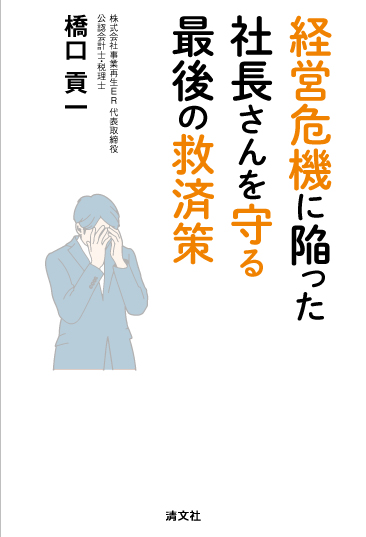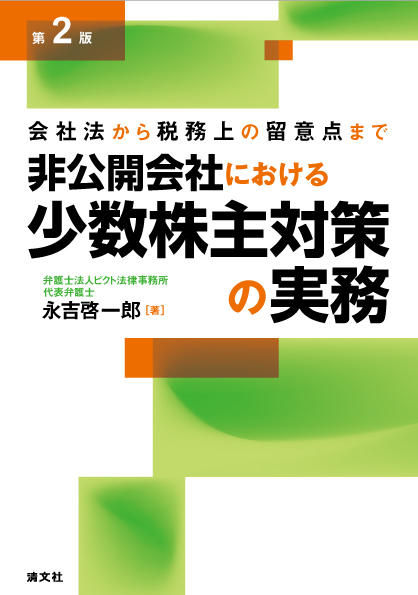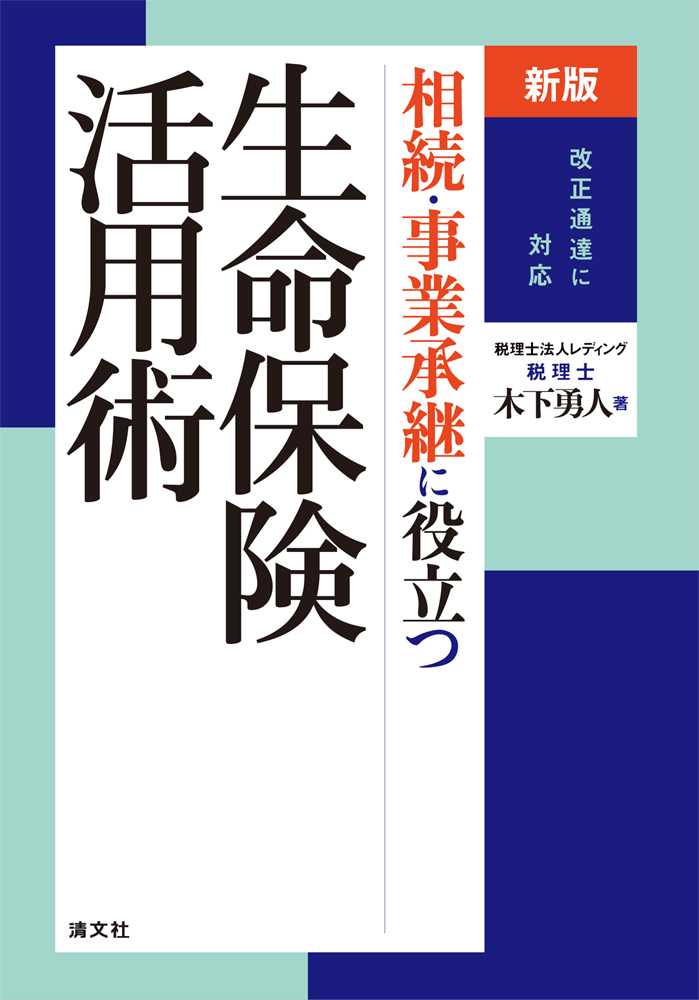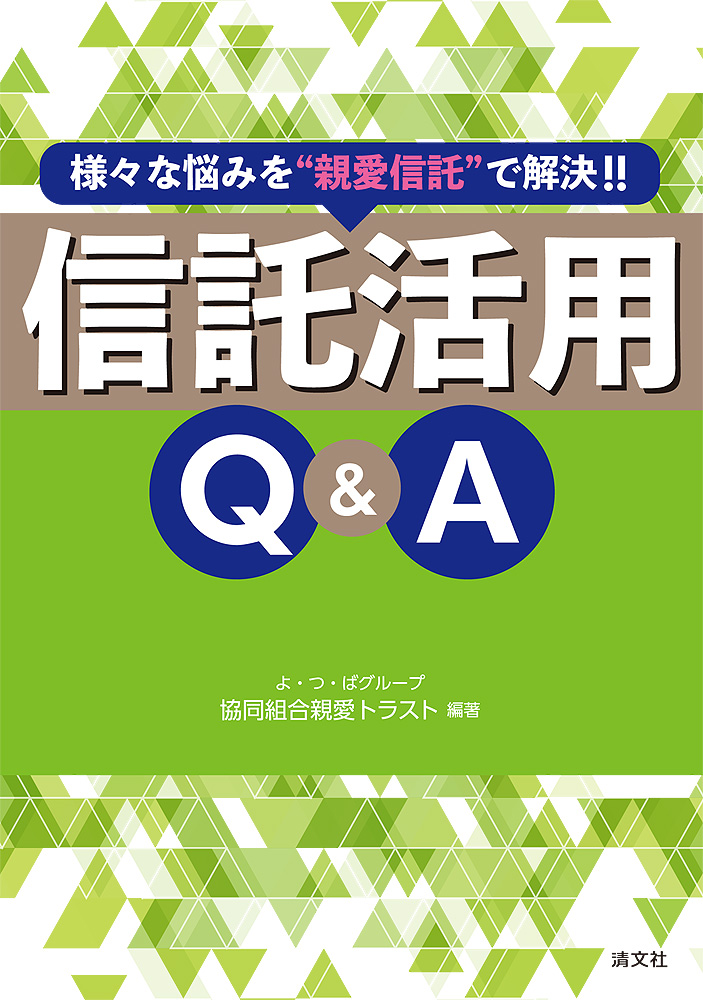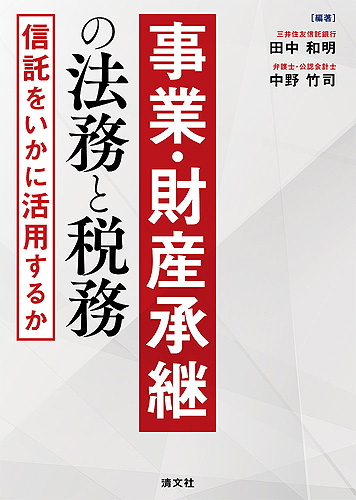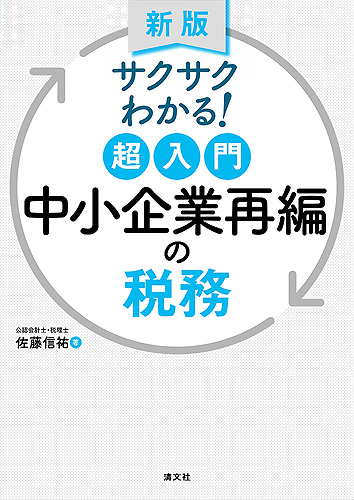人的側面から見た「事業承継」のポイント
【第1回】
「経営への“想い”を円滑に承継する」
社会保険労務士法人スマイング 代表社員
特定社会保険労務士 成澤 紀美
1 はじめに
昨年からにわかに話題となってきた「事業承継」。
単に後継者問題というものではなく「いつ」「誰に」「どのような形で」事業を承継していくべきなのかを考えなければならない。
特に中小企業で事業承継対策を考える場合、「経営そのものの承継」と、「自社株式・事業用資産の承継」の両面の配慮が必要になる。
資産の承継については他の専門家に委ねるとして、ここでは事業活動の根本である、経営そのものの承継についてお伝えしたい。
2 事業承継の方法
事業承継を行う場合、次の方法がある。
(1) 親族に承継する
経営者の子息・子女など、親族に会社を継がせるというのは、日本の中小企業において最も多い承継方法である。一方、親族への承継がうまくいかないという声が多いのも現状である。
これは右肩上がりの経済成長が見込めないこと、少子化など社会的な構造にも要因があるが、「親族が事業を継ぎたがらない」という現実も少なからず存在する。
事業承継は“継がせる側”と“継ぐ側”の意思疎通が大変重要であり、経営者(継がせる側)、後継者(継ぐ側)双方に対して施策を打ち、事業承継成功のために取り組まなければならない。
(2) 従業員に承継する
親族外への承継において代表的なものは、「従業員からの抜擢人事」と、「社外の有能な人物の招聘」の2つが挙げられる。
事業存続に有益な承継を第一に考え、数名の後継者候補を選定・教育し、最終的には他の協力と賛同を得られることが、円滑な承継を行う上で大変重要なポイントになる。
(3) M&Aを行う
M&A(エムアンドエー)は“Mergers(合併)and Acquisitions(買収)”の頭文字をとったもので、昨今、事業承継の手段としての利用が年々増加している。
その背景には、身近に承継に適正な者がいない、親族に事業承継したくても親族が嫌がるといったケースなど、 事業承継をする相手がいないといった理由がある。
3 経営ノウハウの円滑な承継を
いずれかの方法により事業承継を行うとなった場合においても、次世代の経営者となる後継者には、以下のように現経営者が有する経営ノウハウ等を円滑に承継させることが必要になる。
(1) 経営ノウハウの承継
後継者は、経営者として必要な業務知識や経験、人脈、リーダーシップなどのノウハウを習得することが求められる。具体的には後継者教育を実施し、現経営者の経営ノウハウを後継者に承継していくことが必要となる。
(2) 経営理念の承継
事業承継の本質は、経営者の経営に対する想いや価値観、態度、信条といった経営理念をきっちりと後継者に伝えていくことにある。
現経営者が自社の経営理念を明確化し、「何のために経営をするのか」を後継者にきちんと承継していかなければならない。
◆ ◆ ◆
次回は、事業承継の問題点についてお伝えしたい。
(了)