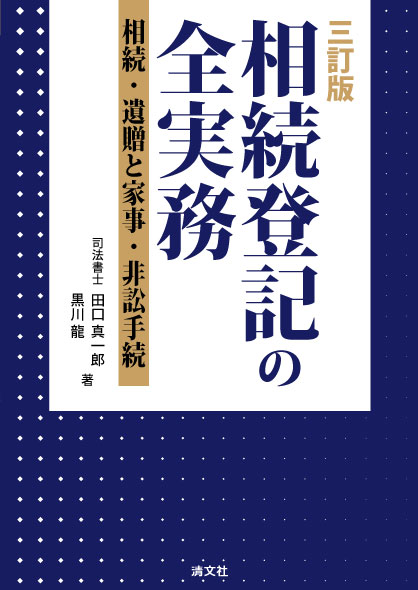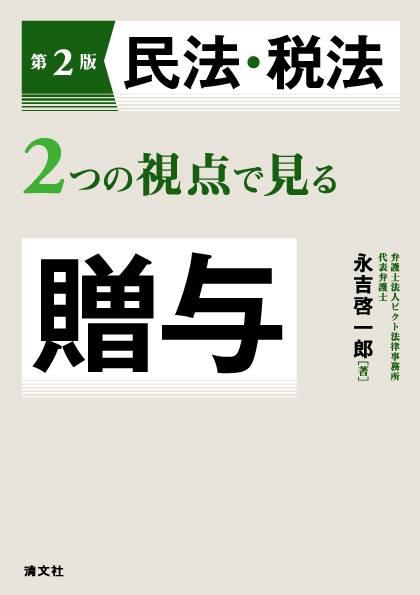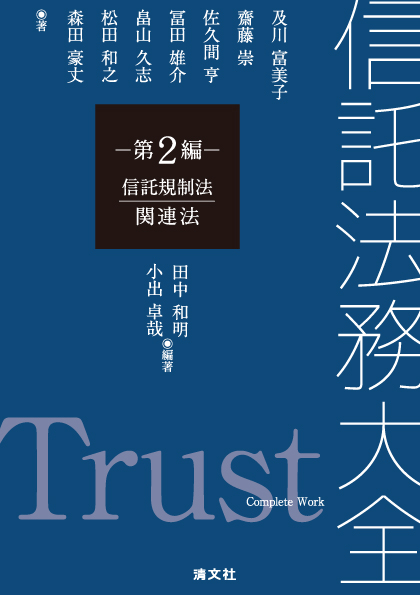相続(民法等)をめぐる注目判例紹介
【第1回】
「法定相続分の預金返還等請求事件」
-最高裁平成29年4月6日判決-
弁護士 阪本 敬幸
1 事案の概要
最高裁平成29年4月6日判決(以下、「本件判決」という)は、信用金庫に債権(普通預金債権、定期預金債権及び定期積金債権)を有していた被相続人の共同相続人の一部が、信用金庫を相手方として、法定相続分相当額の支払いを求めたという事案である。
原審(大阪高裁平成27年11月28日判決)は、従前の裁判所の判例に従い、預金債権は相続と同時に当然分割されるとして、相続人の請求を一部認容したため、信用金庫側が上告。
2 判決要旨
(1) 結論
「共同相続された定期預金債権及び定期積金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない」として、相続人(被上告人)の請求を棄却(原審破棄・自判)。
なお、普通預金債権については、既に最高裁平成28年12月19日決定(以下、「平成28年最決」という)(注)において、「相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる」旨判示されたため、平成28年最決を引用して相続人の請求を棄却。
(注) 平成28年最決については本誌掲載の下記拙稿を参照されたい。
(2) 理由
以下の通り、平成28年最決の定期貯金債権における判断と同様に、契約上、払い戻し制限がある(解約しない限り払い戻しを受けられない)ことを理由としている。
◆定期預金は、預金者が解約しない限り払い戻しができず、契約上、分割払戻が制限されている。このように、定期預金においては、一定期間内には払い戻しをしないという条件と共に普通預金よりも利率が高くなっており、払い戻しの制限は単なる特約ではなく定期預金契約の要素である。
◆定期預金債権には払い戻しの制限がある以上、共同相続人が単独で払い戻しを求める余地はない。
◆定期積金も、解約をしない限り給付金の支払いを受けられないので、定期預金と同様。
補足しておくと、相続により債権は準共有状態となり、その解約権の行使は準共有債権の処分にあたるため、共同相続人全員でなければできないということを前提とするものと思われる。
3 本件判決の意義
本件判決は、定期預金債権及び定期積金債権について、共同相続の場合に当然分割されることはないと判断された点に意義がある。
平成28年最決においては、普通預金債権並びにゆうちょ銀行の通常貯金債権及び定期貯金債権について、共同相続の場合に当然分割されることはないとの判断がなされていたが、定期預金債権及び定期積金債権についての判断はなされていなかった。
本件判決においては、定期預金債権及び定期積金債権についても共同相続の場合に当然分割されることがないと確認されたといえる。
4 本件判決の実務への影響
平成28年最決により、定期預金債権・定期積金債権についても当然分割されることはないと考えられていたものであり、実務上の影響は大きくはないと思われる。
金融機関・遺言作成者・遺言執行者等においては、預貯金債権(及びこれに類似する債権)は全て当然分割されることはないと認識して対応しなければならない。
(了)
「相続(民法等)をめぐる注目判例紹介」は、不定期の掲載となります。