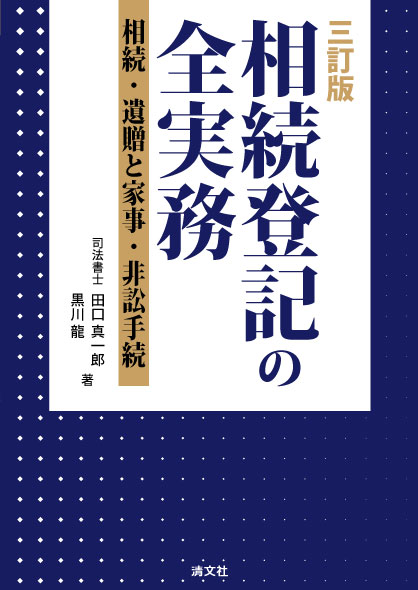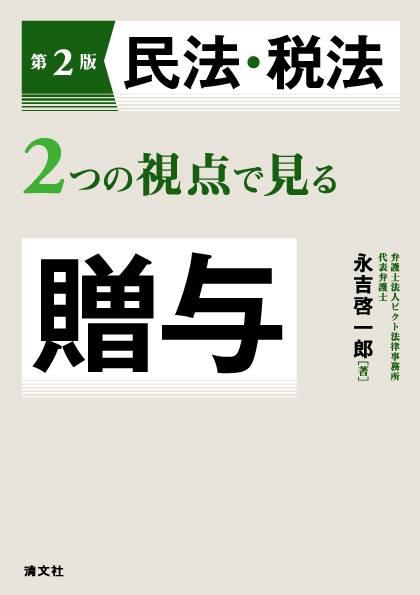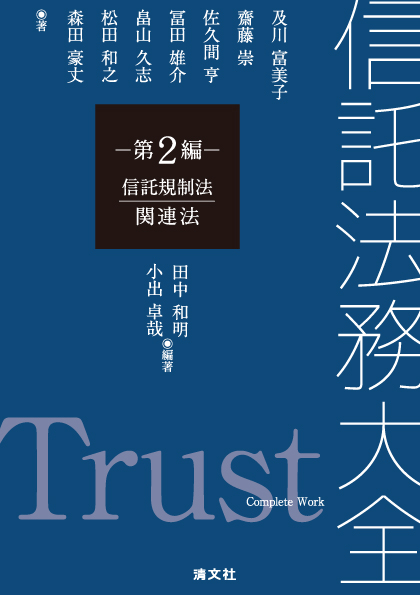民法(相続関係)等改正「追加試案」のポイント
【第1回】
「中間試案パブリックコメント後の検討概要」
弁護士 阪本 敬幸
8月1日付けで「中間試案後に追加された民法(相続関係)等の改正に関する試案(追加試案)」が、パブリックコメントに付された。
本稿では、昨年実施された中間試案に対するパブリックコメント後の法制審議会における検討状況を概説し、次回は追加試案で新たに示された改正内容について紹介したい。
パブリックコメント
「「中間試案後に追加された民法(相続関係)等の改正に関する試案(追加試案)」に関する意見募集」
法務省ホームページ
「「中間試案後に追加された民法(相続関係)等の改正に関する試案(追加試案)」(平成29年7月18日)のとりまとめ」
[1] 中間試案の決定及びパブリックコメント概要
民法(相続関係)等の改正については、高齢化社会の進展や家族の在り方に関する国民意識の変化等の社会情勢に鑑み、配偶者の死亡により残された他方配偶者の生活への配慮等の観点から見直しが必要であると考えられ、平成27年2月に法務大臣による諮問がなされた。
これを受け、法制審議会民法(相続関係)部会(以下、「部会」という)が調査審議を重ね、平成28年6月に中間試案が決定され、平成28年7月から9月まで中間試案に関するパブリックコメント手続が取られた。
中間試案及びパブリックコメントの概要は以下の通りである。
〈中間試案及びパブリックコメントの概要〉
① 被相続人の配偶者の居住権保護のための方策
(ⅰ) 短期居住権の新設
(ⅱ) 長期居住権の新設
▷パブリックコメントの結果
(ⅰ)について概ね賛成が多数
(ⅱ)について賛否拮抗
② 遺産分割に関する見直し
(ⅰ) 配偶者の相続分の見直し(配偶者の相続分引き上げ)
(ⅱ) 可分債権の遺産分割における取り扱いの変更(遺産分割対象とする)
(ⅲ) 遺産の一部分割の明確化(遺産の範囲に争いがある場合に、争いのない一部の遺産分割の審判を行う要件を明確化すること、一部分割後の残部分割に関する規律を明確化すること)
▷パブリックコメントの結果
(ⅰ)について反対意見が多数
(ⅱ)について賛成意見が多数
(ⅲ)について、一部分割の審判の要件の明確化に関しては賛成意見が多数、残部分割に関する規律に関しては反対意見が多数
③ 遺言制度の見直し
(ⅰ) 自筆証書遺言の方式緩和
(ⅱ) 自筆証書遺言の保管制度の創設(遺言保管機関を設ける)
▷パブリックコメントの結果
(ⅰ)、(ⅱ)共に賛成多数
④ 遺留分制度に関する見直し(遺留分権利者の権利行使により、目的物が共有状態となるのではなく、原則として金銭債権を発生させる)
▷パブリックコメントの結果
概ね賛成意見が多数
⑤ 相続人以外の者の被相続人への貢献を考慮するための方策
▷パブリックコメントの結果
賛否拮抗
法務省ホームページ
「「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」(平成28年6月21日)の取りまとめ」
パブリックコメント
「「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」に関する意見募集」
「「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」に関する意見募集の結果について」
[2] 中間試案決定後の状況
1 配偶者の相続分の見直しについて
上記の通り、「② 遺産分割に関する見直し」(ⅰ)配偶者の相続分の見直し(相続分引き上げ)について、パブリックコメントで反対意見が多数を占めた。これを受けた部会では、配偶者の保護の必要性は認められるとして、異なる方策での配偶者保護が検討された(詳しくは次回参照)。
2 可分債権の遺産分割における取り扱いの変更について
「② 遺産分割に関する見直し」(ⅱ)可分債権の遺産分割における取り扱いの変更(遺産分割の対象とする)について、パブリックコメント手続終了後、預貯金債権は相続により当然分割されずに遺産分割の対象に含まれるとする平成28年12月19日最高裁大法廷決定(以下、「本決定」という)が出された。
本決定により、遺産分割が終了するまでの間、預貯金債権の行使には共同相続人全員の同意が必要となったが、遺産分割前に預貯金を払い戻す必要がある場合も考えられるところである(被相続人の債務弁済や、被相続人から扶養を受けていた相続人の生活費支出など)。
このような場合に、「共同相続人全員の同意が得られないことにより預貯金の払い戻しを受けられない」という不都合が生じることを回避するため、家事事件手続法第200条2項の仮分割の仮処分を利用することが考えられるということが、本決定の補足意見において指摘された。
なお、本決定についての詳細は、本誌掲載の下記拙稿を参照されたい。
3 遺産の一部分割の明確化について
「② 遺産分割に関する見直し」(ⅲ)遺産の一部分割の明確化について、パブリックコメントでは、「一部分割の審判の要件を明確化すること」に関して賛成が多数であった。
しかしその後、部会での更なる検討の結果、中間試案における一部分割に関する提案内容について異議があり、中間試案とは異なる観点から見直すべきとの議論があった。
4 相続開始後の共同相続人による財産処分について
中間試案後に本決定が出されたことにより、部会で以下のような議論がなされた。
すなわち、本決定が出されたことにより、共同相続人の1人が、単独で、相続開始後遺産分割前に預貯金債権を処分することはできなくなった。しかし現在も往々にして見られるように、共同相続人の1人が、金融機関に被相続人死亡の事実を伝えないまま、単独で預貯金を引き出し、その結果、取得する遺産の額が増えて不公平が生じることも考えられるところである。
本決定以前は、預貯金債権は当然分割されると考えられており、当然分割により相続人が取得した範囲では、このような預貯金の引き出しも認められていたが、本決定が出された以上、共同相続人による遺産分割前の財産処分について何らかの規制が検討されるべきである。
このため、中間試案においては検討されていなかったが、相続開始後の共同相続人による財産処分についての方策が検討されることとなった。
5 遺留分制度に関する見直しについて
「④ 遺留分制度に関する見直し」について、中間試案では、遺留分権利者が権利行使した場合、原則として金銭債権が発生するとされ、パブリックコメントでもこの点については賛成が多数を占めた。
もっとも、受遺者又は受贈者による金銭交付が困難な場合も生じ得ることから、受遺者又は受贈者が、金銭交付に代わる現物給付を求めることができる制度を検討することとなった。
6 追加試案の作成について
上記のような中間試案決定後の状況を受けて、中間試案の一部(上記[2]1ないし5に記載した点。上記[1]の①③⑤については大きな変更はない)が見直されることとなり、平成29年7月18日、部会が追加試案を取りまとめ、冒頭に述べたとおり、パブリックコメントの手続が取られることとなった。
* * *
次回は追加試案で新たに示された改正内容を紹介したい。
(了)
この連載の公開日程は、下記の連載目次をご覧ください。