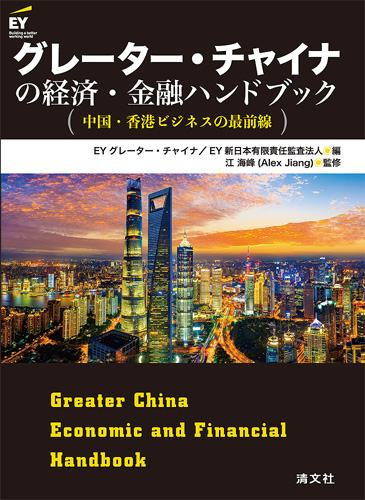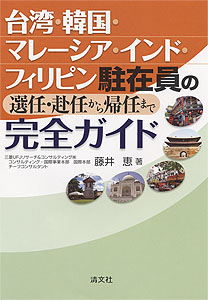香港と日系企業をめぐる最新事情①
“Exciting Hong Kong”
アースタックス税理士法人
アースタックス・ビジネスコンサルティング(香港)有限公司
税理士 白水 幹範
香港って、どんなところ?
〈はじめに〉
とある休日。朝食はいつもの納豆にお味噌汁、家族で街へ外出して、まずはユニクロでフリースを購入、お昼はみんなで回転寿司へ、午後は本屋で週刊誌を、その後ジャスコで晩酌用の焼酎いいちこを購入、夜は友達とワタミで軽く一杯、シメには一風堂のとんこつラーメン。
これ、もちろんすべて香港での話です。
香港の街中には、至るところに日本の物が溢れています。日本食材、日本の衣料品店、日本食レストラン、日本の雑誌、日本のアニメ、日本のリテールショップなど、香港において日本の文化は浸透しています。
香港といえば、観光・グルメ・ショッピングなどをすぐに連想しますが、一方で、金融・貿易・物流・サービスといった様々な産業において、世界中の企業からの資本を集める世界一の競争力をもった都市という一面を持っています。
翻って、今後は人口減少社会を迎える日本。
企業活動がますますグローバル化していくことは必然であり、海外進出は大企業だけに限った遠い話ではなく、身近な中小企業にとっても当たり前の時代がそこまで来ています。
ここでは、日系企業にとって大きな可能性を秘めている香港について、ご紹介させていただきます。
〈香港の概要〉
香港の正式名称は、中華人民共和国香港特別行政区(Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China)といい、中国の南東部、広東省に位置しています。
香港島、大嶼山、九龍半島、そして中国本土に面している新界(262余りの島々を含む)からなります。面積は1,104平方キロメートル、人口は713.63万人(2012年中期現在、香港政府統計処)で、どちらも東京都の約半分強といったところです。
世界的に見ても香港は最も人口密度が高い地域で、香港全域では1平方キロメートル当たりの人口密度は6,580人、九龍地区では44,760人にも及びます(2012年6月末現在、香港政府統計処)。
この九龍地区にある旺角(モンコック)という町は、人口密度が一番高い町というギネス世界記録まで持っているそうです。平日でもお祭りのような雰囲気で、まさに眠らない街香港を象徴するかのように、深夜12時を過ぎても賑わっています。
とはいえ、香港の造成されている土地は全面積の25%も満たないくらいで、公園や自然保護区が40%ほどあるため、意外に思われるかもしれませんが、香港には自然を感じる場所も多いのです。
〈中国返還〉
長きにわたり英国統治下にあった香港は、1984年の英中共同宣言に基づき、1997年7月1日をもって中国に返還されました。
中国返還、そして香港特別行政区設立15周年を迎えた今年2012年7月1日には、ビクトリアハーバーでの花火などをはじめとするさまざまな祝賀イベントが開催されました。
返還後は、「香港特別行政区基本法」において定められている「一国二制度」(一つの国・中国で二つの制度が併存して実施されること)の原則に基づき、外交・国防を除き、香港は高度な自治権が認められました。返還後50年間は返還前の社会・経済制度などの維持が保証される、いわゆる一国二制度が適用されるとの約束が英中間で交わされたため、この制度は今でも順調に機能しています。
すなわち、自由な経済体制が引き続き保障され、規制等による政府のマーケットへの介入を極力排除した自由放任経済により、企業にビジネスの自由を保障しているのです。
また、英国統治下において制定された法制度が適用されており、公正なルールが運用されています。
中国や一部のアジア諸国では、法制度に基づく統治(法治主義)ではなく、権力者の裁量による統治(人治主義)が未だ残っており、外国企業がビジネスを行う場合のハードルを高くしていますが、香港においては、ビジネスにおける契約が当然に守られますし、法に基づかない政府の介入などがなく、極めて透明性の高いビジネス環境が整っています。
また、記憶に新しい2012年9月の尖閣諸島問題を原因とした反日デモ。香港のお隣の深センや広州でも、残念なことにデモが一部暴徒化し領事館や日本料理店への投石行為などがあり、改めて中国ビジネスの難しさを実感させられました。
一方、香港でも反日デモは行われましたが、中国本土のように過激な行動はみられず、秩序が保たれていました。同じ中国とはいえ、中国本土と香港とでは、その安全性も全く異なると感じさせられた一幕でした。
〈公用語〉
香港の公用語は、中国語と英語です。街中で最も広く用いられている言葉は中国語の方言の一つである広東語ですが、中国返還以降も英語教育は重視されており、ビジネスは英語で行うことができることも、香港において外国企業の参入を容易にしている要因の一つです。ストリート名・駅名・建物名などにも英国植民地であったことを感じさせる英語名がついていることがほとんどです。
たとえば、香港島のセントラル地区のWellington Streetは、広東語で威靈頓街(ウァイリントンガーイと発音、ガーイはストリートという意味)といいますが、その英語の発音に近い広東語を語呂合わせでつけられたストリートも多々あります。
最近では、中国経済との緊密化に伴い、中国語の標準語である普通語も普及してきており、若い世代では、英語、広東語、普通語の3言語を自由に操る人材も多くなっています。
香港の投資環境
〈潜在競争力ランキング〉
公益社団法人日本経済研究センター(JCER)では、潜在競争力を調査し、ランキングを作成しています。これは、世界50ヶ国と地域を対象として、今後10年間にどれだけ一人当たりGDP(国内総生産)を増加させるかを要因に、「国際化」「企業」「教育」「金融」「政府」「科学」「インフラストラクチャー(=社会資本)」「IT(情報技術)」の8つの項目をそれぞれに分析し、ランキング化したものです。
そのランキングによると香港は、2006年調査以来6年、連続総合首位を取っています。
ちなみに2011年調査の上位は、1位 香港、2位 シンガポール、3位 米国、そして日本は14位でした(東日本大震災前のデータを採用)。項目別にみると、香港は同年「国際化」と「金融」で1位、「企業」と「インフラ」で2位になっています。
〈香港の競争力の源泉〉
では、香港の競争力の源泉となっているものは、一体何なのでしょうか?
① 自由主義経済
政府の民間の経済活動に対する介入はできるだけ避けて、民間の自由に任せるという基本方針が貫かれています。
② 低税率と簡素な税制
事業所得税16.5%、給与所得税は最高17%(2012/13課税年度)、配当金・キャピタルゲインは非課税、相続税・贈与税・消費税はなし、などのように低税率で、かつ、税金の種類も少なく非常にシンプルな税法体系となっています。
③ 外資企業の進出の容易性
内資・外資企業を差別・制限するような規制がほとんどなく、また、企業設立の手続は極めて簡単に短期間で行えます。
④ 貿易の自由度
関税がなく(タバコなど一部の品目には物品税あり)、通関の手続も迅速で効率的です。
また、外貨規制がなく、海外送金も自由に行うことができます。香港ドルは米ドルにペッグしており、為替相場も安定しています。
⑤ 中国のゲートウェイ
今や世界第2位のGDPを誇る中国へのゲートウェイとしての機能を有します。
中国との経済緊密化協定(CEPA)の締結により、ますます活発化する中国との経済活動において、香港は中国市場進出を見据えたショーケース・テストマーケティングとしての役割を担っています。
⑥ 地理的優位性
アジアの主要都市へ4時間以内のフライトでアクセス可能、さらに5時間のフライト圏内に世界の人口の半数が居住しています。また、日本との時差はわずか1時間です。
⑦ 国際金融センター
全世界の主要な金融機関が集積しており、多くの金融機関のアジアの地域統括本部が置かれ、世界最高水準の金融サービスを享受できます。
⑧ 人材インフラの充実
弁護士、会計士などの優秀な人材が豊富で、かつ、英語、中国語(広東語、普通語)を自由に操る人材を容易に雇用することができます。
次回は、香港へ進出を果たした日系企業の最新情報についてご紹介します。
(了)