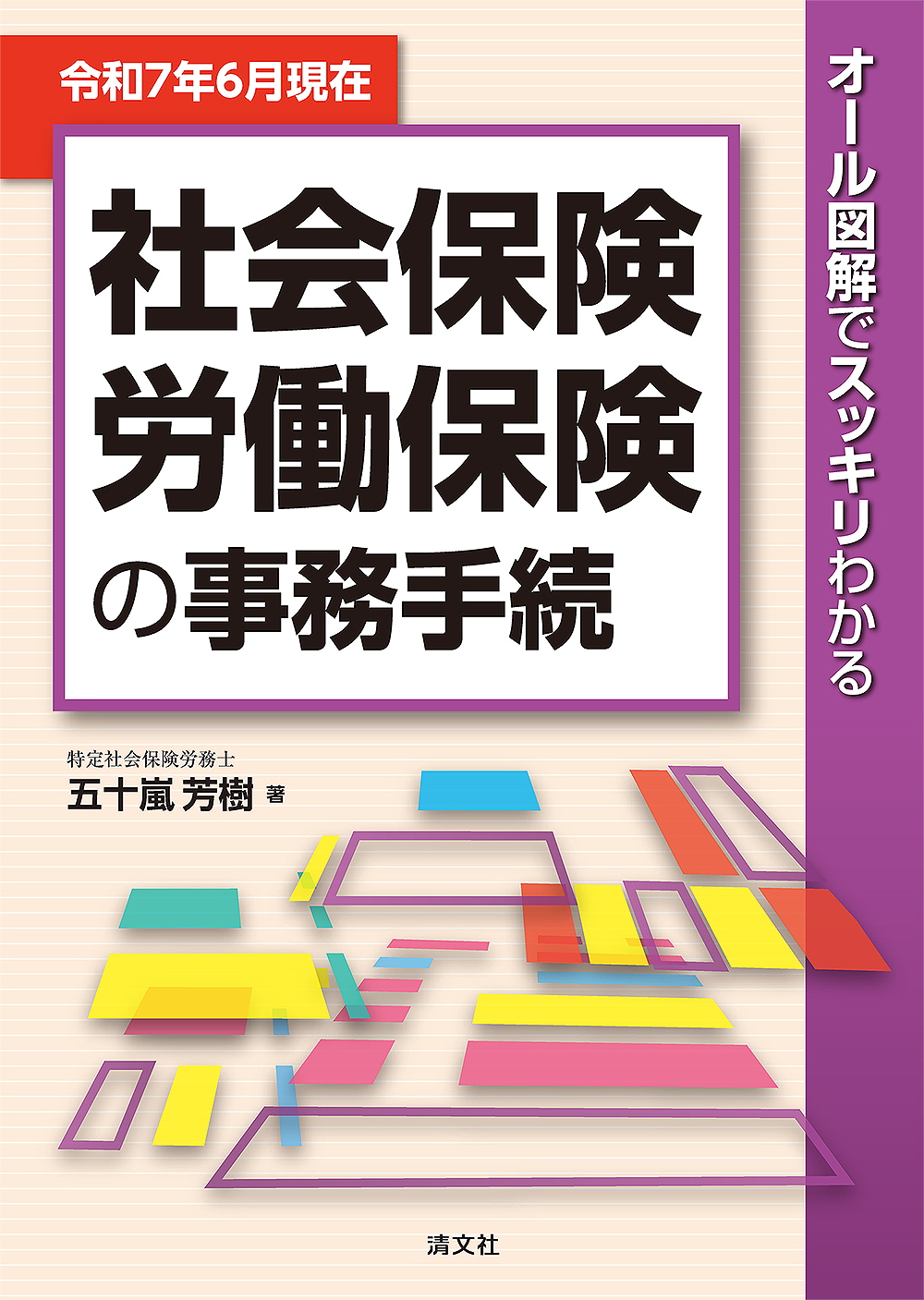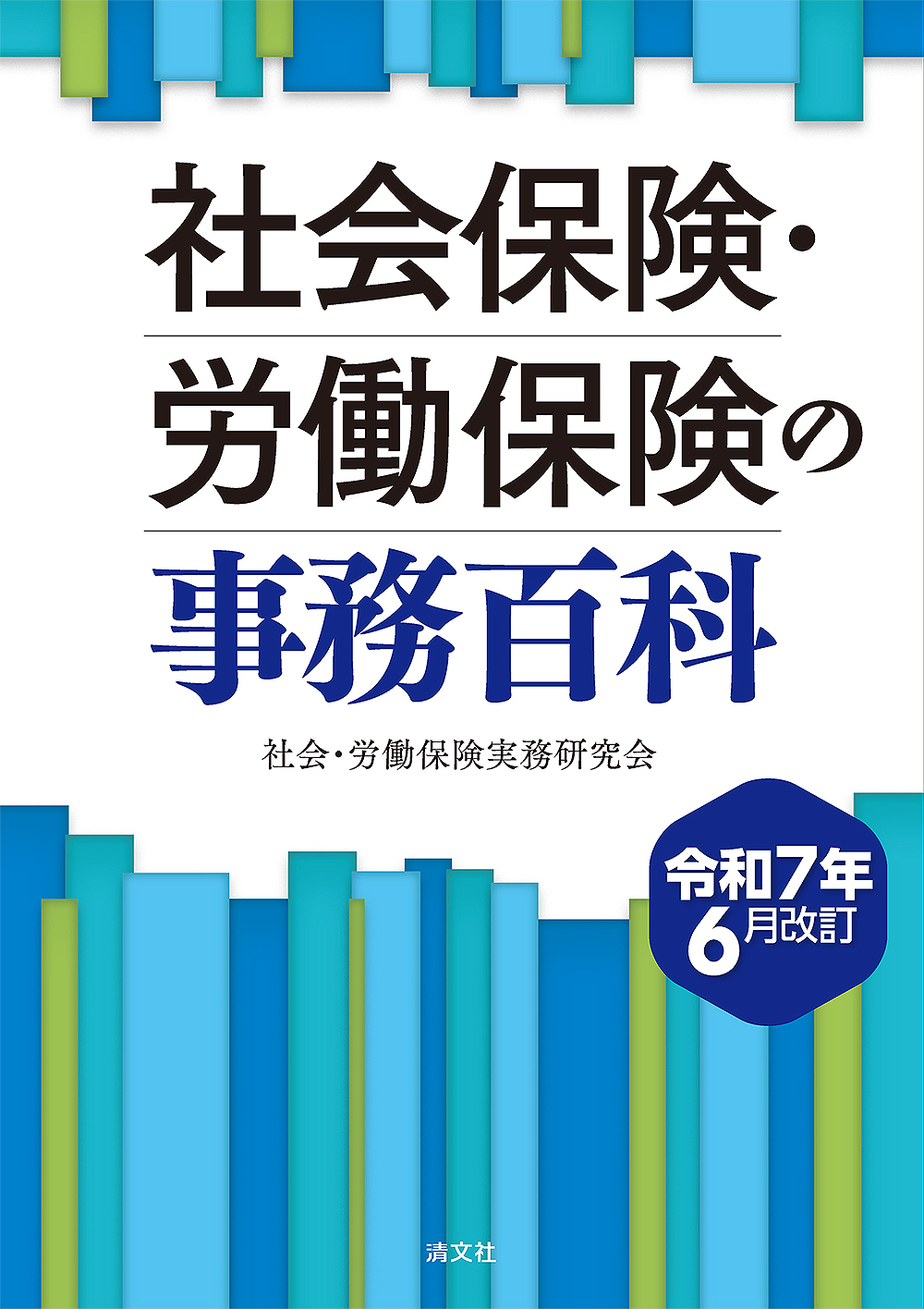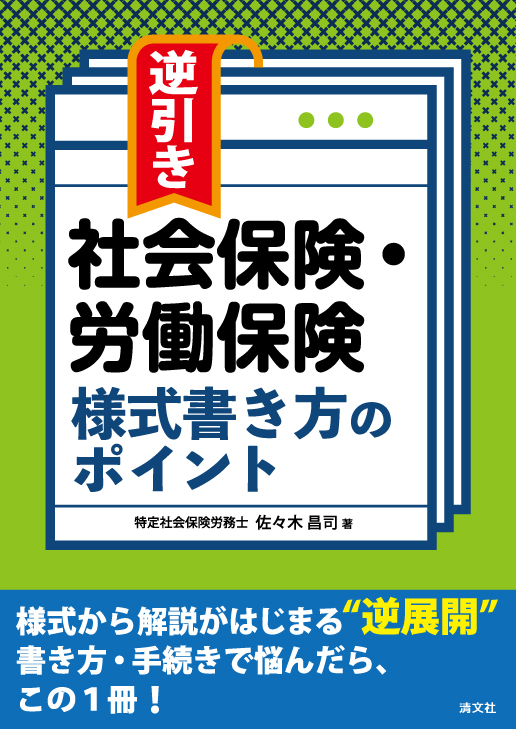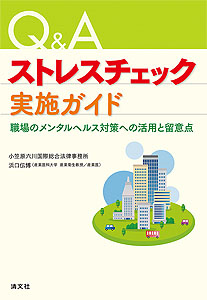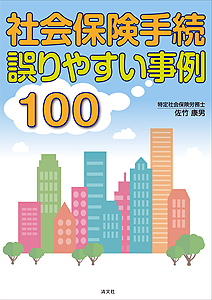〔業種別Q&A〕
労使間トラブル事例と会社対応
【第1回】
「工場内で労働者に労働災害が生じた場合のリスクと対応」
〈製造業〔Q1〕〉
弁護士法人 ロア・ユナイテッド法律事務所
パートナー弁護士 中野 博和
〈製造業の特徴と特有の労務問題〉
1 製造業の特徴
製造業は、新たな製品の製造加工を行い、これを卸売する業種です。製造業における製品は、機械製品、金属製品、電子部品、化学製品など様々です。
日本の労働総人口約6,700万人に対し、1,000万人以上が製造業に就業しており、製造業は日本経済の中心ともいえる産業です。
2 製造業特有の労務問題
(1) 労働災害(労災)
製造業では、製品の製造過程での事故や、長時間労働に伴う過労死・過労自殺などが起こりやすい傾向にあります。
労災が発生した場合、労働者側から安全配慮義務違反等を根拠に多額の損害賠償請求がなされることがあります。
(2) 情報管理
製造業では、製品の情報や製造のノウハウなどが外部に漏れてしまうと、模倣品が製造される等により損害が生じかねませんので、これらの情報を外部に漏らさないように対策をしておく必要があります。
(3) 雇用形態の多様性
製造業は、一般的に人手不足であると言われていますので、派遣社員などを受け入れたりしているところも多い傾向にあります。
形式的には請負や業務委託契約としていても、実質的には注文者が直接指揮命令をしている場合には偽装請負となり違法となってしまいます。
(4) 工場閉鎖に伴う人員整理
採算の取れない工場を閉鎖する場合には、これに伴い、その工場で働いていた従業員を解雇することもあり得ます。
このような経営上の理由による解雇(整理解雇)は、従業員には落ち度がないにもかかわらず行われるものであるため、法的に有効であるか否かは厳格に判断されます。
【Q】
当社の工場内で労働者の転落事故が発生してしまいました。事故後の対応や、今後問題となり得る法的リスクを教えてください。【A】
被災者本人を病院へ連れて行き、治療を受けてもらうことが最優先です。法的リスクとしては、損害賠償請求を受けるリスクや刑事罰を受けるリスクなどがあります。▲ ▼ ▲ 解 説 ▲ ▼ ▲
1 事故後の対応
事故が発生してしまった場合には、何よりもまず先に救急車を呼ぶなどして被災者本人を病院へ連れて行き、治療を受けてもらうことが最優先である。また、同時並行で被災者の家族にも連絡をとるようにする必要がある。その後は、被災者のお見舞いに行ったり、また、万が一被災者が亡くなってしまった場合には葬儀等の法事に参列したりするなど、被災者やその家族に対し、誠意を持った対応をするべきである。
会社は、従業員が労災により亡くなったり、休業したりしたときは、遅滞なく、所轄の労基署長に死傷病報告書を提出する必要がある(労働安全衛生法100条、労働安全衛生規則97条)。なお、就業中又は事業場内などにおける負傷、窒息又は急性中毒による場合には、労災でないときであっても死傷病報告書を提出しなければならない。
この死傷病報告書を提出しない場合や虚偽の内容の報告書を提出した場合には、いわゆる「労災隠し」として50万円以下の罰金に処せられる可能性があるため、注意が必要である(労働安全衛生法120 条、122 条)。
なお、当該事故が労災であるかについて判断し難く、死傷病報告書を提出しなければならないかが判断できない場合には、労基署に事故の状況等について説明・報告した上で、報告書の提出の要否等の対応について相談するべきである。
2 労働災害が発生した場合の会社側のリスク
(1) 損害賠償請求のリスク
労災認定がなされた場合、被災者等には国から労災保険が支給されるが、労災保険は全ての損害をカバーするものではない。そのため、労災が起きてしまった場合、労災認定後に会社に対して損害賠償請求がなされることが多い。会社に安全配慮義務違反が認められれば、場合によっては、億単位の損害賠償請求が認められることもある。
なお、被災者が下請会社の従業員など直接の雇用契約関係がない場合においても、会社が被災者に対して安全配慮義務を負う場合もあるため、このような場合にも、損害賠償請求が認められる可能性がある点には注意が必要である。
(2) 刑事罰のリスク
事故が会社の過失によって発生してしまったような場合には業務上過失致死傷罪(刑法211条)が成立し、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処されるリスクがある。
また、会社が、従業員の危険又は健康障害を防止するための措置を講ずることを怠った場合には、労働安全衛生法違反(同法116条など)として刑事罰に処されるリスクがある。なお、会社が死傷病報告書の提出を怠るといわゆる労災隠しとして刑事罰の対象になることはすでに述べたとおりである。
(3) 行政上のリスク
100人以上の従業員を雇用している会社などでは、労災の多さに応じて、一定の範囲内で労災保険率や労災保険料額が増減される(メリット制)。そのため、メリット制が適用される会社において、労災が発生してしまった場合、労災保険率や労災保険料額が引き上げられることがある。
また、国や地方公共団体などから許可等を得て業務を行っている会社においては、業務停止や許可等の取消しなどがなされることもあり得る。
さらに、国や地方公共団体などからの業務を受注する際の入札において、指名停止、指名回避などがなされることもあり得る。
3 安全配慮義務について
(1) 使用者の安全配慮義務
雇用主である使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をしなければならない(労働契約法5条)。安全配慮義務違反によって事故が発生してしまった場合には、すでに述べたとおり、被災者等に対して損害賠償をしなければならない。
なお、労働契約か否かは働き方等の実態を見て判断されるため、契約書が「業務委託契約」という名称であっても、実態からして労働契約であると判断されれば、安全配慮義務を負うこととなる。
(2) 使用者以外の者が安全配慮義務を問われる可能性
ア はじめに
労働契約を締結している場合だけでなく、ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において、当該法律関係の付随義務として信義則上安全配慮義務を負う(陸上自衛隊八戸車両整備工場事件・最三小判昭和50年2月25日労判222号13頁)。そのため、特別な社会的接触関係が認められれば、直接の雇用主でなくとも、安全配慮義務を負うことになる。
イ 元請企業と下請労働者
下請労働者は、下請企業との間で労働契約を締結しているにすぎず、元請企業との間で直接の労働契約関係はない。そのため、元請企業は、下請労働者に対して安全配慮義務を負わないのが通常である。
もっとも、上記のとおり、元請企業と下請労働者との間に特別な社会的接触関係が認められれば、元請企業も下請労働者に対して安全配慮義務を負うことがある。
特別な社会的接触関係の有無についての具体的な判断基準としては、「元請人の管理する設備、工具等を用いていたか、労働者が事実上元請人の指揮、監督を受けて稼働していたか、労働者の作業内容と元請人の作業員のそれとの類似性等の事情に着目して判断する」(日本総合住生活ほか事件・東京高判平成30年4月26日労判1206号46頁)こととなるものと考えられる。
ウ 派遣先企業と派遣労働者
派遣元企業は、派遣労働者との間で労働契約を締結しているため、労働契約法5条に基づき安全配慮義務を負う一方で、派遣先企業は、派遣労働者との間で労働契約を締結していないため、同条は適用されない。
もっとも、労働者派遣においては、派遣労働者は派遣先企業が管理する事業場等で派遣先企業の指揮命令に従って業務に従事するのが通常である。このような場合には、特別な社会的接触関係が認められ、派遣先が、当該派遣労働者に対して安全配慮義務を負うことも多い。なお、派遣先と派遣元双方の安全配慮義務違反を認めた裁判例として、アテスト(ニコン熊谷製作所)事件(東京地判平成17年3月31日労判894号21頁)がある。
エ 出向先企業と出向労働者
出向においては、出向元企業と出向労働者との間だけでなく、出向先企業と出向労働者との間にも労働契約関係が成立しているものと考えられている。
そのため、出向元企業及び出向先企業いずれも労働契約法5条に基づき安全配慮義務を負うのではないかとも考えられる。
この点につき、JFEスチール(JFEシステムズ)事件(東京地判平成20年12月8日労判981号76頁)では、具体的な労務提供、指揮命令関係の実態から、出向労働者に対する安全配慮義務は、第一次的には出向先企業が負い、出向元企業は、人事考課表等の資料や出向労働者からの申告等により、出向労働者の長時間労働等の具体的な問題を認識し、又は認識し得た場合に、これに対する適切な措置を講ずるべき義務を負うものとされている。
したがって、必ずしも出向元企業及び出向先企業の双方が安全配慮義務を負うわけではない。
(了)
「〔業種別Q&A〕労使間トラブル事例と会社対応」は、毎月最終週に掲載されます。