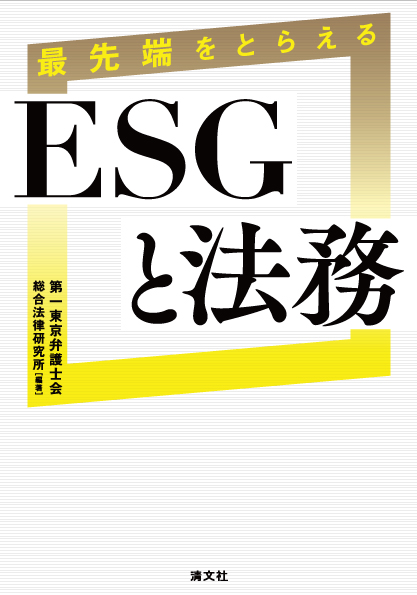エコ関連(環境・エネルギーに関する)
助成金・補助金とはどういうものか?
【第1回】
「関連する助成金・補助金の特徴と留意点」
行政書士 石下 貴大
1 エコ関連の助成金とは?
よく「助成金」というと、雇用関係のものがイメージされやすいが、エコ関連(いわゆる環境・エネルギーに関する)助成金にも多様な種類のものがある。
エコ関連というと非常に広い概念であるが、大きく分けると
① エネルギーの無駄を省く『省エネ』
② エネルギーを創る『創エネ』
③ エネルギーを蓄える『蓄エネ』
に関し普及促進するための「助成金」「補助金」に分けられる。
地球温暖化、砂漠化、生物多様性、環境破壊、資源の枯渇など地球を取り巻く環境問題は多岐にわたっており、我が国としても環境問題への課題は多い。
中でも化石燃料を輸入に頼っている日本にとって、エネルギー問題は非常に重要な問題である。
2010年6月に策定されたエネルギー政策基本法の第三次計画では、2030年に向けた目標として、エネルギー自給率と化石燃料の自主開発比率を倍増して自主エネルギー比率を約70%とすること、電源構成に占めるゼロ・エミッション電源(原子力及び再生可能エネルギー由来)の比率を約70%とすることなどを記載している。
また二酸化炭素の削減目標についても2009年に、排出量を2020年までに1990年比で25%削減するという目標を打ち出した(その後原発の問題もあり2013年の条約第19回締約国会議(COP19)で2020年に「05年比3.8%削減」に修正)。
こうした状況の中で、特にエネルギー問題、低炭素社会への実現に向けた助成金や補助金が地方自治体、環境省、経済産業省、その他外郭団体などから公募されている。
2 どのようなケースで使えるか?
エコ関連の助成金・補助金といっても、所管部署が違えば助成金額、補助率、申請主体から申請するための要件も異なる。
また、これらは毎年決まった時期に公募されるというわけではなく、例えば去年公募されていた助成金や補助金が今年はないというケースも珍しくない。
廃止されていないまでも、助成金額や助成率、要件などが変わっていることはよくあるので、申請に当たっては注意が必要だ。
また、助成金や補助金は返済義務がないのがメリットといえるが、先に支払っている費用に対して一部補填されるというものである。
例えばスーパーで使用している照明をすべてLED照明に換える場合に、関連する助成金の申請が通ったとしても、先にそのLEDの代金や工事費を支払い、その金額に対して助成金が支払われるのである。
当然、申請した際の計画との整合性を報告書の形で提出するので、助成金ありきではなく、それぞれの募集事項に合う事業計画をお持ちの場合に検討したほうがよい。
その一方で、太陽光発電システムの設置工事に関しては、要件を満たせば補助金が支給されるというものもある。以前あったエコポイントも同様といえるだろう。
3 それぞれの補助金のカテゴリについて
省エネ、創エネ、蓄エネについて、それぞれもう少し具体的にみていこう。
① 『省エネ』・・・LED、空調、厨房機器、エコキュート等の省エネ機器など
(例)
省エネルギー型ロジスティクス等推進事業費補助金(省エネルギー型陸上輸送実証事業(省エネルギー型トラック運送に係る革新的省エネルギー機器実証事業))
【補助金の種類】
設備導入、実証事業
【補助対象者】
中小事業者、貨物自動車運送事業者、リース事業者など
【対象設備等】
・省エネ 空調
・省エネ 厨房機器
・省エネ その他省エネ機器
・太陽光発電アイドリングストップ機器
・外部給電式冷凍・冷蔵システム機器
【補助対象費用(費目)】
設備費、工事費、設計費
【対象エネルギー種・カテゴリー】
・電気 節電 蓄電池
・省エネ
・化石燃料 ガソリン
・化石燃料 軽油
・再生可能エネルギー 太陽光
【補助率】
1/2
【補助金総額】
約7,000万円
【リース等の活用】
可能
【公募期間】
2014年6月9日(月)~2014年6月27日(金)まで
【募集団体名】
外郭団体(経済産業省の委託先) パシフィックコンサルタンツ
② 『創エネ』・・・自家発電、コージェネレーションシステム、燃料電池、エネファームなど
(例)
東京都 家庭の創エネ・エネルギーマネジメント促進事業
【補助金の種類】
設備導入
【補助対象者】
個人、個人事業主、助成対象機器の所有者など
【対象設備等】
・創エネ コージェネレーションシステム
・創エネ 新エネルギー 太陽光
・創エネ エネファーム
・蓄エネ 蓄電池
・ビークル・トゥ・ホームシステム
【補助対象費用(費目)】
設備費、工事費
【対象エネルギー種・カテゴリー】
電気、発電、燃料電池、蓄電池
【補助率】
・ガスコージェネレーションシステム:1/4,1/2
・蓄電池システム:1/6,1/2
・ビークル・トゥ・ホームシステム:記載なし
・太陽光発電システム:記載なし
【補助金額上限】
・ガスコージェネレーションシステム:記載なし
・蓄電池システム:500,000円
・ビークル・トゥ・ホームシステム:100,000円
・太陽光発電システム:1キロワット当たり20,000円
【補助金総額】
約67億円
【リース等の活用】
記載なし
【公募期間】
2014年4月1日(火)~2015年3月31日(火)まで
【募集団体名】
地方公共団体、東京都、財団法人東京都環境整備公社、東京都地球温暖化防止推進センター(クール・ネット東京)
③ 『蓄エネ』・・・蓄電池などの蓄エネ設備
(例)
自立・分散型低炭素エネルギー社会構築推進事業
【補助金の種類】
実証事業
【補助対象者】
中小事業者、事業者、民間団体等、公共団体、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人
【対象設備等】
・蓄エネ 蓄電池
・蓄エネ その他蓄エネ設備
・その他 送電線
・その他 インフラ系設備
【補助対象費用(費目)】
調査費、設備費、工事費、旅費、人件費、設計費、委託費、消耗品費、事務費
【対象エネルギー種・カテゴリー】
・電気 節電 エネルギーマネジメント
・電気 発電 燃料電池
・電気 発電 自家発電
・電気 発電 コージェネレーション
・電気 節電 蓄電池
【補助率】
3/4
【リース等の活用】
使用料及び賃借料
【公募期間】
2014年5月16日(金)~2014年6月30日(月)17時必着
【募集団体名】
環境省 地球環境局 地球温暖化対策課
* * *
以上、今回はそれぞれの分類と概要についてみてきたが、次回は先日公募されたばかりで、今注目されている「エネルギー使用合理化等事業者支援補助金」について、申請上の注意点などを踏まえながら具体的に見ていきたい。
(了)