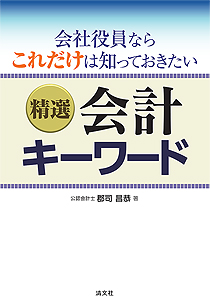〈会計基準等を読むための〉
コトバの探求
![]()
【第1回】
「企業会計原則」と「企業会計の原則」
公認会計士 阿部 光成
◆はじめに
「企業会計原則」は、その設定以来、わが国の会計規範として会計学の発展に非常に大きな役割を果たしていると思われる。
ところが、「企業会計原則」ではなく、「企業会計の原則」と記載している会計基準がある。果たして両者は同じ意味なのだろうか。
たとえ類似した用語であっても、少しの相違によって異なる意味を示すことがある。そして、その用語の選択には、会計基準等の設定者の意思が反映されていることがある。
本連載では、それらの「用語(コトバ)」を取り上げて丁寧に検証し、会計基準等を「正しく読む」ことができるよう解説を行うものである。
今回は「企業会計原則」と「企業会計の原則」を取り上げる。
◆「企業会計原則」とは
「企業会計原則」は、企業会計の実務の中に慣習として発達したもののなかから、一般に公正妥当と認められたところを要約したものである(「企業会計原則の設定について」(1949年7月9日、経済安定本部企業会計制度対策調査会中間報告)二、1)。
そして、「企業会計原則」の一般原則三では、「資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはならない」と規定されており、一般に、資本取引と損益取引との区別の原則と呼ばれている。
◆「企業会計の原則」とは
前述した「企業会計の原則」の用語は、「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」(企業会計基準第1号。以下「自己株式会計基準」という)において登場する。登場するまでの自己株式会計基準の文脈を見てみよう。
まず、自己株式会計基準は、資本剰余金の各項目は、利益剰余金の各項目と混同してはならないとし、資本剰余金の利益剰余金への振替は原則として認められないと規定する(資本剰余金と利益剰余金の混同の禁止。自己株式会計基準19項)。
次に、資本剰余金と利益剰余金に関するこれまでの取扱いについて、自己株式会計基準は、従来、資本性の剰余金と利益性の剰余金は、払込資本と払込資本を利用して得られた成果を区分する考えから、原則的に混同しないようにされてきたと説明する(自己株式会計基準60項)。
そして、平成13年改正商法・会社法における配当に関する定めは、資本剰余金と利益剰余金の混同を禁止する企業会計の原則を変えるものではないとし、「企業会計原則」ではなく、「企業会計の原則」と記載している(自己株式会計基準60項)。加えて、自己株式会計基準62項でも、「企業会計の原則」と記載している。
◆「企業会計原則」と「企業会計の原則」
「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号)では、新たな企業会計基準が「企業会計原則」に優先すると規定している(1項、26項)。
「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号)でも、資産の評価基準については「企業会計原則」に定めがあるが、金融商品に関しては、本会計基準が優先して適用されると規定している(1項)。
また、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号)は、棚卸資産の評価方法、評価基準及び開示に関しては、「企業会計原則」及び「原価計算基準」に定めがあるものの、本会計基準が優先して適用されると規定している(2項)。
このように企業会計基準委員会の会計基準等が「企業会計原則」よりも優先するとする規定を設けていることを考えると、「企業会計原則」と「企業会計の原則」との間には、重要な相違があるのかもしれない。
(了)
文中、意見に関する部分は、筆者の個人的見解です。
「〈会計基準等を読むための〉コトバの探求」は、不定期の掲載となります。