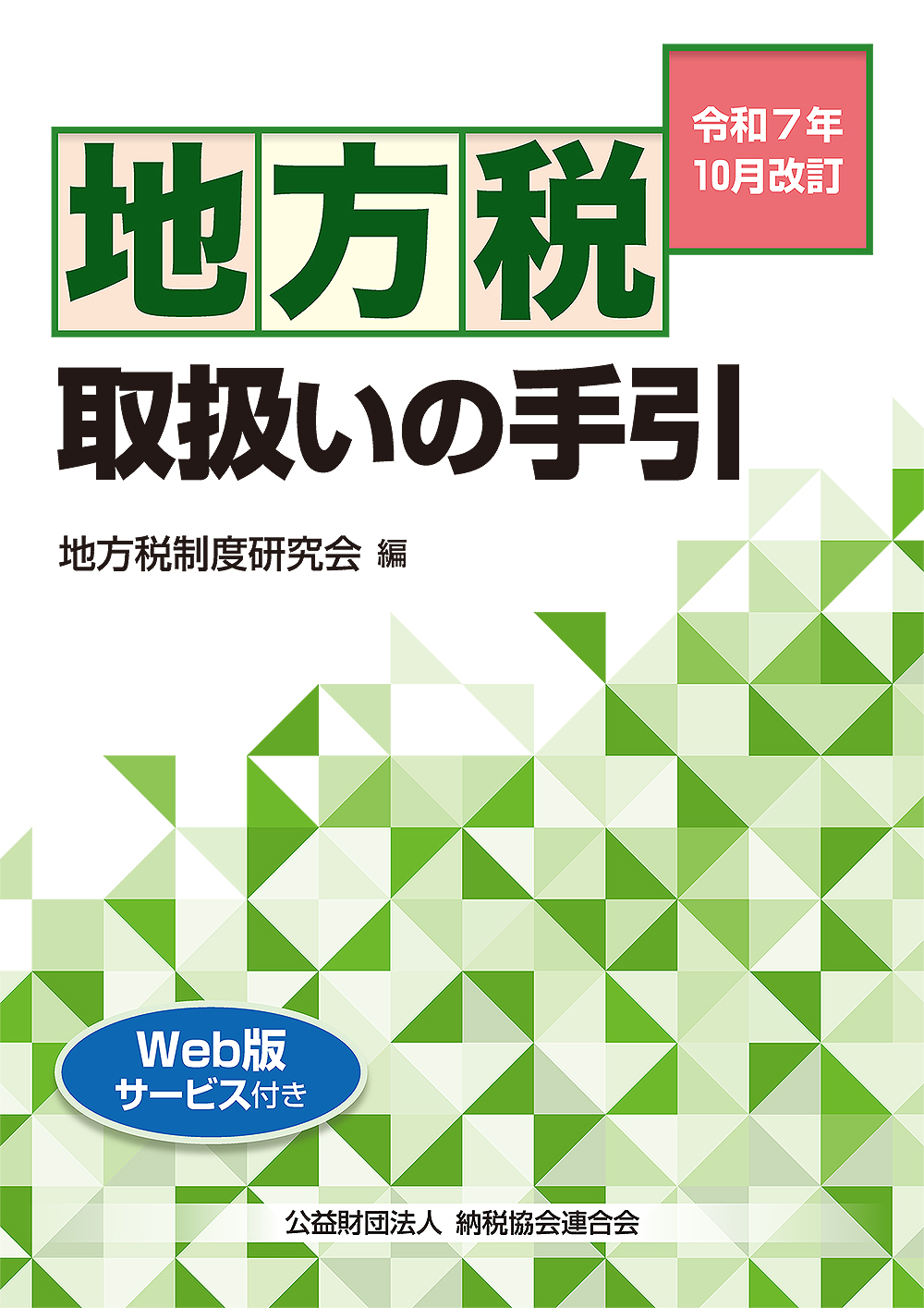土地問題をめぐる2018年法改正のポイント
【第1回】
「所有者不明土地の円滑化等に関する特別措置法の仕組み」
弁護士 羽柴 研吾
1 はじめに
近年、所有者不明の土地が様々な場面で問題になっている。所有者不明土地問題研究会の報告によれば、2016年時点の所有者不明の土地面積は、九州の面積を超える約410万ヘクタールに及んでおり、2040年頃には北海道の面積に迫る約720万ヘクタールにまで拡大すると言われている。
さて、2018年6月6日に、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(以下「所有者不明土地特措法」という)が成立した。同法は、所有者不明の土地が全国的に増加していることに伴い、公共事業の推進等の様々な場面において円滑な事業実施に支障が生じていることを踏まえ、これに対応するために制定されたものである。
また、これに先立つ同年4月25日には、「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」(以下「都市再生特措法等改正法」という)が成立している。同法は、都市の内部で空き地・空き家等の低未利用地が時間的・空間的にランダムに発生する「都市のスポンジ化」が進行していることを踏まえ、その対策を総合的に進めるために、都市再生特別措置法、都市計画法、建築基準法及び都市開発資金の貸付けに関する法律を一部改正するものである。
本稿では、所有者不明土地特措法を解説するとともに、実務家として押さえておきたい今後の所有者不明の土地問題の動向に言及する。その後、都市再生特別措置法等改正法について解説することとしたい。
(※) 本稿では紙幅の関係上、上記法改正に関連する税制措置については割愛している。
2 所有者不明土地特措法について
(1) 所有者不明土地特措法の概要
所有者不明土地特措法は、主として3つの仕組みから構成されている。
【所有者不明土地特措法の3つの仕組み】
① 所有者不明土地を円滑に利用する仕組み
② 所有者の探索を合理化する仕組み
③ 所有者不明土地を適切に管理する仕組み
所有者不明土地特措法の中心をなす概念は、「所有者不明土地」と「特定所有者不明土地」である。その意味は次のとおりである。
▷「所有者不明土地」
相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行ってもなおその所有者の全部又は一部を確知することができない一筆の土地
▷「特定所有者不明土地」
所有者不明土地のうち、現に建築物(物置その他の政令で定める簡易な構造の建築物で政令で定める規模未満のものを除く)が存せず、かつ、業務の用その他の特別の用途に供されていない土地
(2) 所有者不明土地を円滑に利用する仕組み
特定所有者不明土地について、①地域住民等の共同の福祉又は利便の増進を図る事業(地域福利増進事業)のために使用権を設定する制度と、②公共事業における収用手続を合理化・円滑化(土地収用法の特例)する制度が創設された。
なお、地域福利増進事業は、具体的には、公園、広場、購買施設(いわゆる産直施設など)、駐車場などを運営する事業が想定されている。
① 地域福利増進事業のために使用権を設定する制度
本制度は、都道府県知事が、地域福利増進事業を行おうとする者に対し、特定所有者不明土地上に、存続期間10年を上限とする使用権を認める制度である(なお、延長も認められている)。使用権が認められるための手続の流れは次のとおりである。
裁定申請
(事業者による都道府県知事への申請)
↓
公告・閲覧(6ヶ月)
(都道府県知事による公告・閲覧)
↓(※1)
裁定
(使用期間と補償金)
↓
事業者による使用権の取得と補償金の供託
↓(※2)
使用開始/使用権終了後の原状回復
(※1) 権利者が当該土地を事業に供することについて異議を申し出なかった場合
(※2) 事業者が使用権の始期までに補償金を供託しない場合、使用権を認めた裁定の効力が失われる。
② 収用手続を合理化・円滑化する制度
公共事業の用地取得を行うにあたって、地権者の同意が得られない場合等に、土地収用法に基づいて収用を行う方法がある。
土地収用法は、①事業認定手続(国や都道府県知事が、申請事業に土地を収用するに値する公益性が認められるかを判断する手続)と、②収用裁決手続(収用委員会が土地所有者等に対する補償金の額等を決定する手続)から構成されている。
これに対して、所有者不明土地特措法は、上記②の収用裁決手続に関して、収用委員会による審理手続を省略して、都道府県知事が補償金の額を裁定できるものとし、これが公告されることによって土地収用法の権利取得裁決及び明渡裁決があったものとみなすことにしている。
(3) 所有者の探索を合理化する仕組み
① 土地所有者等関連情報等の利用及び提供
地方公共団体の部局が土地の所有者を探索する場合、地方公共団体が保有する公簿等が有力な資料となる。しかし、たとえば、固定資産課税台帳には当該土地の所有者の情報が記載されているが、税務部局の職員は、地方税法の守秘義務を負っているため、これを別の部局に提供することができない問題があった。
そこで、所有者不明土地特措法は、地域福利増進事業等の実施のため、地方公共団体の保有する情報を内部で利用できることとした。
また、地域福利推進事業等を実施しようとする者は、地方公共団体の長に対して、当該土地の土地所有者等関連情報の提供を求めることができ、本人の同意がある場合には、提供を受けることができることとなった。
② 相続登記等に関する不動産登記法の特例
所有者不明の土地が生じる原因の1つとして、数世代の相続が生じているにもかかわらず、相続登記が行われないままになっていることが指摘されている。このような相続登記未了の土地は、所有者の特定に多大な労力を要するため、地域福利増進事業等を実施する障害となるものである。
そこで、所有者不明土地特措法は、相続登記等がされておらず、かつ、公共の利益となる事業地になるような土地を「特定登記未了土地」と定義して、登記官に次の権限を与え、特定相続未了土地の解消を実現しようとしている。
まず、登記官は、特定登記未了土地について、登記名義人の死亡後10年以上30年以内において政令で定める期間を超えて相続登記がされていない場合に、職権でその旨を登記に付記することができる。また、登記官は、特定登記未了土地の登記名義人になり得る者を知ったときは、相続登記を申請するように勧告することができることになった。
(4) 所有者不明土地を適切に管理する仕組み
民法上の制度として、相続財産管理人と不在者財産管理人がある。これは、相続人の存在が明らかでない場合や所在が分からない者がいる場合に、利害関係人の請求によって家庭裁判所が選任した管理人が財産の管理等を行う制度である。
この「利害関係人」とは、法的な利害関係が必要と解されており、行政機関が所有者不明土地を管理しようとしても、何らかの権利義務関係がなければ、財産管理人の選任を請求することができない問題があった。
そこで、所有者不明土地特措法は、国の行政機関の長や地方公共団体の長に、所有者不明土地に関して、財産管理人選任の請求権を認めることとした。
(5) 施行時期
所有者不明土地特措法は、公布の日(2018年6月13日)から起算して6月を超えない範囲で施行される予定である。
(了)
次回は、8/30に掲載されます。