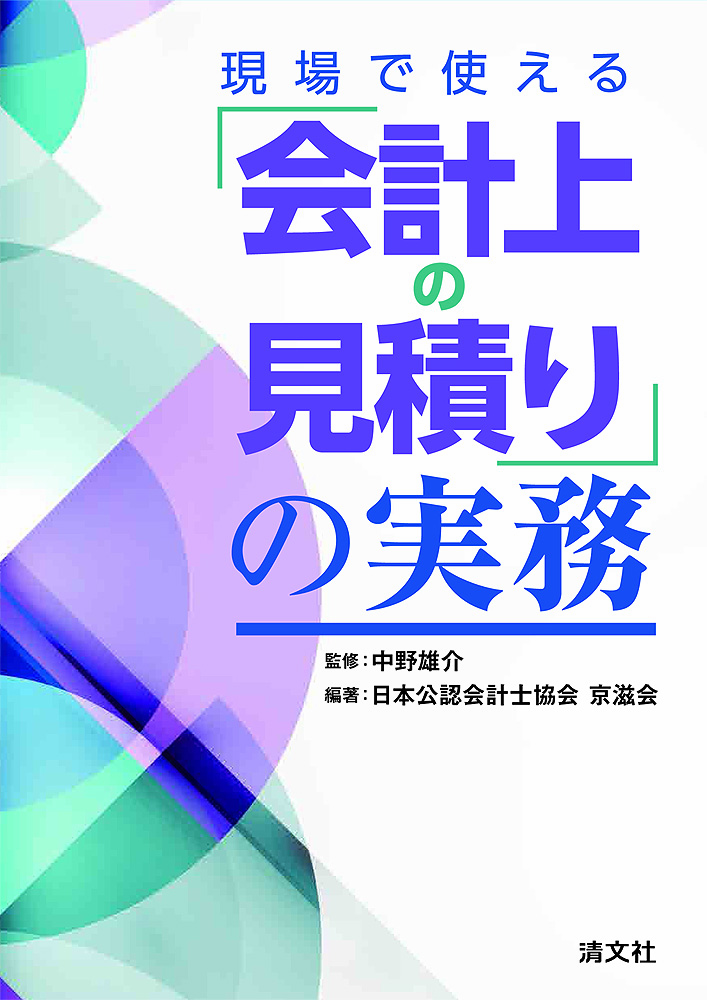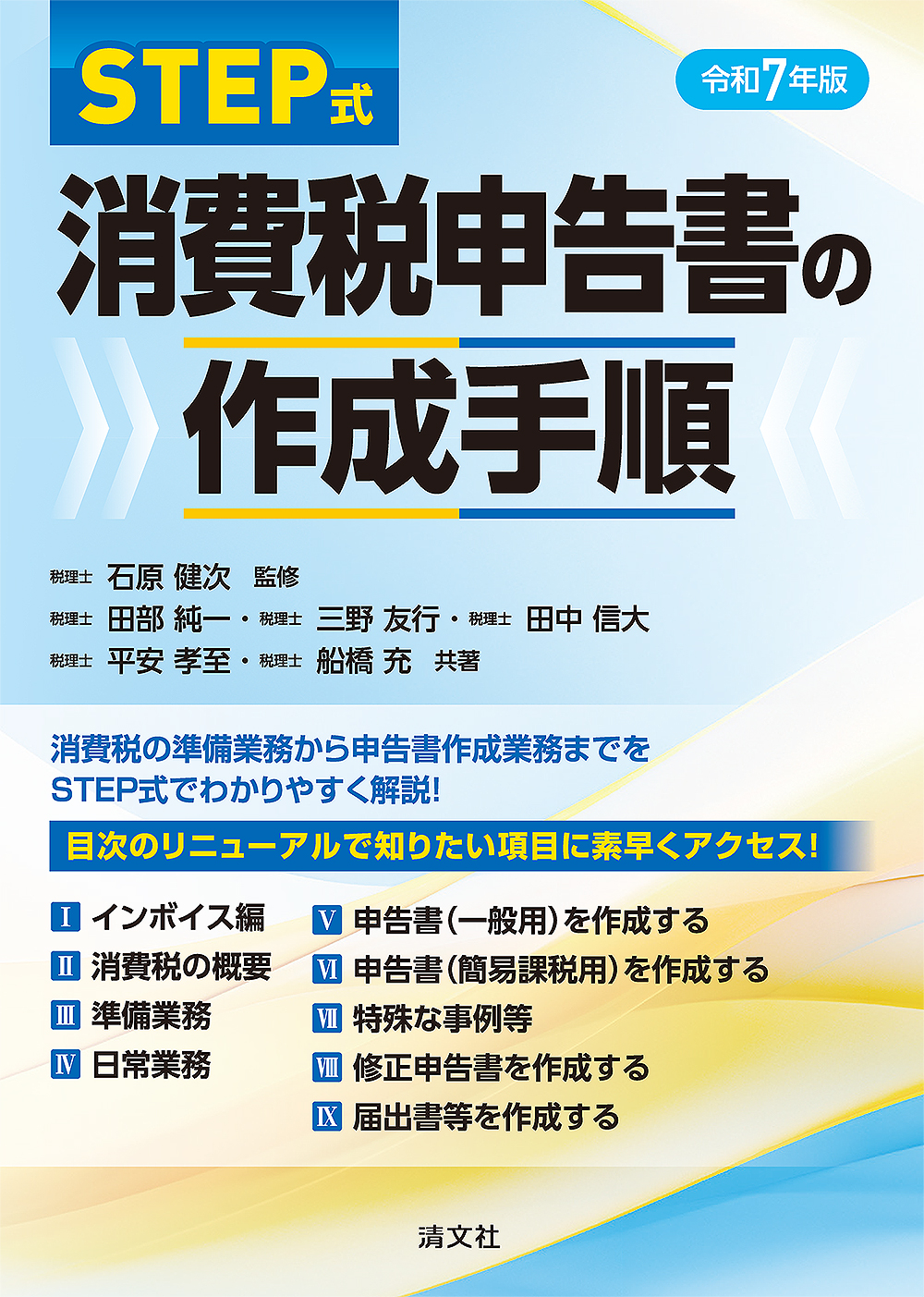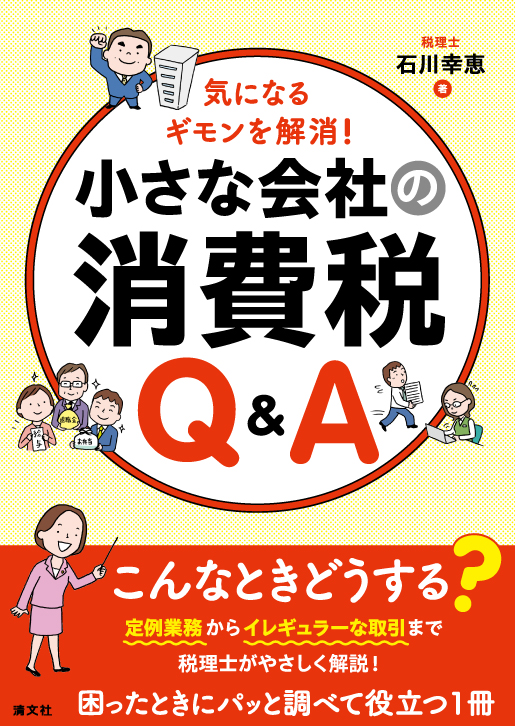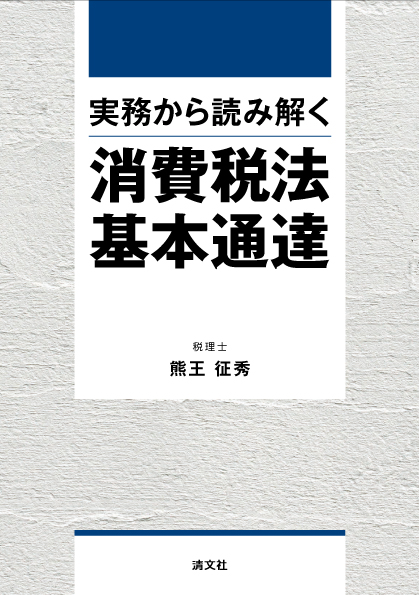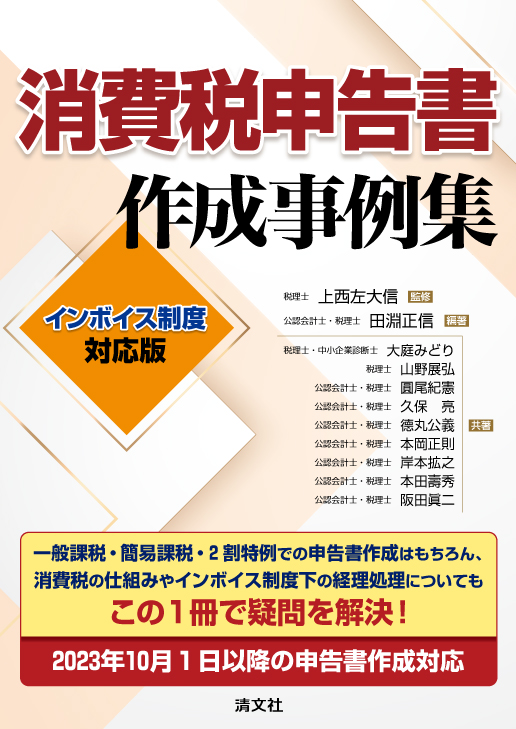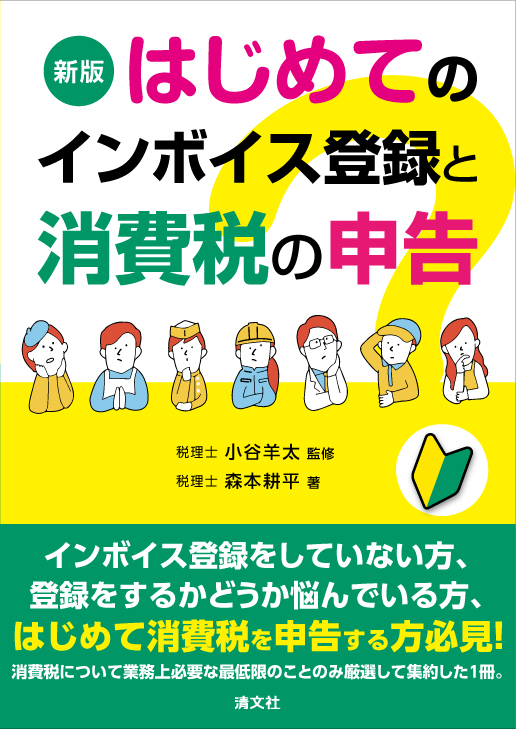《税務必敗法》
【第1回】
「申告書の提出を行っていなかった」
公認会計士・税理士 森 智幸
◆ ◇ ◆ 連載開始にあたって ◆ ◇ ◆
本連載は、税務を行う上で「これをやったら失敗する」という必敗法を紹介するものである。成功するときは、運が味方することもあり、その要因が定かではない。しかし、失敗するときは、必ず何らかの原因がある。その原因を1つずつ取り除いていけば、成功に近づくのである。この考え方は、吉田兼好の徒然草『双六の名人』の中でも紹介されている。兼好が、当時の遊びである双六の名人に、上手な打ち方を尋ねたところ、名人は次のように答えたという。
「勝たんと打つべからず。負けじと打つべきなり。いづれの手か疾く負けぬべきと案じて、その手を使はずして、一目なりともおそく負くべき手につくべし」(「勝とうと思って打ってはならない。負けないように打つべきである。どの手を打つと早く負けてしまうのかを考え、その手を使わないようにし、一手でも負けるのを遅らせる手を選ぶべきである。」)
本連載は、税理士だけではなく、会計事務所の職員も読者の対象としている。必敗法は、税務を行う会計事務所職員もぜひ、身につけていただきたい。
本連載が、税務の一助になれば幸いである。
* * *
【事例】
6月のある日、X会計事務所に税務署から電話がかかってきた。税務署によると、顧問先であるA社の申告書が提出されていないが、どうなっているのかということだった。事務所内で調査をしたところ、担当者が申告期限を勘違いしており、申告書の提出を行っていなかったことが発覚した。
1 はじめに
税務を行う税理士にとって、顧問先の申告書の提出を忘れるということはプロフェッショナルとして絶対にあってはならないことである。
「そんなの当然だろう」と思われるかもしれないが、税理士業務では、多忙なスケジュールや顧問先数の増加により、申告期限を失念するリスクがあるので十分に注意すべきである。筆者の知人の税理士も、うっかり申告期限を失念して提出が期限後となってしまったことがある。
申告書の提出を忘れてしまうと、税法上のペナルティだけでなく、顧問先からの信頼を失い、顧問契約解除にもなりかねない。当然のことを当然に行うのがプロフェッショナルである。
そこで今回は、申告書の提出の失念を含むいくつかのケースとその防止案について説明する。
なお、本稿は法人税、消費税の申告を前提とする。
2 想定されるケースと対応策
(1) 申告書の提出期日を忘れる
① 想定されるケース
(イ) 申告書の提出期日の失念
申告書の提出失念が発生する原因としては、「申告書の提出期日を忘れていた」というものが挙げられる。
その原因として考えられるのは、顧問先が増加し、顧問先の決算期と申告期日を把握しきれなくなってきたということである。法人の場合は、決算月は様々であるため、申告期限も様々である。毎月、法人の顧問先の記帳や決算を行っていると、それらの情報に埋もれてしまい、申告をうっかり忘れてしまうことがありうる。
また、時々、消費税の課税期間を短縮している顧問先もある。3ヶ月ごとあるいは1ヶ月ごとに申告期限が訪れることになるため、こちらも他の顧問先の決算・申告に埋もれて、忘れることもありうる。
(ロ) 電子申告の送信ミス
これは、別稿で詳しく説明するが、電子申告の送信ミスにより、申告書を作成したものの、提出し忘れるというケースが想定される。
(ハ) 申告期限の延長の特例に関する勘違い
法人税の申告期限の延長の特例の適用を受けていないにもかかわらず、その適用を受けていると勘違いして申告期限までに提出しないケースも考えられる。消費税についても同様である。
【参考】消費税及び地方消費税無申告加算税賦課決定処分取消請求事件
税理士のケースではないが、2003年に大手電力会社が消費税の確定申告書の提出を失念したケースがあった。これは、同年6月12日、所轄税務署の職員が同社の従業員に対し、消費税等の申告書の提出の確認を行ったところ、申告書の提出を失念していたことが判明したというものである。そこで、申告期限を過ぎた同年6月13日に確定申告書を提出したものの、所轄税務署は同社に対して無申告加算税約12億円の賦課決定を行った(注)。
なお、確定納付分は納期限までに納めていたことから、同社は申告の遅れだけで12億円の無申告加算税を課すことは過重であるとして行政訴訟を提起したものの、大阪地裁はこの請求を棄却した(大阪地裁平成17年9月16日判決(TAINSコード:Z255-10134))。
(注) この事件が起こった当時は、消費税の申告期限の延長制度はなかった。
② 対応策
(イ) 毎月の申告管理表を作成する
申告書の提出期日の失念を防止するためには、会計事務所全体で申告管理表を作成し、毎月初めに確認することが有効である。管理表の様式はもちろん自由である。その月に申告期限が到来する顧問先が一覧になっている様式のほうが見やすいであろう。
(ロ) デジタル活用によるスケジュール管理
GoogleカレンダーやOutlookカレンダーといった電子カレンダーやグループウェアのカレンダーで申告書提出予定日を設定し、デジタルで管理する方法が考えられる。また、GoogleやMicrosoftのTo-doアプリを使って、行うべきことをリスト形式で管理する方法も有効である。
(ハ) 電子申告は受信通知を確認
電子申告の場合は、必ず受信通知を確認することが重要である。また、担当者任せにせず、必ず上席が確認することで送信ミスを防止できる可能性が高まる。
(2) インターネットトラブル
① 想定されるケース
インターネットに大規模な障害が発生する、あるいはWi-Fiの接続障害で、インターネットがつながらないケースが想定される。
インターネットに接続できないと電子申告もできなくなるので、申告書の提出遅延のリスクがある。
② 対応策
インターネット障害は大規模な場合、長時間つながらないときもある。そのため、申告期限日の3日前までに申告を済ませるのが望ましい。Wi-Fiの接続障害の場合においても同様である。
(3) 電子証明書トラブル
① 想定されるケース
電子申告時は、ICカードである税理士用電子証明書を使用するが、磁気不良などで不具合が生じ、電子署名ができなくなることが想定される。
また、カードリーダライタの故障により電子証明書が使用できなくなるトラブルも想定される。
② 対応策
電子証明書は最低2枚所有することを推奨したい。日本税理士会連合会(以下「日税連」という)の「よくある質問と回答(第五世代電子証明書)」でも2枚所有することのメリットが記載されている。
【Q5】 電子証明書の2枚発行のメリットを教えてください。
A 使用していた電子証明書(ICカード)を紛失・破損しまった場合、もう1枚のICカードに切り替えることにより、電子申告を継続して行うことが可能となり、業務の停滞を防ぐことができます。
(出典:日税連「よくある質問と回答(第五世代電子証明書)」)
また、カードリーダライタも同じく2台所有しておくほうがよいであろう。その理由としては、日税連による動作確認済みのカードリーダライタは一般的に広く販売されているものではないので、すぐに購入できるとは限らないからである。
(4) 郵便トラブル
① 想定されるケース
郵便で想定されるケースとして、郵便局の「ゆうゆう窓口」が24時間対応ではなくなったことに気づかず、申告書を入れた封筒を郵便局に持っていったものの、営業時間を過ぎていて郵送できないケースが想定される。
ゆうゆう窓口は、2020年4月に新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置として原則として平日は19時まで、土日祝日は18時までとなった。コロナ禍前は24時間対応だったが、現在は営業時間が定まっているので注意が必要である。なお、郵便局によって営業時間が異なるので必ず確認していただきたい(一部郵便局は平日21時までのところもある(2025年5月現在))。
その他、郵便に関しては、宅配便で申告書を郵送してしまい、税務署が期限後申告としたケースもある(国税不服審判所平成17年1月28日裁決(TAINSコード:J69-1-01))。そもそも申告書は信書に当たるため、宅配便で送ることはできない。そのため、申告書は郵便又は信書便で送る必要がある。
② 対応策
こちらも、申告期限日の3日前には提出を済ませておくことが望ましい。
また、郵送は、簡易書留など発信日がわかる郵便又は信書便で送ることが必要である(国税通則法22条)。郵送方法は担当者任せにせず、会計事務所内でその方法を統一しておくとよいであろう。
3 申告書の提出を失念した場合の顛末
申告書が期限後提出となった場合、税法上、以下のペナルティが発生する。
【顧問先】
・原則として無申告加算税が課される。ただし、一定の場合は、無申告加算税が課されない場合もある。
・延滞税等が発生する(ダイレクト納付や自動ダイレクトの場合)。
・法人税は、2事業年度連続で無申告又は期限後申告となると青色申告の承認が取り消される。
【税理士】
・正当な理由なく法定申告期限までの提出を怠った場合、業務け怠があったとして税理士法37条違反による懲戒処分が課される可能性がある(国税庁「税理士制度のQ&A」問6-20)。
また、顧問先から契約解除となる可能性も高くなる。申告書の提出失念等には十分注意されたい。
〔編集部追記:2025/6/16〕
上記赤文字部分については、筆者校正後の修正を編集部にて公開前に反映できていなかった箇所となります。
お詫びの上、訂正させていただきます。
(了)
「《税務必敗法》」は、毎月第1週に掲載されます。