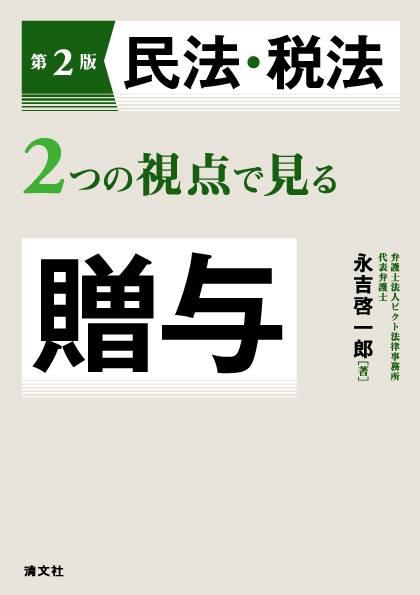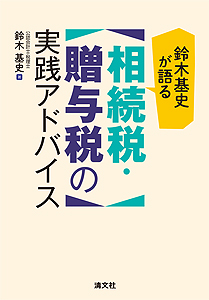鵜野和夫 平成25年度税制改正を読む①
「教育資金をまとめて贈与して一安心」
~父母・祖父母等からの教育資金の一括贈与には、
1,500万円までの非課税の特例~
税理士・不動産鑑定士 鵜野 和夫
(一)
さる有名大学の医学部長を勤め上げ、定年退職してから、自宅を改装して個人医院を開業したところ、その高名のたまものか、患者は引きも切らず繁盛。
「親の心、子知らず」ともいうが、この医院を息子に引き継がせようと夢に見ていたところ、ままならぬのが世の習いとか。
息子は病人の顔を見て一生を送るのは、まっぴらとのこと。それより人を笑わせてと、お笑いタレントの道に足を突っ込む。
これでこの医院もオレ一代で終わりかと、つぶやいていると、庭先から聞こえる、なにやら孫のキャキャと、楽しそうな声。
なんだろうかと、窓ごしに見ると、幼稚園に通い出した孫が、隣の女の子と、お医者さんごっこ。
ありゃ「栴檀(せんだん)は双葉より芳し」「門前の小僧習わぬ経を読む」とは、このことか。
この孫こそ、おれの後継者だ。
(二)
ところで、この孫が、めでたく医学部に入学、卒業、インターンを経て、一人前の医者になるまで、どれくらいの金がかかるか、胸算用したところ、まあまあ、俺の目の黒いうちは大丈夫として、しかし、オレももう歳だしなぁ、その後、頼りない息子がこの孫に教育資金を払ってやれるくらい稼いでくれるのかなぁ。どうも心許ない。
では、今のうちに、それだけの学費を孫に贈与しておくとして・・・・。少なくとも1,500万円は必要だろうな。
ところで、贈与をしたら贈与税がかかるというが、いくらくらい課税されるのか。顧問の税理士先生に電話して聞いてみよう。
(三)
えっ。1,500万円を贈与すると、贈与税が、525万円も課税される。
だけど、毎年110万円ずつ贈与したのなら課税されない。
じゃぁ、そうするか。でも、14年もかかる計算か。
それまで生きていられればいいが。なに、医者の不養生ってこともあるな。
と、悩みが絶えない。
数日後。
孫の学資金に一括して贈与しても、1,500万円までなら贈与税は課税されないという税制が創られることになりそうだよと、税理士から連絡。
それなら、と。
(四)
これは、教育資金の一括贈与の贈与税の非課税の特例といって、30歳未満の者に対して、その直系尊属が、その者の教育資金に充てるための資金を、金融機関に信託した場合に、それを引き出して、入学金や授業料などに充てた場合に、受贈者1人につき1,500万円までは、贈与税を課税しないという税制が、今年の税制改正で創設されるというものです。
(五)
Q
子や孫に、その入学金や授業料などの教育資金を、親や祖父母が贈与しても、贈与税は課税されないというように、今でもなっているんじゃないですか。
A
その通りです。しかし、それは、入学金や授業料などを納付する時に、その都度贈与したものについてです。将来、これくらい必要だろうといって、予め贈与するのは、今までは認められていませんでした。
今回の改正税制は、将来必要となる資金を、まとめて贈与しても、1,500万円までならその時点では課税しないというのが、この特例のミソなのです。
Q
でも、贈与された教育資金を、その子や孫が、自動車を買ったり、レジャーに使ったりしたら。
A
そういうことのないように、その資金は信託銀行、銀行や第一種金融商品取引業者に、子や孫の名義で信託することになっています。
Q
だったら、この時に、子や孫に贈与したということになるじゃないですか。
A
そうです。贈与したが、贈与税は課されないのが、この特例なのです。
そして、子や孫が、入学金や授業料などを学校に納付したとき、その領収書を信託した銀行などに提示して、その金額の払出しを受けるというシステムになっています。
そして、この金額については、贈与税の非課税の特例を受けるという申請書を、その銀行等を通して、税務署に申請することになっています。
Q
ということは、例えば、その子の親が、お金が必要になったからといって、その資金を引き出すわけにはいかないようになっているんですね。
(六)
Q
ところで、入学金や授業料のほか、学習塾などに支払ったものは、この対象になるのでしょうか。
A
小学校、中学校、高等学校、大学の入学金や授業料として納付したものは、1,500万円以下までは非課税になります。
そして、塾などの授業料などは、500万円までは認められる予定といわれています。
Q
学校で1,500万円、塾などで500万円ということは、合わせて2,000万円ということですか。
A
いや、合わせて1,500万円までということです。
(七)
Q
贈与される子や孫は、年齢が30歳未満ということは、生まれたばかりの赤ちゃんでもいいんですね。
A
はい、その通りです。
Q
贈与をするほうは。
A
贈与される者の直系尊属に限ります。
Q
直系尊属というと、どの範囲までですか。
A
両親、祖父母、そして曾祖父です。
Q
子や孫が30歳を超えて、その資金が残っていた場合には、どうなりますか。
A
30歳までには、学業を終了してほしいというのが親心ですが、孔子さまでも、30歳になって、やっと一本立ちしたというくらいですからね。
しかし、この制度では、その子や孫が30歳になった日に、まだ資金が残っていたら、その残金に対して、贈与税が課税されるようになっています。
(八)
Q
ところで、一つ気がかりなことがあります。
銀行などは、信託された金銭を、どのように保管しておくのですか。
A
安全で有利な方法で運用するといっていますが。
Q
でも、運用してくれて増えればいいのですが、運用に失敗して、元も子も無くなるとまでいかなくても・・・。
元本は保証してくれるのですか。
A
信託ですから、元本保証ということは、しないでしょう。
そこから先、どういう信託銀行、銀行や金融商品取引業を選ぶかという判断は、自己責任ということになるでしょうね。
(九)
Q
で、この贈与は、いつから、いつまでにすればいいのでしょうか。
A
現時点では、まだ、法案の段階ですが、法律が成立すれば、平成25年4月1日から平成27年12月31日までに、信託した場合に適用されることになっています。
(了)