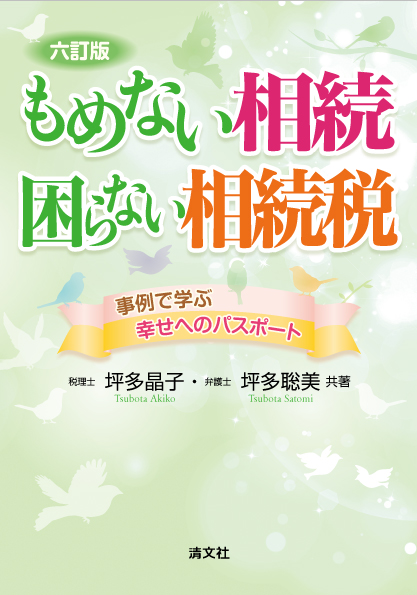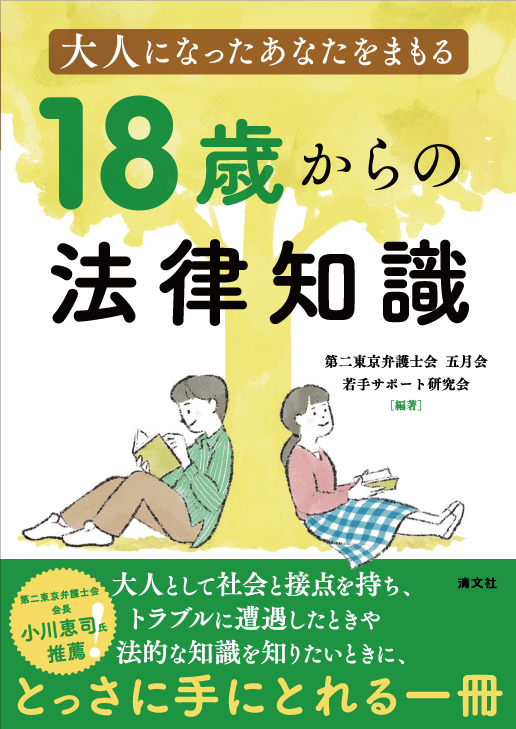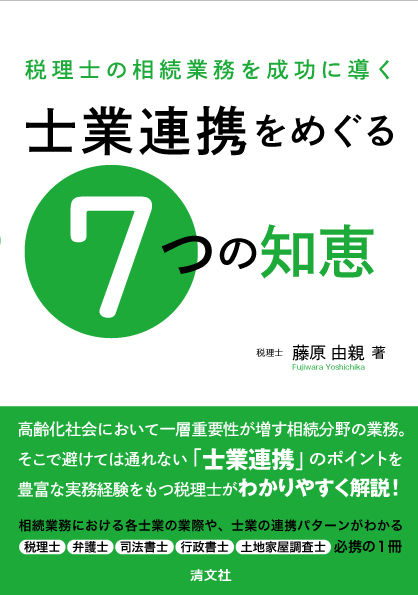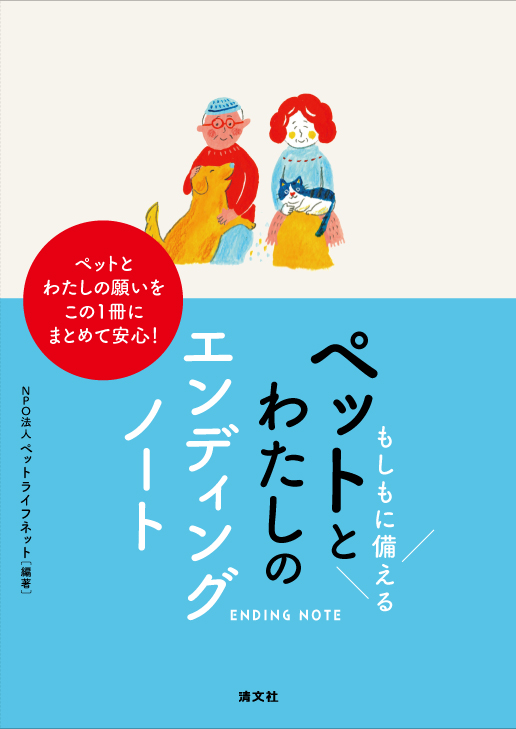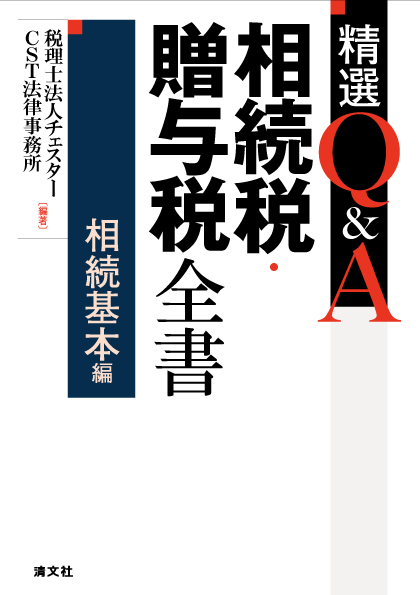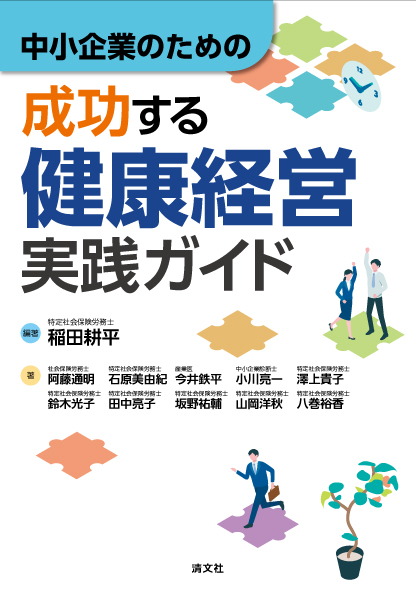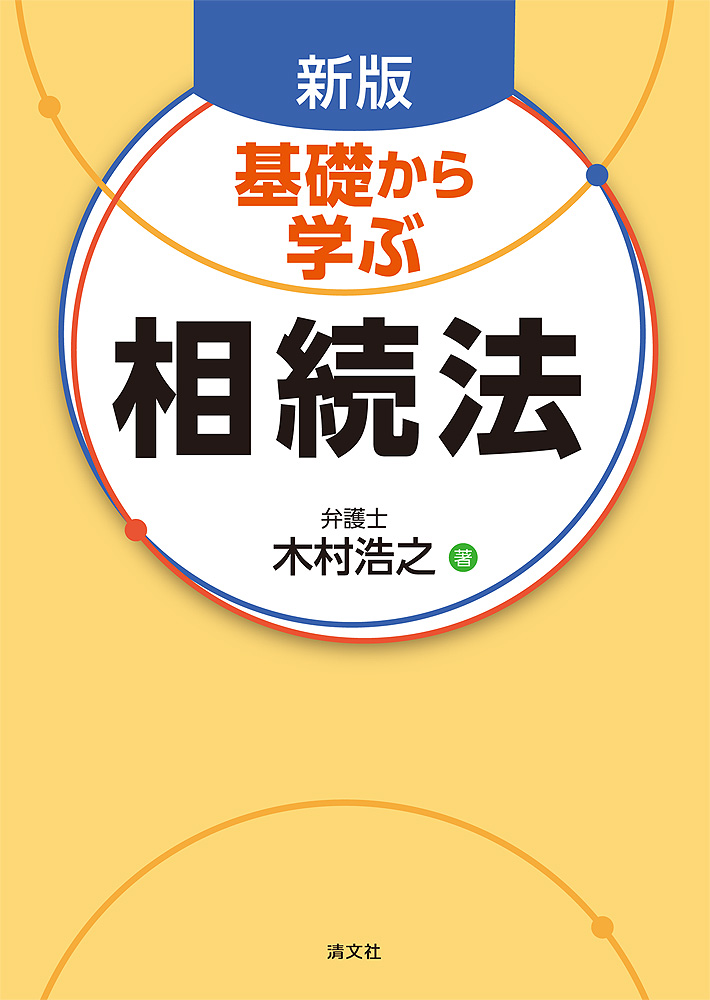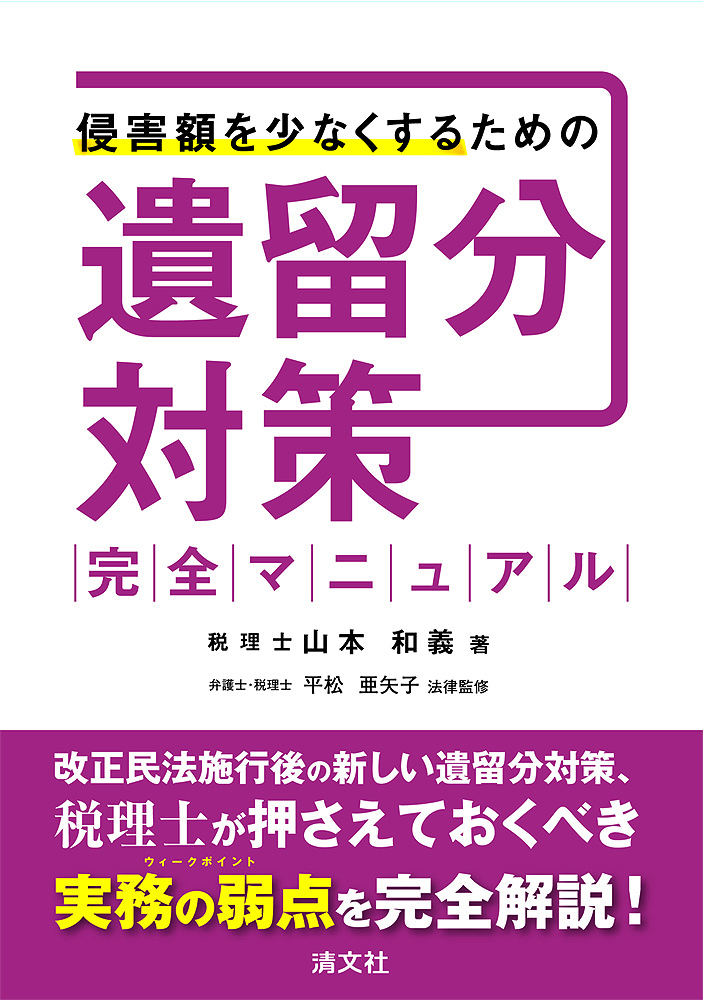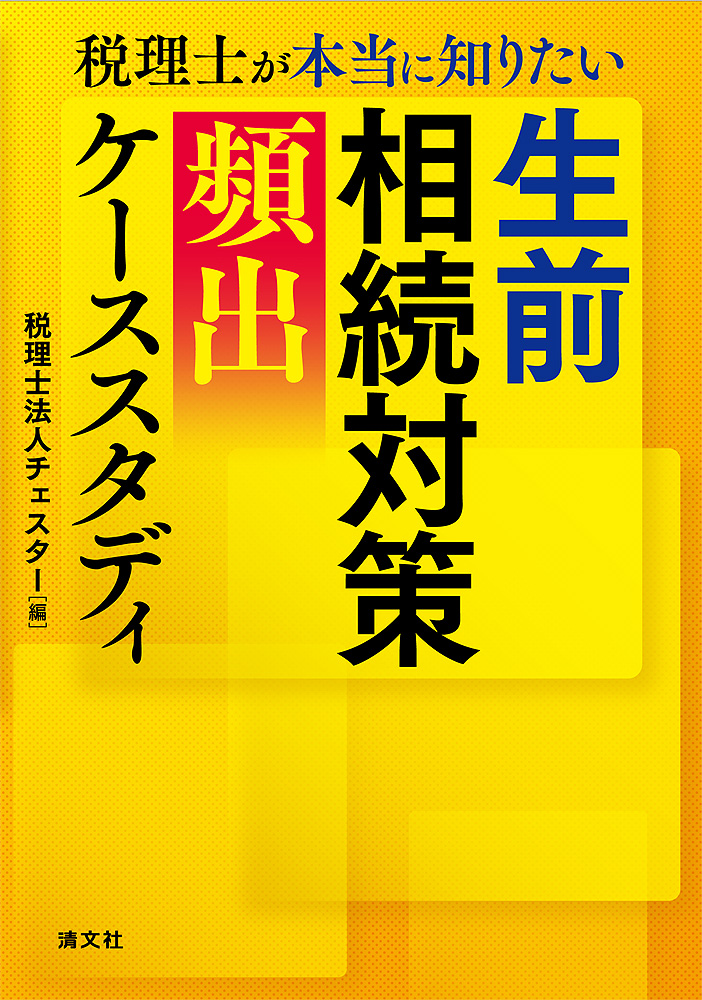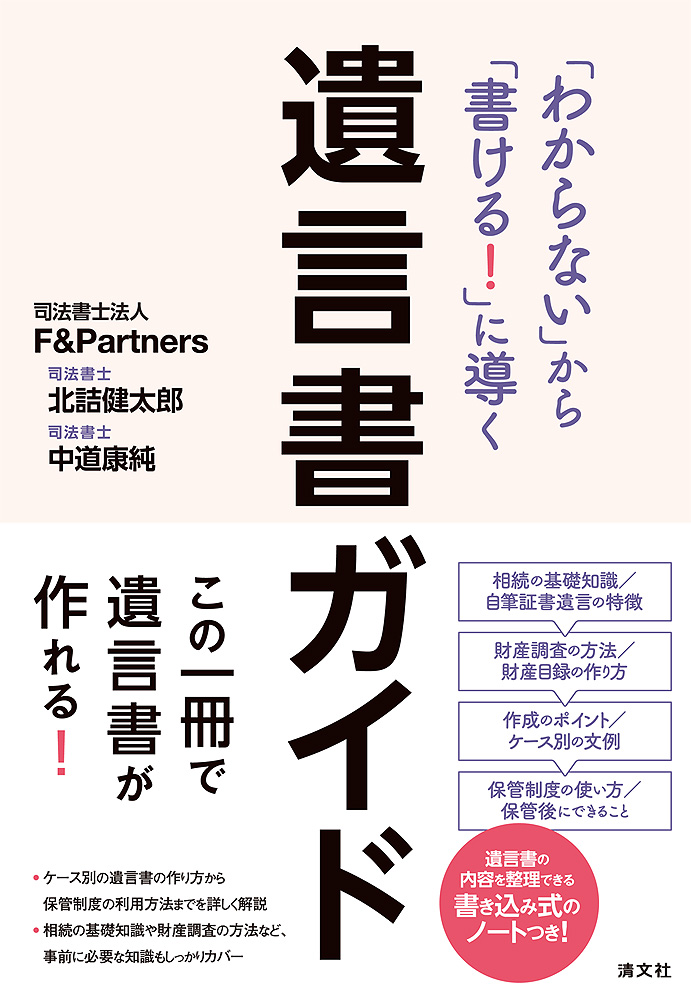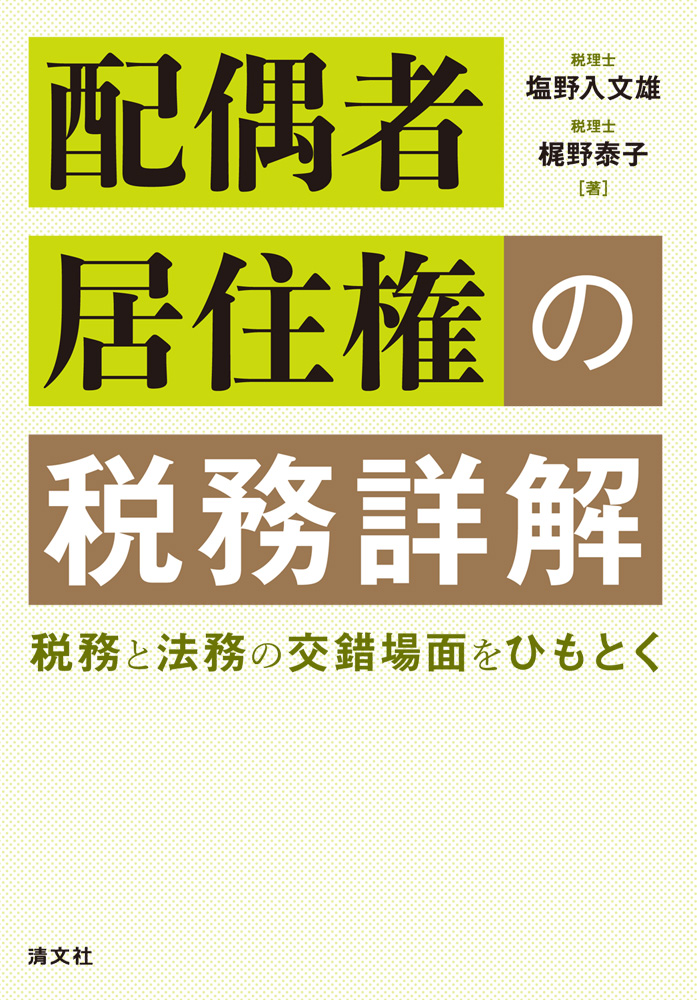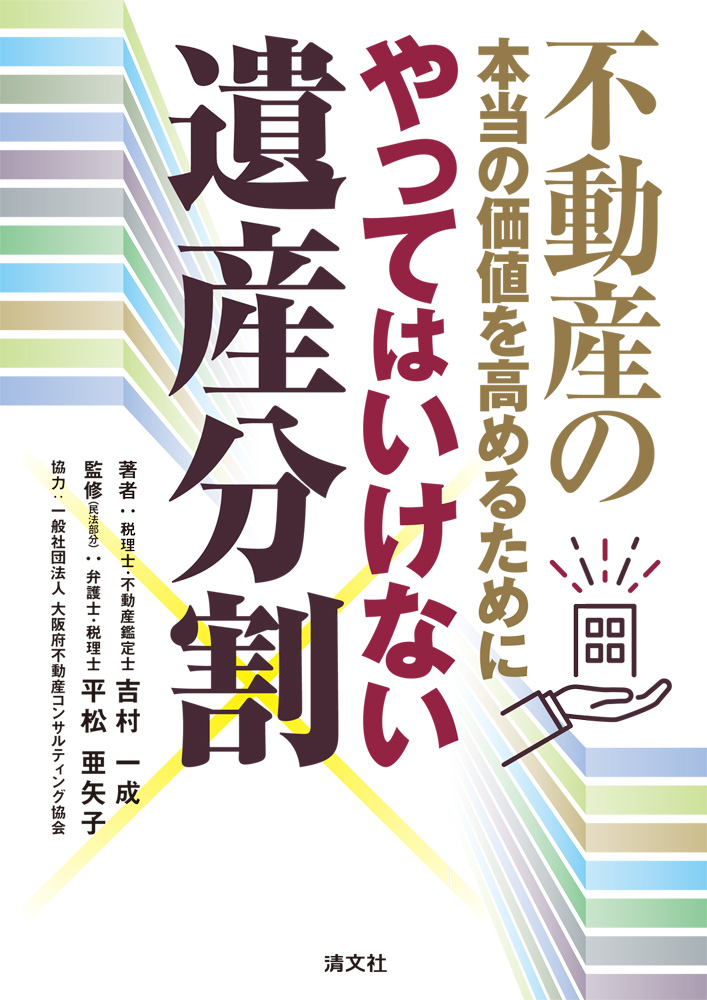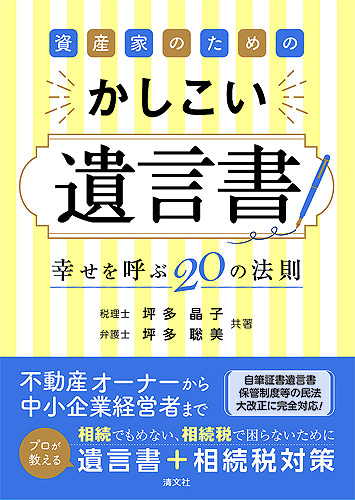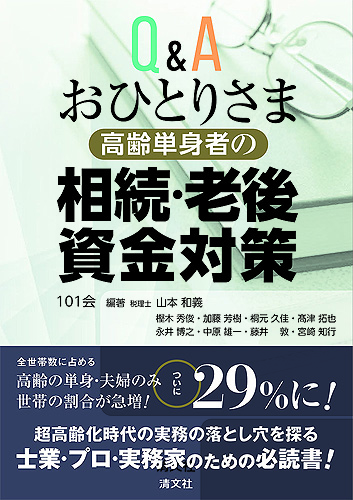私が出会った[相続]のお話
【第1回】
「これから相続案件に携わる税理士の皆さまへ」
~相続実務に関するクライアントへの対応と心がまえ~
財務コンサルタント
木山 順三
〔皆さまへのごあいさつ〕
税理士の皆さま、こんにちは。財務コンサルタントの木山順三です。
私は長年信託銀行マンとして、若い時代は銀行の営業、中堅になり銀行の店部経営、そして50歳から現在に至るまで、コンサルタント業に携わっています。
その間、税理士、弁護士、司法書士、公証人、家庭裁判所調査官、国税調査官、マスコミ・出版関係者等々、さまざまな方との出会いがありました。
私は税理士ではありません。
したがって、これから述べさせていただく税理士の皆さまへのアドバイスは大変僭越であり、ましてや既に多くの経験をされておられる先生方にとっては失礼極まりないものと十分理解しております。
しかしながら、あえて申させていただくならば、業界内部でなく外部から見た客観的な見方も、“岡目八目”というように意外と本質をついている面もあると思います。
年齢だけはたいていの税理士の皆さまよりも勝っている私に免じて、これからの1年間、どうぞお付き合いください。
〔相続に携わる心がまえ〕
さて、皆さまは既に独立されておられたり、特定の税理士事務所で業務をなさっておられることと存じますが、この連載のはじめとして、今回は、これから相続の案件に携わろうとされておられる税理士の皆さまに、ぜひとも心がけていただきたいことについてお話したいと思います。
まずはそれらの事項を、思いつくままに述べてみましょう。
① 顧客指向を忘れずに(面倒くさがらず何事にもマメに活動する)
② 守秘義務は絶対に守る
③ 業界以外の人との連携と人脈づくり
④ リスク管理に注意(高齢者のクライアントには特に注意)
⑤ 法規の遵守
⑥ 常に自己啓発を忘れずに
⑦ 顧客との関係は節度を保つこと
・・・等々
以上、アットランダムに述べてみました。
既に皆さまにおかれては十分に心得ておられることと思いますが、上記項目の中でも特に次の三項目については、老婆心ながら注力願いたいと思います。
まずは、①の「顧客指向を忘れずに」です。
ただしこれは、必ずしもクライアントの言うことを何でも「ハイ、ハイ」と聞くことではありません。
3年ほど前の日経新聞朝刊に、米銀行投資家のケン・モリス氏が言った「NOといえるバンカー」という記事が載っていました。
同氏は「悪質なM&Aをやめるよう経営者に言うべき時がある。感謝されても報酬はゼロ。バンカーとはおかしな商売なのだ」と。その後同氏は独立したが、開業翌日のことを今も忘れない。ヒルトン・ホテルズのトップから売却の相談依頼があった。モリス氏のもとには長年買収提案が押し寄せていたが、価格の低さから反対し続けていた。しかしこの時は妥当な価格であり、大型M&Aに結びつくことができた。「反対したから信用された」と同氏はいう。信用は顧客と命運を共にして初めて勝ち取れるという。
このことは、常に収益目標にさらされている銀行員への格言だけではないと思います。
すべての業界、なかでも信用を構築し長いお付き合いをする税理士業にも通ずるものと思われます。
〔信頼される人脈づくり〕
次に注意していただきたいのが、③の「(税理士)業界以外の人との連携と人脈づくり」です。
この項目は、私自身がコンサル業に携わってから、まさに骨身にしみて実感している事柄です。
おそらく、これから相続案件を手がけようとされる税理士の先生方は、どうすれば相続事案の情報が獲得できるかと日夜頭を悩ましておられることでしょう。
でも、世の中そんなに甘くありません。
どんな人かわからない人に、あなたは相談に行かれますか?
やはり信用のおける事務所、信頼のできる方からの紹介、先輩・後輩等の情報等々、何らかの「人と人とのつながり」から生ずるものなのです。
その意味で、人を好きになりましょう!
現に私は、銀行の現役時代に国税局の査察を受け、その結果その査察官と親しくなり、彼が税理士として独立した後も現在まで交流が続いています。
〔一線を越えやすい税理士業〕
さらに、⑦の「顧客との関係は節度を保つこと」も大切です。
ある相続事案の遺言書に関するもので、私が直接関わった案件ではありませんが、知り合いの弁護士から聞いた話です。
それは、クライアントの自筆証書遺言の中に、顧問税理士への多額の遺贈文言があったというものでした。
当然のことながら、相続人からその作成に至る経緯が問われ、顧問税理士の作為により作成されたものとして自筆証書遺言の無効を主張されたようです。
最終結論まで伺ったわけではありませんので、その結果については不明ですが、税理士業とは、親しくなればなるほど一線を越えやすく、いくら魅力的な誘いをかけられても自分を律しなければならない職業なのです。
それだけに誇り高き職業なのだということを、常に自覚していてください。
〔これからのお話の前に〕
以上、紙面の関係で大雑把な感想を述べさせていただきましたが、税理士の皆さまがクライアントから心から信頼を受け、末永く本業務を続けられ、かつ、発展させられることを願っております。
次回からは、具体的な事案について述べてみたいと思います。
ただし、前もってお断りしておきますが、これからご紹介する事例は、あくまで筆者自身が経験し対応したり聞いたりしたうえで、解決(成功)または未解決(失敗)となった問題であります。
したがって、税理士の皆さまが同じ対応で、同じ結果が出るものではありません。
相続事案というものは、このようにその折の背景、相続人各自の感情、対応のタイミング等により大いに変化するものであることを申し上げておきます。
それだけに、より多くの事案を経験されることが、的確な判断力を醸成することにつながるものと考えています。
(了)
「私が出会った[相続]のお話」は、毎月第1週の掲載となります。