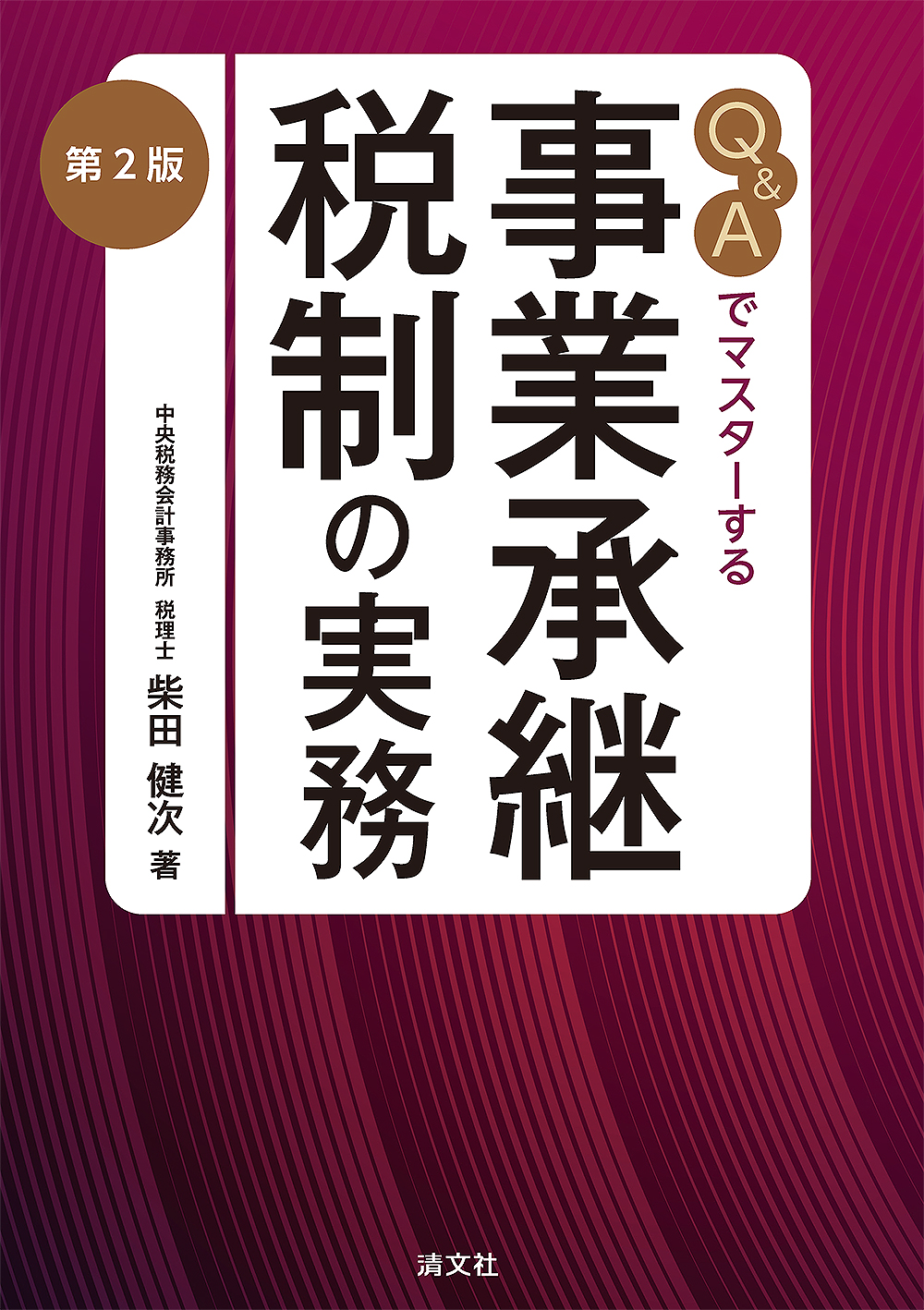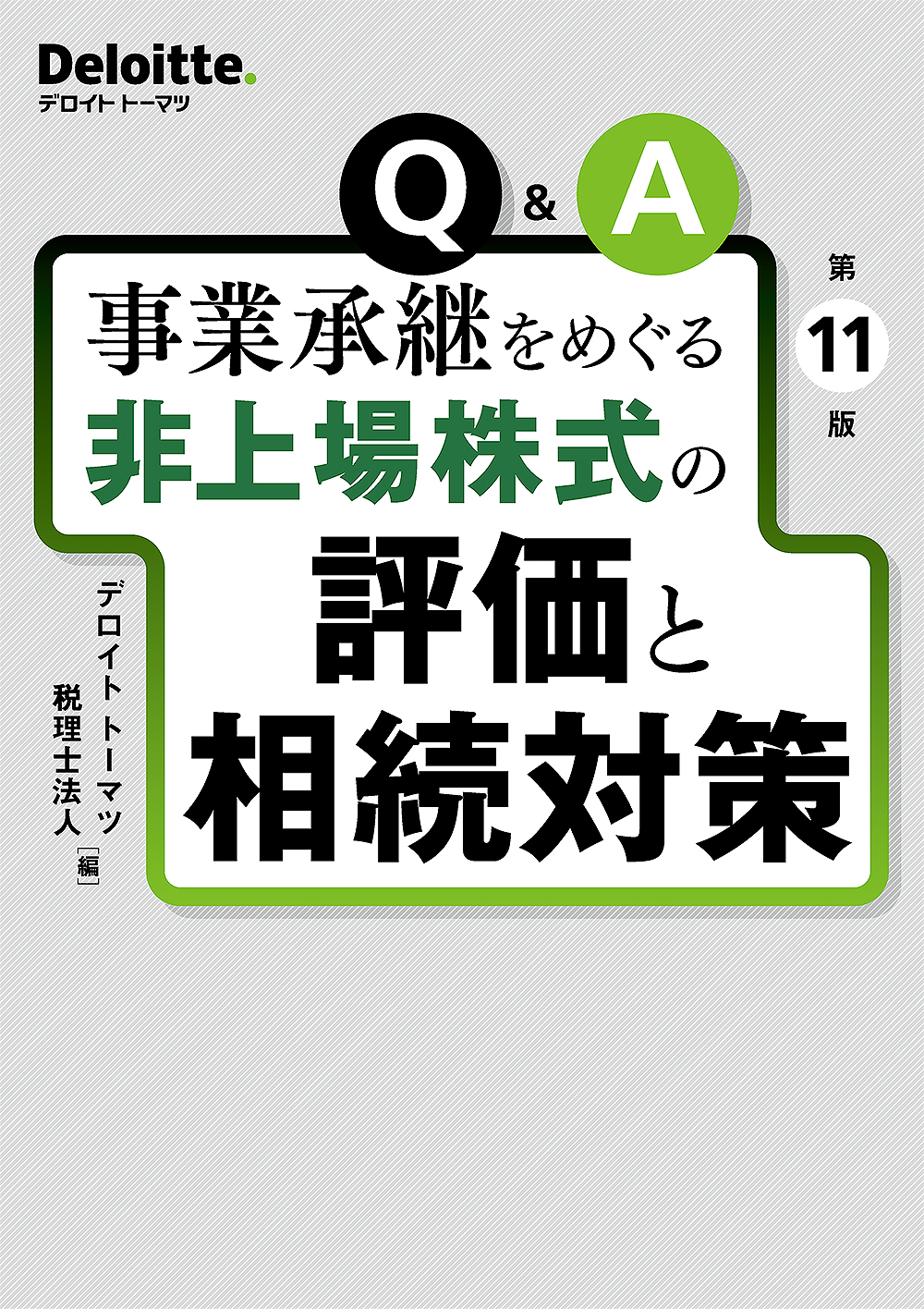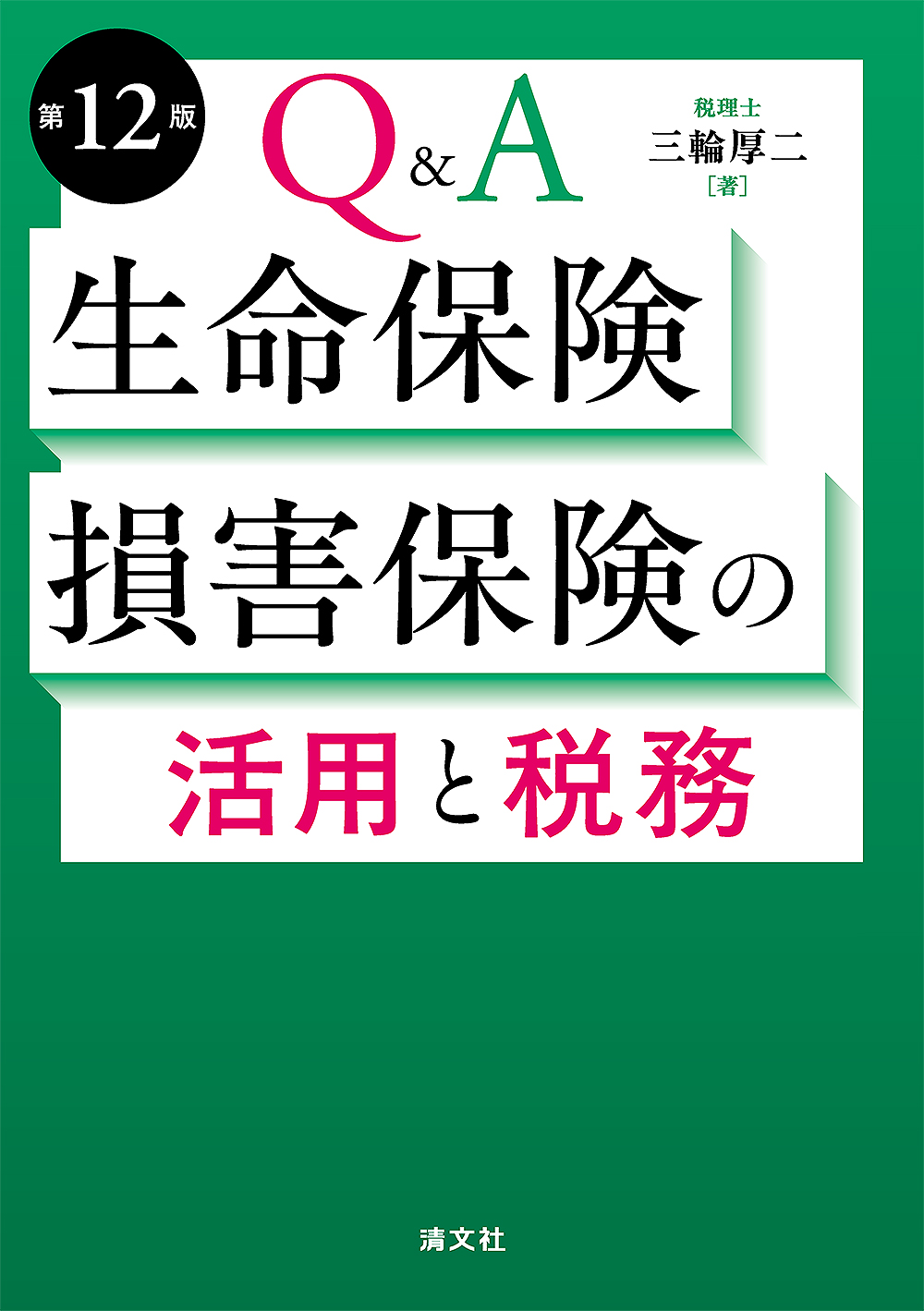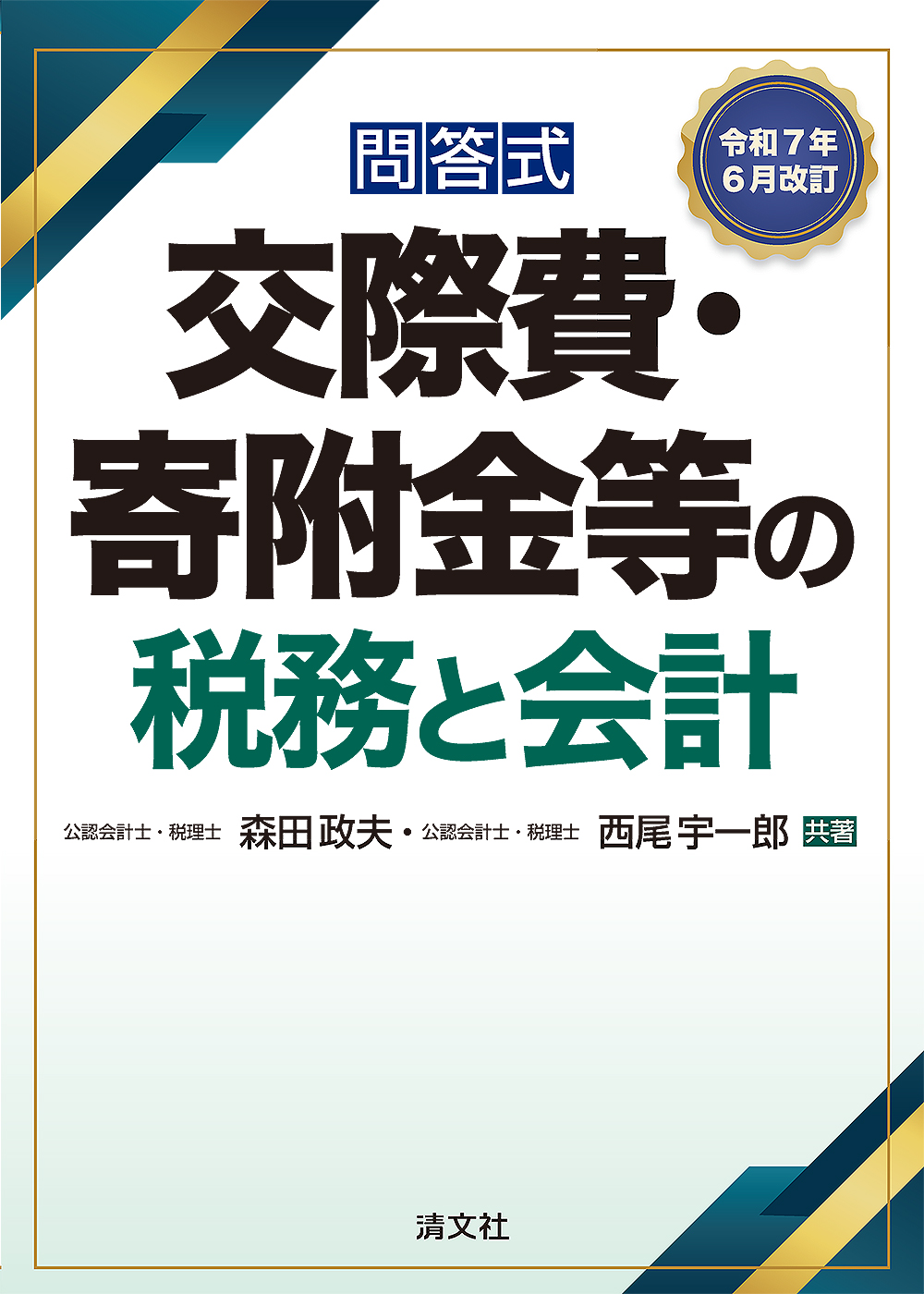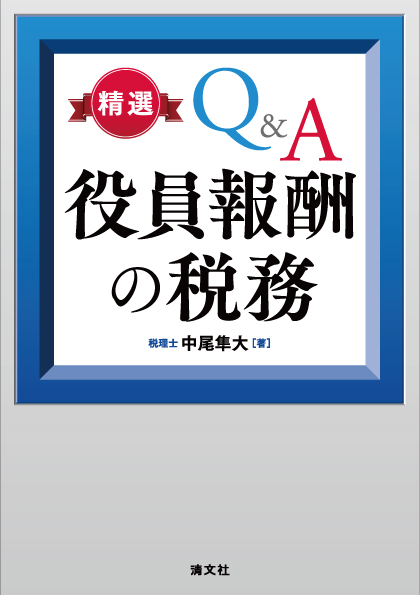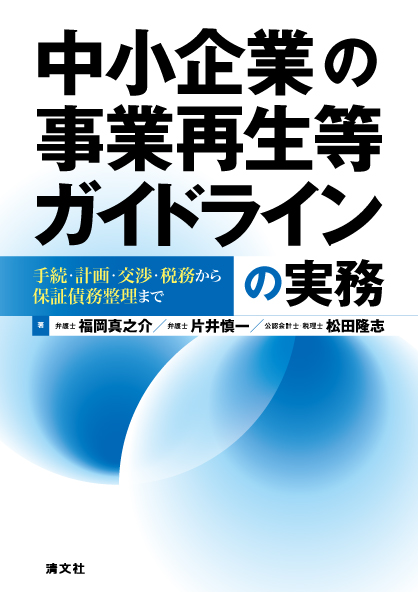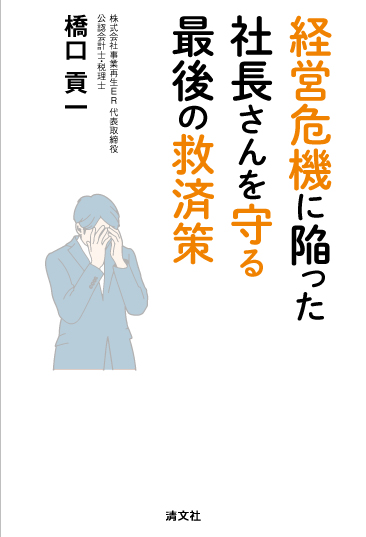社葬をめぐる税務上の留意点
【前編】
太陽グラントソントン税理士法人 マネジャー
税理士 川瀬 裕太
Ⅰ はじめに
中小企業などの創業者であり、代表取締役を長年務めていた方が亡くなったときは、その会社において「社葬」を執り行うことがある。
代表取締役の死亡によって、事業が健全に継承されるかということは、社内の方だけでなく、取引先などの社外の方にとっても関心が高く、社葬を行う態勢がきちんとしているかどうかで大きく評価が分かれるケースもある。
このように、社葬は会社にとっても重要なものであるが、本稿では税務上どういったところに留意すべきかについて確認していきたい。
Ⅱ 社葬費用の法人税法上の取扱い
1 法人税法上の取扱い
社葬費用について、法人税法上は、次のように取り扱うこととされている。
法人が、その役員又は使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができるものとする(法基通9-7-19)。
当該通達の適用に当たっては、①社葬を行うことが社会通念上相当であるかどうか、及び、②負担した金額が社葬のために通常要すると認められる金額であるかどうか、ということがポイントとなる。
① 社葬を行うことが社会通念上相当であるかどうか
「社葬を行うことが社会通念上相当であるかどうか」は、死亡した役員等の死亡の事情、生前における法人に対する貢献度合等を総合勘案して判断することになる。
会社の創業者社長が亡くなった場合であれば、職務上の地位、会社への貢献度合を考慮すれば、社会通念上相当と認められる場合に該当すると考えられる。中小企業では、親族を役員としているケースもあるが、名前だけの役員の場合には、会社への貢献度合という点で社葬を行う十分な理由がないこともあるため、留意が必要である。
一方で、一般社員が業務外の事由で亡くなった場合であれば、職務上の地位や会社への貢献度合という点から、社葬までは行わないのが一般的である。ただし、建築現場での作業中の事故、海外出張の際の飛行機事故など業務上の死亡の場合には、職務上の地位や会社への貢献度合に関わらず、社葬を行うのに十分な理由があることから、社会通念上相当と認められる場合に該当する余地があると考えられる。
② 負担した金額が社葬のために通常要すると認められる金額であるかどうか
「社葬のために通常要すると認められる費用」とは、通常は、会葬のための費用が該当し、密葬の費用、墓石、仏壇、位牌等の費用、院号を受けるための費用など個人が負担すべきであると認められる費用は、これには該当しない。
社葬のために通常要すると認められるものとしては、下記のような費用が該当すると考えられる。
- 社葬の通知や広告のための費用
- 葬儀場、駐車場の使用料
- 祭壇、祭具の使用料
- 供花、供物、花輪の費用
- 屋外設備(受付用テント、照明器具など)の使用料
- 読経料
- 配車費用(遺骨、遺族、御来賓の送迎)
- 警備関係の費用(交通整理、式場内の警備)
- 会葬者への礼状、会葬礼品の費用
- 会場での飲食費
2 合同葬
個人と会社が合同で行うものや、関連会社が共同で社葬を行うような「合同葬」という葬儀の形式がある。
この場合に、税務上留意すべき点は、費用の分担である。
個人と会社が合同で行った場合には、親族などに係る分を区分して計算根拠を作成しておくことが必要と思われる。関連会社が共同で社葬を行う場合には、単に関連会社であるという理由だけで費用の分担がなされるときは、本来負担しなければならない会社に対する寄付金とみなされるケースもあるため、各関連会社にとって社葬を行うだけの十分な理由があるかどうかを検討する必要がある。
3 代表的な判決・裁決
上記で述べた事項に関する代表的な判決・裁決の事例を紹介しよう。
① 香典返しが社葬費用に当たらないとした事例
社葬に要した費用を損金に算入したことは相当と認められるが、引物は、元来香典の返戻と解されるものであるので、これに要した費用は、個人が負担すべきであるから、これを社葬に要した費用に含めて会社の損金に算入することは相当ではないとされている(昭和50年10月16日裁決)。
② 「おとき」が社葬費用に当たらないとした事例
社葬のために通常要すると認められる金額には、故人の遺族の負担すべき費用は含まれず、通常は、会葬のための費用がここでいう社葬のため通常要すると認められる費用に当たるものと解するのが相当であり、葬儀の後に場所をホテルに移して行われた「おとき」(参列者に食事を提供する仏事)については、故人の追善供養のため行われたものと認められるから、この費用は会葬のための費用ということはできず、得意先、仕入先等取引関係者に対する分は交際費とし、親族などの分は役員賞与に該当するとされた事例がある(昭和60年2月27日裁決)。
③ 業務上の事故により死亡した役員につき、実際に社葬を行わないとしても、弔意を示すために葬儀費用の一部を相当な金額の範囲内で負担することは社会通念に照らして自然であるとされた事例
葬儀費用については、法人の役員等の死亡によってその費用を負担した場合、社葬とすることが社会通念上相当と認められるときに、社葬のために通常要する金額の限度で損金算入が認められているところ、当該事例では、社葬を行っていないけれども業務上の死亡であることを考慮すると、葬儀費用を一部負担することにより弔意を示すことは社会通念上相当と認められる。
したがって、役員退職給与の過大額の認定に当たり、役員退職給与の算定基準の中で葬儀費用の趣旨として100万円を加算することは相当であるとされた事例がある(平成10年4月7日仙台高裁)。
〔凡例〕
相法・・・相続税法
相基通・・・相続税基本通達
法基通・・・法人税基本通達
所基通・・・所得税基本通達
(例)相法13①二・・・相続税法13条1項2号
(【後編】(12/21公開)に続く。)