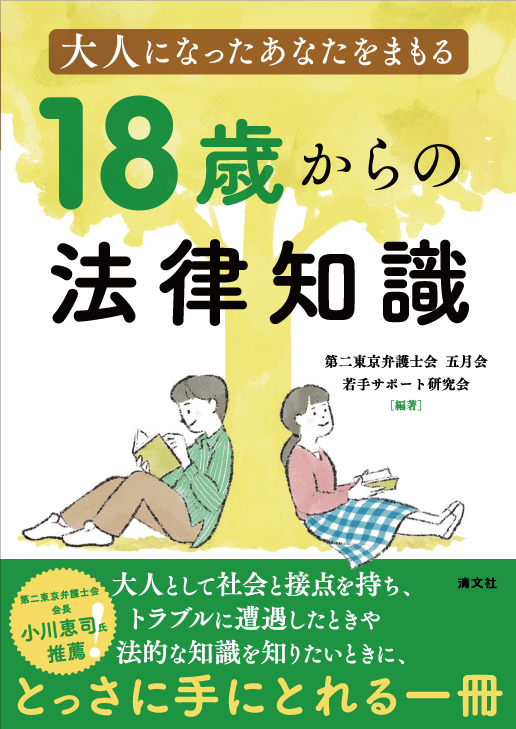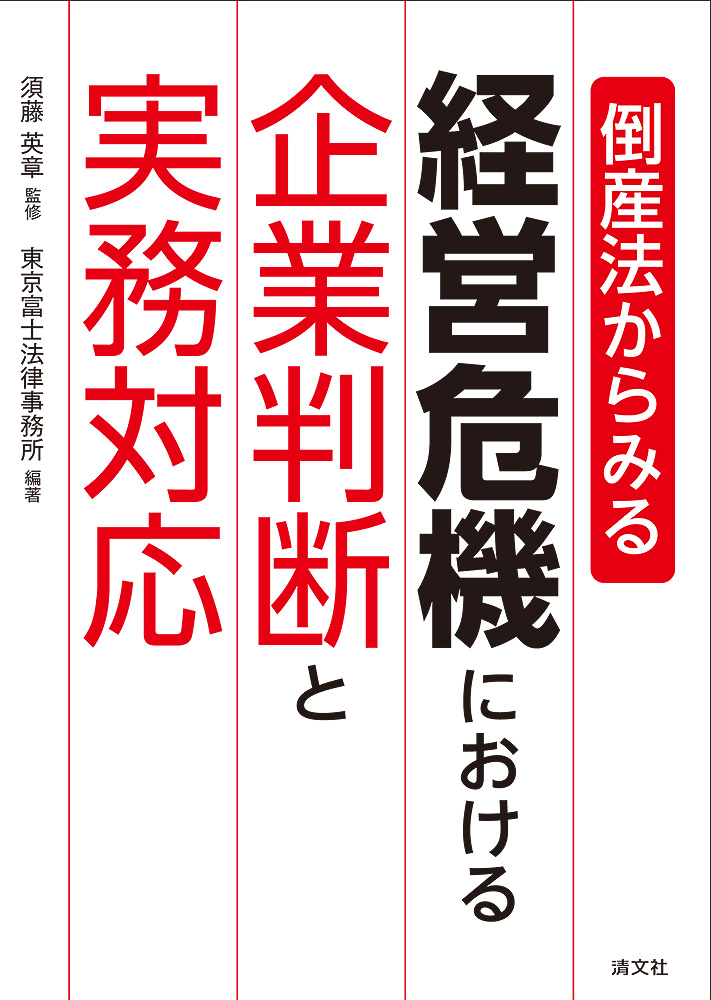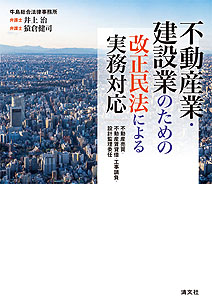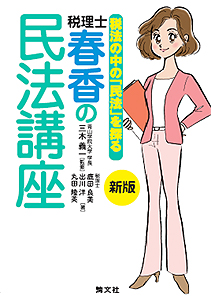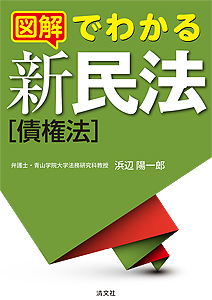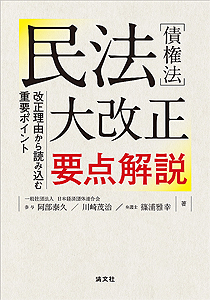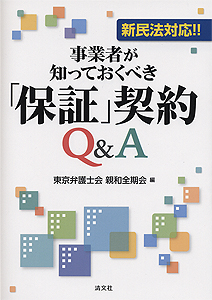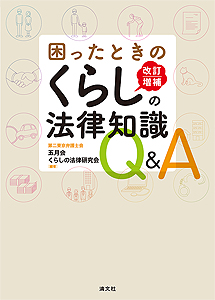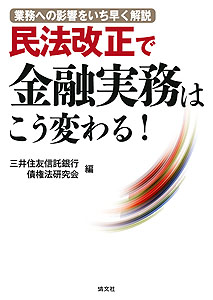民法改正(中間試案)
─ここが気になる!─
【第1回】
「保証人保護(1)」
弁護士 中西 和幸
連載にあたって
平成25年2月26日、民法(債権関係)の改正に関する中間試案が法務省から公表され、6月17日までのパブリック・コメント手続に付されている。
この債権法改正については、まず改正そのものの手続について問題がないとはいえず、また、改正内容も、これまで積み重ねられてきた取引や裁判の実務が変更を余儀なくされるなど、多大なる影響を及ぼす可能性があるため、その社会的影響が大きいといえる。そのため、慎重な対応が必要である。
そして、慎重な対応をするためには、まずは中間試案の内容を把握しなければならない。
ところが、債権法改正の範囲は広範囲にわたっており、そのすべてを把握することは大変である。
そこで本連載では、各種ビジネス法務の経験から、実務上中間試案の内容を把握しておきたい論点についてピックアップし、コンパクトに解説したい。
1 はじめに
民法改正については、一定の範囲で弱者保護の観点も盛り込まれている。その最も著名なものの1つが、個人保証契約の制限についてである。
民法改正は中間試案の段階であり、その中で個人保証の制限については、「引き続き検討する」とされており、最終的に民法改正案に盛り込まれるかどうか定かではない。しかし、日本経済新聞に特集が掲載されるなど、その関心は高いことがうかがわれる。
そこで、今回は、個人保証の制限について解説する。
2 個人保証の制限の概要
(1) 対象となる個人
対象となる個人は、自然人を意味し、法人は除かれる。そして、いわゆる経営者は、かかる個人から除かれる。
もともと、制度趣旨が「個人の保証人が必ずしも想定していなかった多額の保証債務の履行を求められ,生活の破綻に追い込まれるような事例が後を絶たないこと」にあるところ、経営者自身は、自らの事業が不振になれば保証債務の履行を求められることは理解しているし、また、当該事業からは配当や役員報酬が得られるため、保証債務を負担させても不都合とはいえないからと解される。
(2) 対象となる取引
個人保証の制限が課される取引は、
① 金銭消費貸借及び手形割引を主債務とする取引にかかる根保証に対する個人保証(銀行等金融機関からの借入れ等を想定しているようである)
② 貸金等債務を主たる債務とする個人保証(①と主たる債務は同じであるが、根保証契約に限定していない点が異なる)
のどちらかを選択することとされている。
いずれも、貸金以外の取引に伴う連帯保証契約(例えば、売買契約等の代金支払に関する連帯保証等)については適用されないことになる。
3 無保証取引の現況
(1) 保証人の機能
個人保証が制限された場合、不動産等の有力な担保となる資産を有しない経営者は、企業や事業拡張、日々の資金繰りの目的で融資を受ける際、苦労することになることが予想されるが、現行法下でもその点は変わらない。
個人による保証につき制限がない現行法下では、以下のようになる。
保証人がいない場合、事業者だけの信用力により融資の可否が決まることになる。そのため、担保に提供する有力な資産がなければ、おのずから融資審査のハードルは高く、また、審査に通ったとしても、融資額が抑えられてしまう。
しかし、保証人がいれば、事業者だけでなく、保証人の信用力も加えて金融機関に対して融資を申し込むことになり、事業者と保証人の資産状況や返済能力次第で融資の可否、融資額や融資条件が決定されることになる。そのため、審査は通りやすくなり、また融資額も引き上げられることになる。
金融機関の立場からみると、保証人は回収リスクを回避・低減させる極めて有効な手段である。したがって、これを制限することは、回収リスクが増加することになるため、金融機関としては、リスクの高い融資を拒否したり、融資に応じるとしても融資金額や金利、また返済条件等を厳しくせざるを得ないことが考えられる。
(2) 各種無担保・無保証融資の現状
① 創業者支援融資
まず、創業者・起業者の中には、資産も保証人も準備できないことが少なくなく、これに対応するため、新創業融資制度(日本政策金融公庫)や起業挑戦支援無担保無保証貸出制度(商工中金)などの政府系金融機関による融資制度や、民間金融機関による融資などがある。
こうした制度は、起業前や起業後一定の期間内の融資に限られるため、利用できる事業者が限られている。
② 通常期の無担保・無保証融資
創業者・起業者に限られない無担保・無保証融資もあるが、政府系金融機関や民間金融機関は、融資審査が厳しいことが予想される。
また、ノンバンクは融資審査が比較的厳しくはないが、金利が高いため、よほど短期に資金が準備できるなどの特殊事情がない限り、利用を控えた方がよいであろう。
③ 無担保・無保証の審査対応
無担保・無保証の融資審査を受けるためには、金融機関の立場に立てば、担保や保証がないまま融資をしても返済される可能性が高いと信用できることが必要である。すなわち、事業遂行による借入金の返済が合理的かつ無理のないことを金融機関に説明して説得しなければならないのである。
しかし、金融機関を納得させるような事業計画を作成することについては、得意ではない経営者が多いものと予想される。こうした事業計画を作成するため、費用はかかるが専門家に依頼することも検討した方がよいであろう※。
※ 専門家を探す方法の1つとして、経営革新等支援機関を利用することが考えられる。
以上のことは、個人保証が認められている現行法の下でも有効な方法であるので、検討していただきたい。
4 個人保証が禁止されると
個人による保証の禁止により、確かに、保証人の予想外の生活破綻を避けることはできるかもしれない。その一方で、中小企業等や新規事業の創業者が融資を受けることが困難となり、経済の活性化が妨げられることにもなりかねないというデメリットがある。
すなわち、個人保証が禁止されると、金融機関の融資審査体制及び審査基準が現在の無保証融資のように厳しくなる可能性がある。
一方、金融機関としても、個人保証に頼らない融資商品の開発等が必要になり、また、個人保証に頼らない融資審査体制の構築が必要になろう。
しかし、単に融資商品の開発や審査体制の構築といっても、現在の融資商品や審査体制は、長年の経験や蓄積に基づいて構築・開発されているものであり、日本では、保証人のない融資についての経験やノウハウが豊富に蓄積されているとは言い難いように思われる。
そのため、もし、個人保証を禁止したとしても、円滑な融資取引が定着するためには、相当程度の長い期間が必要ではなかろうか。
5 まとめ
このように、個人保証の禁止といっても、実現するためには、事業者と金融機関を巻き込んだビジネス全体に影響することが予想される。
明治以来長年にわたって利用され定着してきた保証人制度は、確かに、保証人の予想外の生活破綻という悲劇を招いてきたというデメリットはある。その一方で、事業者の創業や事業継続に一定の役割を果たしてきたというメリットも見逃せない。とりわけ、過酷な取立てや高金利等については、現在、貸金業法の度重なる改正によりある程度抑えられている。
保証人の悲劇について、従前のような個別の対応により抑制するのか、それとも個人の保証人を一律禁止することがよいのか、今後の議論の要点ではなかろうか。
「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」
本稿はあくまでも筆者の個人的見解に基づくものであり、筆者の所属する法律事務所の意見を代表するものではない。
また、本稿は、実務的な視点からより分かりやすく解説するため、表現等において若干正確さを欠く可能性があることに留意されたい。
また、筆者は、必ずしも民法改正に賛成するものではなく、また、民法改正については、必ずしも社会一般に広く賛同が得られている法改正ではないことにも留意されたい。
(了)
「民法改正(中間試案)―ここが気になる!」は、毎月第2週・4週に掲載します。