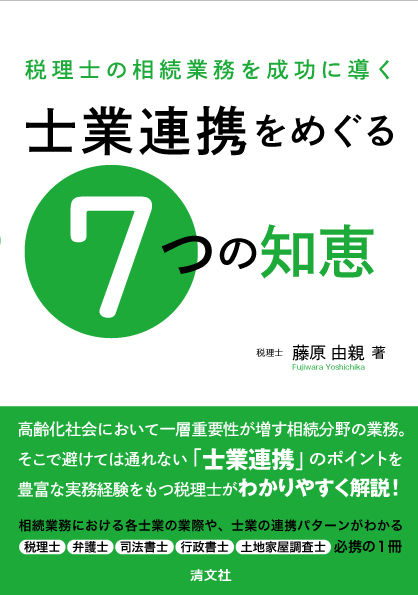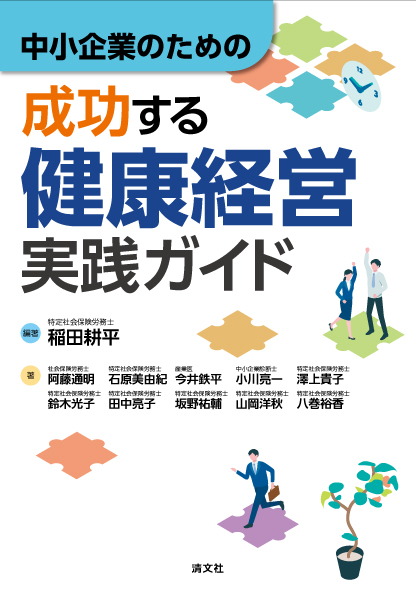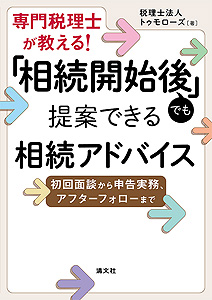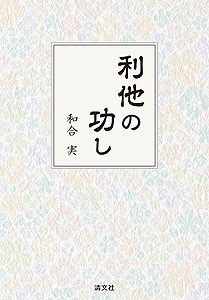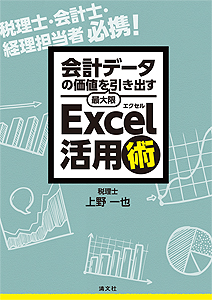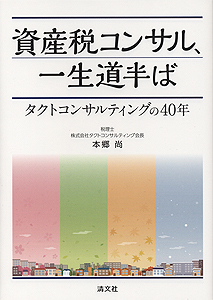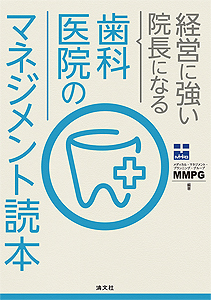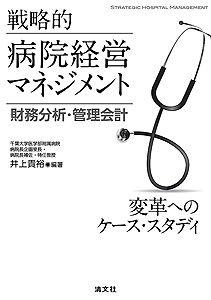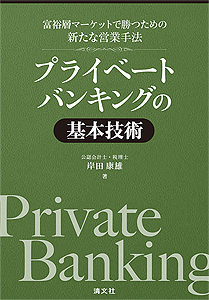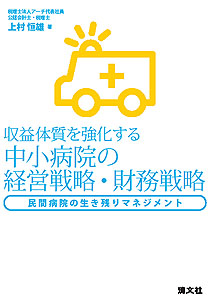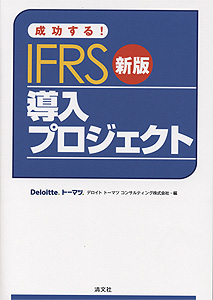起業家が求める税理士の役割、
税理士が求める経営者の姿勢
【上】
「アーリーステージにおける税理士の役割」
株式会社クロスフィールド 取締役
税理士法人あおやま 代表社員
公認会計士・税理士 松元 良範
はじめに
会社のアーリーステージ(起業準備から起業を経て2、3年程度)の方々をサポートする機会が多いが、そのアーリーステージの過ごし方で、その後の会社の発展もしくは存続可能性が概ね決まってくると言っても過言ではない。
実際、創業して10年後に残っている会社は、ほんの数%にすぎない。
また、アーリーステージにおける経営者の経営スタンスは、自ずと対税理士との関係においても表れてくるものである。
そこで、税理士との人間関係を通して普段接しているアーリーステージの経営者の方々を考察し、我々税理士には何ができるのか、どうあるべきかについて考えてみたい。
1 起業準備段階での税理士の役割とは
これから起業しようとする方々から多く寄せられる質問の1つとして、例えば、個人事業が良いのか会社形態が良いのか、そして会社の場合どのような会社形態がいいのか、といった質問がある。
しかし、これに対応する普遍的な解答はない。
例えば、従来の得意先と独立起業後も取引を継続するために会社形態であることが条件とされる場合には、個人の戦略や嗜好とは別に、否応にも会社形態にしなければ事業がスタートできない場合もある。また、以前から付き合いのあるビジネス上のパートナーと一緒に起業する場合には、必然的に個人ではなく会社形態にするのが通常であろう。
そして、特段そういった事情がない場合には、個人と会社とで税務上どちらが有利なのか、といった点に着目する方々が大半である。
とかく起業する前においても節税の観点から事を考えがちではあるが、節税は利益あってこその話である。そもそも利益が出なければ、そのようなことを考えても全く意味がない。
利益が出なければ、そもそも事業を継続することができないのだ。
まずは、利益を出せる事業構想であるのか、自分はそれを実現できるだけのアイデア、経験、スキル、人脈等を果たして持っているのか、これについてまず自問自答してほしいと常々考える。
税理士の立場からすると、多くの方々が起業し、我々の顧問先になっていただき、共に成長していくのはこの上ない喜びである。
しかし、起業したものの、数年ですぐ行き詰まる会社が実に多い。うまくいかない典型的なパターンは、これまで自分が全く経験していない領域で事業を起こす場合である。
つまり、素晴らしいアイデアこそあるものの、それを実現するための具体的なプランがない。
このようなケースで、我々税理士として彼らをサポートできることは一体何であろうか。
彼らがこれから始めようとするビジネスそのものについては、我々も門外漢であることは間違いない。しかし、何もできないわけではない。
まずは、経営者には事業で収益を上げることに専念してもらい、その他もろもろのバックオフィス業務については我々が一手に引き受けることである。しかし、これは至極当たり前のことであり、これだけでは十分ではない。
もう一歩踏み込んで、彼らのサービスや商品に対して、買う側の立場だとしたらどう思うのか、どう感じるのかを、素人の観点、しかし客観的な観点から意見を述べることはできるだろう。
経営者はなかなか第三者の意見を聞く機会が少ない。創業時から事情を知っている我々税理士は、経営者に対して客観的な意見を消費者と同じ立場から物申すことができる数少ない立場の人間であり、経営者からみても単なる帳簿付け、申告書作成をお願いしているだけでなく、そういった役割を期待しているはずである。
経営者と税理士は単に税金の話だけではなく、ビジネスそのものについても議論できる関係になってこそ、お互いに成長できるのだと思う。
2 経営者と対立する場面で必要なこと
しばしば一般の会社において、営業と経理部とが対立する場面を見かける。
営業は、第一に売上を上げることが本来の仕事である。一方、経理部は会社の帳簿に会社の取引の実態を適切に反映すること、そのために、現場から正確な情報を入手することが仕事である。この役割分担が、時として対立関係に発展する。
例えば売掛金の額と入金額とが違う場合、経理の立場からすると、この差の原因が分からなければ会計処理ができない。営業に問い合わせると、「得意先に問い合わせるのが面倒だし、大した差ではないから適当に処理してくれ」と要望されてしまう。
あるいは、相手の会社名や参加した人数が書かれていない飲み代の領収書が営業から経理へ提出される。経理では交際費なのか会議費なの判断がつかない。そこで営業に問い合わせると、「いちいち細かいことを聞いてくる」と不満を言われる。
営業からすると、「経理の依頼ばかり聞いていると管理業務ばかり増えて営業に専念できない」「誰が稼いで会社を支えていると思っているのか」などと、怒鳴り合いの関係になってしまう。
税理士と顧問先との間においても、記帳業務を請け負っている場合には、同じような関係になる場合がある。
顧問先から請求書や領収書を預かって、税理士の方で記帳するのだが、顧問先からいただく資料だけでは、会計処理に必要な情報が不足している場合が往々にしてある。
そこで、顧問先に問い合わせると、「そんな細かいこと覚えてないから適当にやってくれ、忙しい中、資料をそろえて渡しているんだ、それでも不満があるのか」と。
「それも含めて税理士にお願いしているのだ」と。
このような経営者の中には、実は着々と売上を上げている方々が多い。ある意味、立派な経営者である。しかし、経理の重要性についての認識が足りない。
このような場合には、会計処理の重要性、そして現場からの情報の必要性について理解してもらうよう税理士も努力しなければならない。社内で管理業務を行ってくれる事務職員を雇えれば、その社員に整理をしてもらえば良いかもしれない。しかし、そこまでの余裕がない場合には、経営者を説得してそこはきちんとやってもらうように指導しなければならない。
ただし、単に、「お願いします」ではなく、やはりここでも経営者の立場になって考える必要がある。
資料整理はとても大変な作業である。経営者にとって最低限の労力で済み、かつ、記帳する上でも必要最低限の情報をいただくための工夫を、経営者と一緒に議論すべきである。
税理士が単に請負作業者として仕事をしているのでは、会社にとっても良くないのだ。
(了)