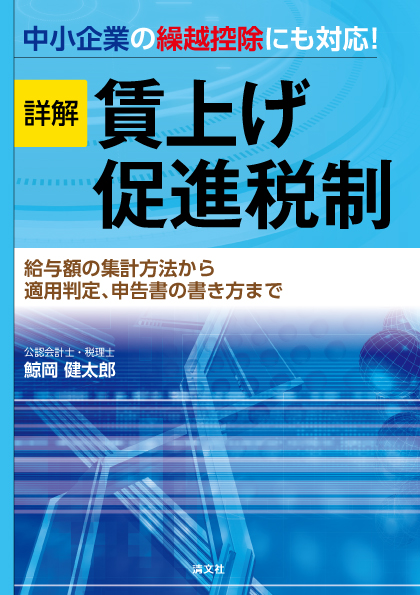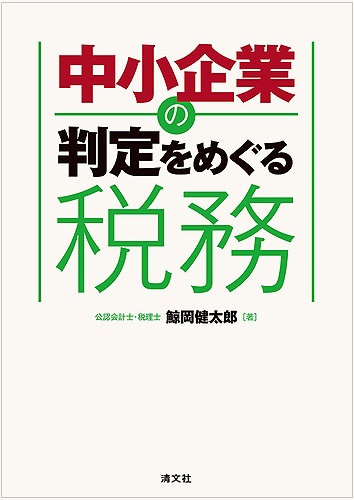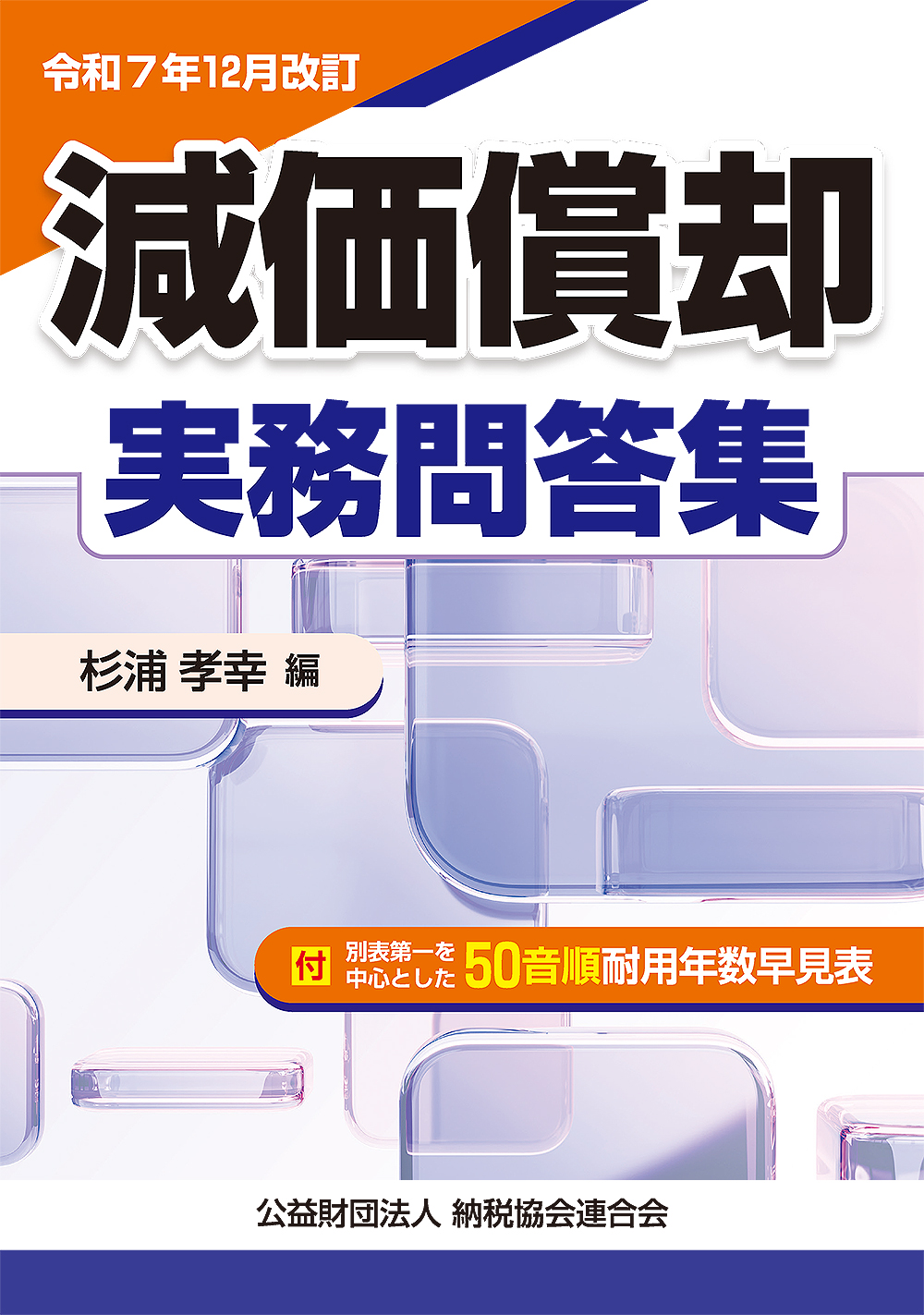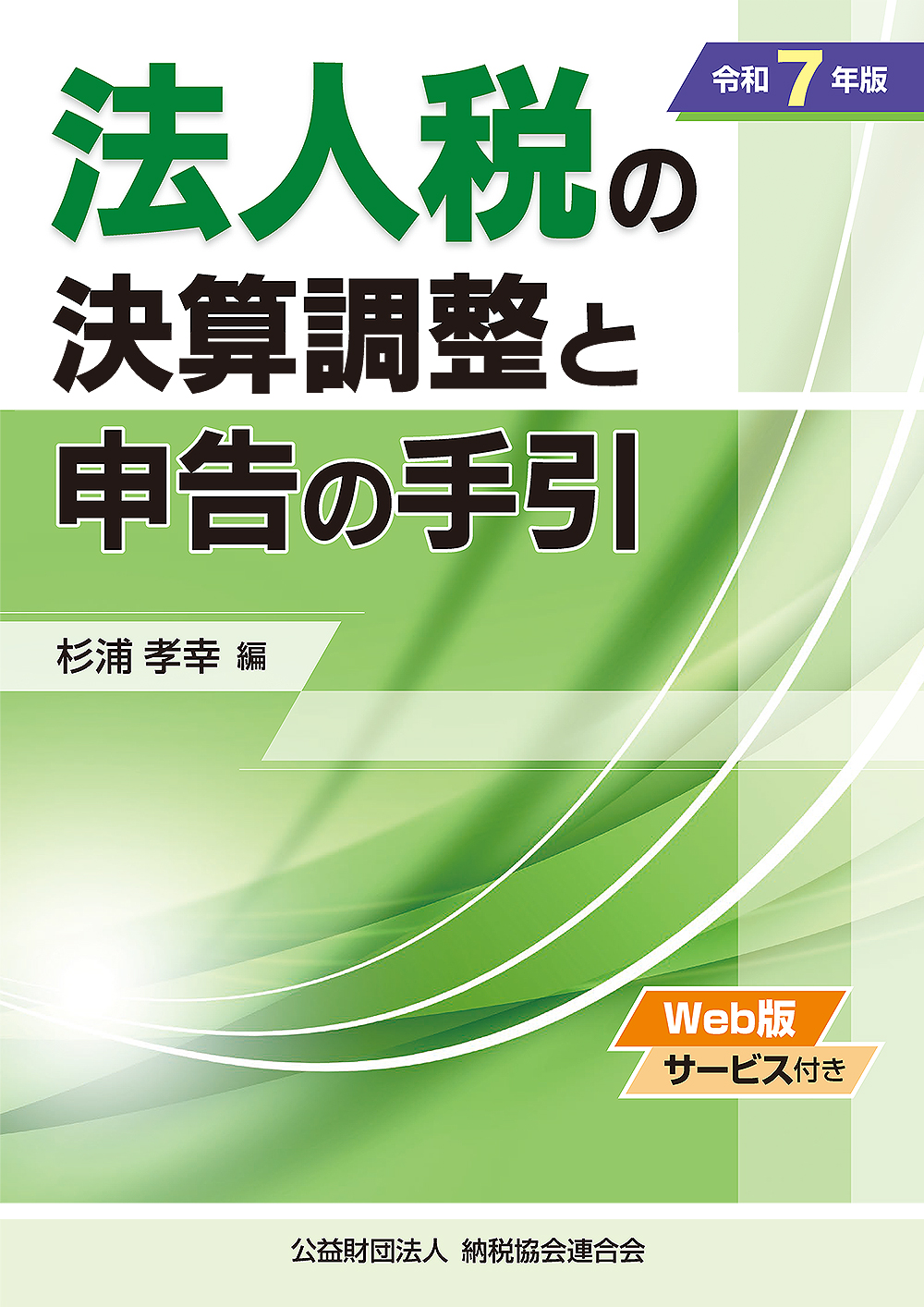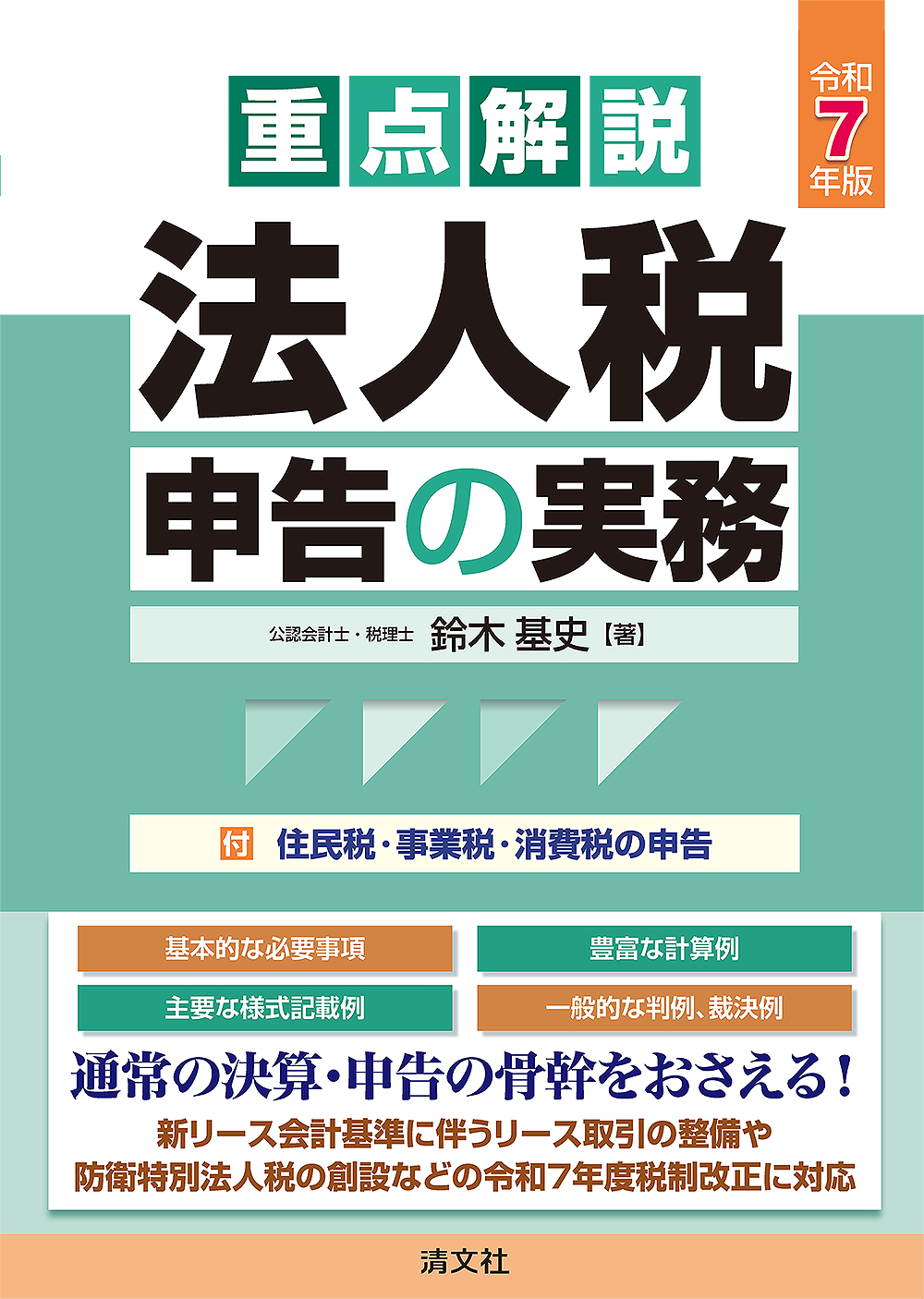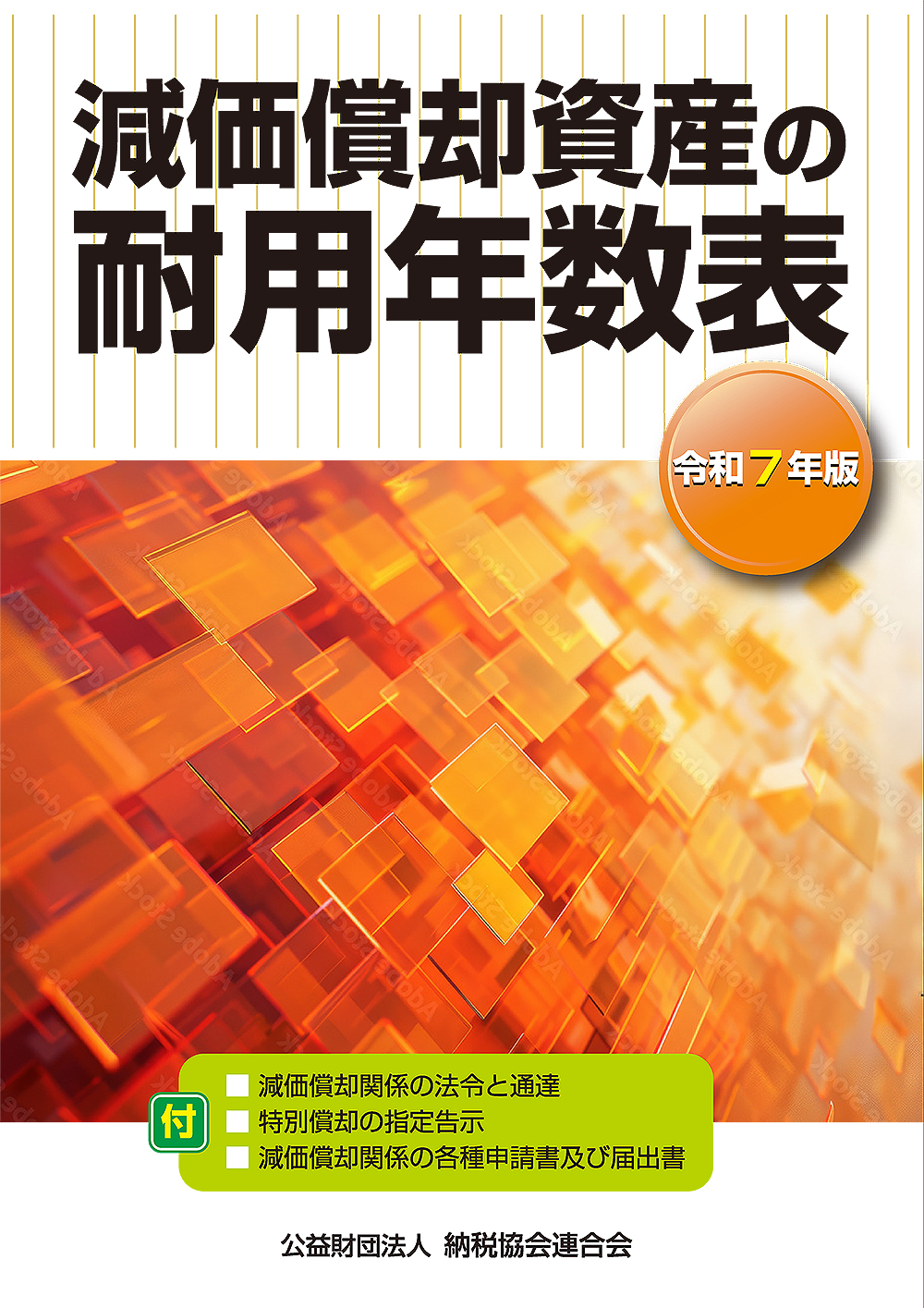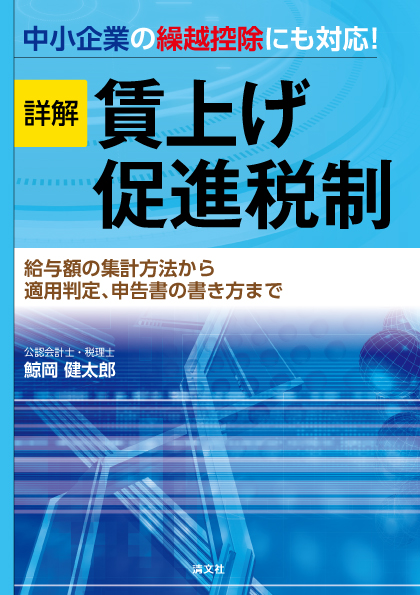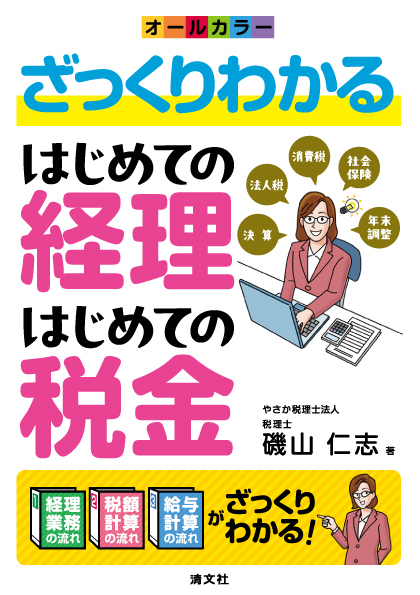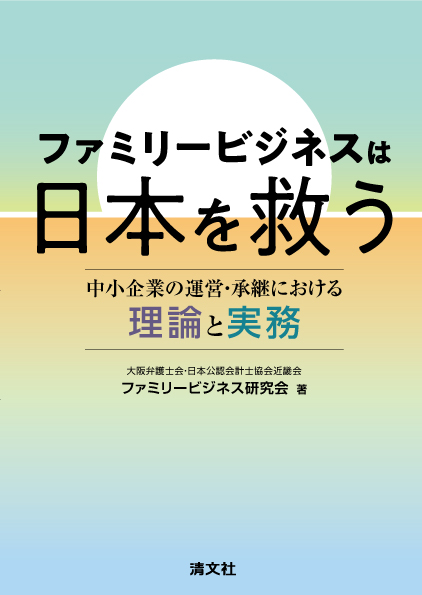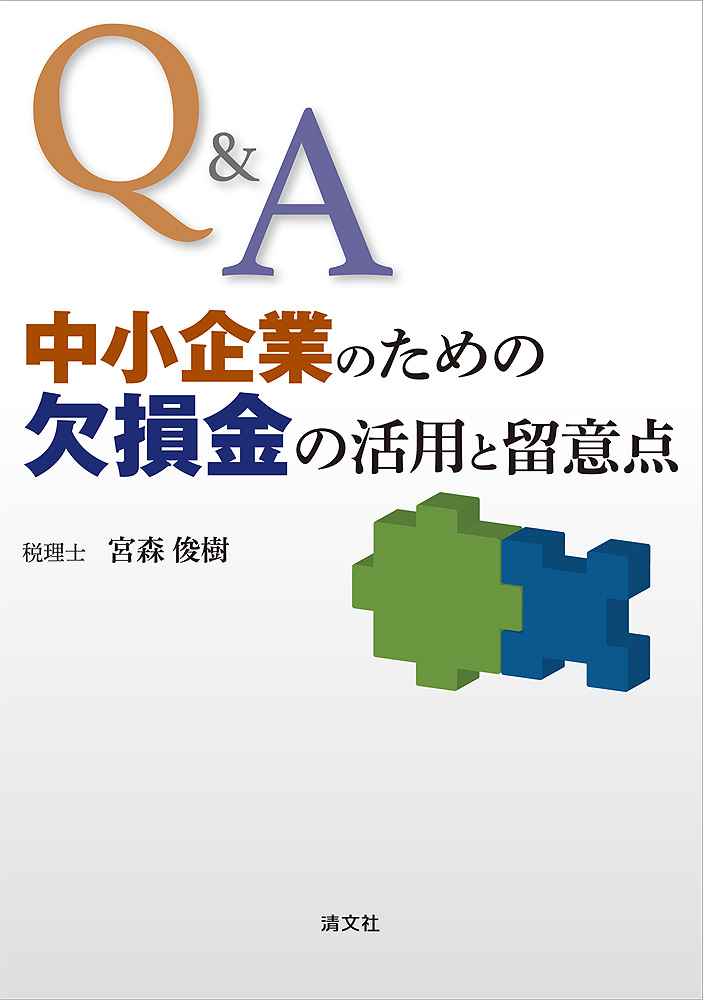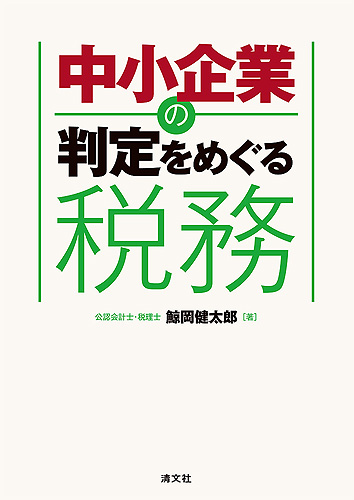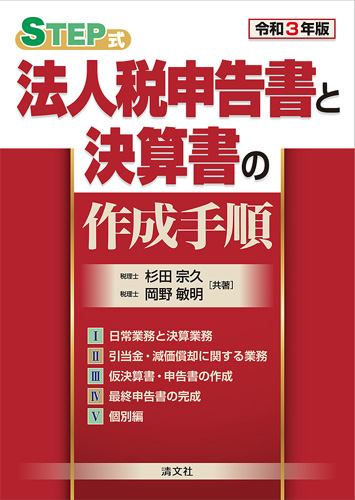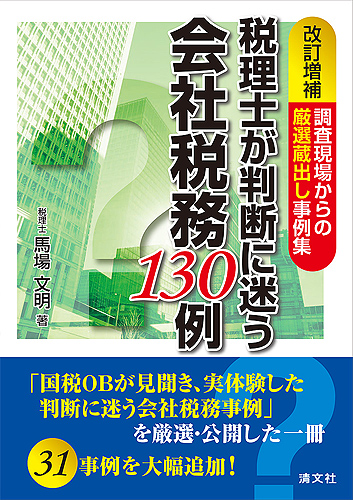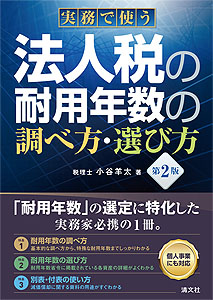令和元年度(平成31年度)税制改正における
「みなし大企業」の範囲の見直しについて
【第1回】
「令和元年度税制改正前の規定と問題点」
公認会計士・税理士 鯨岡 健太郎
1 はじめに
現在、法人税に関する租税特別措置として「中小企業者」を対象とした措置がいくつか講じられている(※)。この「中小企業者」という用語は、法人税法における「中小法人」の範囲とは若干異なるもので、租税特別措置法固有のものである。
(※) 中小企業者向けの租税特別措置としては、以下の制度がある。
・中小企業技術基盤強化税制(研究開発税制。措法42の4③~⑤)
・高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除(措法42の5①②)
・中小企業投資促進税制(措法42の6①②)
・地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は税額控除(措法42の11の3①②)
・特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額控除(措法42の12の3①②)
・中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除(措法42の12の4①②)
・給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除制度(措法42の12の5②③十二)
・法人税の額から控除される特別控除額の特例(措法42の13⑥)
・被災代替資産等の特別償却(措法43の3①②)
・特定地域における工業用機械等の特別償却(措法45②表四)
・中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(措法67の5①)
・被災代替資産等の特別償却(震災特例法18①)
・再投資等準備金制度(震災特例法18の3①)
この点に関し、令和元年度税制改正において、中小企業者の範囲から除外される「みなし大企業」の範囲について改正が行われ、法人税法における「みなし大企業」の範囲との整合性が図られた。
そこで本稿では、令和元年度税制改正における「みなし大企業」の範囲の改正内容について説明を加える。
なお文中、意見にわたる部分は筆者の私見であることをあらかじめ申し添える。
2 「中小企業者」及び「みなし大企業」の意義(令和元年度税制改正前)
「中小企業者」とは、資本金額(出資金額)が1億円以下の法人のうち「みなし大企業」以外の法人、又は資本(出資)を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人をいう(旧措令27の4⑫)。
ここで「みなし大企業」とは、資本金額(出資金額)が1億円以下の法人のうち、以下のいずれかに該当する法人をいい、一定の租税特別措置の対象とされる中小企業者の範囲から除外されることとなる。
◆その発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上が同一の「大規模法人」の所有に属している法人
◆その発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上が(複数の)「大規模法人」の所有に属している法人
また「大規模法人」とは、以下のいずれかに該当する法人をいう。
➤資本金額(出資金額)が1億円を超える法人
➤資本(出資)を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人
これらをまとめると、下図のようになる。
3 法人税法における「みなし大企業」の範囲
租税特別措置法における「みなし大企業」とは別に、法人税法においても「みなし大企業」の概念は存在する。すなわち、法人税法における「中小法人等」の範囲を定義する上で、「みなし大企業」に該当するものを除くこととされているのである(法法57⑪一)。
法人税法における「みなし大企業」の範囲は以下の通りである(法法66⑥二・三)。
◆大法人(注1)との間に当該大法人による完全支配関係がある普通法人
◆普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式及び出資の全部を当該全ての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合において当該いずれか一の法人と当該普通法人との間に当該いずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときの当該普通法人(注2)
(注1) 「大法人」とは、以下に掲げる法人をいう。
・資本金額(出資金額)が5億円以上である法人
・相互会社
・受託法人(法人課税信託の受益者である一定の法人)
(注2) 要するに、100%グループ内の複数の大法人に発行済株式(出資)の全部を保有されている普通法人、ということである。
4 改正前の問題点
上述のように、中小企業者の範囲から除外される「みなし大企業」の判定基礎となる「大規模法人」は、資本金額(出資金額)が1億円超の法人か、資本(出資)のない法人のうち常時使用従業員数1,000人超の法人のいずれかに該当する法人ということになるが、当該大規模法人との間に完全支配関係のある法人は含まれていなかった。
そのため例えば、「大規模法人」の100%子会社の資本金を1億円以下とすれば、当該子会社は「みなし大企業」となるものの「大規模法人」には該当しないこととなるから、当該子会社以下の100%子会社(大規模法人から見れば孫会社以下)は再び「中小企業者」に該当してしまう状況にあった。
このように、「大規模法人」と「大法人」の定義が異なる結果、大規模法人の孫会社以下の法人について、租税特別措置法上は「みなし大企業」に該当しないが、法人税法上の「みなし大企業」に該当する、という不整合が生じていた(下図参照)。
また、租税特別措置法における「大規模法人」が資本金額(出資金額)1億円超の法人を対象としているのに対し、法人税法における「大法人」は資本金額(出資金額)5億円以上の法人を対象としていることから、親会社の資本金が1億円超5億円未満の場合、その100%子会社(資本金1億円以下)は、租税特別措置法上は「みなし大企業」に該当するが、法人税法上の「みなし大企業」には該当しない、という不整合も生じていた(下図参照)。
〔凡例〕
法法・・・法人税法
措法・・・租税特別措置法
措令・・・租税特別措置法施行令
震災特例法・・・東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
(例)措法42の12の5③十二・・・租税特別措置法第42条の12の5第3項第12号
(了)
次回は8月29日に掲載します。