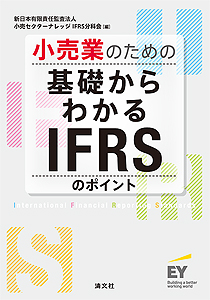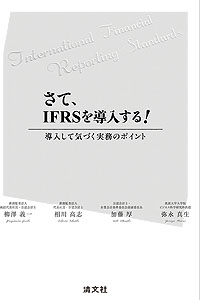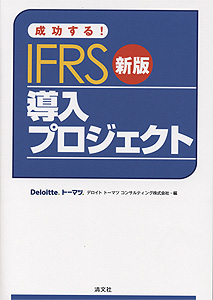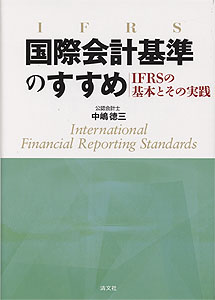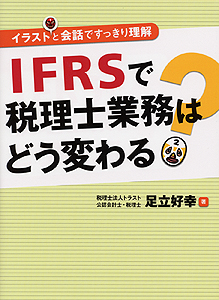IFRSは今、どうなっているのか?
【前編】
公認会計士 乾 隆一
2012年10月2日(火)、4ヶ月ぶりに金融庁13階共用第1特別会議室にIFRS関係者が集まった。日本でのIFRS適用に関して議論している企業会計審議会総会・企画調整部会合同会議が開催されたからだ。
2012年7月。IFRSに関して大きな2つの発表があった。
まず7月2日、金融庁が「国際会計基準(IFRS)への対応のあり方についてのこれまでの議論(中間的論点整理)」(以下、「中間的論点整理」)を公表した。
そして7月13日、SEC(米国証券取引委員会)が、「Work Plan for the Consideration of Incorporating International Financial Reporting Standards into the Financial Reporting System for U.S. Issuers(スタッフによる最終報告)」(以下、「スタッフ最終報告」)を公表した。
これらの公表から3ヶ月。その間に、金融担当大臣は2回交代した。
しかし、10月2日の会議では目新しいことはなく、IASBの現在の状況報告などがメインであった。
では、IFRSはどのように進んでいくのであろうか。
2009年6月。企業会計審議会は、「我が国における国際会計基準の取扱いについて(中間報告)」(以下、「中間報告」)を公表した。この中で、2010年3月期から一定の条件を満たした上場企業へのIFRS適用が認められた。また、2012年を目途として、IFRSの強制適用の判断を下すことになった。
そして、この「中間報告」を受け、2010年3月期にIFRSによる開示第1号の企業が出た。日本電波工業である。翌2011年3月期からは、HOYA、住友商事がIFRSを適用し始めた。2012年3月期からも2社。2013年3月からは4社がIFRSを適用する予定になっている。
しかし、「中間報告」に明示された2012年を目途としたIFRS適用の判断は、どうやら2012年中にはなされそうにない。
そもそも、米国は2011年にIFRS適用の判断をする予定であった。その判断を受けて日本もIFRS適用の判断をするのではとも言われていた。しかし、米国の判断は延期されて今に至っている。しかも、2012年になっても判断は行われず、7月になってようやく、上記スタッフ最終報告が出されたにすぎない。スタッフ最終報告であるから、SECの最終報告ではない。
つまり、大統領選が終わり、次期政権が確定しない限り、米国におけるIFRS適用戦略は不透明であるとみられている。
そして、そんな米国を見て動いている日本。
2011年6月。自見金融担当大臣(当時)の政治主導の発言のもと始まった企業会計審議会総会・企画調整部会合同会議。ほぼ毎月会議が開催され、1年の議論の末、公表されたのが、冒頭の「中間的論点整理」である。
企業会計審議会は、過去、いくつもの中間報告と呼ばれる報告書を公表している。しかし、中間的論点整理という名称のついた報告書は初めてである。1年に及ぶ議論にもかかわらず、中間報告になるまで議論をまとめられず、とりあえず出された報告書、それが今回の「中間的論点整理」という印象を抱いてしまったのは、筆者だけであろうか。 【後編へ続く】
(了)