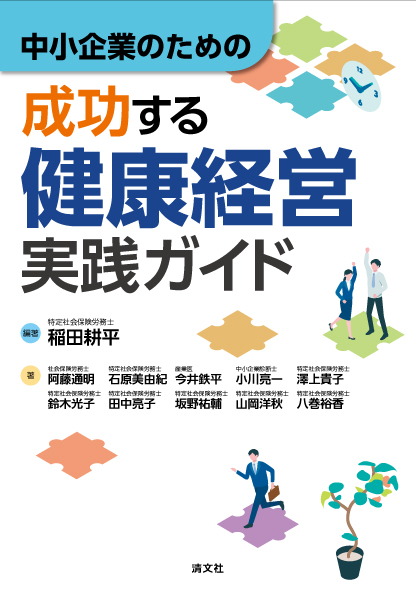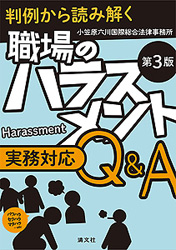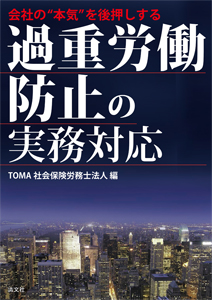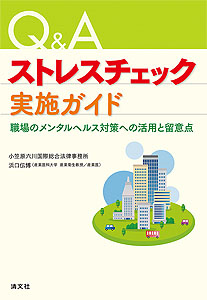パワーハラスメントの実態と対策
【第1回】
「職場で起きるハラスメント」
特定社会保険労務士 大東 恵子
〈はじめに〉
ここ数年、各方面から「ハラスメント」という言葉をよく耳にするようになった。
職場においては、「セクシャルハラスメント」「パワーハラスメント」「モラルハラスメント」「ジェンダーハラスメント」「アルコールハラスメント」など、多くのハラスメント行為が問題視されており、裁判にまで発展するケースも数多く報告されている。
21世紀職業財団が行った調査では、約5割の会社で「何らかのハラスメント行為が発生している」という結果が出ており、現在もなお増加傾向にあると言われている。また、その責任も、加害者だけではなく会社に対しても追及され、両者に対して損害賠償を命ずる判例も数多くある。
例えば、ある病院内で起きたパワハラに関する判例では、加害者に対して1,000万円、使用者である病院側に対しては500万円の損害賠償が命ぜられた(誠昇会北本共済病院事件,平16.9.24判決)。
このように、職場におけるハラスメントの問題は、決して対岸の火事では済まされない、身近でとても大きな問題となっている。
職場で起こるハラスメントには上記のとおりさまざまなものがあるが、以下では、「セクシャルハラスメント」と「パワーハラスメント」について整理したい。
〈セクシャルハラスメント〉
セクシャルハラスメント(セクハラ)とは、性的嫌がらせ・性的脅かしのことをいい、「相手方の意に反する性的な言動で、それに対する対応によって仕事を遂行する上で一定の不利益を与えたり、就業環境を悪化させたりすること」と定義される。
1999年には、男女雇用機会均等法が改正され、事業主にセクハラ防止の配慮義務が課された。2007年にはさらなる改正が行われ、セクハラの被害対象を女性のみから男性を含めた労働者全般にまで拡げ、事業主の義務もより強化された。セクハラの防止を就業規則に規定すること、情報の周知や相談窓口の設置が求められている。
このように法律で事業主の対応がしっかりと定められているので、実際に事件が起こり、その義務を果たしていなかった場合の責任は重い。
〈パワーハラスメント〉
パワーハラスメント(パワハラ)とは、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、義務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」と定義される(厚生労働省「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告(平成24年1月)」より)。
平成24年に厚生労働省が行った調査では、過去3年間に45.2%もの会社がパワハラに関する相談を受け、そのうちの70.8%に実際にパワハラに該当する事案があったと報告している。
このようにパワハラは、ハラスメントの中でも、近年急速に増加している問題の一となっている。
パワハラというのは、その性質上、上司や先輩など職場におけるなんらかのパワー(権力)を持つ者が「指導」や「叱責」と称して行うケースが圧倒的に多い。そのため、罵声や暴言など一見するととんでもないと思う行為も、指導や叱責という名の元に実態が隠れてしまい、気づいた時には大きな問題に発展してしまうケースも少なくない。
一方、「パワハラ」という言葉が広まったことにより、「ミスを指摘したり、注意しただけなのに、パワハラだと言われてしまい、指導がやりにくい」という現場の声も多くある。
このように職場におけるパワハラは増加傾向にあるにもかかわらず、その実態から線引きが難しく、とても扱いづらい問題である。
しかし、放っておくと職場環境は悪化し、仕事能率は落ち、業績は低迷する。結果的にこの「パワハラ」は損害賠償にまで発展してしまい、金銭だけでなく会社の評判までも失いかねない、大きなリスクのある問題なのである。
* * *
次回から、このパワハラに着目して、その実態を探っていきたい。
【参考文献】
岡田康子・稲尾和泉『パワーハラスメント』(2011年)日本経済新聞出版社
公益社団法人21世紀職業財団『職場のパワーハラスメント対策ハンドブック』(2013年)厚生労働省
笹山尚人『それ、パワハラです―何がアウトで、何がセーフか―』(2012年)光文社
山口厚『刑法入門』(2013年)岩波書店
涌井美知子『改訂 職場のいじめとパワハラ防止のヒント』(2010年)経営書院
(了)