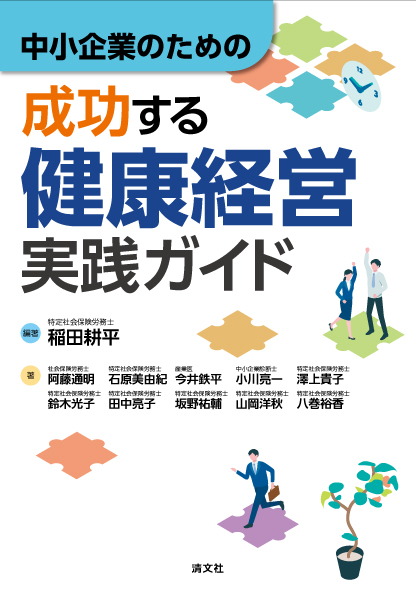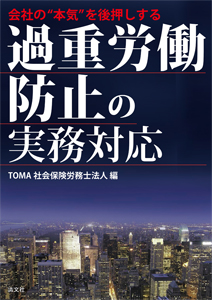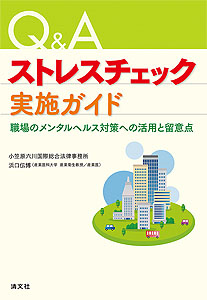介護事業所の労務問題
【第1回】
「介護事業所を取り巻く環境変化と労務管理」
クロスフィールズ人財研究所 代表
社会保険労務士 三浦 修
1 介護保険事業所を取り巻く環境変化
介護保険法は平成12年に施行されて以来、3年に一度の見直しが行われており、平成27年にも改正が予定されている。
今回の改正(平成27年4月)については、これまで以上の大改正となっており、介護事業者はどのような方向性で経営を行っていけばよいのかを慎重に検討をしなければならない。
介護保険法、介護報酬の改正について、主なテーマには以下のようなものがある。
◆介護職員処遇改善加算の要件が変更
◆デイサービスの報酬を類型化、新基準の地域密着
◆サービス提供体制強化加算の見直し
◆地域区分、区分支給限度額の見直し
◆同一建物減算、訪問介護、居宅の改定
◆運営推進会議の役割と外部評価
◆総合事業のガイドラインの内容と対策
◆地域密着型デイサービスへの移行対象が、利用定員18人以下の事業所に
◆自己負担2割への引上げ
◆お泊りデイサービスの届出と規制強化
◆特別養護老人ホームの要介護3以上の利用制限
このように、大きな変化を迎えようとしている中、これまでの福祉という観点からの介護事業所経営は厳しくなっていくのではないだろうか。介護保険法と介護報酬をしっかりと理解し、経営、マネジメント等を学んだ上で、今後はよりシビアに介護事業経営を行っていかなければ成り立たないのではないか、とさえ思える。
2 介護事業所の特徴
健全な介護事業経営を行う上で、重要なのは上記に加え、正しい労務管理と人事管理を行うことである。そのためにも、介護事業者自身とその中で働いている介護職員の特性を知ることが必要である。
以下、介護事業所特有の労務問題が起こる背景について紹介したい。
① 国の制度事業である
介護事業は、国の介護保険制度事業である。都道府県知事、または市町村より指定を受けて介護サービスを提供している介護事業者は、介護保険法上の基準(人員基準・運営基準・設備基準)を満たした上で事業の展開を行っている。
このような中、ジレンマになっていることの1つが、「介護職員に売上が見えにくい」という点である。介護職員にとって介護事業は、現場のサービス提供に加え、地域貢献・社会貢献という面から理解されること、また利用者、ご家族への想いが強いことなどから、事業としての売上が意識されることが少なく、経営者である介護事業者の考え方とズレが生じてしまうケースが多々ある。
② 女性が多い職場である
男性と女性の比率に関しては、どの介護事業所も女性が多い傾向にある。このような中、よく取り上げられる問題が「労働時間(特に深夜勤務)」「いじめ、嫌がらせ」「様々なハラスメント(セクハラ・パワハラなど)」などである。また女性が多いということと直接の関係性はないが、精神疾患が多いという特徴もある。
③ 資格者が優遇される
第2回で解説する「人員基準」に大きく影響するが、資格者が優遇される業界であることから、介護福祉士や看護師などの有資格者が多数就業している。しかしながら、協調性のない有資格者が資格を持たない職員に横柄な態度をとったり、介護福祉士などの資格の有無が役職・人事に影響し、人員配置の流動性が確保できなくなるなどの問題も多々起きている。
特に小規模の事業所では、資格の有無により職員の配置換えが効率的に行えなくなる、という点が今後ますます大きな問題となっていくだろう。
④ 慢性的な人手不足である
建設事業、保育事業等と同様、またそれ以上に介護事業所は慢性的な人手不足である。言い換えれば、労働者にとって介護業界は売手市場になっていることから、突然退職やモラル低下などの問題が発生している。
つまり、採用当初は一生懸命働いていても、ちょっとした問題や不満が生じると他の事業所に移ることが容易にできるため、職員の意識低下を招きやすい状況となっている。
⑤ 職員の年齢構成が幅広い
最近では、若い介護職員から70歳以上の介護職員など、様々な年齢で構成している事業所が見られるようになってきた。年齢構成が幅広いことによるメリット・デメリットとしては、様々なことが考えられる。
例えば、高齢の職員の場合、利用者とコミュニケーションを取りやすいという反面、自動車の運転やパソコン入力による報告書作成等は苦手なことが多い。それに対し、若い職員の場合は、パソコン等のシステムに強い、様々な面において情報収集力が高いといったメリットがある反面、どうしても利用者との年齢が離れているため、ミスコミュニケーションが起こる可能性が高いというデメリットも想定される。
* * *
上記の特徴を理解した上で労務管理を行うためには、避けては通れない重要な事項がある。それは、介護保険法の基準のひとつである、「人員基準」の存在である。この問題点を理解したうえで労務管理、人事管理を行わなければならない。
これから数回にわたり、人員基準の視点で、介護事業所の労務管理について解説していきたい。第2回である次回は、介護事業所における募集・採用の難しさと、介護保険法における人員基準について解説を行う。
(了)