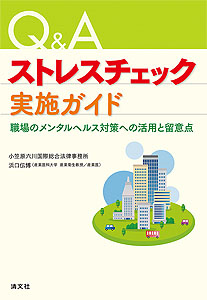[平成27年9月30日施行]
改正労働者派遣法のポイント
【第1回】
「労働者派遣法改正の背景」
特定社会保険労務士 岩楯 めぐみ
条文ミスや衆議院解散に伴う総選挙で二度にわたり廃案となった改正労働者派遣法が、平成27年9月11日に第189回通常国会で成立し、平成27年9月30日から施行されている。
今や多くの会社で活用されている労働者派遣だが、今回の改正は、派遣可能期間の考え方を刷新する等、大幅な変更を含んでいる。知らぬ間に労務トラブルを抱えることがないよう、しっかりと内容を理解しておきたいところである。
今回の連載では、まず概要を把握していただくことを目的に、4回にわたって改正労働者派遣法のポイントを紹介したい。各回では次の項目を取り上げていくことを予定している。
【第1回】 労働者派遣法改正の背景
【第2回】 新しい期間制限の考え方
【第3回】 雇用安定措置の義務化・キャリアアップ措置の新設
【第4回】 特定労働者派遣事業区分の撤廃等
第1回は、改正の内容をみる前に、なぜ今労働者派遣法が改正されたのか、改正の背景や目的について確認する。
1 改正の契機は「附帯決議」
今回の改正は、平成24年の労働者派遣法改正時に「附帯決議」として衆参両議院の厚生労働委員会で示された事項が契機となっている(【資料1】)。
参議院のサイトによると、「附帯決議とは、政府が法律を執行するに当たっての留意事項を示したものですが、実際には条文を修正するには至らなかったものの、これを附帯決議に盛り込むことにより、その後の運用に国会として注文を付けるといった態様のものもみられます」とある。附帯決議は、法的に拘束力を持つものではないが、決議事項についてはその後の取組について国会で確認されることになるため、政治的には拘束力を持つものとされている。
附帯決議をきっかけに検討がなされ、法律として成立することはしばしばみられるが、今回はまさにこの例であり、平成24年改正時に積み残された課題等について検討が行われ改正されるに至った。
【資料1】
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等
に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議
平成24年3月27日
参議院厚生労働委員会
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
1 登録型派遣の在り方、製造業務派遣の在り方及び特定労働者派遣事業の在り方については、本法の施行後1年を目途として、東日本大震災による雇用状況、デフレ・円高等の産業に与える影響及び派遣労働者の就労機会の確保等も勘案して論点を整理し、労働政策審議会での議論を開始すること。
2 いわゆる専門26業務に該当するかどうかによって派遣期間の取扱いが大きく変わる現行制度について、派遣労働者や派遣元・派遣先事業主に分かりやすい制度となるよう、速やかに見直しの検討を開始すること。検討の結論が出るまでの間、期間制限違反の指導監督については、労働契約申込みみなし制度が創設されること等も踏まえ、丁寧・適切に、必要な限度においてのみ実施するよう徹底すること。また、労働契約申込みみなし規定の適用に当たっては、事業主及び労働者に対し、期間制限違反に該当するかどうか等の助言を丁寧に行うこと。
3 いわゆる偽装請負の指導監督については、労働契約申込みみなし制度が創設されること等も踏まえ、丁寧・適切に実施するよう徹底すること。また、労働契約申込みみなし規定が適用される「偽装する意図を持っているケース」を、具体的に明確化すること。併せて、事業主及び労働者に対し、偽装請負に該当するかどうかの助言を丁寧に行うとともに、労働者派遣と請負の区分基準を更に明確化すること。
4 労働契約申込みみなし制度の創設に当たり、派遣労働者の就業機会が縮小することのないよう、周知と意見聴取を徹底するよう努めること。
5 派遣労働者に対する労働・社会保険適用を一層促進するため、現行の派遣元指針及び派遣先指針に記載されている労働・社会保険適用の促進策の法定化を含む抜本強化について検討すること。
6 優良な派遣元事業主が育成されるよう、法令遵守の一層の徹底、派遣労働者の労働条件の改善等、労働者派遣事業適正運営協力員制度の活用も含めた適切な指導、助言等を行うこと。
7 派遣労働者の職業能力の開発を図るため、派遣元事業主は派遣労働者に対し教育訓練の機会を確保し、労働者派遣業界が派遣労働者の雇用の安定等に必要な職業能力開発に取り組む恒久的な仕組みを検討すること。
8 本法施行に当たっては、あらかじめ、派遣労働者、派遣元・派遣先事業主等に対し、日雇派遣の原則禁止、派遣労働者の無期雇用への転換推進、均衡待遇の確保「マージン率」の情報公開など今回の改正内容について、十分な広報・情報提供を行い、周知徹底するよう万全を期すこと。
2 わかりにくい現行制度
労働者派遣は、職業安定法で禁止されている「労働者供給」(=供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させること)の例外として、“臨時的・一時的な労働力の需給調整手段”として“常用代替のおそれが少ないもの”、つまり、正社員の職場を奪わないことを前提に解禁された。このため、派遣可能期間には制限が設けられ(原則1年、上限3年)、3年を超える長期間の派遣は認めない仕組みとなっていた。
しかし、いわゆる「専門26業務」(政令で定めた業務(【資料2】)、平成24年改正により26業務から28業務へ変更)は、専門的な知識や特別の雇用管理が必要なため“常用代替のおそれがない”として、例外的に派遣可能期間に制限を設けず、長期間の労働者派遣が可能となっていた。
【資料2】 政令で定めた業務
施行令 第4条 第1項
第1号(情報処理システム開発関係)
第2号(機械設計関係)
第3号(機器操作関係)
第4号(通訳、翻訳、速記関係)
第5号(秘書関係)
第6号(ファイリング関係)
第7号(調査関係)
第8号(財務関係)
第9号(貿易関係)
第10号(デモンストレーション関係)
第11号(添乗関係)
第12号(受付・案内関係)
第13号(研究開発関係)
第14号(事業の実施体制の企画、立案関係)
第15号(書籍等の制作・編集関係)
第16号(広告デザイン関係)
第17号(OA インストラクション関係)
第18号(セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係)
施行令 第5条
第1号(放送機器操作関係)
第2号(放送番組等の制作関係)
第3号(建築物清掃関係)
第4号(建築設備運転等関係)
第5号(駐車場管理等関係)
第6号(インテリアコーディネータ関係)
第7号(アナウンサー関係)
第8号(テレマーケティングの営業関係)
第9号(放送番組等における大道具・小道具関係)
第10号(水道施設等の設備運転等関係)
「専門26業務」であれば派遣可能期間に制限がなく長期間の労働者派遣が可能なため、その該当性が重要になるのだが、「専門26業務」にあたるか否かについては判断に迷うことも多く、行政と企業で見解が異なる場面もみられた。また、「専門26業務」の周辺業務として、「付随業務」と「付随的な業務」という2つの考え方があり、派遣労働者を「付随業務」に従事させるのはいいが、「付随的な業務」に従事させる場合は業務全体の1割以下でなければならない等、複雑な仕組みとなっていた。
そこで、実務的にも判断に迷うことがないわかりやすい制度へ変更する必要があった。
3 「10.1問題」
法律の成立からわずか19日で、しかも、通常1日施行が多い中で30日施行となった背景には「10.1問題」がある。これは、平成24年改正時に創設された「労働契約申込みみなし制度」が平成27年10月1日から施行されることに伴い、労務トラブルが多発するのではないかと懸念されている問題だ。
ここで、「労働契約申込みみなし制度」について、改めてその概要を確認しておこう。
「労働契約申込みみなし制度」は、派遣先が違法派遣であることを知りながら派遣労働者を受け入れていた場合、違法状態が発生した時点で、その時点における同一の労働条件で派遣先が派遣労働者に対して労働契約の申込みをしたものとみなす制度だ。
この制度の対象となる違法派遣は4タイプ(【資料3】)。これら4タイプのいずれかに平成27年10月1日以降該当していた場合は、派遣先の意向に関わらず、自動的に派遣先が派遣労働者へ労働契約の申込みをした扱いとなり、派遣労働者が承諾すれば労働契約が成立することになる。
【資料3】 労働契約申込みみなし制度の対象となる違法派遣
① 派遣労働者を港湾運送業務等の派遣禁止業務に従事させること
② 無許可又は無届出の者から労働者派遣の役務の提供を受けること
③ 期間制限に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること
④ 派遣法又は同法の規定により適用される労働基準法等の規定の適用を免れる目的で、請負その他労働者派遣以外の名目で契約を締結し、必要とされる事項を定めずに労働者派遣の役務の提供を受けること(いわゆる偽装請負等)
先述の「専門26業務」のわかりにくさを解消することは、違法派遣の4タイプのうち「③ 期間制限に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること」と関係する。
例えば、派遣先が「専門26業務」に該当していると考えて3年を超えて労働者派遣を受け入れていたところ、ある日、突然、派遣労働者から『私がやっている業務は「専門26業務」には該当しないのではないですか?既に3年を超えているので「労働契約申込みみなし制度」の対象となり、直接雇ってもらえると聞いたのですが。』と言われたらどうするか。「専門26業務」への該当性を明確に説明できる状況になければ、派遣先は対応に苦慮することになるだろう。
このような状況下で、トラブルを避けるために平成27年9月末までに終了する派遣契約が増えるのではないか、また、平成27年10月以降「労働契約申込みみなし制度」の適用を巡る訴訟が多発するのではないかと考えられていた。そこで、混乱を避けるためにも、期間制限の考え方に関するわかりにくさを10月1日前までに解消しておく必要があった。
4 改正の目的
今回の改正の目的としては、大きく次の3つがあげられる。
まず1つめは、実際に働く派遣労働者や派遣元・派遣先にとってわかりやすい制度にすることである。「専門26業務」にあたるかどうかで派遣可能期間の取扱いが大きく変わる現行制度を見直し、新しい考え方が導入されている。
2つめは、派遣労働者の雇用の安定と処遇改善を推進することである。リーマンショック以降に“派遣切り”が社会問題となり、平成24年改正から「派遣労働者の保護」が法律名にも明記され、派遣労働者を保護する施策が追加されたが、今回の改正でさらに付加されている。
3つめは、派遣事業への規制強化である。労働者派遣は法制定以降、派遣労働が可能となる対象業務を拡大する等の規制緩和を進めてきたが、悪質な派遣業者も少なからずいることから、平成24年改正より緩和から規制へと軸を変えている。今回の改正は派遣事業の許可そのものに関わる内容を含んでいる。
* * *
以上、労働者派遣法が改正された背景や改正の目的について確認したが、労働者派遣を導入して既に30年が経過し、運用上の不具合を是正する時期にきているといえるのではないだろうか。
【第2回】からは、個別の改正点についてみていく。
(了)