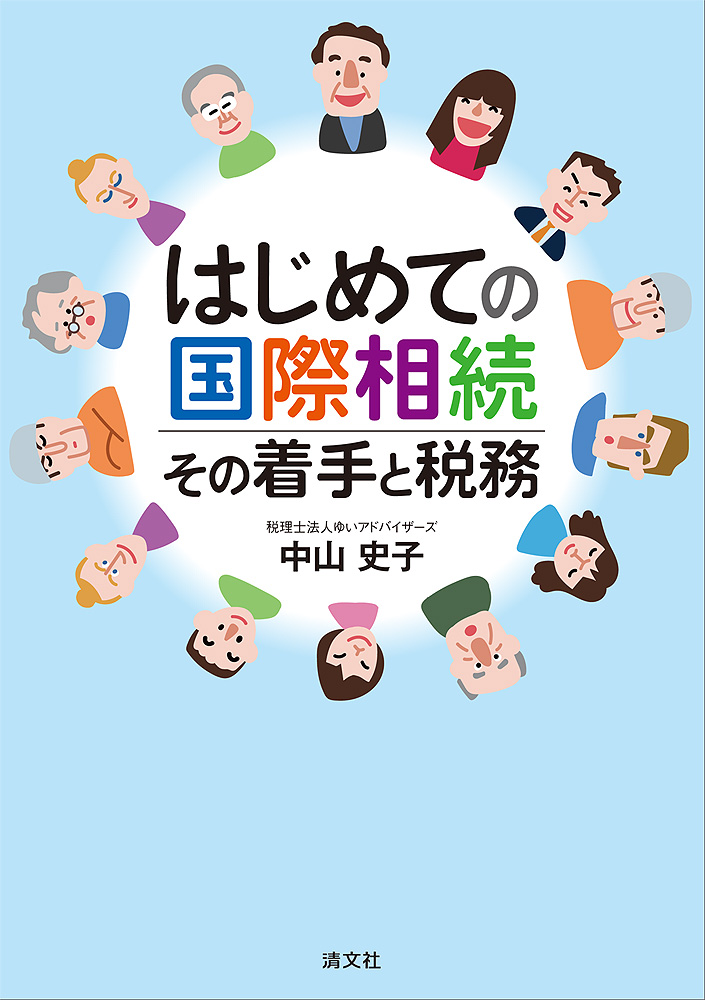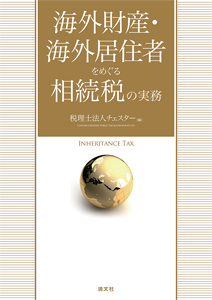外国人労働者の雇用と在留管理制度について
【第1回】
「外国人雇用をめぐる主な注意点」
KPMG BRM株式会社
マネージャー
申請取次行政書士 佐々木 仁
1 はじめに
昨今のグローバル化の波は、大企業だけでなく、中規模あるいは零細な企業の雇用の現場にも押し寄せてきている。有用な人材は国の枠を超え、就学や就職の場を海外に求めている。
将来的に生産拠点や市場を海外に、と考える企業であれば、相互の社会や文化に理解のある、あるいは日本に関心を持つ外国人労働者を雇用することは、当面のニーズに応えるだけでなく、将来にわたって、その企業の発展に大きな影響を及ぼすだろう。
そこで本稿では、今後も増え続けることが予想される外国人労働者の雇用に関して、日本の在留管理制度の観点から想定される問題点及び本年7月9日から新たに施行された在留管理制度について、概括的に述べることにする。
2 外国人を雇用する場合に想定される問題点
外国人を雇用した場合、企業はどのようなことに気をつけなければならないか。
初めから既にスキルや知識を持っている外国人を呼び寄せて雇用する場合も多いが、ここでは参考例として、日本の大学を卒業する留学生を雇用するケースを取り上げてみたい。
日本の社会や文化にある程度慣れており、また多くの場合、語学にも堪能なことから、企業が卒業予定の留学生を雇用するケースが増えている。
日本に来る多くの留学生は優秀な人材が多く、将来的に大いに活躍が期待されるが、他の日本人労働者と大きく異なる点として、日本に居住し活動するための適切な「在留資格」への変更、または取得手続が必要なことを忘れてはならない。
留学生は「留学」の在留資格を得て来日している。そのため、例えば授業の合間にアルバイトとして働く場合でも、入国管理局から「資格外活動」の許可を事前に得る必要があり、かつ、労働時間に上限が定められている(原則週28時間以内、長期休暇期間除く)。
また、当初留学生としての在留資格をもって在留していても、大学を卒業し留学生でなくなれば、日本に居続けるためには、期限内に在留資格を変更しなければならない。
あるいは在留期限が近日中に迫り在留資格を変更するだけの残存期間がなければ、一旦本国に帰国したうえで、日本にいる親族や代理人等に日本の入国管理局から「在留資格認定証明書」を取ってもらい、その証明書を外国人本人が本国の日本大使館に持参して査証(「ビザ」)を取得し、日本に再度上陸する必要がある。
企業が外国人を雇用するときは、通常、本人の資質や印象に注目するため、本人が保有している在留資格の内容について注意が払われることは少ない。ところが、もしその在留資格が適切なものでなければ、予定したとおりその外国人が働くことができないこともあり得るので、十分注意していただきたい。
在留資格に基づかない、いわゆる「ビザなし就労」は不法在留であり、露見すると本人が強制退去命令を受けるほか、コンプライアンス上、雇い入れた企業にも多大な損害が起きる恐れがある。
なお、在留資格の変更や在留資格認定証明書の取得には申請から取得まで数週間かかり、さらに本国でビザを取得して来日するまでは就労することができない。よって、在留資格の変更申請や在留資格認定証明書の交付申請のタイミングが遅れると、当初予定していた雇用の開始日に間に合わなくなる可能性も出てくる。
このように、留学生を卒業後雇用する場合は、現在の在留資格の有無及び有効期限の確認と、有効な在留資格の取得または変更までに必要な時間を見越した、ある程度の時間的な余裕を忘れないようにしたい。雇用が決まったら、できるだけ早く手続することが望ましい。
3 在留資格について
そこで、これまでに何度も出てきた「在留資格」とは何であろうか。
「在留資格」とは、外国人が日本に在留する間に「出入国管理及び難民認定法(入管法)」で定められたカテゴリーに基づいて活動を行うことができる資格である。
入管法に定められた活動以外は日本国内で行うことが認められておらず、観光目的等の短期滞在(在留期間90日以内)でビザの取得が免除される場合を除き、適切な在留資格に基づいた入国管理の手続を経ることなく日本に在留することはできない。
一般的に外国人が日本に3ヶ月以上在留する、中・長期在留者として入国するための手続は次のとおりである。
- 在留資格に基づき、該当する外国人(申請人)は、親族や代理人等に依頼して日本国内の入国管理局で「在留資格認定証明書」を取ってもらい、申請人がいる本国に送付してもらう。
- 申請人本人が「在留資格認定証明書」を持参して本国の日本大使館に出向き、査証(ビザ)を取得する(在留資格認定証明書の有効期間(上陸申請まで):交付後3ヶ月以内)。
- 入国する際に、査証が貼付されたパスポートと「在留資格認定証明書」を入国審査官に提示する。
① 「企業内転勤」
② 「人文知識・国際業務」
③ 「技術」
④ 「投資・経営」
各資格の活動内容、及び認定されるための最低限の基準は、以下のとおりである。
① 企業内転勤
海外に本店・支店等のある企業や団体の従業員が国内の本店・支店や子会社等に期間を定めて転勤して行う活動で、下記「人文知識・国際業務」または「技術」に該当する活動 【基準】
転勤の直前に「技術」または「人文知識・国際業務」に該当する業務に従事し、その期間が継続して1年以上あること
② 人文知識・国際業務
〔人文知識〕
国内の企業や団体との契約に基づいて、法律学・経済学・社会学等人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動
〔国際業務〕
外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務に従事する活動 【基準】
〔人文知識〕
従事しようとする業務について、これに必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業または同等以上の教育を受けたこと、若しくは10年以上の実務経験
〔国際業務〕
翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾、室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事し、かつ3年以上の実務経験(大学を卒業した者が翻訳、通訳または語学の指導に係る業務に従事する場合、この限りでない)
③ 技術
国内の企業や団体との契約に基づいて、理学や工学等自然科学の分野に属する技術・知識を必要とする業務に従事する活動
【基準】
従事しようとする業務について、必要な技術または知識に係る科目を専攻して大学を卒業、またはそれと同等以上の教育を受け、若しくは10年以上の実務経験
④ 投資・経営
国内において貿易等の事業の経営を開始、または国内事業に投資して、経営や管理を行う活動。または投資している外国人に代わってその経営や管理を行う活動
【基準】
事業所として使用する施設が国内に確保されており、申請者以外に2人以上、国内に居住し常勤職員として従事すること。また、申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院で経営または管理に係る科目を専攻した期間を含む)
上記に記載されたもの以外にも、各資格にそれぞれ定められた基準があるので、雇用が予定されている外国人がどの在留資格に該当するか、また必要な手続についての詳細は、専門家にご相談いただきたい。
次回は、新たな在留管理制度について解説する。
(注1)
外国人が受ける報酬は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上である必要がある。
(注2)
「短期滞在」から上記の在留資格に直接変更することはできない。
(注3)
「人文知識・国際業務」「技術」の場合、外国人が転職しても、在留資格を変更する手続は必要とされていない。
「企業内転勤」の場合は転職を想定していないため、外国人が日本在住のまま別の企業に転職したい場合は、「人文知識・国際業務」や「技術」に在留資格変更の手続を行う必要がある。
(了)