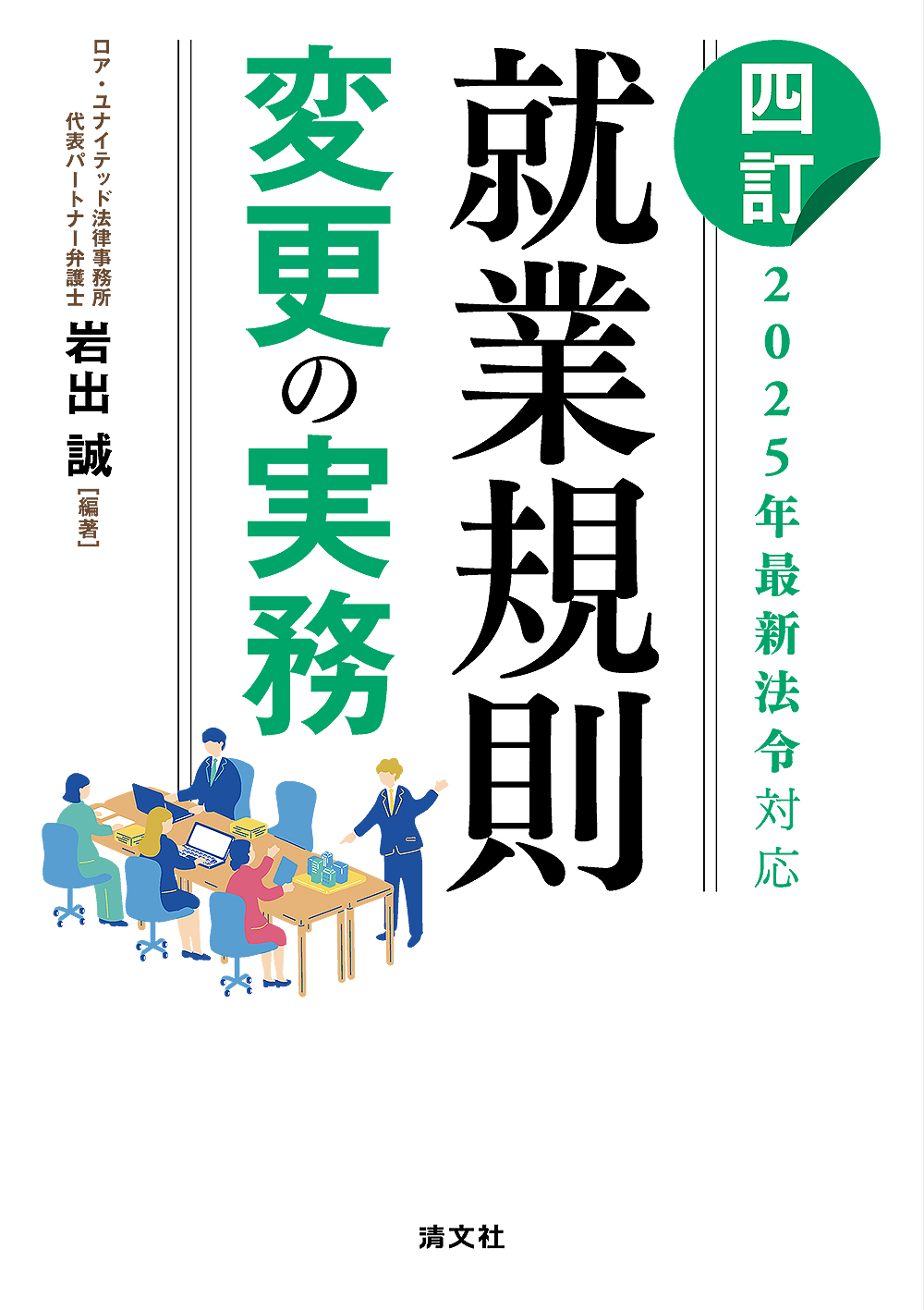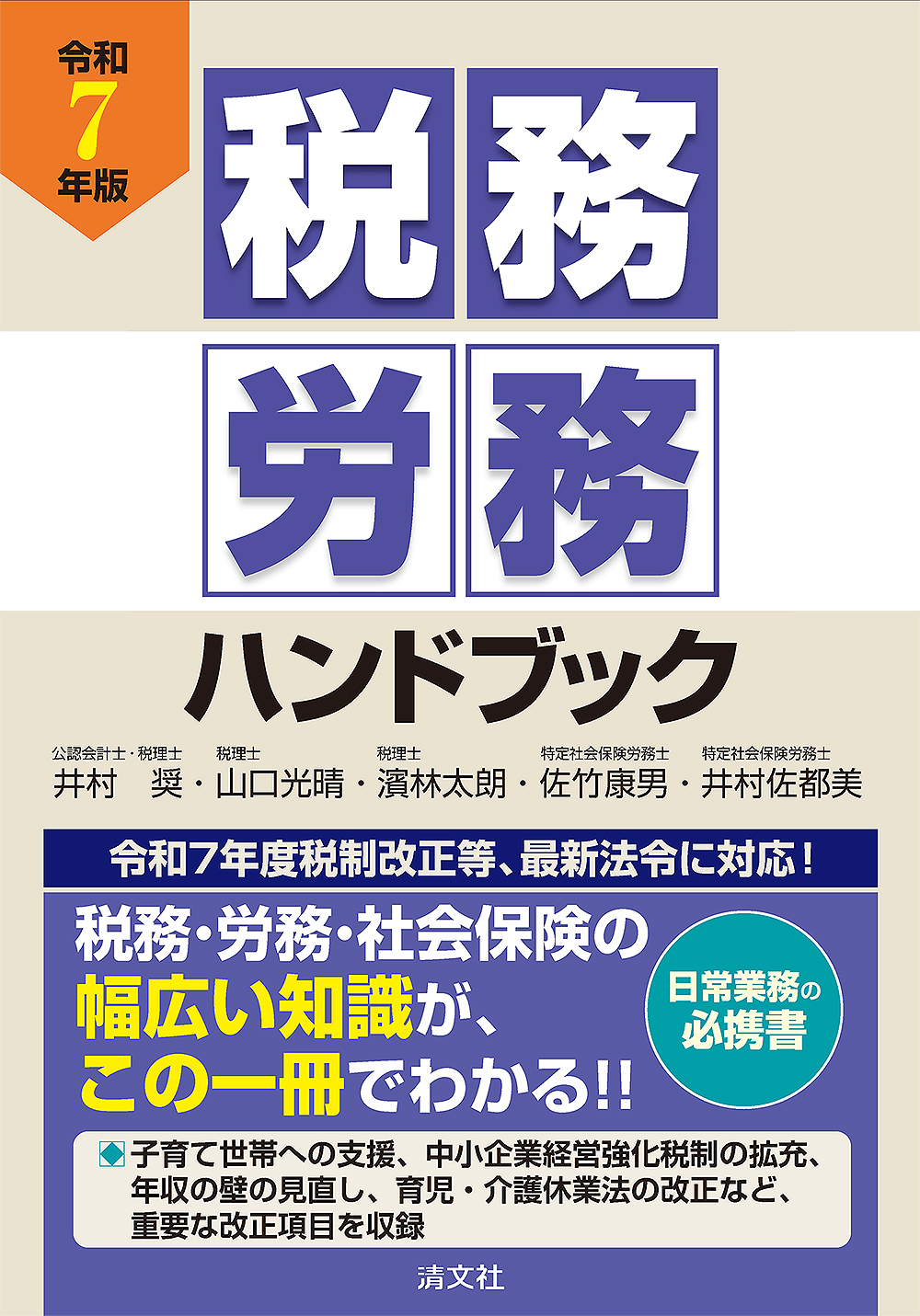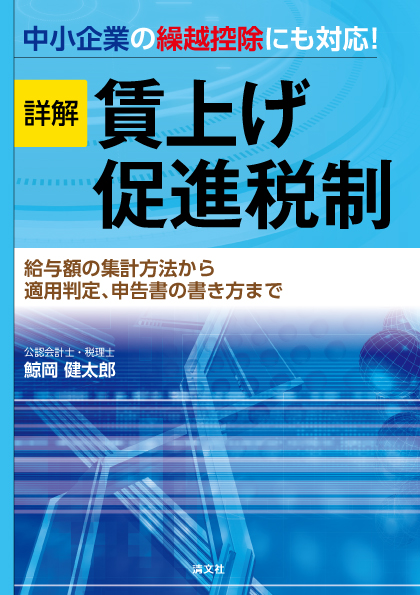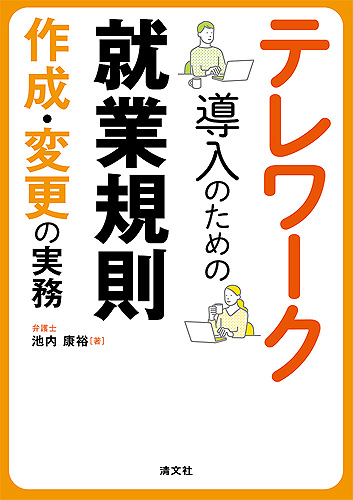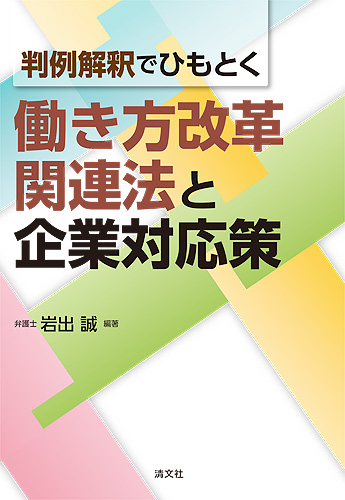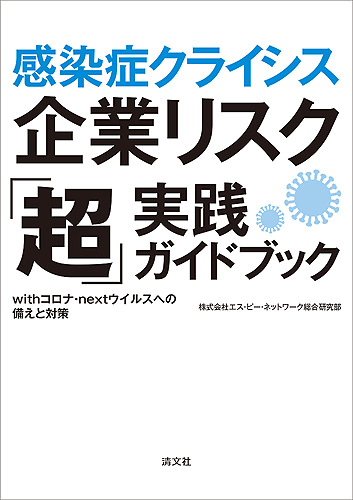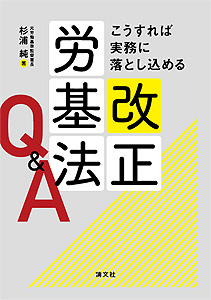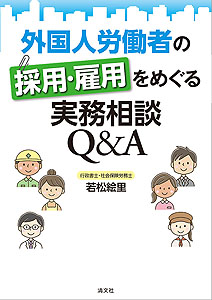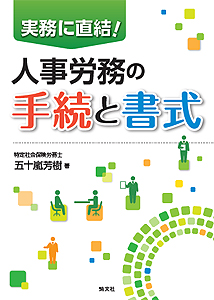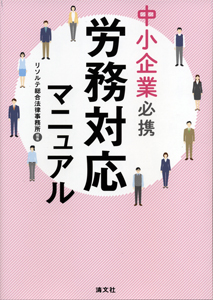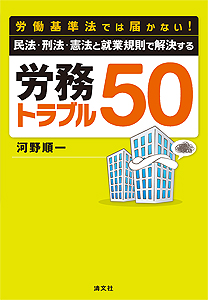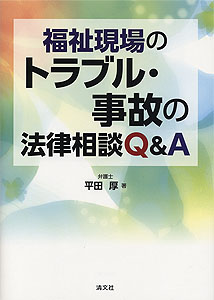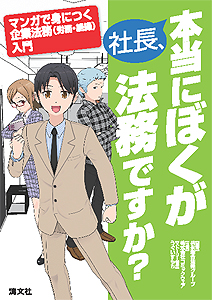競業避止規定の留意点
【第1回】
「競業避止規定の重要性」
特定社会保険労務士 大東 恵子
昨今、1990年代から2000年代にかけて、円高や平成不況、リーマンショックなどの影響により企業の売上が低下し、人件費の圧迫過剰雇用に直面した結果、雇用の調整が大きな経営課題となっている。そのため、日本的経営であった終身雇用制を維持することは困難な状況にある。
なお、終身雇用された労働者との契約は、労働基準法上(労働基準法第14条)は「期間の定めのない雇用」(=「無期雇用」)である。
法律上の定義はなく、実態を指していう言葉であって明確な判断基準はない。
終身雇用制の崩壊に伴い「就社」という「入社から定年まで一企業で労働」という思考から、労働者自身のライフプランの実現、グローバル化や情報化の傾向により、社内外問わず適材適所を求めた人の流動性が活発化している。
一方、企業にとってはポテンシャルの高い優秀な人材(取締役や支配人(会社法14条等)幹部労働者)、知識・ノウハウ・情報を持った労働者の流動は大きな痛手である。
こういった人材の流動化等の影響により、機密を争点とした紛争は増加傾向にあり、主な漏洩経路として退職者等が絡んだ機密侵害が深刻化している。
そこで、企業経営を左右しかねない機密情報を扱う労働者に対し、「競業避止措置」をとることが重要となる。
競業避止義務とは、一定の者が、自己又は第三者のために、その地位を私的に利用して、営業者の営業と競争的な性質の取引をしてはならない義務である。
労働法においての競業避止義務の概念は、下記のとおりである。
■在職中に使用者の不利益になる競業行為(兼職など)を行うことを禁止すること
■一般の企業において、労働者が退職後に競業他社への就職を禁ずることを定めた、契約書や就業規則に含まれる特約(競業禁止特約ともいう)
なお、「不正競争防止法」にも、労働者(退職)に秘密を保持する義務が課せられる条文がある。保護する対象に対して、行為の規制(禁止)となる要件を定めている。
1 窃盗、詐欺、強迫その他の不正手段により営業秘密を取得する行為(以下「不正行為」という。)又は不正行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。以下同じ)(同法2条4号)
(例) 持出厳禁データなど管理関係者を騙し又は無断で社外に持ち出し、コピーを取ったりして競争会社に販売などを行うのが典型的なケース。
2 営業秘密を保有する事業者(以下「保有者」という。)から営業秘密を示された場合において、不正の競業その他の不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為(同法2条7号)。
現行法上「競業避止義務」が課せられるためには、企業の経営に直接関与し、企業との利害の一致が要請される。つまり、取締役や支配人、幹部労働者である。一般労働者(退職者含む)では、企業経営に直接関与しないため、企業と利害の一致にはならないケースが多い。
そのため、企業が取り得る事前措置として、競業避止規定や不正競争防止法説明や機密保持契約書等を設ける必要がある。
次回は、退職した労働者も秘密保持義務を負うか否かについて、判例を交えて解説する。
(了)