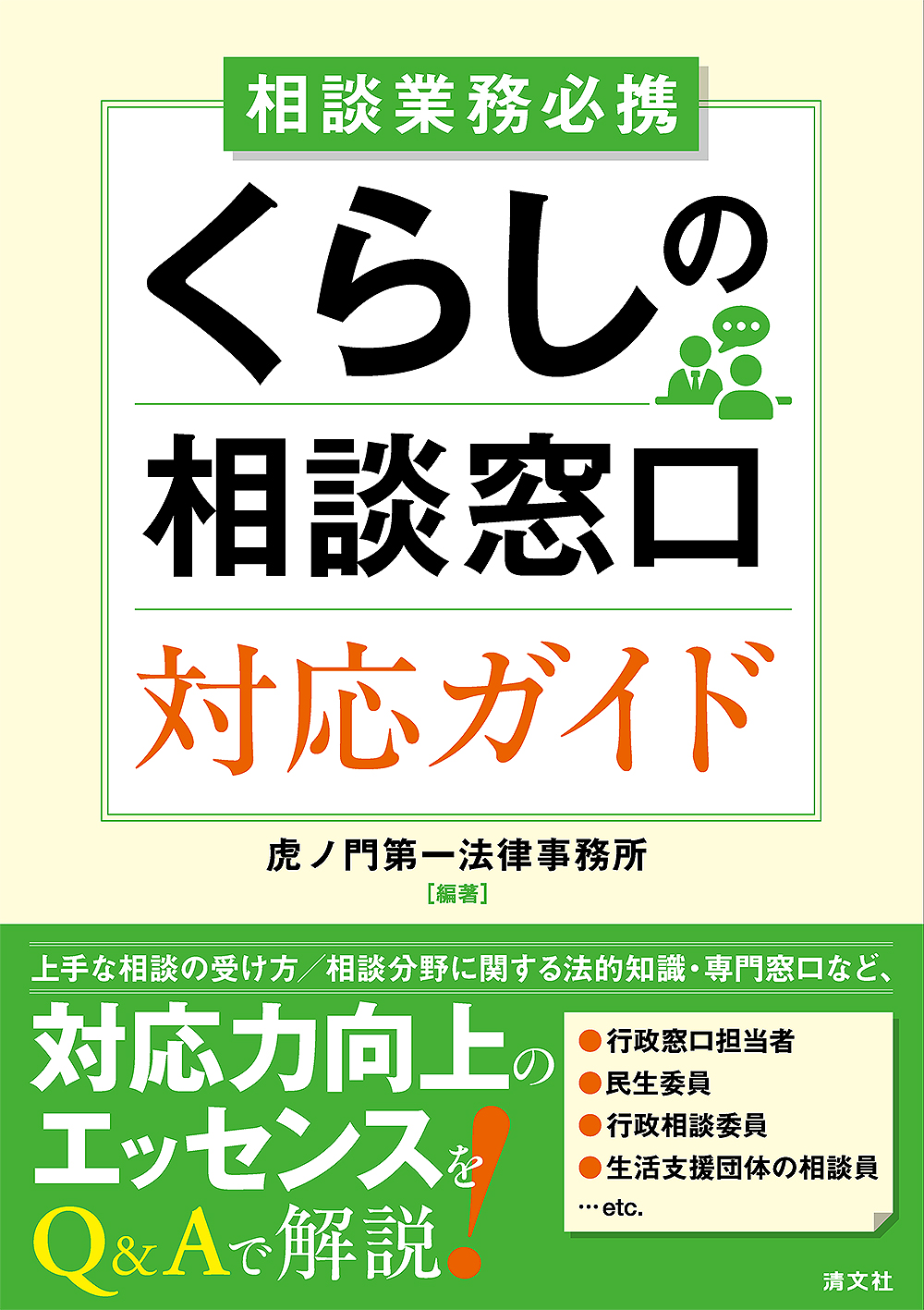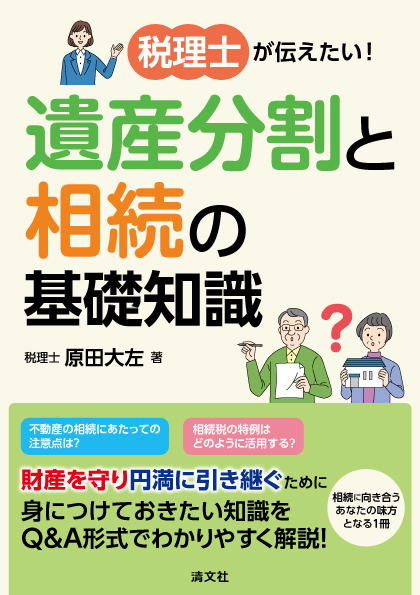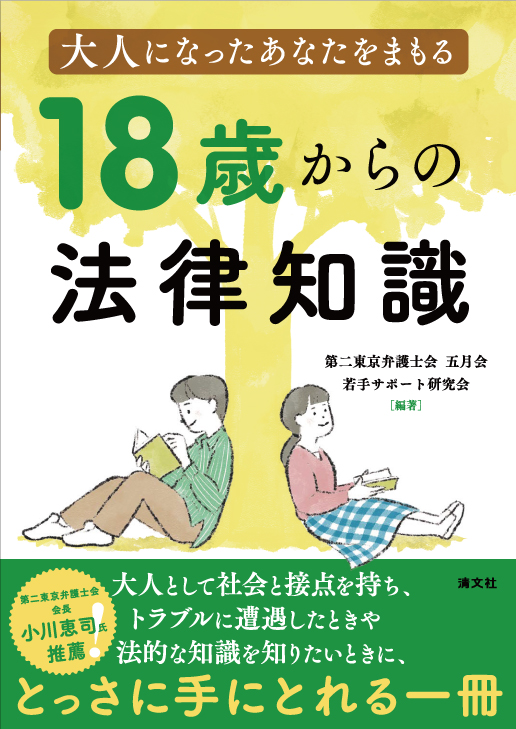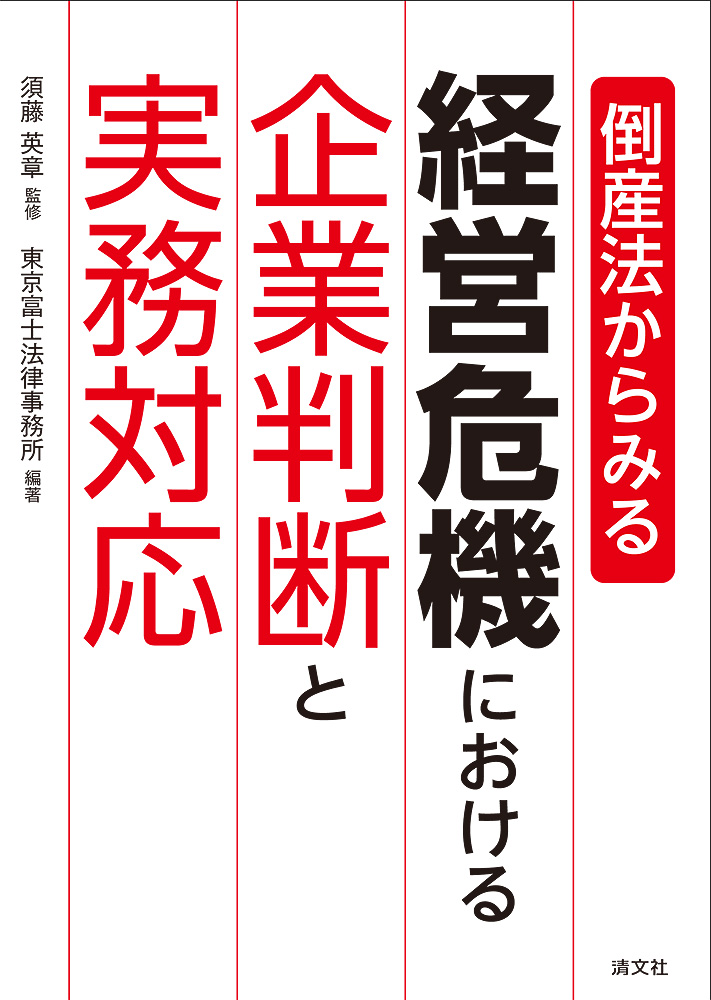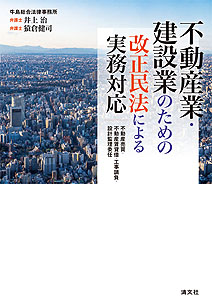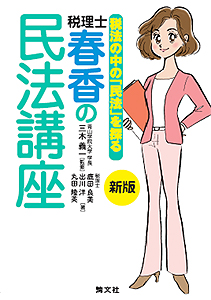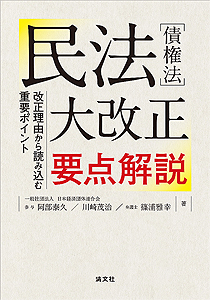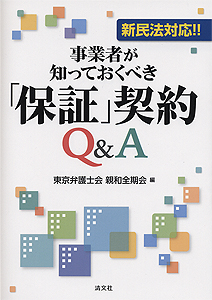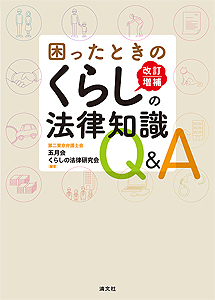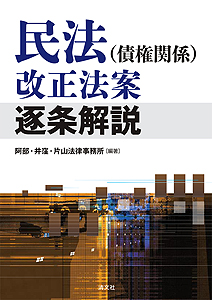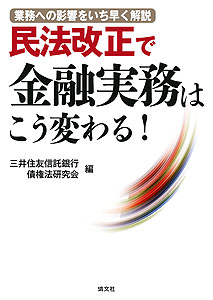民法改正(中間試案)
─ここが気になる!─
【第5回】
「民事法定利率」
弁護士 中西 和幸
1 民事法定利率に関する改正の概要
前回は損害賠償について解説したが、こうした損害賠償請求に関しては、民事法定利率の問題も同時に考えなければならない。
この民事法定利率は、民法制定当時から変わっていないが、現在の預金金利の水準が低いことから、その変更も民法改正で議論されている。
そこで今回は、利率をどうするか、固定金利か変動金利か、中間利息控除ではどう取り扱うか等について解説する。
2 民事法定利率の変更
(1) 民事法定利率が問題となる場面
民事法定利率の出番は、概ね2つに分けられる。
まずは、金銭消費貸借における利息や、履行遅滞による遅延損害金などにおいて利率を明確に定めなかった場合である。
もう1つは、当事者間に法的な関係がなかったところへ債権債務関係が発生する場合、すなわち交通事故等の不法行為における損害賠償請求権や不当利得関係が生じた場合の返還請求権である。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。