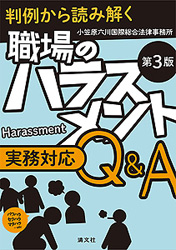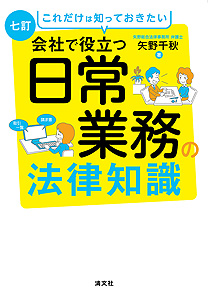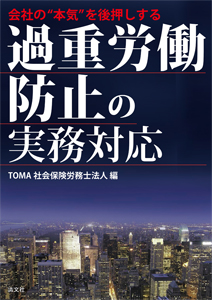〈2026年1月施行〉
下請法改正と企業対応のポイント
【前編】
「下請法改正の概要」
弁護士法人東町法律事務所
弁護士 木下 雅之
1 はじめに
2025年5月16日、下請法の改正法案が衆議院本会議において可決、成立した。
改正の主な目的は、近年の急激な労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇を背景に、中小企業をはじめとする事業者が物価上昇を上回る賃上げを実現するためには、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる「構造的な価格転嫁」の実現を図っていくことが重要だという点にある。かかる改正法の目的から、2026年の春闘を見据えた中小企業の賃上げ原資の確保につなげるため、改正法の施行日は2026年1月1日とされており、事業者は早急な対応が必要となるが、改正法は下請法の適用範囲を拡大するとともに、親事業者による禁止行為も拡充するなど、実務への影響は小さくない。
なお、「下請」という用語は発注者と受注者が対等な関係ではないという語感を与えること、時代の変化に伴い発注者である親事業者の側においても「下請」という用語は使われなくなっていることなどの理由から、改正法では、「下請」等の用語が見直されており、「親事業者」を「委託事業者」、「下請事業者」を「中小受託事業者」、「下請代金」を「製造委託等代金」等に改めるとともに、法律の名称も「下請代金支払遅延等防止法」から「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に改められることとなった。以下では、かかる用語の見直しに倣うこととし、便宜上、改正法を「中小受託取引適正化法」、現行下請法を単に「現行法」という。
2 協議を適切に行わない代金額の決定の禁止(禁止行為の拡充)
上述した改正の目的に照らし、適切な価格転嫁の円滑化は重要なテーマの1つであるところ、中小受託取引適正化法は、委託事業者の新たな禁止行為類型として、「協議を適切に行わない一方的な代金額の決定」を追加した。
具体的には、中小受託事業者の給付に関するコストが上昇しているなどの場合において、中小受託事業者から価格協議の求めがあったにもかかわらず、当該協議に応じなかったり、当該協議において中小受託事業者が求めた事項について委託事業者が必要な説明もしくは情報の提供を行わなかったりするなど、一方的に代金を決定して、中小受託事業者の利益を不当に害する行為は禁止される(中小受託取引適正化法5条2項4号)。
これまで、コストが上昇しているにもかかわらず価格を据え置く行為については、「買いたたき」(現行法4条1項5号)に該当するものとして、対処がなされてきた。しかしながら、従来の「買いたたき」は、「市価」の把握が困難な場合に、「従前の対価」をもって「通常支払われる対価」として取り扱い、「従前の対価」に比して著しく低い下請代金の額を不当に定めることを「買いたたき」にあたるものと解釈しており、基本的には、従前の対価を引き下げる場面を想定した規定であった。
そのため、コストの上昇局面において当該上昇分を対価に反映しない行為についても、「買いたたき」に該当するものとして対処することが適当であるかどうかは疑問の残るところであったが、中小受託取引適正化法は、一方的ではない実質的かつ実効的な価格協議が確保されることで適正な価格転嫁が実現されるという考えの下、「対価」ではなく「交渉プロセス」に着目した禁止行為類型を新設したものである。
3 手形払い等の禁止(禁止行為の拡充)
現行法上、委託事業者は、受領日から60日以内のできる限り短い期間内において支払期日を定めた上(現行法2条の2)、その支払期日までに製造委託等代金を支払わなければならない(現行法4条1項2号)。
もっとも、支払手段については、現金払いを原則としつつも、手形やその他の支払手段(電子記録債権、ファクタリングなどの一括決済方式)による支払も認められており、例えば、受領日から60日以内の支払期日に手形を交付すれば、委託事業者は支払遅延とならないものの、中小受託事業者は、そこから手形サイトに相当する期間を待たなければ現金を受領することができず、手形等による支払いは、実質的に資金繰りの負担を中小受託事業者にしわ寄せする結果となっていた(手形を割り引くことによって満期日よりも前に現金化することは可能であるが、手形の割引には手数料がかかるため、この場合、製造委託等代金の満額を受領することはできない。)。
このような状況に対して、公正取引委員会および中小企業庁は指導基準を変更し、2024年11月1日以降は、手形サイトが60日を超える手形は割引困難手形(現行法4条2項2号)に該当するものとして取り扱ってきたが、中小受託取引適正化法は、これを一段進め、同法上の支払手段として、手形サイトに関係なく、手形払いを一切認めないこととした(中小受託取引適正化法5条1項2号)。また、電子記録債権やファクタリングなどの一括決済方式についても、支払期日までに代金に相当する金銭(手数料等を含む満額)を得ることが困難であるものについては認めないこととしている(同号)。
4 適用対象取引への「特定運送委託」の追加(適用範囲の拡大)
現行法上、運送委託は「役務提供委託」(現行法2条4項)に該当するところ、いわゆる自家使用役務(委託事業者が自ら用いる役務)は役務提供委託に含まれないこととされている(同項にいう「提供の目的たる役務」にあたらない。)。
そのため、例えば、売買契約の売主である発荷主(例:卸売業者)が、買主である着荷主(例:小売業者)に対して、売買の目的物の引渡しを履行するため、運送事業者Aに運送を委託し、さらに運送事業者Aが当該運送業務を運送事業者Bに再委託するような場合、発荷主と運送事業者Aとの間の運送委託は、発荷主が引渡しの履行のために自ら用いる役務として自家使用役務にあたり、現行法の適用対象外とされていた(独占禁止法の物流特殊指定で対応)。一方、運送事業者Aと運送事業者Bとの間の再委託は、自家使用役務ではなく、役務提供委託に該当するため、現行法が適用される。
しかしながら、このような住み分けは事業者にとってわかりにくいばかりか、自家使用役務にあたる運送取引においても、立場の弱い物流事業者が長時間の荷待ちや契約にない荷役などの附帯作業を無償で行わされているなどの実態があり、下請法による機動的な対応の必要性が指摘されていた。
そこで、中小受託取引適正化法では、上記の例でいう発荷主と運送事業者Aとの間の運送取引についても、「特定運送委託」として、新たに同法の適用対象取引に追加されることとなった(中小受託取引適正化法2条5項、同6項)。
ただし、条文上、「事業者が業として行う販売・・・の目的物たる物品・・・の当該販売・・・に対する運送の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること」とされていることから(中小受託取引適正化法2条5項)、あらゆる運送委託が対象となったわけではなく、「特定運送委託」に該当する取引は、あくまでも「取引の目的物を顧客へ運送する場合の運送委託」に限定されている点は、留意が必要である。
5 従業員基準の追加(適用範囲の拡大)
現行法は、委託取引の内容(委託取引基準)と資本金の区分(資本金基準)によってその適用範囲を形式的・機械的に画している。
しかしながら、資本金基準については、資本金制度の柔軟化や減資手続の緩和などの影響もあり、実質的には事業規模は大きいものの当初の資本金が少額である事業者や、減資によって下請法の適用を意図的に潜脱する事業者の例などが見られた。
そこで、中小受託取引適正化法は、その適用範囲を画する基準として、従来の資本金基準に加えて、新たに従業員数の基準を追加することとした。具体的には、常時使用する従業員の数が300人を超える事業者が、常時使用する従業員の数が300人以下の事業者に対して製造委託等をする場合(役務提供委託等では100人が基準)には、資本金基準を満たすか否かにかかわらず、中小受託取引適正化法の適用対象となる(中小受託取引適正化法2条8項5号、同6号、同条9項5号、同6号)。
6 その他の改正事項
以上のほか、その他の改正事項の内容は、以下のとおりである。
もっぱら製品の作成のために用いられる木型、治具等についても、金型と同様に製造委託の対象物として追加【中小受託取引適正化法2条1項】
現行法でいう3条書面の交付義務について、中小受託事業者の承諾の有無にかかわらず、必要的記載事項を電磁的方法により提供可能【中小受託取引適正化法4条】
「遅延利息の支払義務」の対象に「減額」の場合を追加【中小受託取引適正化法6条2項】
面的執行の強化として、事業所管省庁の主務大臣に指導・助言権限を付与するとともに、「報復措置の禁止」の申告先として事業所管官庁の主務大臣を追加【中小受託取引適正化法8条、同5条1項7号】
勧告時点において違反がなくなっていても再発防止策などを勧告できるよう、既に違反行為が行われていない場合等の勧告に係る規定を整備【中小受託取引適正化法10条】
(了)
【後編】は7/31に掲載予定です。