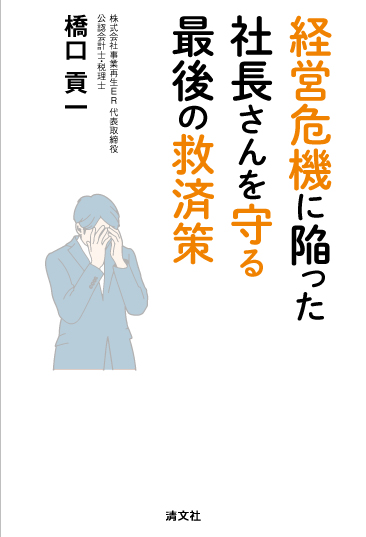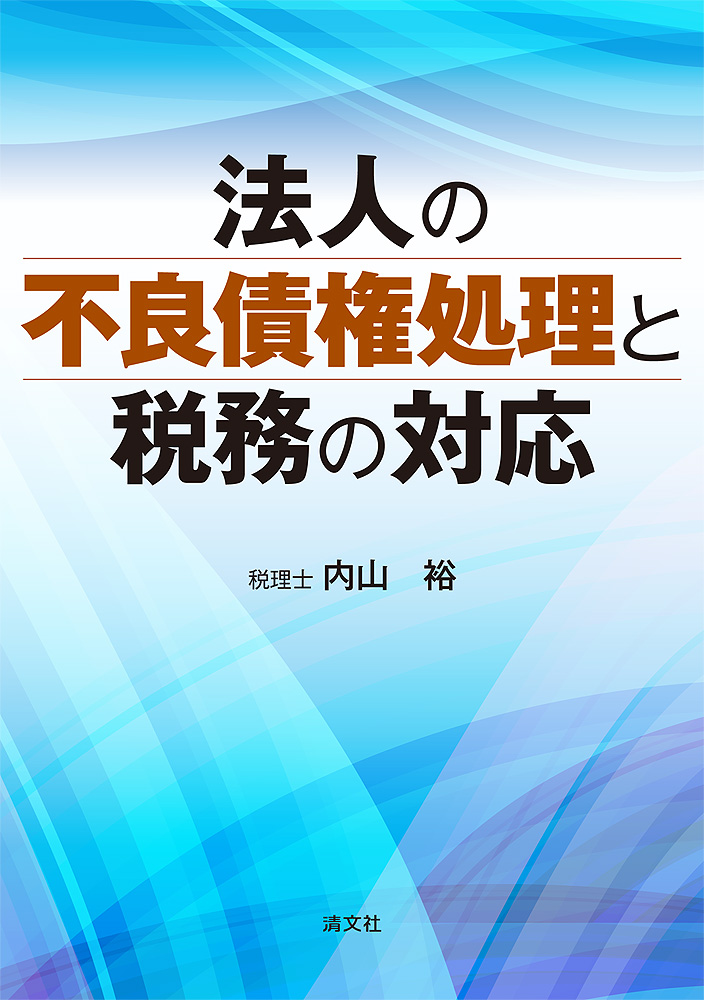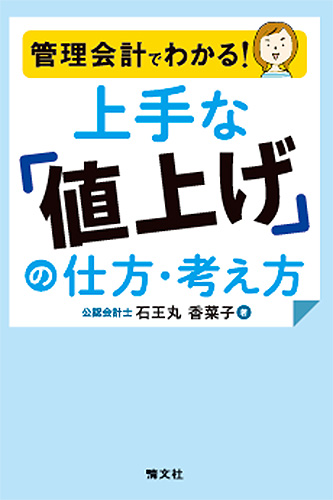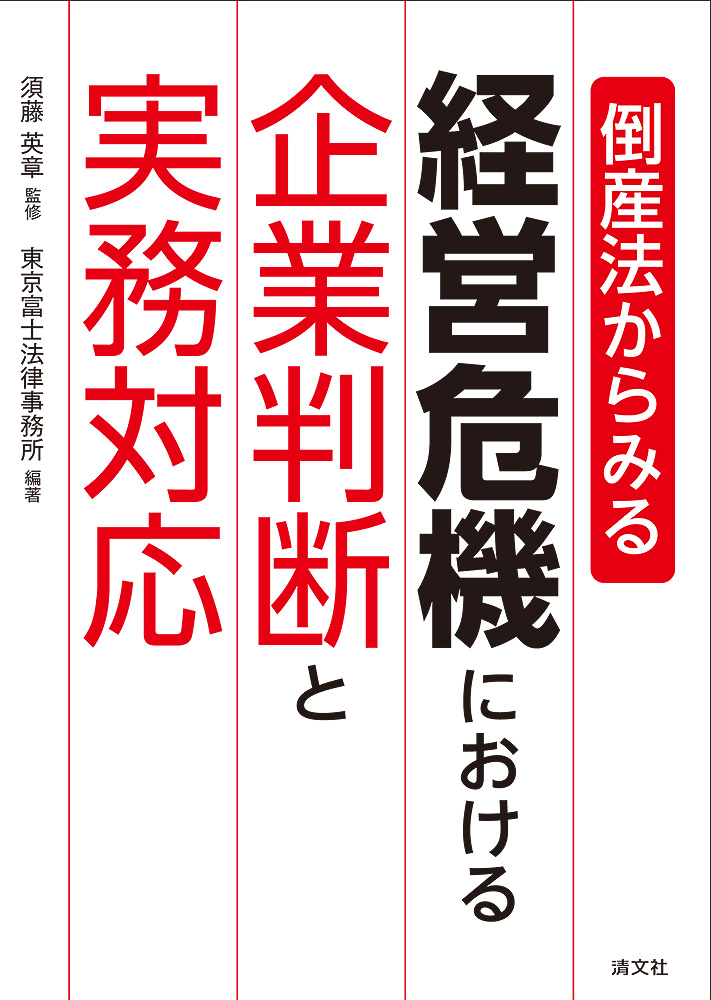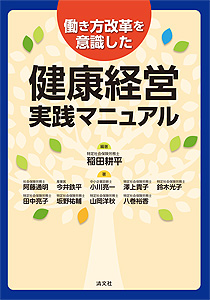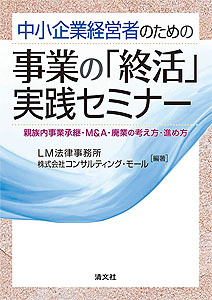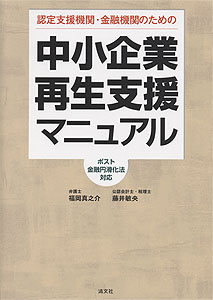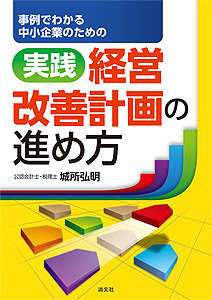[新型コロナウイルスを乗り越えるための]
中小企業の経営相談
【第1回】
「財務状況の把握」
虎ノ門第一法律事務所
弁護士 山口 智寛
株式会社バンカーズ・アイ
代表取締役 山田 正貴
◆はじめに◆
新型コロナウイルス肺炎の感染拡大により、企業活動が大きく停滞しています。事業計画の中止、売上低下、仕入停止、予定していた出資の撤回、売掛金の未回収といった問題が次々に押し寄せて来て、急速に財務状況が悪化し、どうしてよいかわからなくなっている事業者も少なくありません。実際に、事業停止や破産に追い込まれる企業も増えてきています。事業者の立場として、あるいは事業者を支援する専門家の立場として、この局面を乗り切るためには、ネガティブな発想のみに支配されて思考停止、活動停止状態に陥ってはなりません。できる限り広く正確な情報を収集することに努め、事態の打開に協力してくれる人を募り、今できる最善のことは何かをよく考え、そして実践していく。私たちにはそれができるか否かが問われています。
この連載では、経営不振に陥った事業者(主に中小企業を想定していますが、基本的には規模の大小や組織構成を問わずに当てはまる内容です)、及び、経営不振に陥った事業者を支援する立場にある専門家向けに、危機を乗り越えるために必要な「今すぐに役立つ」情報を提供していきます。少しでも記事を読んでくださった方のお役に立つことができれば幸いです。
-相談内容-
当社はコロナショックのあおりを受けて売上げが激減してしまっています。このままだと会社の存亡自体が危ないということは肌感覚で感じているのですが、具体的に「いつ」「どうなってしまうのか」は把握できていません。どうすれば自社の財務状況を正確に把握できるでしょうか。
● ● ● 回 答 ● ● ●
1 財務状況の把握の必要性
経営者が自社の財務状況が悪化していることを感じていても、具体的にどの程度悪化しているのかは把握できていないという場合は非常に多い。あるいは、事業から利益を生み出すことができていると安心していたところ、一時的な運転資金の不足により結局事業継続が困難になってしまうということもある。
経営目標や事業計画を設定しておらず、いわゆる「どんぶり勘定」で経営をしている会社、経営者が決算書を注視していない会社、融資を受けるために決算書の中身を粉飾しており実態数値を把握できていない会社は、平時においてもこのような状況に陥りやすい。コロナショックにより社会、経済に混乱が生じている今は、尚更である。
もとより会社経営には不確定な要素が多く、経営者の不安の種は尽きない。しかし、漠然とした不安を抱えているだけで、その不安の中身を具体的に知らないというのは、姿の見えない敵と戦っているようなものである。
企業活動の本質は、手元資金を活用して事業を行い、それによって利益を獲得して資金を生み出し、その資金を活用してまた事業を行うという循環の中にある。経営不振に陥っているということは、この循環のどこかに問題が生じているということを意味する。
そこで、財務状況の改善の第一歩として、自社の財務状況を分析して、どこにどのような問題があるのかを明確にすることが必須である。
2 どうやって財務状況を把握するのか
(1) 財務諸表の分析
敢えて言うまでもないが、会社の財務諸表(貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書等)は財務状況の把握のための最も直接的な資料となる。企業活動の結果は、財務諸表において客観的な数値として表されており、その数値から自社の経営状況とその課題を把握することができる。
主な分析手法として、収益性分析、安全性分析、生産性分析といった方法があり、経済産業省が無料で提供しているツール「ローカルベンチマーク」(通称:ロカベン)を使うと、これらの手法による分析を簡単に行うことができる。
指示に従って自社の財務情報及び周辺事情を入力すると、各種の指標に関する点数が表示されて、「自社がどのような会社なのか」がわかる。さらに、業界内の平均値との比較もできるので、是非活用していただきたい。
(2) 試算表(月次)の分析
試算表は、財務諸表を作成する前に勘定への転記が正確に行われているかどうかを月次で検証するための集計表である。言ってしまえば、1ヶ月ごとの貸借対照表と損益計算書であり、特に、売上の状況、利益の状況、現預金残高の増減状況の把握のために有効である。また、現在値の把握だけでなく、将来値の予測や目標値の設定にも使うことができる。
試算表は、可能な限り、迅速かつ正確に作成することが好ましい。試算表ができ上がるのが遅くなれば、その分、会社の経営改善のための意思決定も遅くなるし、できたものが不正確であれば、誤った意思決定をしてしまう可能性も出てくる。
迅速性の点については、できれば月末に締めた数字を元に翌月15日ころまでには実際値を元にした試算表ができているようにしたい。正確性の点については、請求書や通帳の適切管理、経理書類の整理、在庫の正確な把握等の前提が必要であり、そのためには会社内の各部署と経理部門や外部専門家とのスムーズな連携が求められる。
(3) 資金繰り表(日次)の分析
資金繰り表(日次)は、会社の日々の資金状況の集計表である。貸借対照表の勘定科目のうち現金と預金の部分のみを一日単位で記録したものであるが、単純に「入金」と「出金」だけで管理するのではなく、具体的な入出金の中身(例えば、入金であれば売上なのか借入金入金なのか、出金であれば仕入支払いなのか借入金返済なのか納税なのか等)について、区分ごとに色分けして可視化するとなお良い。
このような資金繰り表を元に、現預金残高の減少が続いている場合に資金ショートの可能性がある日を予測したり、逆に資金に余裕があるタイミングを見定めたりすることができる。そこを出発点として、経営改善のスケジュールと方策を検討することとなる。
3 緊急時の財務状況改善のポイント:まずは利益確保より資金確保
本来、財務状況の改善のためには、本業での「利益」の確保と、手元「資金」の確保の両面からのアプローチが必要であるが、今回のコロナショックのような緊急時においては、まずは資金確保を優先すべきである。
先述のとおり、企業活動が「手元資金を活用して事業を行い、それによって利益を獲得して資金を生み出し、それをまた事業に使う」ことの循環であるとして、その出発点はあくまでも手元資金である。手元資金が枯渇すれば事業活動そのものが立ち行かなくなり、最悪、倒産が現実味を帯びてくる。資金に余裕があればこそ、経営者は心理的余裕をもって経営に専念でき、金融機関への返済や経費の削減に頭を悩ませたり、取引相手との条件交渉で足元を見られたりしなくて済む。
したがって、緊急時の財務状況の改善策としては、まず、資金繰りに焦点を当て、融資や補助金などの資金を増やすための手段と、金融債務のリスケや各種支払いの繰り延べなどの資金流出を減らすための手段の検討を最優先で行うべきである。次回の記事(4/16公開予定)ではこの点に焦点を当てる。
4 専門家への相談
多忙な経営者が、上記のような分析や検討を独力で行うことは無理がある。また、会社の顧問税理士が、「経営改善に役立つ」財務分析資料の作成や分析、それらに基づく資金繰りの助言に対応できるとは限らない(これは税理士が悪いという意味ではなく、会社が従前から顧問税理士に依頼していた内容と財務状況の改善のために必要な内容がかけ離れているという側面が大きい)。そのような場合には、経営改善に強い税理士や資金繰りコンサルタント等の専門家の関与があることが望ましい。
なお、会社の経営状況を良くするためには、結局のところ、経営に関して責任を持つ者が主体的に動くことが必要不可欠である。経営改善について専門家が関与する場合でも、経営者は全てを他人任せにしてはならず、必ず自分自身が腑に落ちるまで説明を受けて情報を共有し、当事者意識をもって各種対応にあたるべきである。
(了)
次回は4/16の公開予定です。