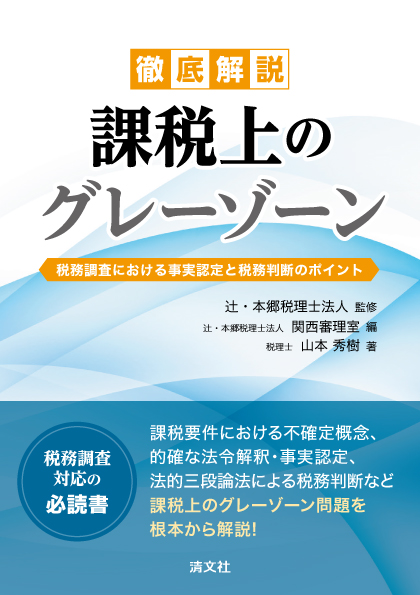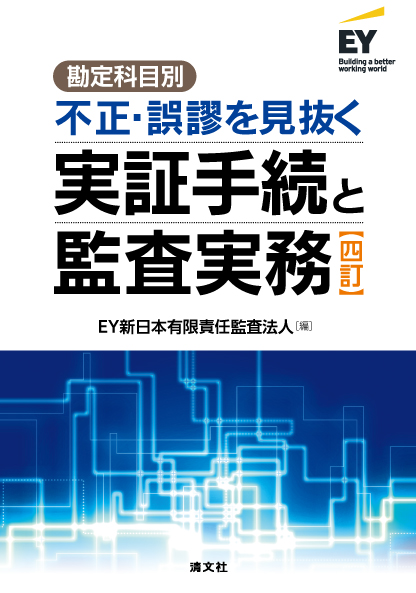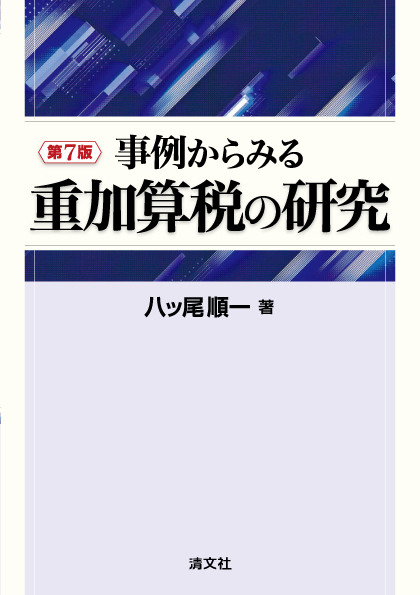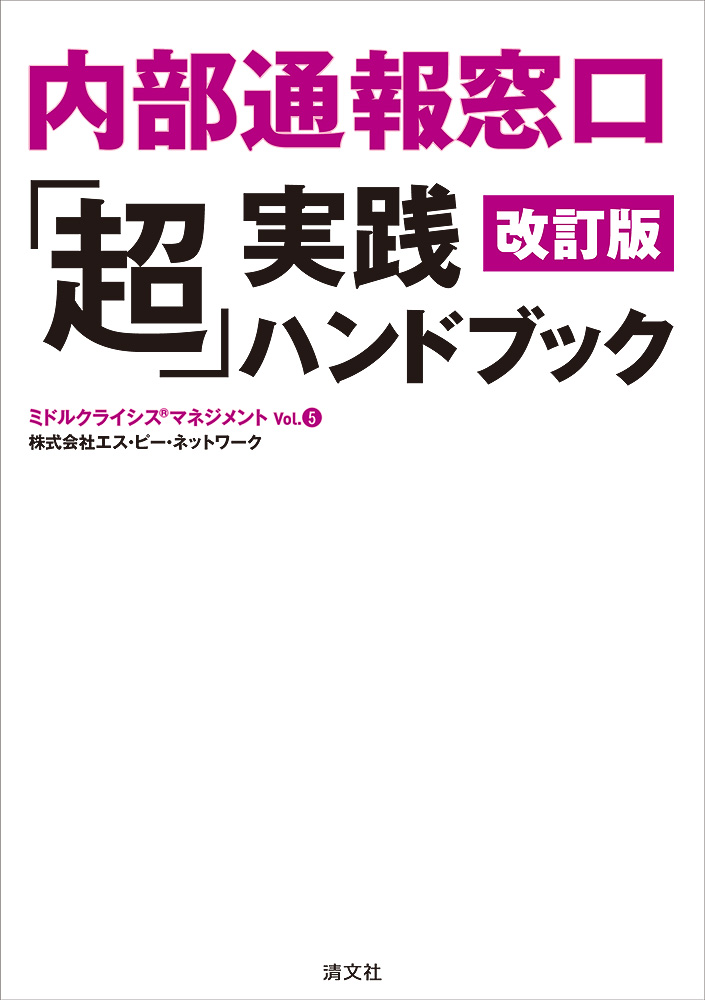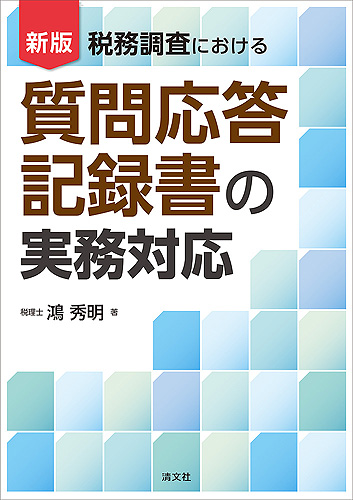社長の帰還
小泉と新田は社長の自宅から引返して食事をとった後、30分ほど前から店の前で様子をうかがっていた。その間、藤田社長らしき人物は戻って来なかった。
時間になり2人が店に入ると、ミキと税理士の林が待っていた。
いかにも育ちが良さそうな感じの林税理士に対し、小泉は調査に入った経緯、午前中の調査の経過を説明した。聞けば林の父親も税理士で、息子の林は3年ほど前に税理士試験にやっと合格したらしい。現在37歳で父親と二人三脚で税理士事務所の業務をしているとのこと。無予告調査について苦情を言うこともなく、小泉と談笑をしながら、社長の藤田が戻るのを奥の小部屋で待っていた。
ミキも林税理士が来たからか、午前中に比べ少し落ち着きを取り戻していた。2人の調査官と林にコーヒーを出し、店の出入り口を気にしながら言った。
「早く帰って来ないかしら、いったいどこに行ったんでしょう。兄さんったら・・・」
林税理士が預かっていたすし勢の総勘定元帳を調べたり、午前中の続きで聴取り調査を行っているうちに、時計は4時を回っていた。そろそろ調べることもなくなり、話も尽きかけたころ、店の出入り口に右足を引きずる一人の男がヌッと現れた。
昼間から酒を飲んでいるのか顔が赤黒く光っている、とにかく尋常な顔色ではない。
「・・・ミキ、今帰った。」
驚くミキ
「兄さん!どこに行っていたの? 税務署の人がお待ちかねよ。」
小泉と新田はすかさず藤田社長に来意を告げ、身分証明証を提示した。
藤田は身分証明証に目をやることもなくソッポを向きながら
「税務署? 何しに来たんだ。俺は何も悪いことなんてしちゃいない。」
ミキが言う
「だって兄さん、急にいなくなるんだもの。なぜ逃げたの?」
藤田
「何、逃げた?俺が?? 俺は逃げてなんかいない。急に用を思い出したから出かけただけだ。それの何が悪い。」
酒臭い息を吐きながら我を張る藤田を前に、先行きが怪しまれた。
たしかに藤田社長はどう見ても体の具合が悪そうだ。現在39歳のはずだが、多楠が言っていたように、60歳代、しかも後半の老人に見える。長年の飲酒や喫煙が招いた結果なのか。
小泉調査官は思った。
“多楠君がこの社長を老人に見誤ったのもよくわかる。この間、内偵調査のときに社長はカウンターの中ですしを握っていたはず。あのとき、一見老人に見えるこの目の前の男が39歳の社長だとは自分ですら考えも及ばなかった。ベテランの寿司職人くらいの感じで見ていた。”
“カウンター越しの藤田は、はつらつと元気に寿司を握っているように見えた。それが職人気質なのか。”
そんな思いを巡らせながら、小泉が切り出した。
「社長、現金出納帳と売上帳はどうしましたか。」
藤田
「出納帳? そんなもの知らねぇ。」
そんなはずはないと食い下がる小泉に、知らないと言い続ける藤田、ここで新田が口を開いた。
「知らないわけがないでしょう。妹さんは今朝までこの小部屋にあったと言っています。」
それを聞いた藤田は、シワだらけの顔の中にあって埋もれそうな小さな目を、これ以上開けられないぐらい大きく見開いて言った。
「そうだ! 捨てた、捨てたんだよ!」
新田は表情を変えずに続ける
「どこに?」
藤田社長
「・・・忘れた。酔っぱらってたから・・・」
このやり取りに呆れ顔のミキと林税理士であったが、小泉と新田はけっしてあきらめない。2人して懸命に社長を諭す。
「捨てるはずがない。社長、ちゃんと答えてください。」
実は、一般的に藤田のような職人が調査で最も手強い相手なのだ。怖いもの知らず、まして酔っぱらっているからまともな会話にならない。
▼ ▲ ▼
東上野税務署、庁舎の外はすっかり日が暮れていた。
4時過ぎに小泉調査官から藤田社長が店に現れたといったん連絡が入り、一度は安堵した田村と多楠であったが、その後5時半ごろ再び田村の携帯電話に小泉から連絡が入った。
「お疲れ様、田村です。」
「何? これから社長と一緒に自宅に帳簿を取りに行くだって? 自宅は文京区白山・・・わかった。気をつけて、夜も遅くなるし、調査先の営業もあるから早めに切り上げて、ご苦労様。」
多楠は田村の電話でのやり取りを聞いて思った。
“どうやら新田さんと小泉さんは帳簿を確認するために、藤田社長の自宅に向かうらしい。・・・これは長期戦になるな。”
6時ごろまで2人を気遣っていた淡路調査官であったが、子供の保育園のお迎えがあるからと帰って行った。三浦は所用があるとのことで5時過ぎに早々と帰っていた。
時刻はとうに午後8時を回っていた。昼は狭い庁舎の中で大勢の人がひしめく東上野税務署であったが、今は閑散としている。3階の法人課税部門には田村統括官と多楠、あとわずかの職員しか残っていない。副署長室で待機している安倍、法人課税部門の総責任者である法人課税第1部門の柳沢統括官と部下数名、あとは2階の総務課の職員ぐらいである。
田村も多楠も、夕食をとっていない。多楠はというと、今日一日、まったく仕事が手につかなかった。
新田の鬼のような顔が脳裏に焼きついて離れない。
社長の自宅に向かった2人はその後どうなったんだろうと気がかりな多楠、長い沈黙と静寂が続く。
人気がなくなった税務署の庁舎はすっかり静まり返っていた。
そのとき、田村の携帯電話が鳴った。
それは小泉からの電話であった。
(続く)
この物語はフィクションであり、登場する人物や団体等は、実在のものとは一切関係ありません。
〔小説〕『東上野税務署の多楠と新田』は、毎月第1週に掲載されます。