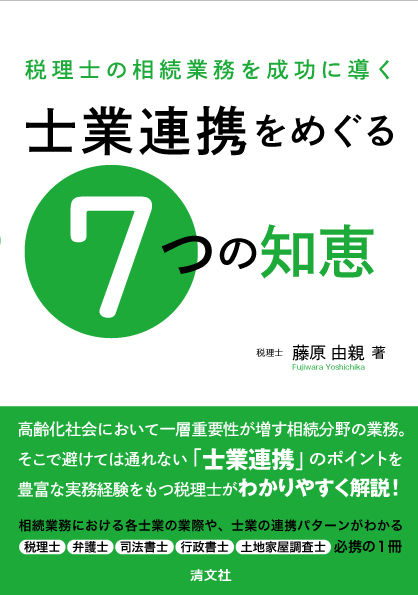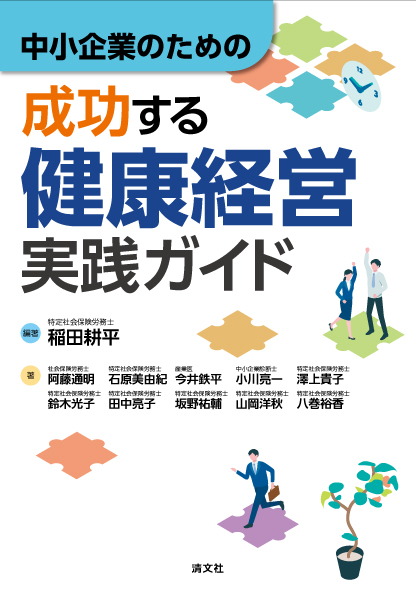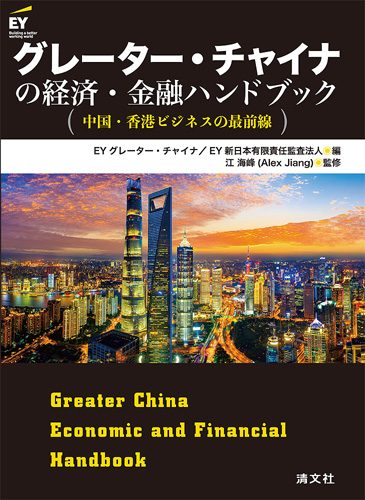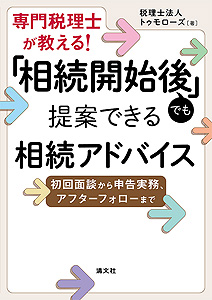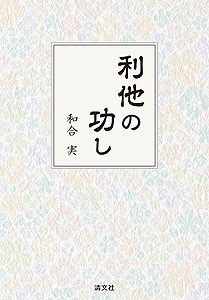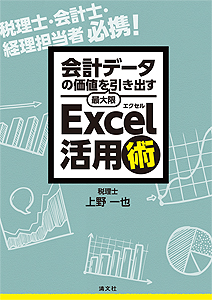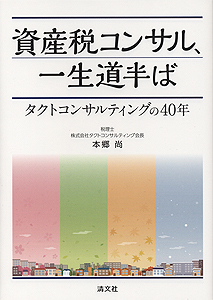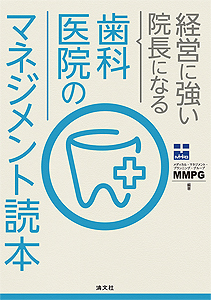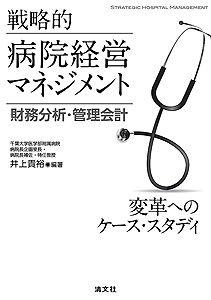〔新規事業を成功に導く〕
フィージビリティスタディ10の知恵
【第12回】
(最終回)
「公的支援制度を上手く活用するには(後編)」
中小企業診断士 西田 純
前回は、特に海外でフィージビリティスタディを実施するために役立つ各種公的支援制度のご紹介と、採択確率を上げるためのノウハウについてお伝えしました。最終回の今回は、公的支援制度に採択された後の実施段階で気を付けるべき点についてお伝えします。
* * *
日頃の学会活動や自腹を切っての現地調査、現地エージェントとの関係作りなどが奏功し、厚みのある企画書が評価されて無事公的支援制度で採択されたとします。採択される企業(案件)の数は制度によっては2~3社(件)だけという場合もありますし、逆に10社を超える企業からの提案が一度に採択される場合もありますので、採択後の事務手続きは制度によってバラつきがあるようですが、どれも一様に報告書の作成と提出締切スケジュールが最初から決められている、と考えておいて間違いはありません。
この報告書が成果物として扱われるケースが多いですので、それを目指して決められた期間のうちに何度か現地を訪問し、現地でセミナーを開き、短期研修生を日本に受け入れ、さらに事業の実証試験を現地と日本で実施する、というようなプロセスを踏むことになります。
これら活動の記録が最終的には報告書の骨子となるのですが、実施機関との契約交渉もそれを前提に進められます。JICAの案件などでは分厚い契約書が出来上がってきますが、先方にはこれまで数多くの企業と実施してきた知見が溜まっていますので、いったん業務がスタートすれば思いのほか早く書類手続きが進められていきます。
さて契約が無事に整い、いよいよF/S事業の実施が始められるところまで来たとします。これまでお話してきた技術的な知恵に加えて、以下のような点に気を付けてスタートさせると円滑で有意義な事業が実施できると思います。
▷ 実施機関に「ファン」を作る
JICAにしても各省庁にしても、実施機関にはそれぞれ独自の政策課題というものが存在しています。彼らからすれば、公的支援制度を実施することで実現したいゴール、のようなものですが、採択された事業にもさまざまなものがあり、必ずしもすべての案件が上手く政策課題を満足させるというわけではなかったりします。同じ制度で採択した案件でも「良い子・悪い子・普通の子」がいるというわけですね。
最初の評価がどうあれ、事業の実施を通じて最終的には彼らの政策課題に貢献するような流れに持って行ければ、担当者は必ずファンになってくれるのですが、そうすると政策担当者として持っている情報の中から実際の事業展開に役立つような情報を教えてくれるようになったりします。
そのために心がけるべきことは、円滑で密度の濃いコミュニケーションを取る努力、でしょうか。
単に面談するだけでなく、必ずパワーポイントの資料を用意し、それが内部の説明資料などに転用しやすいように配慮する、契約上要求されていなくても、現地調査の前後には必ず短時間報告できる機会を設ける、ウェブサイトを頻繁にチェックし、支援制度や採択案件に近いと思われる情報は把握しておくなどの努力により、「この人は自分たちの事業の意義について理解してくれている」と担当者に思わせることができればしめたものです。
▷ 実施機関の現地関係者を大事にする
多くの場合、各種支援制度は実施機関の本部(=東京)を中心に運営されており、現地事務所や大使館などにとっては、あくまで進捗を把握しておくだけの対象と認識されている場合が多いようです。
ところがビジネスを進める立場から言えば、F/Sを実施すればそれで終わりというわけではなく、むしろ実際に事業が進み出した後の現地における橋頭堡(きょうとうほ)作りが課題となってくるわけですから、F/S段階とはいえ現地関係者とのチャネルをしっかり作っておくことに越したことはありません。
あまり頻繁に報告に行くのもためらわれるかもしれませんが、プロジェクトリーダーが出張した際には必ず現地事務所を訪問する、など対応のルールを決めておき、たとえ挨拶だけであっても現地のオフィスを訪れ、進捗に関わる報告をしておくことをお勧めします。
▷ 現地パートナー企業とのチャネルをできるだけ太くする
F/S段階を経て実際の事業展開を進めるために何よりも重要なのは、現地パートナー企業との太くて活動的なチャネルを持つことでしょう。公的支援制度を使って調査を実施できることの大きなアドバンテージとして、このチャネル作りにしっかりと時間を使えることが挙げられます。現地での調査活動、セミナー実施、実証試験そして日本への受入研修など、さまざまなフェーズで先方とのチャネルが強化できる機会があるので、ぜひそれらを活用して複合的なチャネルづくりを心掛けてください。
他方で、報告書作成については本連載の1回目から10回目にかけてお話したように、「市場予測」に軸足を置いた「収益予測」を行う中で、「リスク対応策」をしっかり提案し、それを「見える化」できれば報告書の中で「仮説検証」プロセスの結果を伝えやすくなります。そのために重要な「現地調査」を円滑に進めるには、出発前の「事前調査」が重要だということもお伝えしましたね。「社内の立ち位置」にも配慮しつつ、御社の将来にとって有意義な新規事業の提案を進めて行くために、公的支援によるF/S事業は重要な役割を果たします。
提案が採択された暁にはこれらの技術的な視点をしっかり保ちつつ、実施機関とのコネクションを活かして事業推進に役立つフィージビリティスタディを実施されることをお祈りします。
* * *
さて、これで私のフィージビリティスタディに関するお話はおしまいです。一年間ご愛読いただき、どうもありがとうございました。
(連載了)