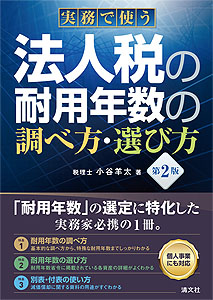「生産等設備投資促進税制」
適用及び実務上のポイント
【第1回】
「制度の全体をおさえる」
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士 村田 直
◆「生産等設備投資促進税制」新設の背景
平成25年3月29日に「所得税法等の一部を改正する法律案」が国会で成立し、同3月30日に公布された。今回の税制改正は、平成24年12月の衆議院選挙の結果を受けた政権交代により、自民党が中心となって作成した「平成25年度税制改正大綱」が基となっている。
平成25年度税制改正大綱の冒頭においては、今回の税制改正の基本的考え方として、その1つに、「成長による富の創出に向けた税制措置」を挙げている。景気の底割れを回避し、「成長と富の創出の好循環」を実現するため、特に日本経済再生に向けた緊急経済対策の施策については、その効果が最大限に発揮されるよう、期限を区切り、大胆かつ集中的に税制上の措置を講ずる、としている。
その具体的項目として、「民間投資の喚起による成長力強化」、「人材育成・雇用対策」、「中小企業対策・農林水産業対策」を挙げ、「民間投資の喚起による成長力強化」については、以下のように、「生産等設備投資促進税制」を新設する、としている。
「成長と富の創出の好循環」を実現し、わが国経済を再生していくためには、製造業を中心とする投資に対する慎重な姿勢を反転させ、設備投資の拡大によって経済の底上げを図るとともに、生産設備の更新を通じて産業競争力の強化を図る必要がある。このため、国内における設備投資へのインセンティブを広く付与する生産等設備投資促進税制を創設し、生産等設備への投資額を一定以上増加させた場合に、新たに取得等をした機械・装置について特別償却・税額控除を可能とする。
(「平成25年度税制改正大綱」第一 平成25年度税制改正の基本的考え方より)
上記の根底には、いわゆる“アベノミクス”と呼ばれる安倍政権の経済政策がある。
アベノミクスは、「大胆な金融政策」「機動的な財政政策」「民間投資を喚起する成長戦略」の“3本の矢”で構成されており、今回の税制改正はまさに、この「民間投資を喚起する成長戦略」を税制面で後押しするもので、その中でも「生産等設備投資促進税制」は、今回の“アベノミクス減税”の目玉政策の1つとして注目されている。
◆「生産等設備投資促進税制」の全体像
「生産等設備投資促進税制」の概要については、平成25年度税制改正大綱において、以下のように記載されている。
(1) 国内設備投資を促進するための税制措置の創設
青色申告書を提出する法人の平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度(設立事業年度を除く。)において取得等をした国内の事業の用に供する生産等設備で、その事業年度終了の日において有するものの取得価額の合計額が次の①及び②の金額を超える場合において、その生産等設備を構成する資産のうち機械装置をその法人の国内にある事業の用に供したときは、その取得価額の30%の特別償却 とその取得価額の3%の税額控除との選択適用ができることとする。ただし、税額控除における控除税額は、当期の法人税額の20%を限度とする(所得税についても同様とする。)。
① その法人の有する減価償却資産につき当期の償却費として損金経理をした金額
② 前事業年度において取得等をした国内の事業の用に供する生産等設備の取得価額の合計額の110%相当額
(注1) 生産等設備とは、その法人の製造業その他の事業の用に直接供される減価償却資産(無形固定資産及び生物を除く。)で構成されているものをいう。なお、本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設等は、該当しない。
(注2) 償却費として損金経理をした金額は、前事業年度の償却超過額等を除き、特別償却準備金として積み立てた金額を含む。
(「平成25年度税制改正大綱」より)
また、地方税の項目においては、中小企業者等に限り、「法人税の特別償却又は税額控除を法人住民税及び法人事業税に適用する」と規定されている。
◆「生産等設備投資促進税制」の条文構成
「生産等設備投資促進税制」の概要は上記のとおりであるが、実際の条文では、租税特別措置法において、法人及び個人向けにそれぞれ規定されている。
法人については、「国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却又は法人税額の特別控除」として第42条の12の2(連結納税に対応する条文は、第68条の15の3)に、個人については、「国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却又は所得税額の特別控除」として、第10条の5の2に規定がある。
政省令も既に公布されており、租税特別措置法施行令において、法人については第27条の12の2(連結納税に対応する条文は、第39条の45の3)、個人については第5条の6の2に規定されている。なお、「生産等設備投資促進税制」に関する法令解釈通達などについては、現時点(執筆5/4)でまだ発表されていない。
この「生産等設備投資促進税制」は、該当すると税効果のインパクトがかなり大きくなるケースが想定される。
ただし、設備投資を前提とする減税措置ということは、当然、事前に周到な計画が必要になる。また、適用事業年度の前事業年度の設備投資も、本税制の適用にあたって大きく影響する。
専門家としては、今後、相談やアドバイスを求められる場面が増えると予想されることから、適用要件等をしっかり把握し、的確に助言することが必須となる。
次回からは、本制度の詳しい要件の検討に入りたい。
(了)
「「生産等設備投資促進税制」適用及び実務上のポイント」は、隔週の掲載となります。