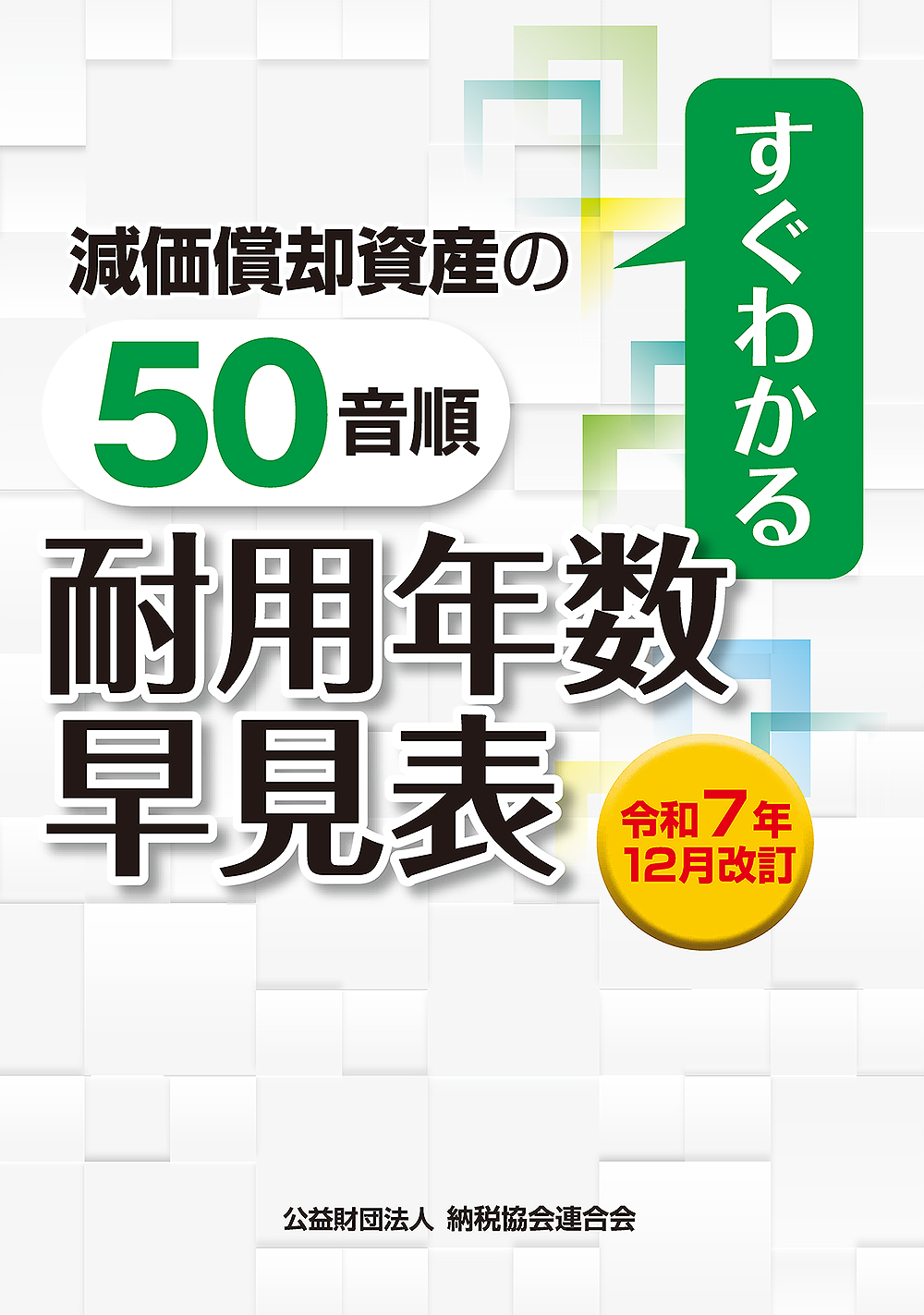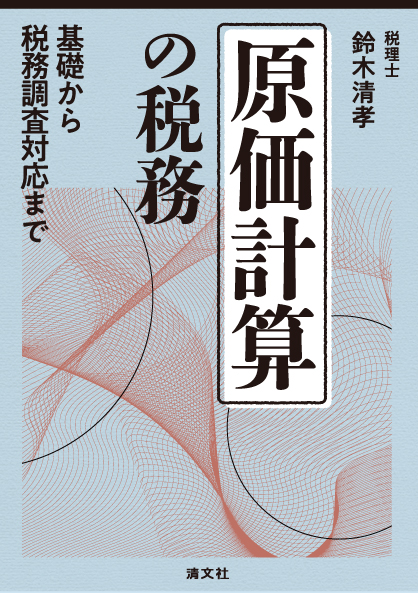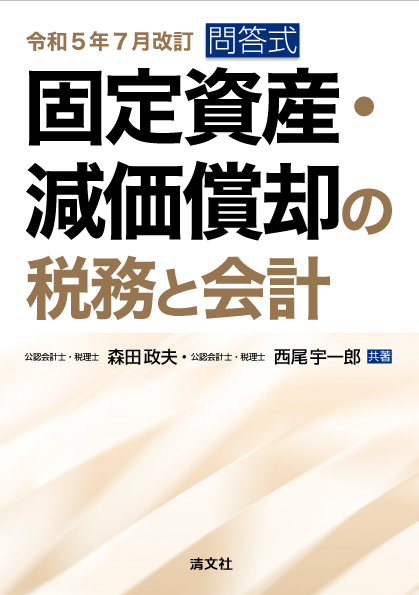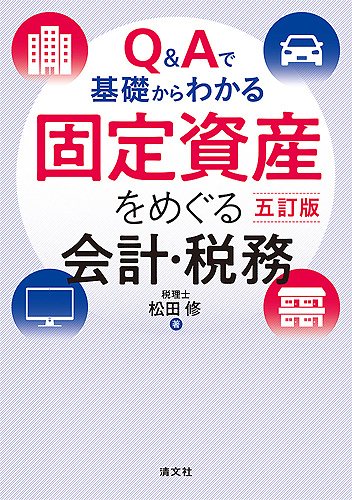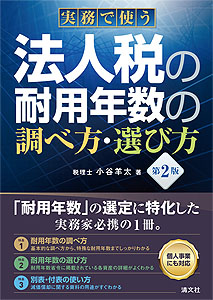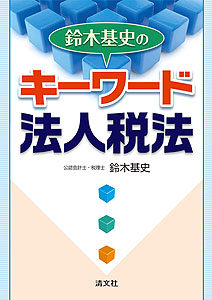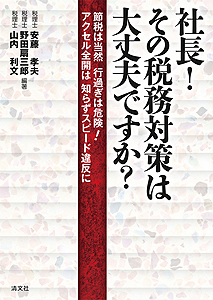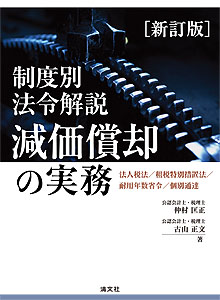法人税の解釈をめぐる論点整理
《減価償却》編
【第1回】
弁護士 木村 浩之
1 はじめに
減価償却をめぐっては、もとより、税務調査等において、資本的支出と修繕費の区分が問題となることが非常に多いといえるが、そのほか、減価償却資産とその他の資産との区分(減価償却資産の範囲)、固定資産の取得価額、少額の減価償却資産等の判定、耐用年数表の適用、除却損失の計上など、その論点は多岐にわたっている。
また近年、減価償却に関する重要な税制改正が相次いでなされており、償却限度額を計算するに当たっても、留意すべき事項は多いといえる。
そこで、本稿では、減価償却をめぐる主要な論点について整理し、6回にわたって解説することとしたい。取り上げる予定のテーマは、以下のとおりである。
① 減価償却資産の範囲
② 固定資産の取得価額
③ 少額の減価償却資産等の該当性
④ 資本的支出と修繕費の区分
⑤ 償却限度額の計算
⑥ 耐用年数表の適用
⑦ 除却損失の計上
2 減価償却資産の範囲
(1) 減価償却資産の一般的要件
減価償却の対象となる資産は、法人税法上、「建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう」とされている(法法②二十三)。
これを受けた政令は、「棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの(事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)」として、減価償却資産に該当する資産を具体的に列挙した上で、その範囲から一定の資産を除外している(法令13)。
また、明文に規定はないものの、他人の保有する資産を事業の用に供したとしても、それは自己の減価償却資産とはならないのであるから、減価償却の対象となる減価償却資産については、「自己が保有するものであること」が当然の前提であると解されている。
そこで、減価償却資産に該当するための一般的な要件として、
① 棚卸資産等に該当しないこと
② 事業の用に供していること
③ 時の経過により減価すること
④ 自己が保有する資産であること
という要件が導かれる。以下、順に解説する。
(2) 棚卸資産等に該当しないこと
ア 棚卸資産との区分
棚卸資産とは、法人税法上、「商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で棚卸しをすべきものとして政令で定めるものをいう」とされ(法法②二十)、政令がこれらをより具体的に列挙している(法令10)。
(棚卸資産の範囲)
法令第10条 法第2条第20号 (棚卸資産の意義)に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
一 商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)
二 半製品
三 仕掛品(半成工事を含む。)
四 主要原材料
五 補助原材料
六 消耗品で貯蔵中のもの
七 前各号に掲げる資産に準ずるもの
列挙されているものに共通する考え方は、棚卸資産となるのは、販売用の資産であるか、あるいは販売用資産の製造等に使用されて短期間に消費されるものであるということである。
したがって、次の要件のいずれかを満たすものは棚卸資産に該当し、減価償却資産と区分されることになる。
〈減価償却資産から除かれる棚卸資産〉
① 販売用の資産
② 販売用資産の製造等のために短期間に消費される資産
例えば、①についていえば、販売促進を目的とした展示物がある場合、それを後に販売する予定であれば棚卸資産に該当することとなり、販売が予定されていなければ減価償却資産に該当することとなる。
また、②についていえば、製造に使用される資材がある場合、それが反復継続して使用されず、短期間に消費されるものであれば、棚卸資産(貯蔵品)に該当することとなり、反復継続して使用されるものであれば、減価償却資産に該当することとなる。
イ 繰延資産との区分
繰延資産とは、法人税法上、「法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう」とされ(法法②二十四)、政令は、「法人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち次に掲げるもの」として、繰延資産に該当するものを具体的に列挙した上で、その範囲から一定のものを除いている(法令14①)。
(繰延資産の範囲)
法令第14条 法第2条第24号 (繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、法人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。
一 創立費(発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきものをいう。)
二 開業費(法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。)
三 開発費(新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発又は市場の開拓のために特別に支出する費用をいう。)
四 株式交付費(株券等の印刷費、資本金の増加の登記についての登録免許税その他自己の株式(出資を含む。)の交付のために支出する費用をいう。)
五 社債等発行費(社債券等の印刷費その他債券(新株予約権を含む。)の発行のために支出する費用をいう。)
六 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる費用で支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもの
イ 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用
ロ 資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立ちのき料その他の費用
ハ 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
ニ 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
ホ イからニまでに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用
(以下略)
この繰延資産から除かれるものとして、「資産の取得に要した金額とされるべき費用(固定資産の取得価額を構成するもの)」がある。このことから、法人が支出する費用のうち、固定資産の実質的な対価となるものについては繰延資産には該当せず、そのような対価関係のない事実上の効果を有するにすぎないものが繰延資産に該当することになる。
例えば、商標や意匠(デザイン)等の作成費用については、権利として登録する場合には、その実質的な対価として権利(固定資産)の取得価額を構成するのに対して、権利として登録しない場合には、そのような対価関係のない事実上の効果を有するにすぎないものとして、固定資産ではなく、繰延資産に該当し得ることになる。
(3) 事業の用に供していること
「事業の用に供している」というためには、単に「資産を保有している」というにとどまらず、その資産を実際に使用し、それが収益を生む源泉となっていると認められることが必要である(最判平成18年1月24日・民集60巻1号252頁参照)。
したがって、いわゆる稼働休止資産については、収益を生む源泉とはなっていないことから、事業の用に供しているとはいえず、減価償却資産とはならない。
もっとも、現実に収益を生んでいないとしても、単に保管するだけにとどまらず、いつでも事業の用に供することができるように維持管理等されているものについては、潜在的には収益の源泉となるべきものであるから、減価償却資産に該当し得ると解される。
例えば、賃借人のいないマンションであっても、入居者を募集している場合には事業の用に供しているといえるのであり、減価償却資産に該当することになる。また、稼働休止中の資産であっても、稼働中の資産の控え(スペア)等としてメンテナンスを継続されている場合には、減価償却資産に該当することになる(法基通7-1-3参照)。
(4) 時の経過により減価すること
減価償却資産に該当するためには、時の経過により減価する(価値が低減する)ものであることが必要である。ここでいう減価には相場の変動といったものを含まず、資産そのものが消耗等することによって減価するものであることが必要である。
したがって、土地等が減価償却資産には該当しないことはもちろん、美術品、芸術品、骨董品、クラシックカーなど、主にその資産が持つ物理的な効用以外に大きな価値が認められているものについては、減価償却資産には該当しない(法基通7-1-1参照)。
(5) 自己が保有する資産であること
減価償却の対象となる資産は、原則として、自己が所有する資産である必要がある。ただし、次の例外がある。
ア 形式的な所有権の場合
自己が所有する資産であっても、その所有権が形式的なものにすぎない場合には、実質的な資産価値を保有するものとはみられず、減価償却資産とはならない。逆に、他人が所有する資産であっても、その所有権が形式的なものにすぎず、自己が実質的な資産価値を保有するとみられる場合には、減価償却資産となり得る。
例えば、自己所有の資産を譲渡担保によって所有権移転した場合であっても、その所有権移転は担保提供を目的とした形式的なものであり、実質的な資産価値の移転を伴ったものとはいえないことから、その資産は自己が保有するものといえる。
また、同様に、自己が購入した資産を所有権留保によって所有権移転していない場合であっても、その留保された所有権は担保目的の形式的なものであり、実質的な資産価値の移転はあるといえることから、その資産は自己が保有するものといえる。
イ 他人の資産に対する資本的支出の場合
他人の資産に対する資本的支出であっても、その価値を実質的に保有するとみられる場合には、減価償却資産となり得る(耐通1-1-4参照)。すなわち、賃借した他人の土地や建物に資本的支出をした場合であっても、その価値が増加した部分を自己が使用収益し、かつ、その使用収益に関する何らかの権利性が認められるのであれば、自己の保有する減価償却資産に該当することになる。
裁判例においても、自己の事業の用に供している他人の資産につき、資本的支出があった場合には、仮にその資産を正当に使用する権限がなかったとしても、実際に使用収益しており、かつ、費用償還請求権などの権利を有している場合には、その実質的な価値を保有するものとして、自己が保有する減価償却資産に該当することが認められている(大阪高判昭和38年7月18日・税資37号795頁参照)。
これに対して、資本的支出によって価値が増加した部分に権利性があるとまでは認められず、その実質的な価値を保有するものではない場合には、繰延資産又は寄附金に該当することとなる。
なお、賃借建物に対する造作についても、以上と同様に解することができる(耐通1-1-3参照)。
次回は固定資産の取得価額について整理する。
〔凡例〕
法 法・・・法人税法
法 令・・・法人税法施行令
法基通・・・法人税基本通達
耐 通・・・耐用年数の適用等に関する取扱通達
(例)法法34①三・・・法人税法34条1項3号
(了)