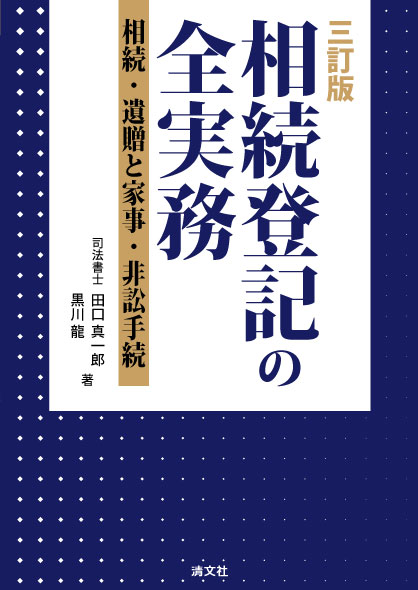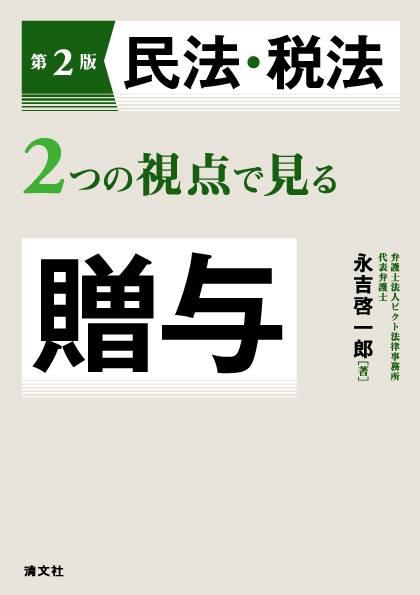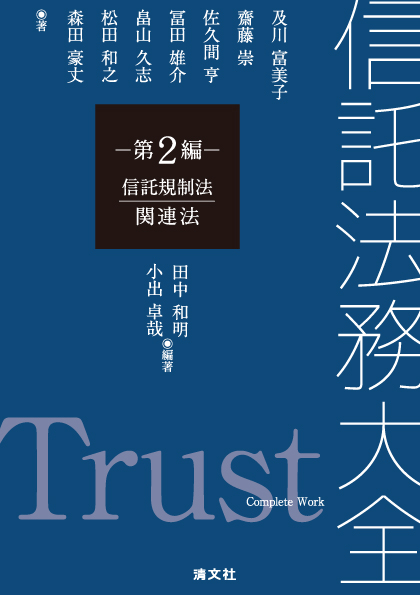〈Q&A〉
税理士のための成年後見実務
【第1回】
「どんな場合に成年後見制度の利用が必要になるのか」
司法書士法人F&Partners
司法書士 北詰 健太郎
◆連載開始にあたって◆
認知症を患う高齢者の人数が増加しており、2025年には700万人にもなるといわれています(※1)。これにともない、認知症等により判断能力が不十分な人などのサポートを行う制度である「成年後見制度」の利用者も増加傾向にあります。2022年12月末時点での成年後見制度(成年後見、保佐、補助、任意後見)の利用者は、約245,000人でした(※2)。成年後見人等の援助者に専門家が就任する場合、司法書士や弁護士が就任することが多いですが、税理士もわずかではありますが、成年後見人等として活動している実績があります。
(※1) 厚生労働省「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)~認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて~(概要)」
(※2) 最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況-令和4年1月~12月-」
成年後見業務は、本人と家族との関係性や、財産の額、内容等によって注意点や対応方法が異なり、実務の現場では答えのない問題にあたることが多い業務です。おそらく成年後見業務に対応している税理士の方々は、相談できる同業の方なども少なく、悩みながら対応されているのではないかと思います。
本連載では、成年後見業務に関心がある税理士の方々を念頭に、実務の現場で起こりうる問題と対応方法等について、司法書士がQ&A形式で解説します。
【Q】
「成年後見制度」の存在は知っていますが、どのようなケースで利用されているのでしょうか。
【A】
税理士の方のなかには、「成年後見制度がどんな場合に利用されることになるのかわからない」という方もいらっしゃると思われます。
実際に成年後見制度の利用に至るケースを知ると、実は今まで気が付かなかっただけで、成年後見制度のニーズが発生していたということがあるかもしれません。
以下の解説で具体的なケースを確認します。
● ● ● ● 解 説 ● ● ● ●
現に成年後見制度を利用されている方も、何らかのきっかけがあり、思いがけず利用することになったという方が多いと思われます。成年後見制度の利用に至るケースとして多いのは以下の通りです。
1 不動産の売却が必要なケース
高齢者の方が施設に入所することになり、不要となった自宅を売却することがあります。この場合に不動産の所有者である高齢者の方が、認知症により判断能力が低下していると、不動産の売却が困難となることがあります。売買契約を締結するにも法的には一定の判断能力(意思能力)が必要とされており、判断能力がない状態で締結した契約は無効となるためです。
所有者の判断能力が低下した状態でも、生活資金を捻出するためにどうしても早期に売却が必要な場合は、成年後見制度の利用をすることになります。司法書士のもとには所有者の家族や仲介を担当する不動産会社から相談を寄せられることがあり、その流れで成年後見人への就任を依頼されることがあります。
2 遺産分割協議を行うケース
相続が発生し、遺産分割協議を行う場合、有効に遺産分割協議を行うためには、参加した相続人に十分な判断能力が備わっている必要があります。もし判断能力を欠いた状態で遺産分割協議を行っても、遺産分割協議自体が無効となってしまうリスクがあります。相続手続を進めていくなかで、相続人のうちに認知症等により判断能力が十分でない方がいることが判明した場合には、成年後見制度の利用を検討することがあります。
3 その他
上記1、2のほかにも、高齢者施設や行政機関等から身寄りのない高齢者の方のサポートの依頼を受けたり、お付き合いのある顧客から顧客自身や身内の成年後見人への就任を依頼されたりする場合などがあります。
4 認知症の問題にどのように向き合うべきか
税理士実務を行ううえでも、顧客の判断能力の程度が問題になる事例は少なくないと思います。上記2で紹介した遺産分割協議以外にも、例えば、生前対策として贈与を行う場合には、贈与当事者に判断能力が備わっていることが前提になります。どの程度厳密に判断能力を求めていくかについては、顧客と各専門家の考えによることになりますが、認知症を患うことが珍しいことではない現代では、しっかりとした確認をしたうえで実行することが必要だというのが筆者の考えです。仮に判断能力が十分でない状態で生前贈与を行っても、後々無効を争われる可能性もあり、顧客に不利益を与えることにつながりかねません。成年後見制度には、さまざまな課題がありますが、認知症を患う方が増加していくなかでは必要な制度です。本連載を通して税理士の方々に、成年後見制度を少しでも身近に感じていただければと考えています。
(了)
「〈Q&A〉税理士のための成年後見実務」は、毎月第2週に掲載されます。