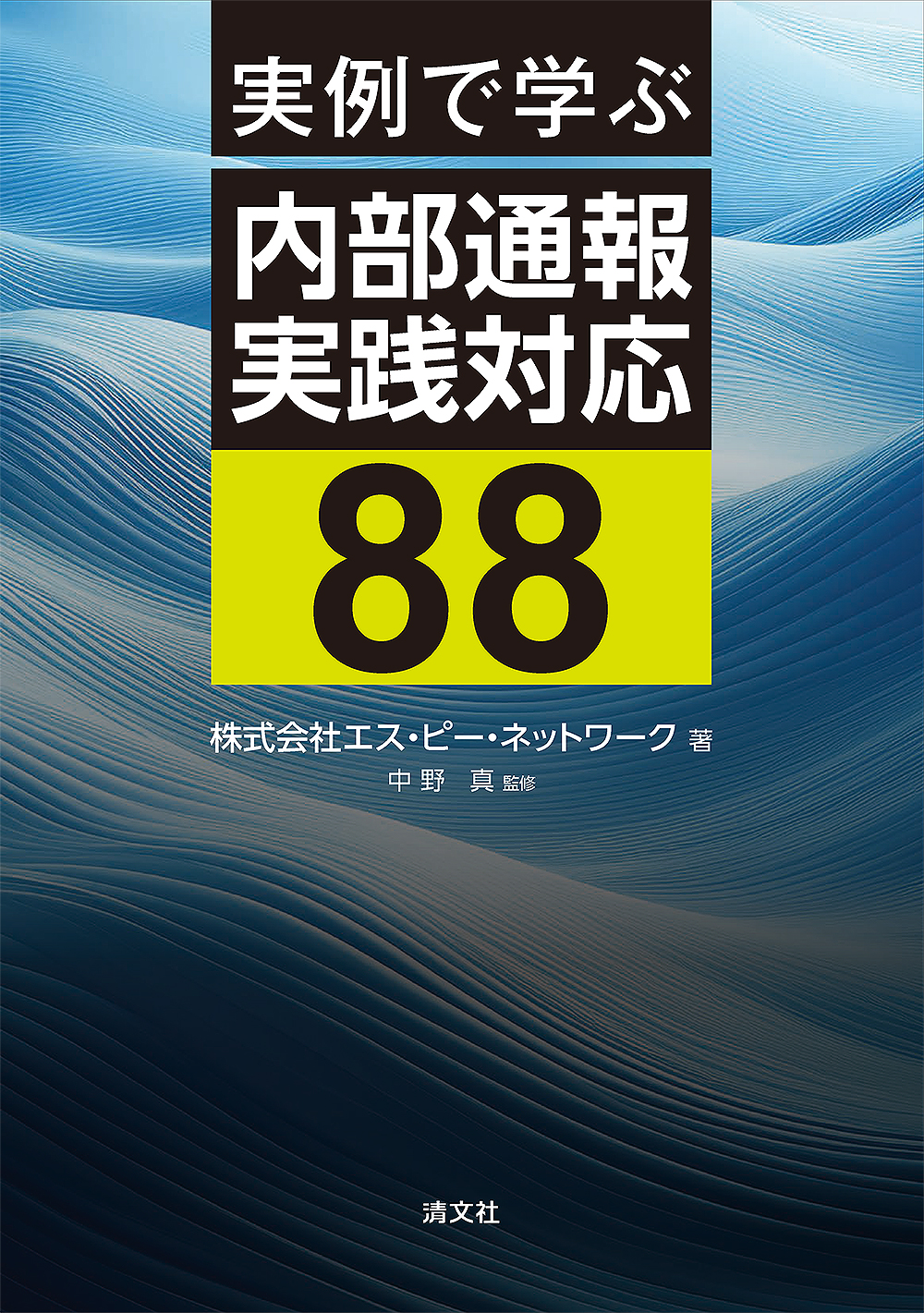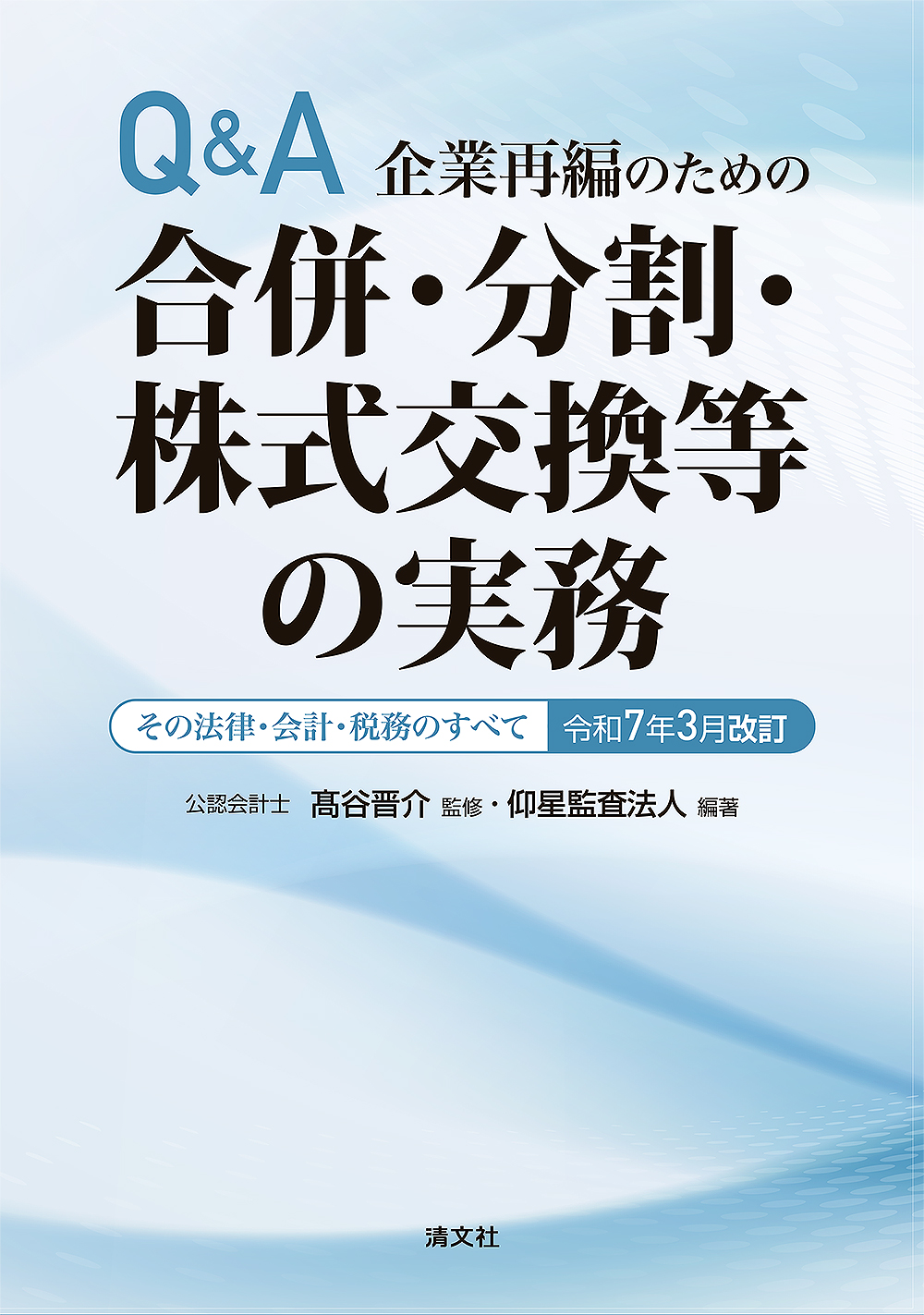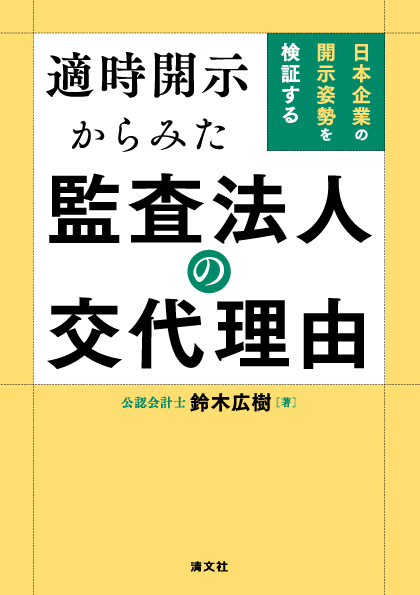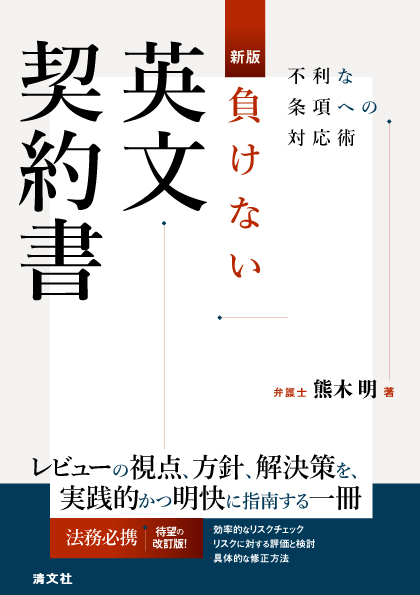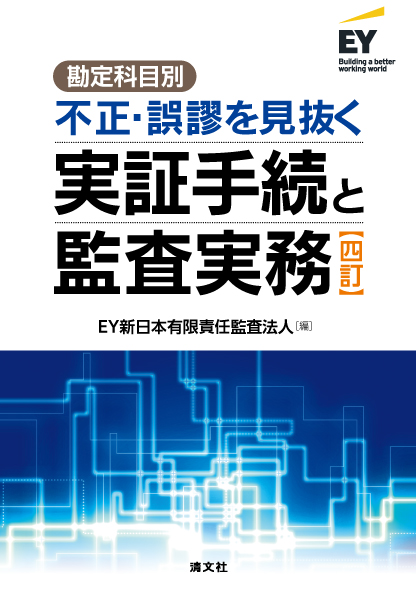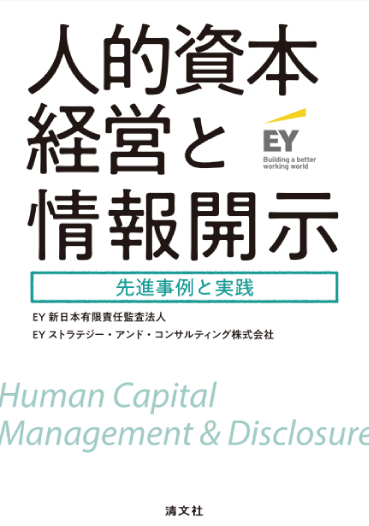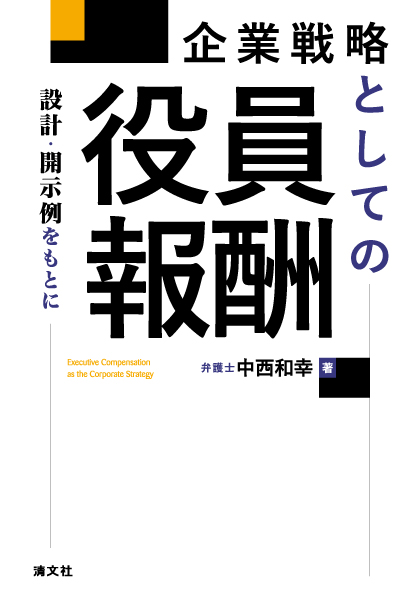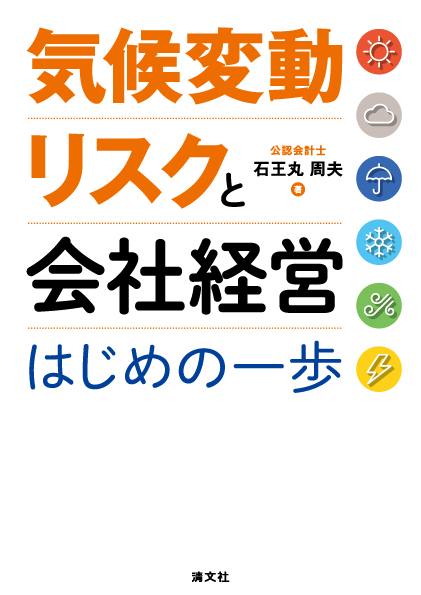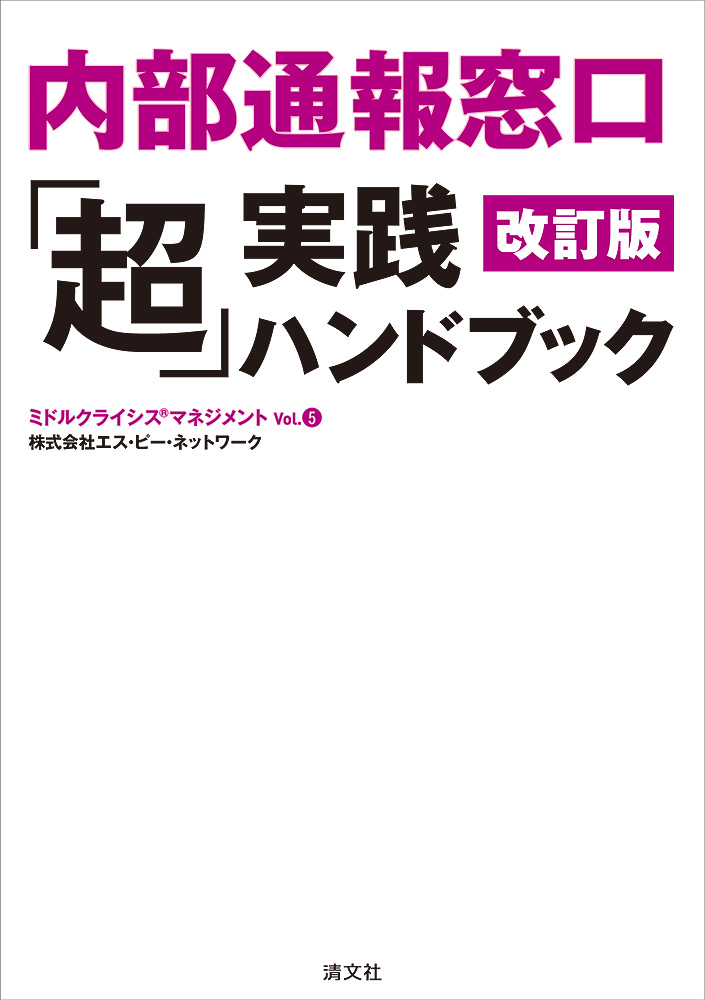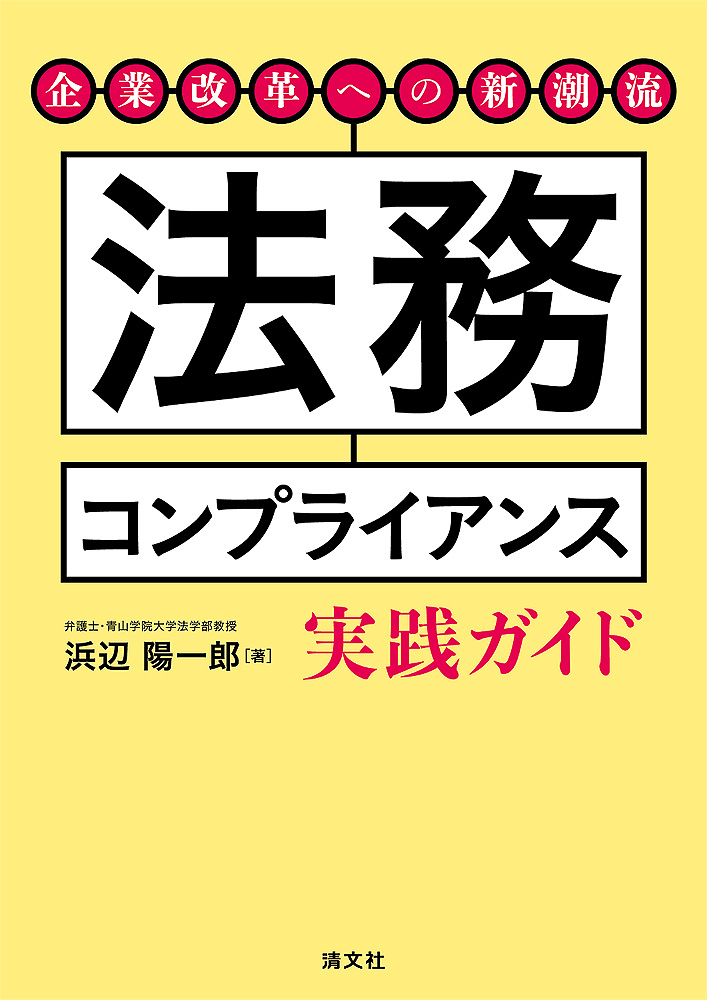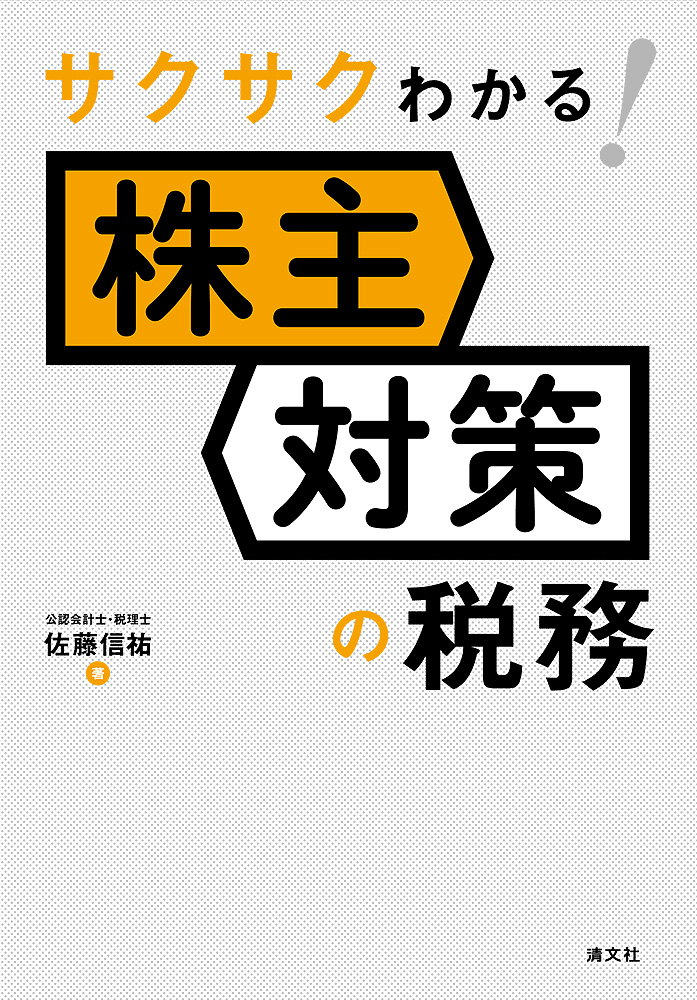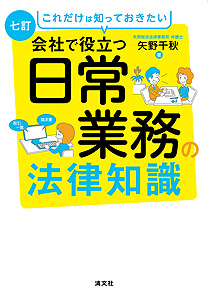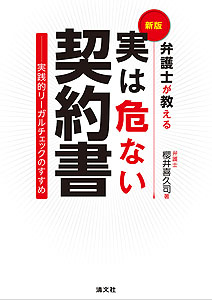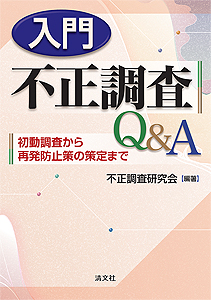改正会社法と
本年の株主総会実務対応
三井住友信託銀行 証券代行コンサルティング部
担当部長 斎藤 誠
いよいよ本年5月1日に改正会社法が施行されることとなった。現行の会社法が2006年5月に施行されて以来の実に9年ぶりの大改正である。
本年の株主総会実務対応の留意点は、まさに改正会社法対応となろう。
ここでは改正会社法への対応を中心に本年株主総会対応のポイントを解説する。
なお、文中意見にわたる部分は筆者の個人的見解であることをあらかじめお断りしておく。(本稿での会社法、会社法施行規則についての条文は改正後の条文を指すものとする。)
1 社外取締役を置くことが相当でない理由の説明
事業年度末に社外取締役を置いていない会社(監査役会設置会社、大会社かつ有価証券報告書提出会社)では定時株主総会で「社外取締役を置くことが相当でない理由」を説明しなければならない(会社法327条の2)。この規定には経過措置が設けられていないので、改正会社法の施行日以降に定時株主総会を開催する会社は、即、同法の適用を受けることとなる。
なお、当該定時株主総会で社外取締役を選任する場合であっても、説明義務があるので注意が必要である。具体的な説明の内容は、社外取締役を「必要としない」理由ではなく、置くことがかえって「マイナスとなる」というレベルとされているため、説明にはかなり頭を悩ませることになろう。説明のタイミングとしては、報告事項の報告において「対処すべき課題」または「役員の状況」等で説明することが考えられる。
2 事業報告の作成について
事業報告の作成に関しては、施行日の前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る事業報告についてはなお従前の例によるので(改正法務省令附則2条6項本文)、本年3月決算会社であれば事業報告の作成は従前のとおり改正前会社法で基本的にはOKとなる。
しかしながら、上記「相当でない理由」については、施行日以後に監査役の監査を受ける事業報告に関しては記載しなければならないので(同附則2条6項ただし書き)、現実的に3月決算会社の場合には「相当でない理由」の記載が必要となるであろう。
なお、実際の記載に際しては「役員の状況」等に記載することが考えられる。その理由は「当該事業年度における事情に応じて記載し、社外監査役が2人以上あることのみをもってその理由とすることはできない」(会社法施行規則124条3項)とされる。
なお、事業報告に関する改正対応としては以下のものがあり、原則本年5月決算会社から適用となる。
- 内部統制システムの運用状況の概要(同118条2号)
- 会社に特定完全子会社がある場合の株式の帳簿価額の合計額等(同条4号)
- 会社と親会社等との間の一定の利益相反取引が会社の利益を害さないかどうかについての取締役の判断および理由等(同条5号)
- 指名委員会等設置会社の場合の常勤の監査委員の選定の有無、理由(同121条10号)
- 親会社等が規定されたことに伴う社外役員に係る親族関係やグループ会社からの役員としての報酬を受けているときの記載の変更(同124条1項3号・7号)
- 会計監査人の報酬等について監査役会(または監査委員会等)が同意した理由(同126条2号)
3 株主総会参考書類の作成について
株主総会参考書類の作成に関しては、施行日前に招集の手続きが開始された株主総会に係る株主総会参考書類の記載については、なお従前の例によるとの経過措置が設けられた(改正法務省令附則2条5項)。
この場合の「招集の手続」とは「株主総会参考書類の記載も含む招集事項を決定する取締役会」を指すものである。3月決算会社では5月の連休明け以降の取締役会で招集を決定することが一般的であることから、その場合には株主総会参考書類は改正会社法対応での記載となることに注意しなければならない。
社外取締役を置いていない会社が、取締役選任議案を提出するのにもかかわらず、社外取締役選任議案を提出しない場合には、株主総会参考書類に社外取締役を置くことが「相当でない理由」を記載しなければならない(会社法施行規則74条の2第1項)。記載に際しては、会社の「その時点における事情に応じて記載しなければならず、社外監査役が2人以上いることのみをもって理由とすることができない」とされる(同条3項)。
その他株主総会参考書類に関しては以下のとおり、主に社外取締役・社外監査役の要件の厳格化等に伴う改正事項がある。
- 子会社等が規定されたことに伴う取締役選任議案・監査役選任議案の記載の変更(同74条3項、76条3項)。具体的には候補者がオーナー等で会社の経営を支配している者であるときはその旨、または候補者が当該オーナー等による経営を支配する会社の業務執行者であるときは、その地位・担当を記載する。なお、本項については本年4月決算会社までは株主総会参考書類の作成を従前のとおりとする経過措置が設けられた(改正法務省令附則2条2項)。
- 親会社等が規定されたこと等に伴う社外取締役・社外監査役選任議案の記載の変更(同74条4項、76条4項)。
- 会計監査人選任議案における監査役会(または監査委員会等)が当該候補者を会計監査人の候補者とした理由ほか(同77条3号・5号・8号)
なお、役員選任議案に関しては、候補者のふりがなの記載、新任者である旨の表示、独立役員である旨の記載など任意ではあるが、株主の検討材料としての記載が多くみられるようになってきた。候補者の顔写真を掲載している事例もあり見やすさ分かりやすさについても配慮が必要であろう。そのほか社外役員に関しては独立性の説明についても注意したい。
4 ウェブ開示の拡大
今般、会社法施行規則等の改正によりウェブ開示の対象範囲が大幅に拡大された。拡大されたウェブ開示の対象は以下のとおりであるが、特段の経過措置が付されていないので、本年6月株主総会でも活用できることとなった。
〈ウェブ開示の改正内容(拡大された事項)〉
① 事業報告(会社法施行規則133条3項)
・主要な事業内容
・主要な営業所および工場ならびに使用人の状況
・主要な借入先および借入額
・直前3事業年度の財産および損益の状況
・監査役の財務および会計に関する相当程度の知見
・上位10名の株主の氏名等
・当該事業年度中に使用人等に交付した新株予約権等に関する事項
② 計算書類(会社計算規則133条3項)
・株主資本等変動計算書
連結株主資本等変動計算書は現在でもウェブ開示の対象なので(会社計算規則134条4項)、個別の株主資本等変動計算書がウェブ開示の対象となれば、連結と個別の株主資本等変動計算書をセットでウェブ開示の対象とすることが考えられるであろう。
なお、「相当でない理由」については、事業報告および株主総会参考書類ともウェブ開示は不可であるので注意されたい(会社法施行規則94条1項、133条3項)。
5 本年の総会準備に際して
改正会社法への対応が本年株主総会でのメインテーマではあるが、現在策定が進められているコーポレートガバナンス・コードについても本年6月1日からの適用開始が予定されている。同コードでは独立社外取締役を2名以上確保することが求められているほか、株主との対話を求める施策が盛り込まれている。
株主総会は株主との対話の有効な機会であることから、本年は株主総会での株主との対話のあり方についても注目されるであろう。まずは会社側からの情報開示として招集通知の早期発送への取組みや情報量の拡大などが考えられる。情報量もただ増やせばいいというものではなく、いかにわかりやすく有用なものとするかが重要である。
そのほか本年は監査等委員会設置会社への移行の検討など会社のガバナンス対応についても注目が集まることとなるので、総会準備の早い段階から対応事項について整理しておくことをお勧めする。
(了)