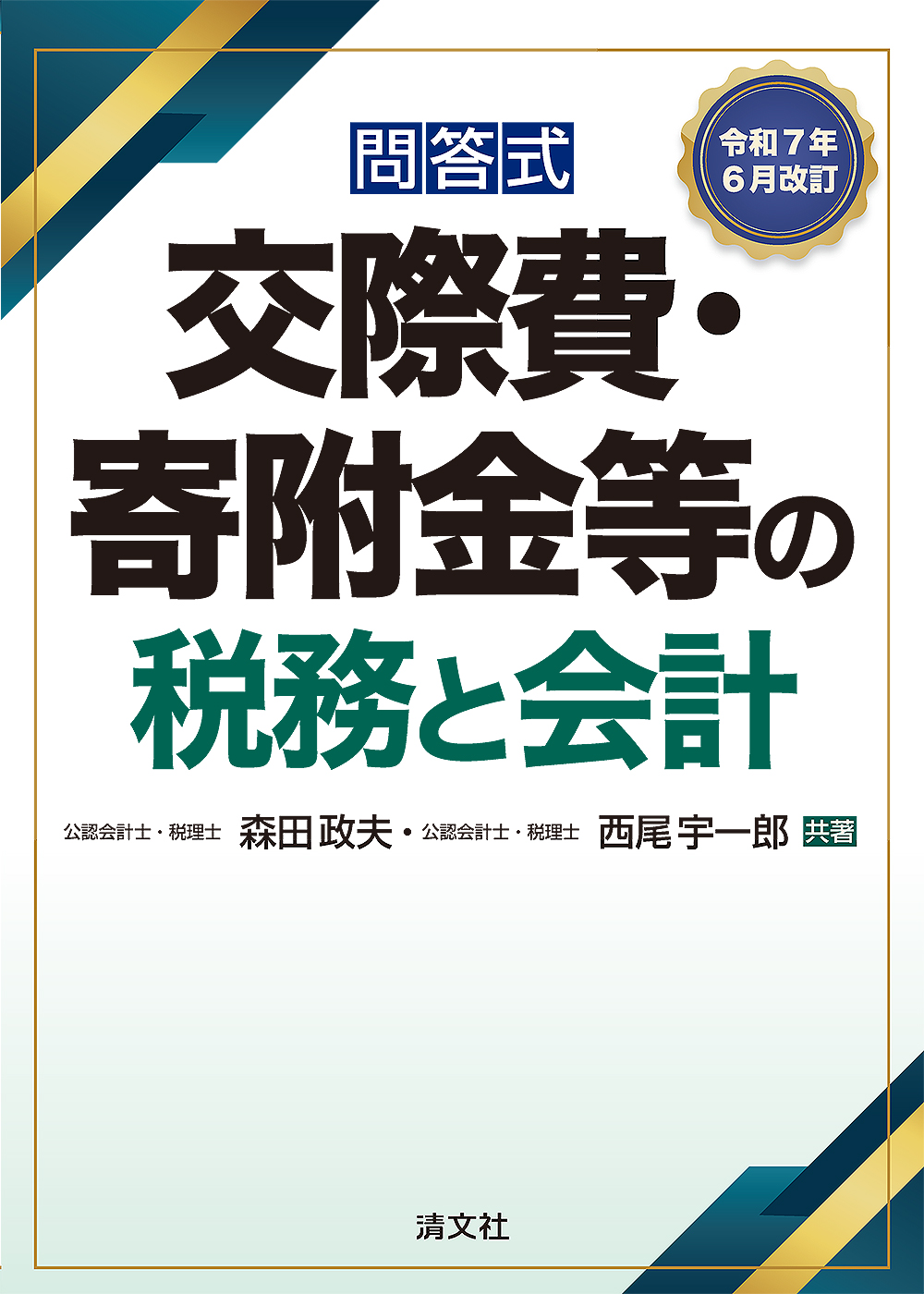法人税の解釈をめぐる論点整理
《寄附金》編
【第1回】
弁護士 木村 浩之
1 はじめに
法人が対価性のない、あるいは対価性の乏しい行為をすることで、第三者に対して経済的な利益の移転がなされる場合がある。そのような利益の移転行為については、法人の事業に直接又は間接的に関連する場合と、間接的にも関連しない場合があり得るが、その境界は必ずしも明確でないといえる。
そこで、そのような利益の移転行為については、それが法人の事業と直接関連することが明らかな場合を除き、寄附金に該当するものとして、一定の基準によって損金算入限度額を定めて、その限度額の範囲内でのみ損金算入を認め、それを超える部分については損金算入を認めないものとされている(法法37①)。
この寄附金税制は、事業とは関連しない、あるいは関連性の乏しい支出を無制限に認めることによって、各事業年度の所得金額を操作されるおそれがあること、他方、事業に関連する支出は本来費用となるべきであるが、その事業関連性は必ずしも明確に判断できるものではないことから、一種の割り切りとして、損金算入限度額の範囲内であれば、事業関連性の有無を問わず、形式的に損金算入を認めるが、それを超えるものについては、一律に損金算入を否定するものである。
実務上は、税務調査などにおいて、寄附金該当性をめぐって争われることが非常に多いことから、本稿では、寄附金の範囲に関する論点を中心として、寄附金税制に係る論点を整理することとしたい。
取り上げる予定のテーマは、以下のとおりである。
◇ 寄附金の範囲(総論)
◇ 隣接費用との区分
◇ 貸倒損失等との区分
◇ 対価性の有無等
◇ 特殊な相手方に対する寄附金
◇ 資本等取引と寄附金
2 寄附金の範囲(総論)
寄附金とは、
ⅰ) 事業に直接関連せず、
ⅱ) 任意になされる、
ⅲ) 対価性のない(乏しい)支出
を意味する。
法律上は、「寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。)」とされている(法法37⑦)。
また、寄附金には、無償行為による支出以外に、対価の不均衡(低廉取引)によってなされる経済的利益の移転も含まれ、法律上は、「資産の譲渡又は経済的な利益の供与をした場合において、その譲渡又は供与の対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額に比して低いときは、当該対価の額と当該価額との差額のうち実質的に贈与又は無償の供与をしたと認められる金額」も寄附金に含まれるとされている(法法37⑧)。
このように、寄附金には、経済的利益の移転が広く含まれるものと解されるが、事業に直接関連する費用(法律上は、「広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費」と規定される)については、寄附金に含まれないとされている。
そこで、寄附金の範囲(寄附金該当性)をめぐっては、第一に、寄附金に含まれない費用(事業に直接関連する費用)に該当するか否かが問題となる。第二に、「任意に」経済的利益の移転がなされたものといえるかが問題となり、第三に、「対価性」の有無等が問題となる。
言い換えれば、第一の問題は、隣接費用との区分の問題であり、第二の問題は、貸倒損失等との区分の問題であり、第三の問題は、対価性の有無等という本来の意味での寄附金該当性の問題である。
〈寄附金該当性をめぐる問題〉
① 隣接費用との区分
② 貸倒損失等との区分
③ 対価性の有無等
3 隣接費用との区分
(1) 広告宣伝費等との区分
広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用は、一般的な販売管理費に含まれるものであり、事業と直接関連することが明らかといえることから、これらの性質を有する支出等については、寄附金には該当しないことになる。
この広告宣伝費等に該当するか否かは、その目的及び効果に照らして実質的に判断がなされるべきであり、
ⅰ) 誘引効果を得ることを主たる目的としたものであり、
ⅱ) 実際に宣伝効果を有するもの
であれば、その支出等の名目いかんにかかわらず、また、その支出等の相手方が事業とは直接関係のない者であったとしても、広告宣伝費等に該当し得ることになる。
例えば、販促キャンペーンとしてのキャッシュバックや景品供与等が広告宣伝費等に該当することはもちろん、宣伝効果を期して自社製品を配布すること、大会やイベント、あるいは一定の団体に資金を提供すること(ただし、自社名の表示など、実際に宣伝効果を有することが必要である)、広告宣伝を統括する親会社に合理的な範囲で負担金を拠出することなども広告宣伝費等に該当するのであり、寄附金には該当しない。
(2) 交際費等との区分
交際費等については、事業との関連性が一定程度認められるものの、冗費としての性格を有するものであることから、寄附金税制とは別に、租税特別措置法によって損金算入が制限されている(措法61の4①)。この交際費等と寄附金については、対価性がない(乏しい)という点で共通していることから、その区分が問題となる。
一般には、その区分に当たっては、交際費等に該当するか否かを先に判断し、交際費等に該当しない場合に、寄附金に該当するか否かを判断することになる。
交際費等の要件は、次のとおりである。
ⅰ) 相手方が事業に関係のある者であり、
ⅱ) 目的が親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図るものであること
したがって、事業に関係のない者に対して利益の供与がなされた場合、また、事業に関係のある者に対して利益の供与がなされた場合であっても、それが事業とは無関係の目的からなされたものであるときには、交際費等には該当せず、寄附金(場合によっては、役員に対する給与)に該当し得ることになる。
(3) 役員又は従業員に利益供与がなされた場合の費用区分
ア 給与に該当する場合
法人から役員又は従業員に対して経済的利益の供与がなされた場合、明確な対価関係が認められないとしても、通常、それは役員等としての地位に基づいて利益を受けるものであり、広く労務の対価としての性質を有するものとみなされることになる。
したがって、そうではないことが明らかなもの(役員等以外の地位に基づいて利益を受けるものであることが明らかなもの)を除き、給与に該当することが多いといえる。
また、第三者に対して経済的利益の供与がなされた場合であっても、その第三者が役員等の親族などの関係者であり、法人から供与された利益が実質的には当該役員等個人に帰属するとみられる場合は、その者に対する寄附金ではなく、当該役員等に対する給与となる(拙稿《役員給与》編・6(2)参照)。
すなわち、利益供与が役員等個人の私的な理由によってなされる場合、本来個人が負担すべきものを法人が代わって負担する場合(法基通9-4-4の2参照)には、その利益は当該個人に帰属するものとして、その者に対する給与に該当することになる。
イ 福利厚生費に該当する場合
前記アのとおり、法人が役員等に経済的利益の供与をした場合は、通常は、給与に該当することになる。もっとも、形式的には、役員等個人に利益が帰属するかのようにみえる場合であっても、実質的には、法人の便宜のためになされるものについては、福利厚生費として給与には該当しないと考えられる。
この福利厚生費に該当するための要件は、次のようなものとなる。
ⅰ) 個人の利益を図る目的を超えてなされるものであり、
ⅱ) それが法人の事業遂行の目的のために必要であり、
ⅲ) 対象となる者には不合理な限定がなされておらず、
ⅳ) その金額が合理的な範囲にとどまるもの
このようなものであれば、その経済的利益は実質的には役員等個人ではなく、法人自身に帰属するものとして、福利厚生費に該当することになると考えられる。
例えば、職場の士気、労働意欲を高めるために社員優待制度を設けること、社員の結束を高めるために社員旅行をすること、健康増進のための器具備品を備えること、健康診断の費用を負担することなど、合理的な範囲で物心両面から職務環境を整えることは個人の利益を図る目的を超えて法人の事業遂行の目的のために必要であるので、その対象者に不合理な限定がなされておらず、その範囲が過剰なものではない(費用対効果が均衡していると言い得る)限りにおいては、その利益は実質的には法人自身に帰属すると言えることから、福利厚生費として損金算入が認められる。
次回は、「貸倒損失等との区分」について解説する。
〔凡例〕
法法……法人税法
法令……法人税法施行令
法基通…法人税基本通達
(例)法法34①三 … 法人税法34条1項3号
(了)