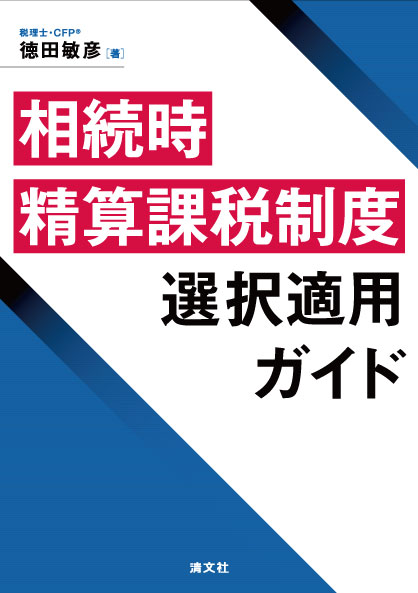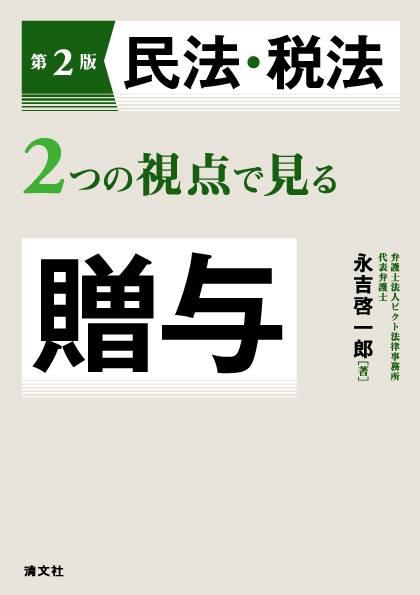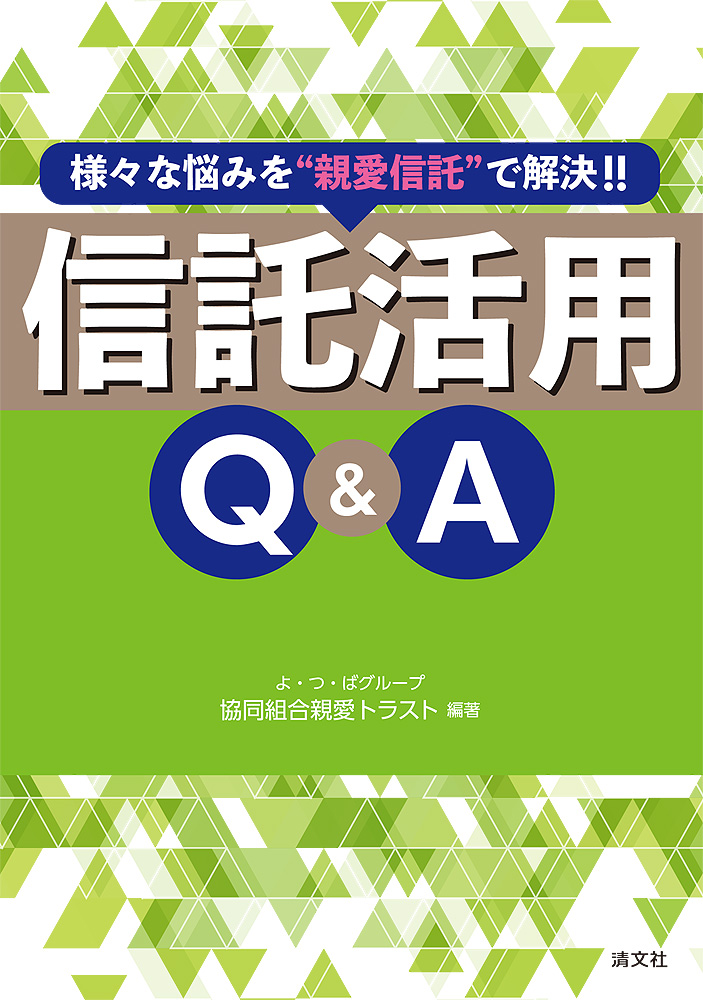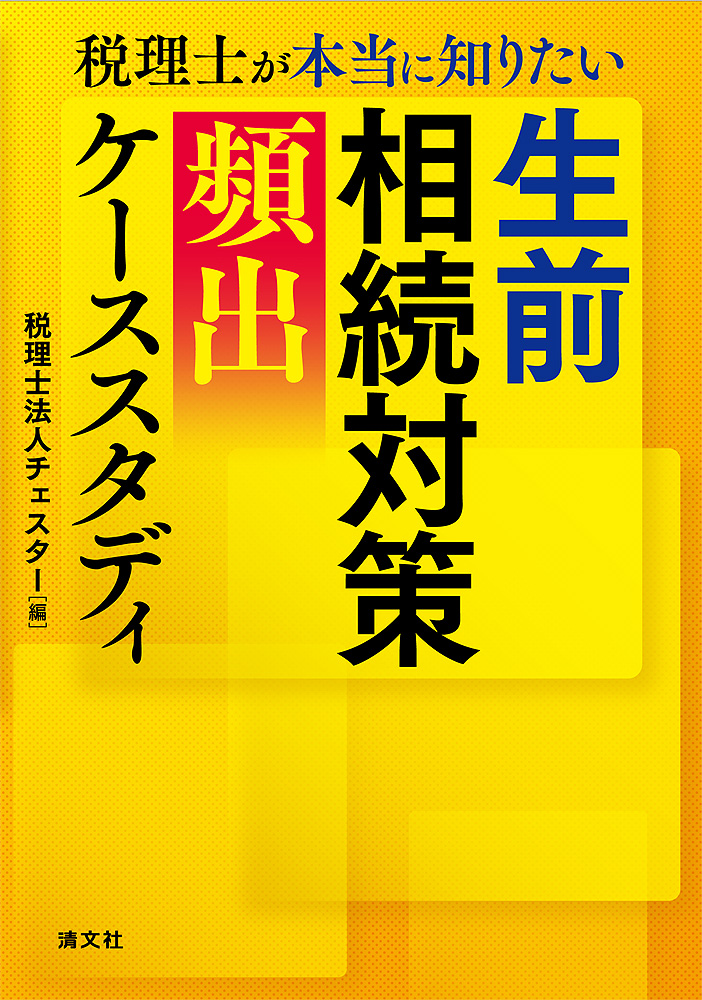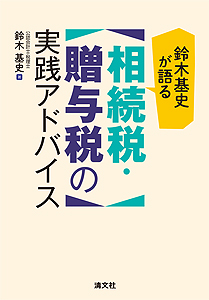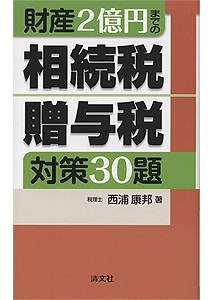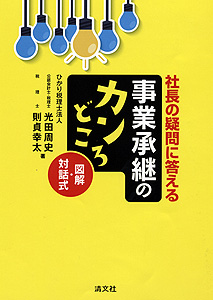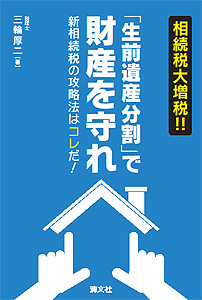相続税対策からみた
生前贈与のポイント
【第1回】
「贈与契約・贈与財産管理と
贈与税の課税方法の選択」
税理士法人タクトコンサルティング
税理士 山崎 信義
はじめに
相続税節税の王道は、課税対象となる個人財産を減らすことにある。
このため、相続税の節税対策の一環として、親から子、祖父母から孫に対する財産の生前贈与は、相続税の節税対策の定番として広く行われているところである。
ただ、このような親族間での財産の贈与は、その実態が外部からは分かりにくく、贈与の事実をめぐって税務当局とのトラブルが生じやすい。税務当局とのトラブルを生じさせないためにも、贈与に関する十分な理解が重要となる。
そこで本シリーズでは、相続税対策の一環として行われる親族間での財産の贈与について、平成25年度税制改正を踏まえつつ、実務上留意すべき事項を述べたいと思う。
1 税務トラブルを避けるための贈与契約と贈与財産の管理のポイント
相続税法においては、贈与により財産を取得した個人について贈与税の納税義務を課している。ただし、相続税法上、贈与についての定義規定は設けられておらず、実務上は贈与に関する民法の規定を踏まえ、贈与があったかどうかを判定している。
民法上、贈与は当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる(549条)。贈与契約は口頭でも可能だが、その契約が本当に成立したことを明確にするため、書面により贈与契約書を作成しておいた方がよい。
さらに、過去の国税不服審判所の裁決事例等をみると、税務上贈与として認められるためには、贈与を受けた財産を受贈者が管理し、使用することも必要である。例えば、親から子への預貯金の贈与について、名義だけを子に変更しても、通帳やキャッシュカードを親が管理している、子が預金を引き出して使った形跡がないというような場合は、“名義預金”として親の財産と認定され、相続税の課税対象とされるおそれがあるので、注意を要する。
なお、贈与税の申告及び納税を行うことは、贈与が行われたかどうかの事実を認定する上での証拠の1つにすぎない。贈与が行われたかどうかは、具体的な事実関係を総合勘案して判断されることになるので、この点についても注意したい。
2 相続税対策から見た贈与税の課税方法の選択
贈与税の課税方法には、「暦年贈与課税制度」と「相続時精算課税制度」の2種類がある。
暦年課税制度は、その年1月1日から12月31日の1年間に贈与でもらった財産につき、基礎控除の110万円を超える金額に税率を乗じて贈与税を計算する方法である。
贈与税は累進課税制度を採用しており、贈与を受けた金額の大きさに応じて税率も高くなるので、一度にまとまった額の財産の贈与を受けると贈与税の負担がかなり重くなる。このため、1回あたりの贈与額を小さくし、贈与する人数と回数(年)を多くすれば、子の贈与税負担を抑えながら親の財産を減らすことができ、安全確実な相続税の節税対策となる。
ただし、贈与した財産であっても相続税の対象とされる場合があるので注意が必要である。被相続人から財産を相続した人が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産は、原則、相続税の課税対象とされる。
相続税の節税を考えるなら、相続人となる子への贈与は早いうちから始めておくべきである。また、子の配偶者や孫など遺産を相続しない人へ贈与した財産は相続税の課税対象とならないので、贈与する相手は子以外にも広げておくとよいだろう。
相続時精算課税制度は、原則、その年1月1日現在で65歳以上の親(※1)から、同20歳以上の子(※2)が財産の贈与を受けた場合に、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に子がこの特例の選択する旨の届出書を贈与税の申告書に添付して住所地の税務署に提出したときは、贈与により取得した財産の額から2,500万円の特別控除を差し引き、差引後の金額に20%の税率を掛けて贈与税を計算するという税制である。
相続時精算課税制度の選択をした場合、子に贈与をした財産は最終的には贈与時の相続税価額により親の相続税の計算に取り込まれ、相続税の課税対象とされる。贈与財産も相続税の課税対象となるので、相続時精算課税制度による贈与については、基本的に相続税の課税対象額を減らす効果はない。さらに、贈与者が平成27年以降に死亡した場合には、相続時精算課税に係る贈与財産について、増税改正後の税制により相続税が計算される。
また、相続税の課税対象とされる財産の価額は贈与時の相続税評価額とされるので、贈与時よりも相続時の相続税評価額が高い場合はよいが、反対に贈与時よりも相続時の相続税評価額が低い場合であっても、贈与時の高い評価額で相続税の計算を行うことになり、結果的に税負担が増加することになる。
平成27年以降に実施される相続税増税を念頭に置けば、現時点での贈与について相続時精算課税制度を選択すると税務上不利となるケースが大半であろう。
相続時精算課税制度は選択制であり、いったん選択すると暦年課税制度への変更ができない。課税方法の選択については、慎重に検討したい。
【参考】
平成25年度税制改正において、平成27年1月1日以後の贈与より、受贈者及び贈与者の要件が下記のとおり拡充される。
(※1) 贈与者:(改正前)65歳以上の親→(改正後)60歳以上の親
(※2) 受贈者:(改正前)20歳以上の子→(改正後)20歳以上の子・孫
(了)
「相続税対策からみた生前贈与のポイント」は、隔週の掲載となります。