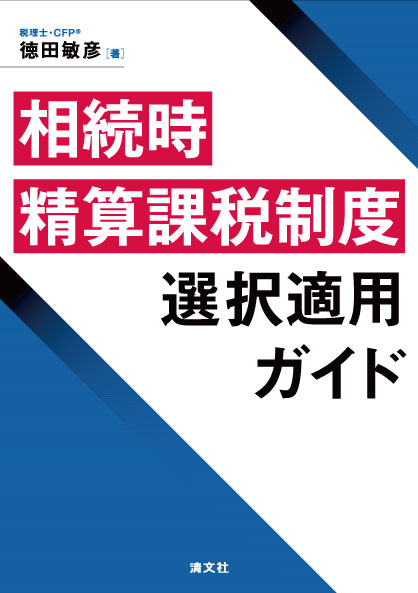〔実務で差がつく!〕
相続時精算課税制度Q&A
【第1回】
「令和6年以降の贈与で、申告期限内に相続時精算課税選択届出書のみを提出した後に申告漏れの財産があった場合又は評価誤りがあった場合の対応」
税理士 徳田 敏彦
◇◆◇連載開始にあたって◇◆◇
令和6年から改正された「相続時精算課税制度」がスタートした。しかし、まだまだ運用が定着した状況ではなく、国税庁も新たに関連する質疑応答事例等を発表している段階である。
そこで本連載では、税理士が相続時精算課税制度を選択する際の留意点に加え、選択した後での修正等の留意点も踏まえ、具体的な事例を用いたQ&A形式で、改正された「相続時精算課税制度」を解説するものとする。
* * *
【Q】
甲は令和6年7月に父から現金100万円の贈与を受けた。甲は相続時精算課税制度を適用するため、令和7年3月の贈与税申告において贈与金額が相続時精算課税に係る基礎控除額以下であることから「相続時精算課税選択届出書」のみを提出した。その後、令和7年4月になり、甲は令和6年中に父から別途500万円の贈与を受けていたことが判明した。
この場合に贈与税の申告、納税はどうなるのか。
【A】
期限後申告を行う。ただし、贈与税の計算は相続時精算課税を選択した場合の計算となるが、相続時精算課税制度の特別控除額2,500万円を控除できないため、基礎控除額110万円のみを控除して贈与税を算出する。
◆ ◇ ◆ 解 説 ◆ ◇ ◆
今回の事例のように令和6年以後の贈与で贈与金額が基礎控除額110万円以下の場合には「相続時精算課税選択届出書」のみを提出して、申告期限内に贈与税の申告書を提出しないケースが発生する。
このような場合に、申告期限後に申告漏れ財産があった場合や評価誤りがあった場合の取扱いに留意が必要である。
1 申告漏れ財産があった場合の対応(本事例)
相続時精算課税選択届出書を期限内に提出しているので、同じ特定贈与者(本事例では父)からの贈与財産で申告漏れの財産については相続時精算課税を適用して計算する。その場合、特別控除額2,500万円は控除できるのか。
相続時精算課税の特別控除額2,500万円は、期限内申告書に控除を受ける金額その他必要な事項の記載がある場合に限り適用を受けることができる(相法21の12①)。
また、相続時精算課税の適用を受ける財産について、その記載がなかったことについてやむを得ない事情があると税務署長が認めるときは、その記載をした書類の提出があった場合に限り、特別控除の適用を受けることができるとされている(相法21の12③)。
つまり、特別控除額2,500万円は原則として期限内申告が要件である。
そのため、今回の事例のように、相続時精算課税選択届出書のみを提出していて期限内申告書を提出していないケースでは、特別控除は適用できずに期限後申告(相続時精算課税)を行うことになる。
〈期限後申告での贈与税〉
(贈与金額100万円 + 申告漏れ贈与金額500万円 - 基礎控除額110万円 - 特別控除額0円(※))× 贈与税率20% = 98万円
(※) 翌年に繰り越す特別控除額は2,500万円のままである。
2 期限内申告において評価誤りがあった場合の対応
今回の事例とは異なるが、期限内申告において贈与財産の評価に誤りがあった場合はどうなるのか。
前提として、本事例と同様に申告期限においては贈与金額が基礎控除額以下のため「相続時精算課税選択届出書」のみを提出しているが、その資産について評価誤りがあり、贈与金額が基礎控除額を超えることが判明した場合である。
相続時精算課税の適用を受ける財産について、その記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認められる場合には特別控除が適用できるとされているが、そもそも、特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出した場合に限り適用することができる。
そのため、このような同一資産の評価誤りの場合でも、相続時精算課税選択届出書のみが提出され、期限内申告書が提出されていないケースでは特別控除額は適用できないことに留意が必要である。
〔凡例〕
相法・・・相続税法
(例)相法21の12①・・・相続税法21条の12第1項
(了)
「〔実務で差がつく!〕相続時精算課税制度Q&A」は、不定期の掲載となります。