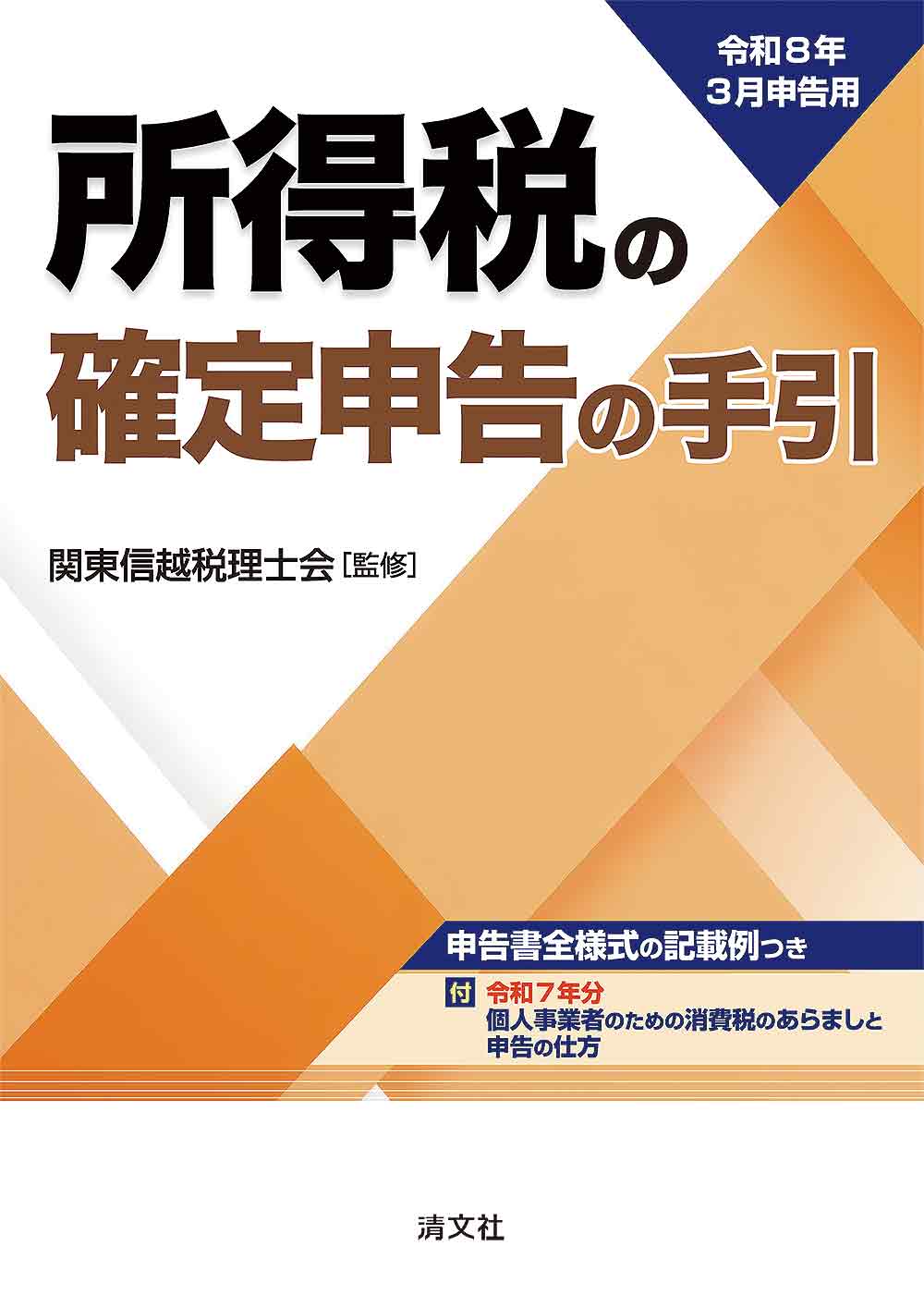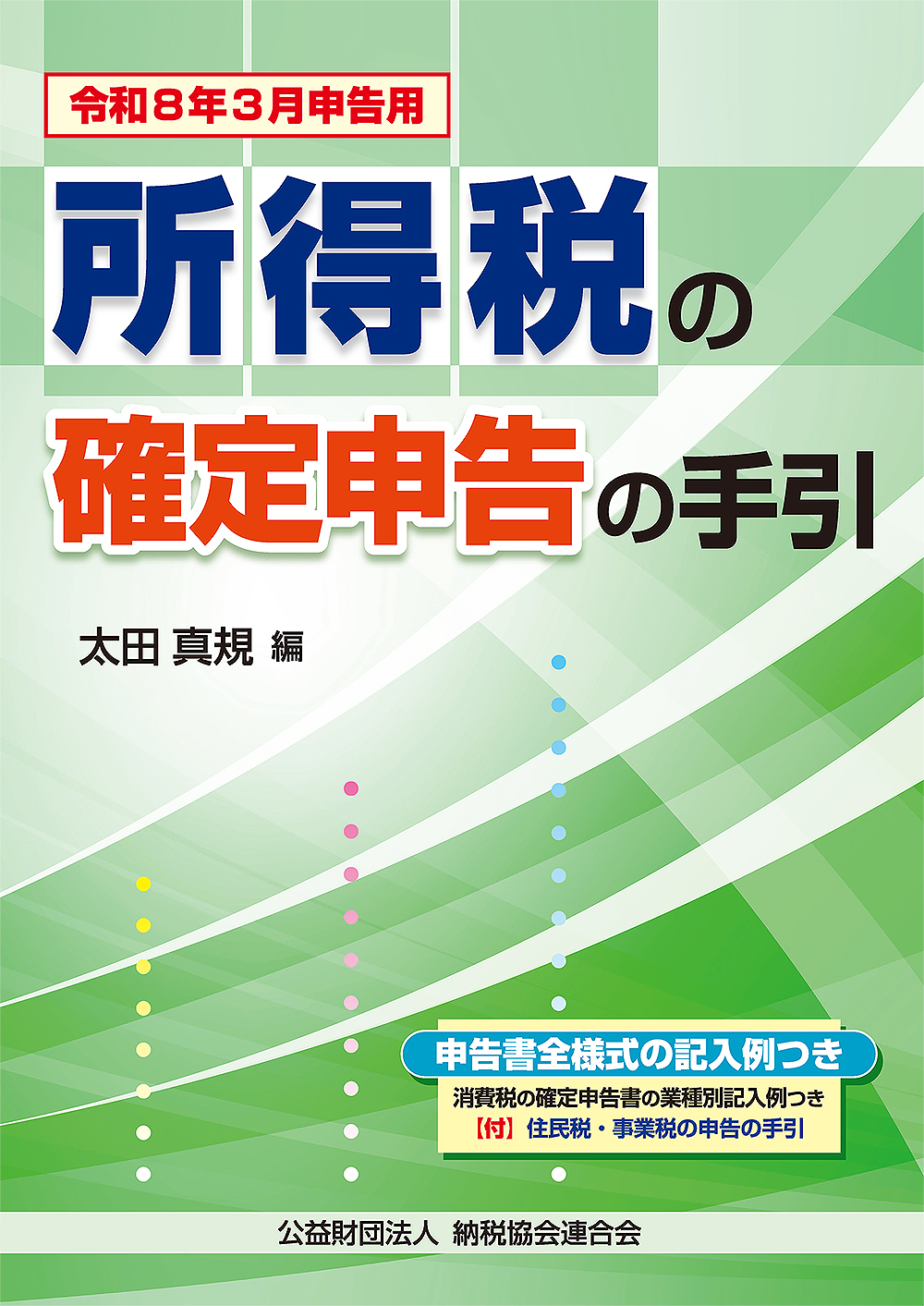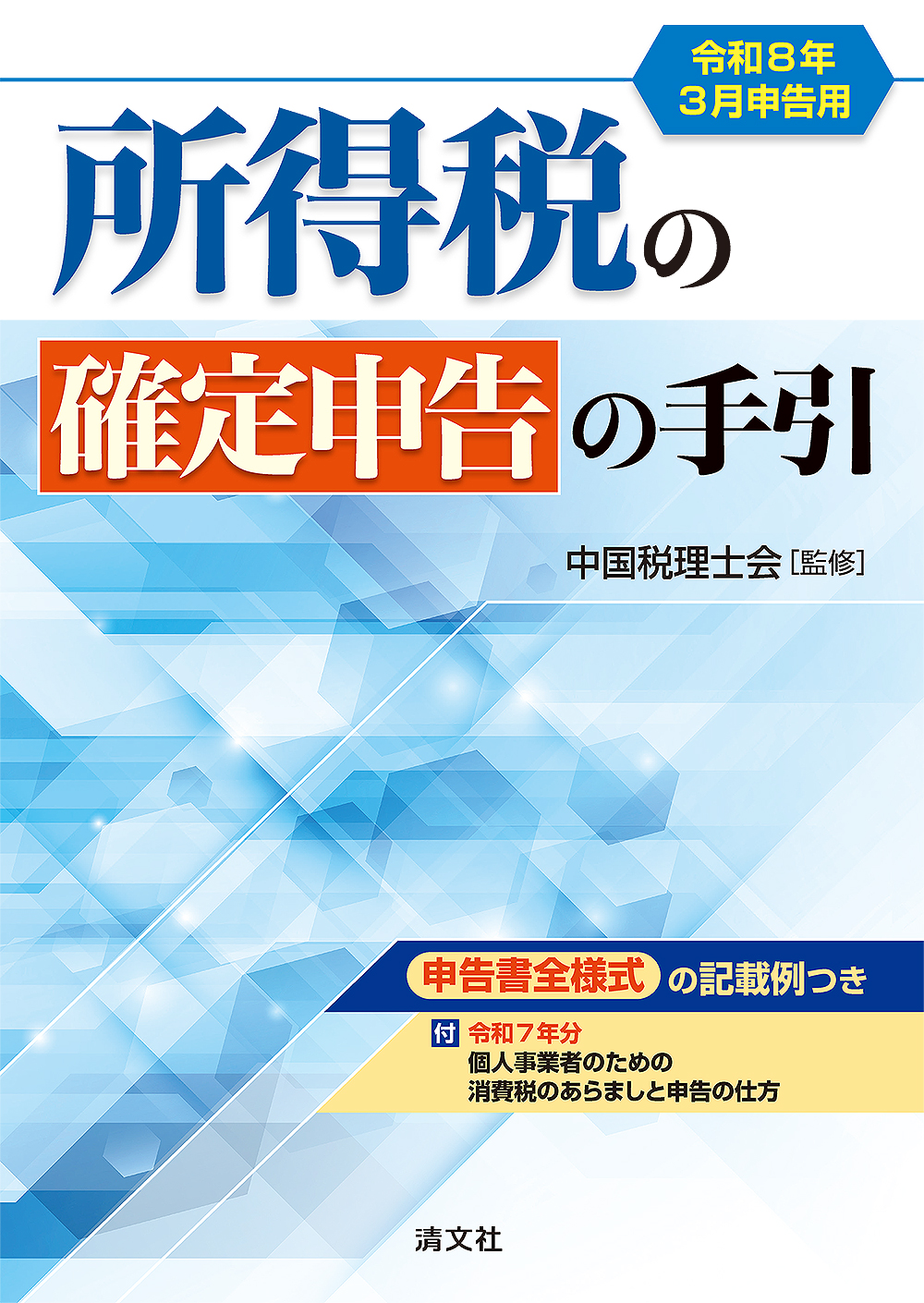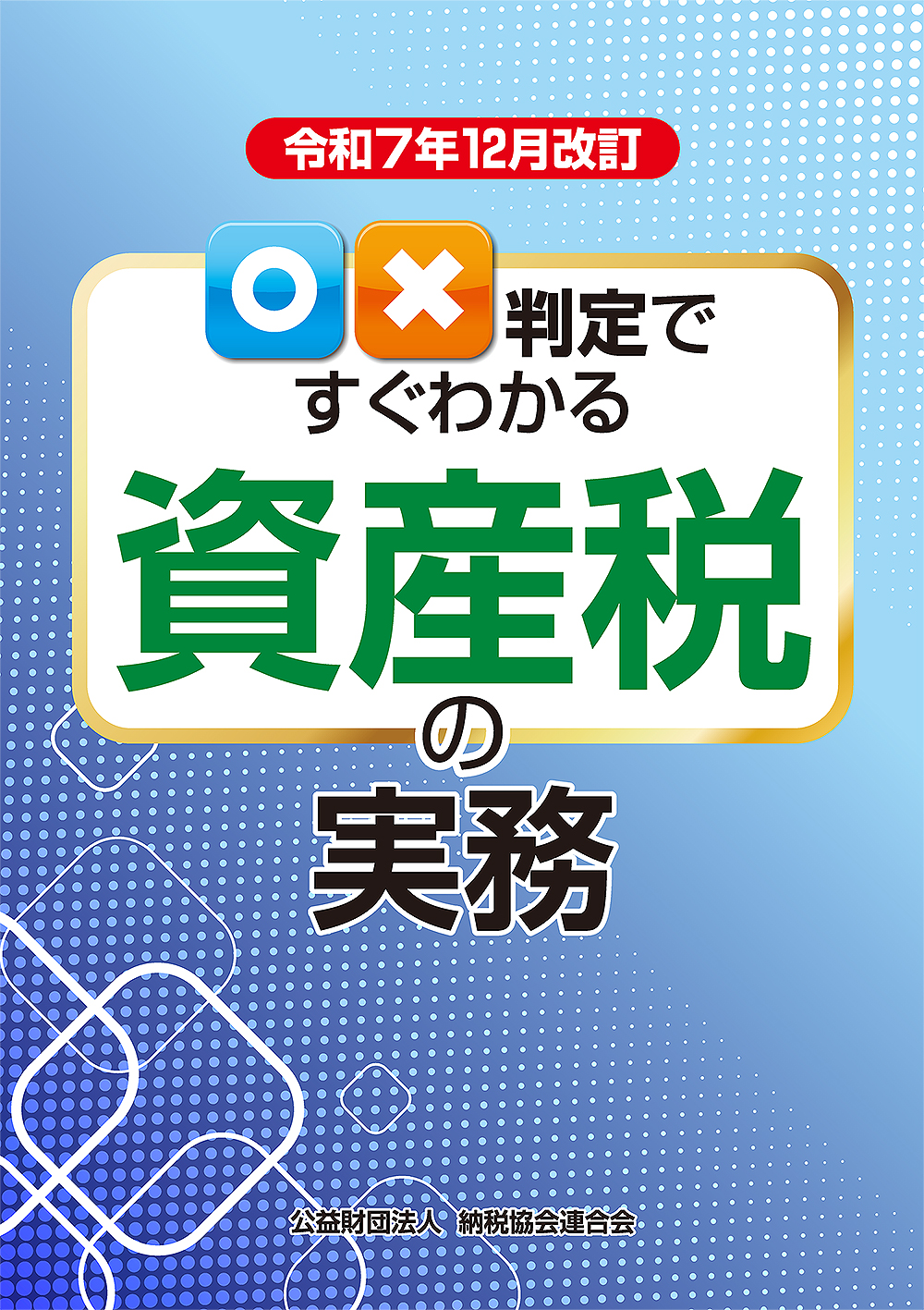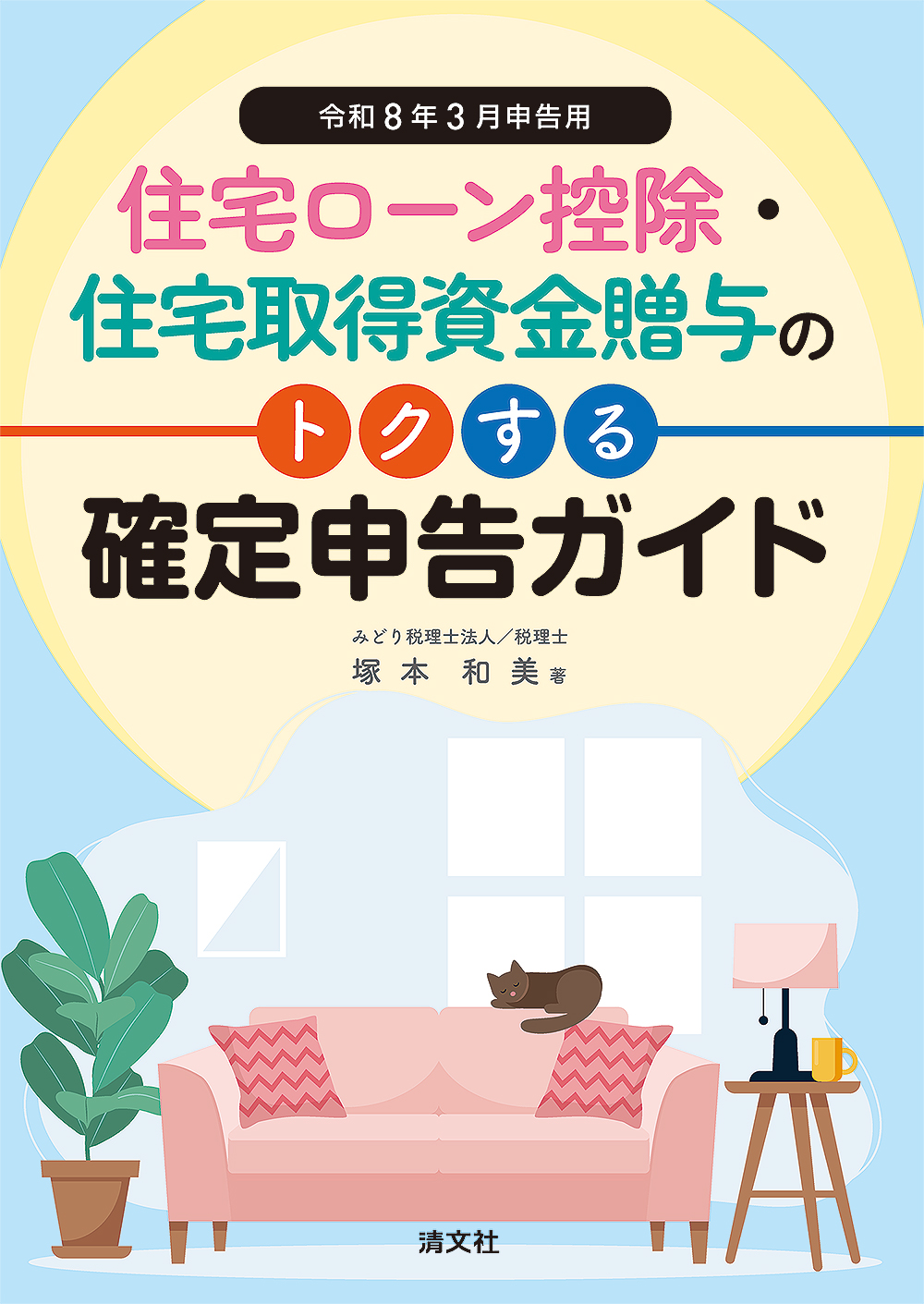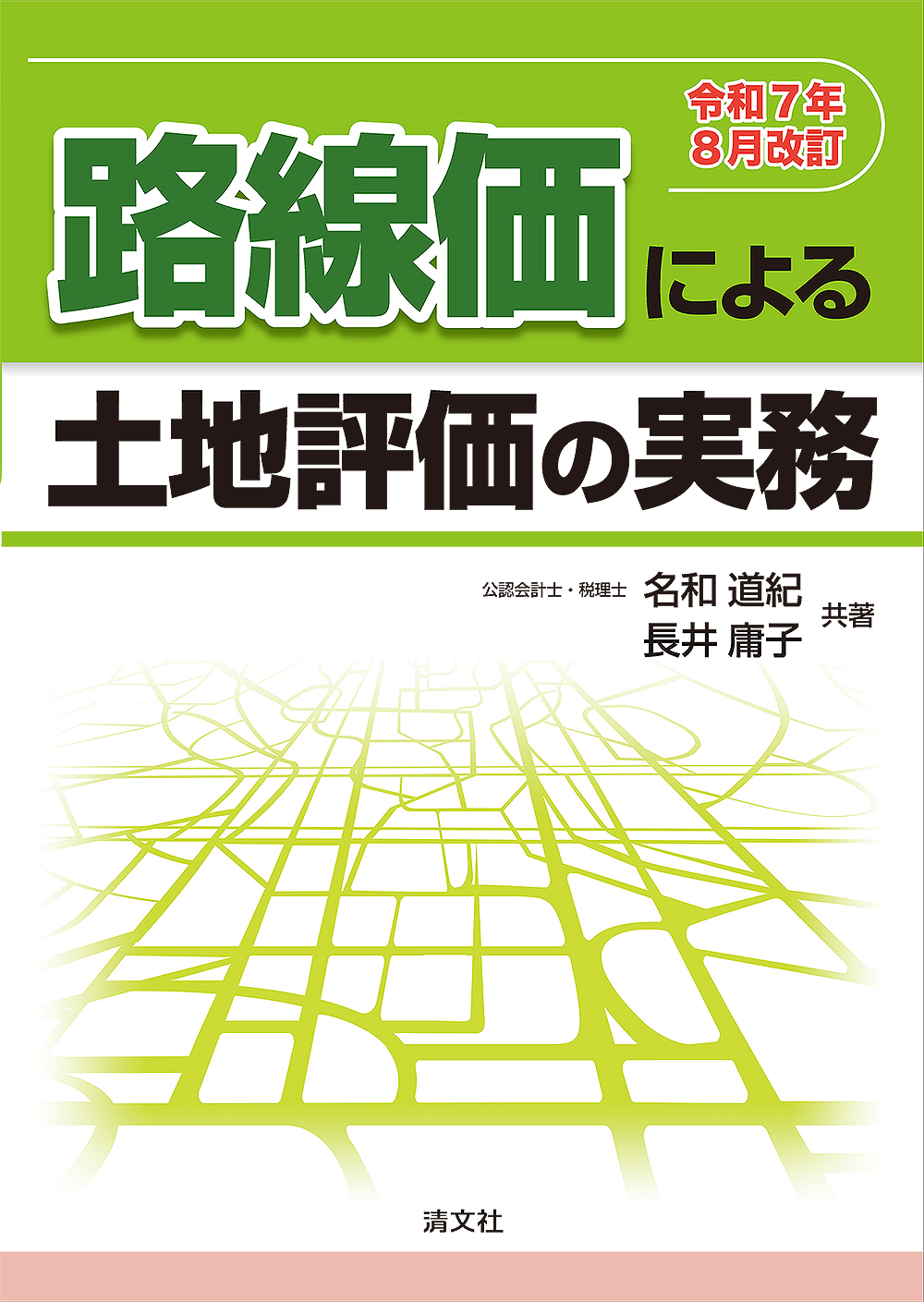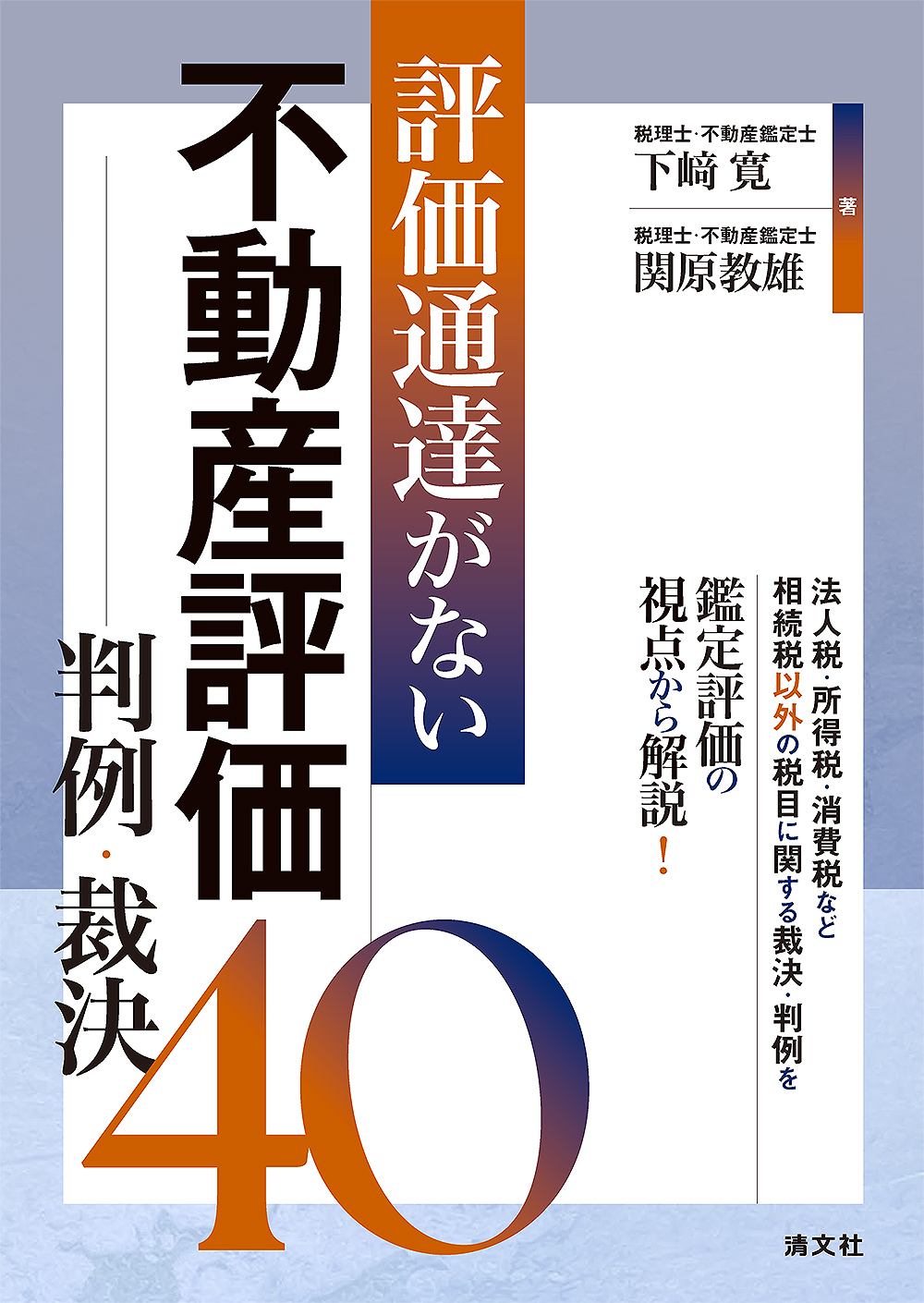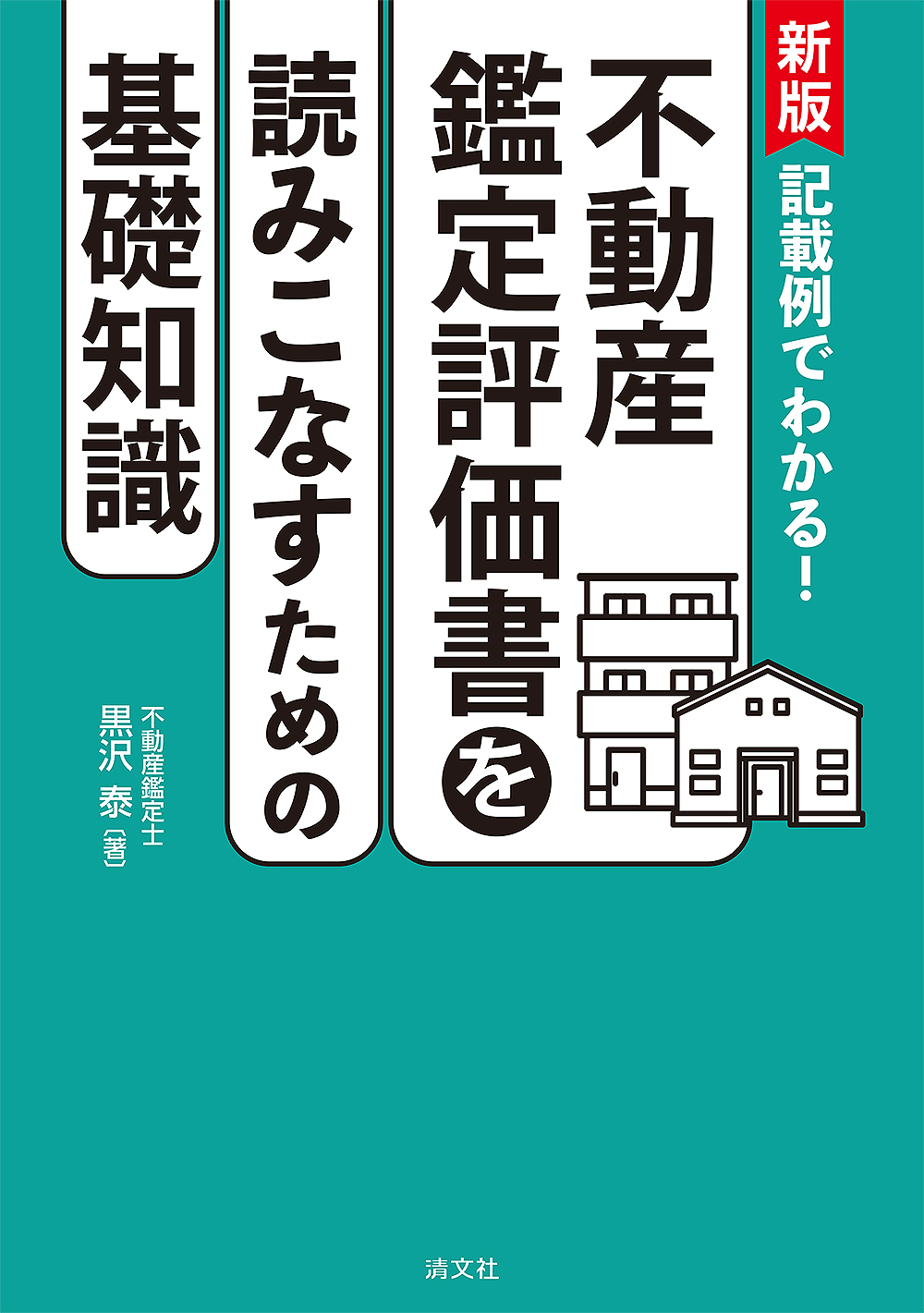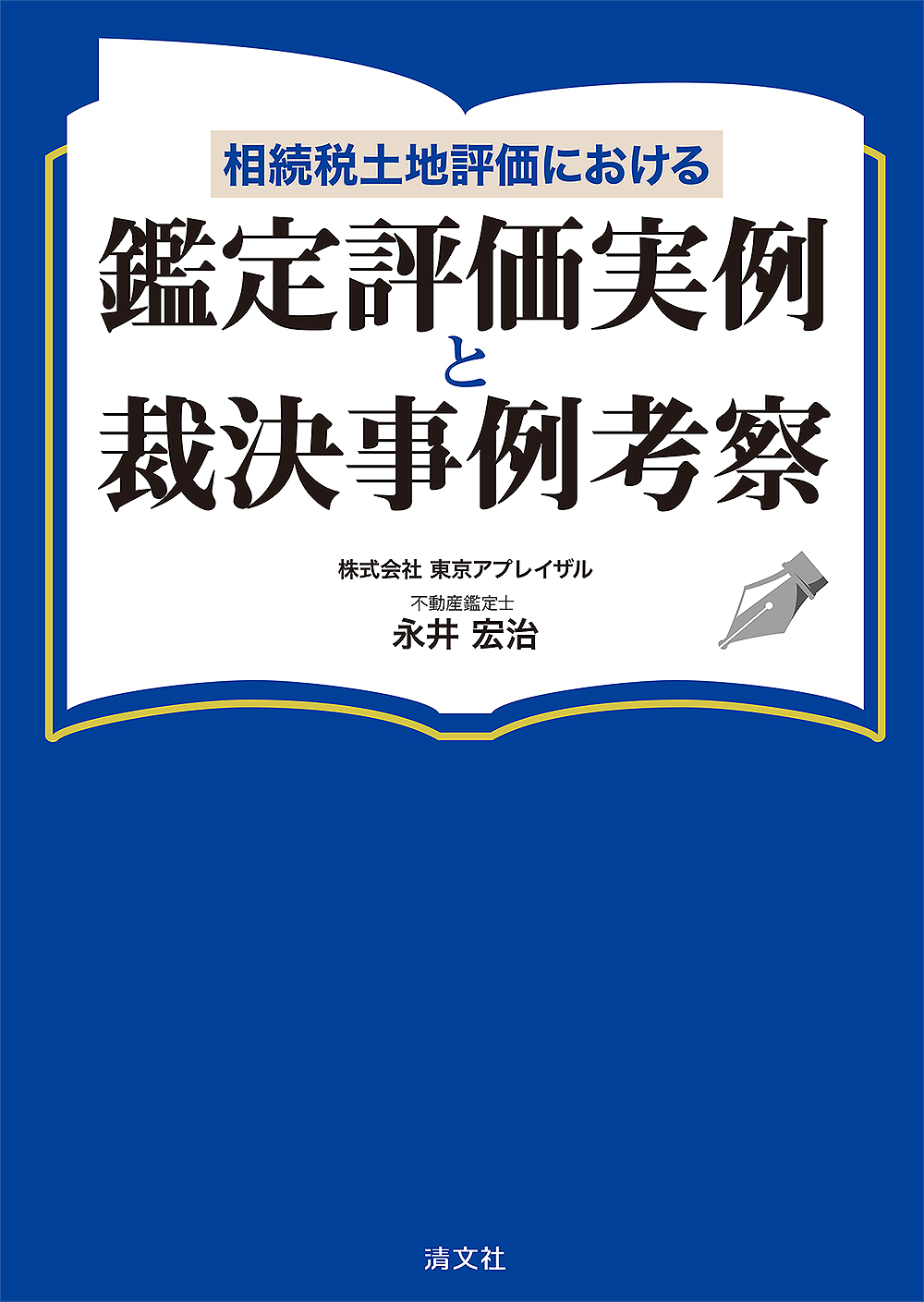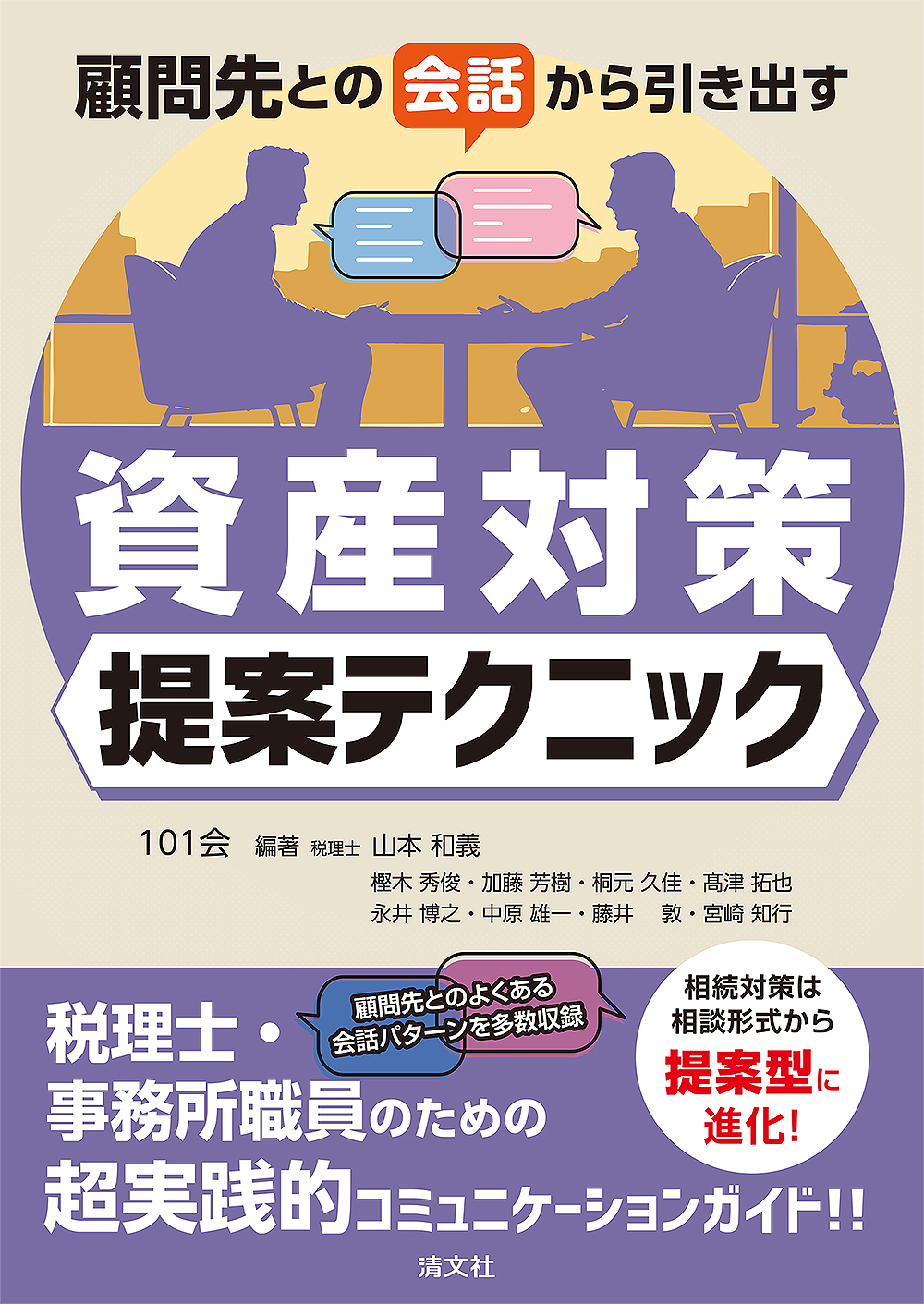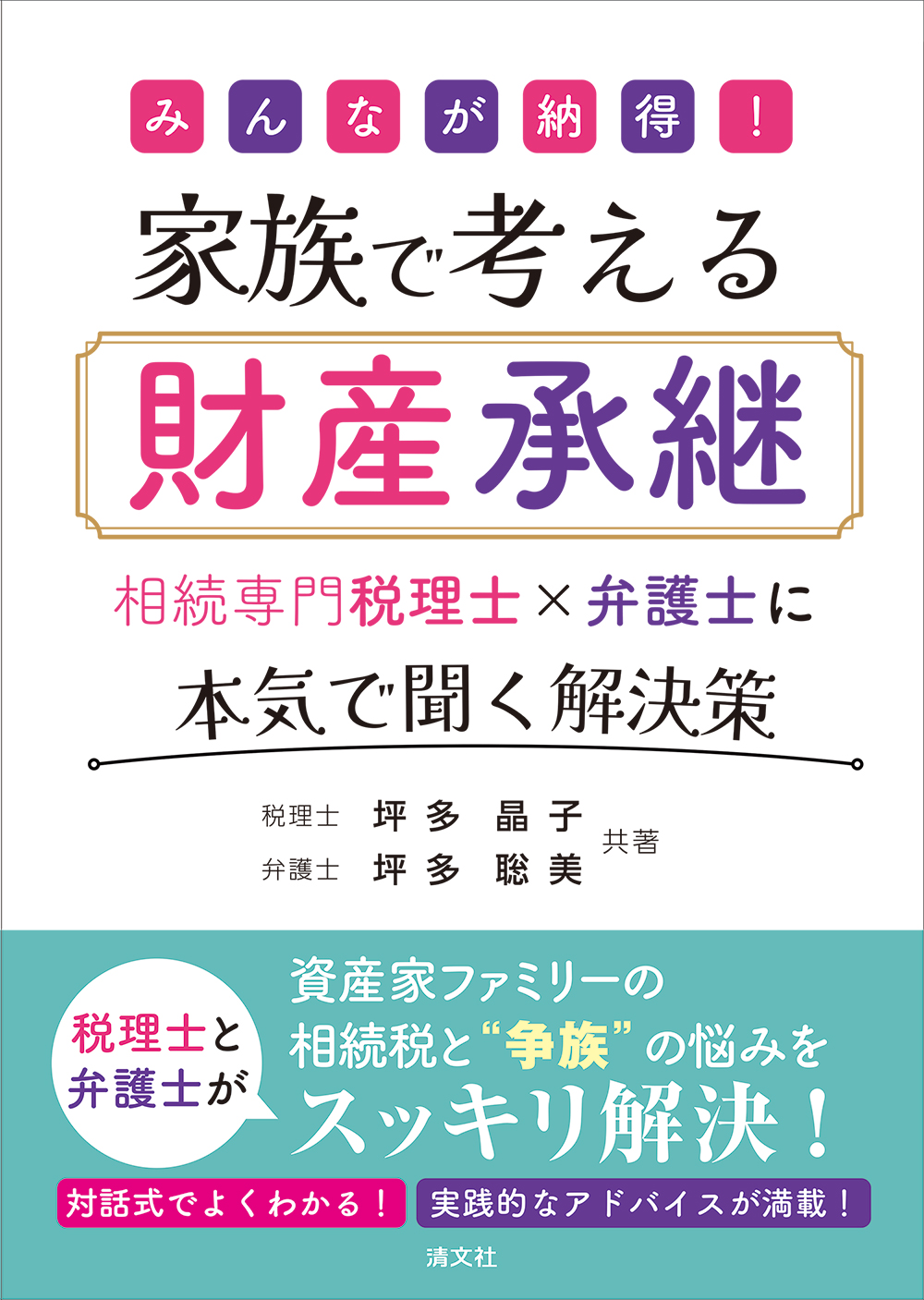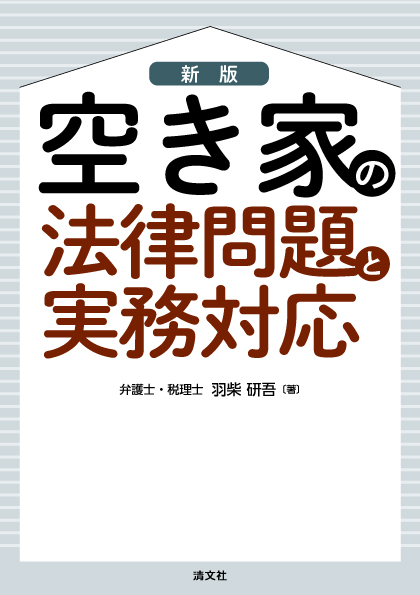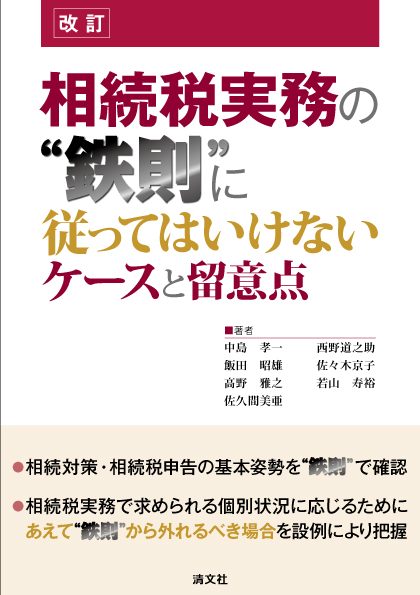マンション保有者のための相続税対策とその留意点
【第1回】
「既存のマンション保有者が検討すべき対策」
ミレニア綜合会計事務所
代表税理士 甲田 義典
【はじめに】
来年からはじまる相続税の増税により、相続税対策についての関心が高まっている。
特に近年では、購入代金のうち建物部分の比率の占める割合の高い都心の高層マンションを取得することで、評価の低い建物に組み替えて財産の評価額を減らし節税をはかることを検討しているケースもあるようだ。
このような背景を踏まえ、本稿では相続税対策を中心に居住用・投資用を目的とした区分所有によるマンション保有者または購入検討者に焦点を当てた税金対策について、①既存のマンション保有者と②購入検討者に分け、全2回にわたり解説する。
第1回は、既存のマンション保有者が検討すべき対策について解説したい。
1 『居住用マンション』を保有している場合
居住用のマンションを保有している場合には、主に以下の特例の活用が考えられる。
(1) 贈与税の配偶者控除
贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合において、110万円の贈与税の基礎控除のほかに、最高2,000万円までの控除(配偶者控除)をすることで、合計で年間2,110万円までの贈与を無税で行うことが認められている(相法21の6)。
したがって、マンションの評価額が2,110万円以下であれば、マンションの所有権のすべてを無税で配偶者へ移転することが可能である。ただし、この特例を受けた居住用不動産や金銭は、贈与を受けた配偶者の二次相続の相続財産として相続税の課税対象となるため、二次相続対策もあわせて検討する必要がある。
(2) リフォームした場合の所得税の特例
リフォームをする場合においても、相続税対策では、マンションの取得と同様に現金が「修繕費」や「資本的支出」というかたちで建物へ組み替えられるため、財産の評価額を減らす効果が期待できる。
また、所得税についても、居住者が住宅ローン等を利用して一定要件を満たすリフォームを行った場合には、そのリフォームに係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除する「住宅借入金等特別控除(居住年が平成26年4月1日以降で認定住宅であれば控除期間最長10年間、控除額最大500万円)」又は「特定増改築等住宅借入金等特別控除(居住年が平成26年4月1日以降で控除期間最長5年間、控除額最大62.5万円)」の適用が認められている(措法41、41の3の2)。
そのほか、住宅ローン等を利用しない場合であっても、居住者が既存住宅について一定の要件を満たす住宅耐震改修をしたとき、バリアフリー改修工事若しくは省エネ改修工事をしたときは、それぞれの規定により定められた金額を、その年分の所得税額から控除する「住宅耐震改修特別控除(控除額最大25万円)」、「住宅特定改修特別税額控除(控除額最大 バリアフリー:20万円 省エネ:35万円)」の適用を受けることが認められている(措法41の19の2、41の19の3)。
なお、適用要件や手続規定の概要は、国税庁ホームページの以下のリンク先を参照されたい。
【参考】 国税庁ホームページ
- 「住宅借入金等特別控除」
- 「特定増改築等住宅借入金等特別控除」(バリアフリー改修工事)
- 「特定増改築等住宅借入金等特別控除」(省エネ改修工事)
- 「住宅耐震改修特別控除」
- 「住宅特定改修特別税額控除」(バリアフリー改修工事)
- 「住宅特定改修特別税額控除」(省エネ改修工事)
(3) 小規模宅地等の特例
相続の開始の直前において被相続人等(被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族。以下同じ)が使用していた一定の居住用宅地で240㎡(平成27年1月1日以後の相続又は遺贈により取得した場合には330㎡)までの部分は、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、その部分の80%を減額することができる(措法69の4)。
小規模宅地等の特例は、相続税対策の出口戦略(すなわち相続発生時の税金対策)として検討していくのが通常である。しかし、区分所有によるマンションの場合には、土地(敷地利用権)部分の価値が相対的に低いケースが多いため、節税効果は限定的なものになると考えられる。
2 『投資用マンション』を保有している場合
(1) 不動産管理会社の活用
投資用マンションを複数保有している場合には、法人へ名義変更して家賃収入を個人から法人への付け替えを検討することが可能と考えられる。
一般的に不動産管理会社を利用した節税効果には、不動産を保有する者に集中する不動産賃貸収入を、相続人等が出資した不動産管理会社を通じて役員となった親族等へ給与を支払うことにより分散させ、不動産を保有する者の不動産所得に係る所得税等を節税できるほか、年間の不動産収入に係る相続財産の増加を防ぐ効果が期待できる。
また、親族等が得た給与収入は、将来の相続税の納税資金として確保することが可能であるだけでなく、不動産管理会社にプールされた内部留保を役員退職金として支給することで所得税等を軽減させることが可能と考えられる。
(2) リフォームをした場合(修繕費と資本的支出)
上述のとおりリフォームによる支出は、マンションの取得と同様に現金が建物へ組み替えられ財産の評価額を減らす効果が期待できる。
投資用マンションのリフォームに係る修繕費で、通常の維持管理や修理のために支出されるものは不動産所得の必要経費になる(所法37)。しかし、一般に「修繕費」といわれるものでも資産の使用可能期間を延長させたり、資産の価額を増加させたりする部分の支出は原則として「資本的支出」として「修繕費」とは区分され、不動産所得の計算上、減価償却の方法により投資用マンションの耐用年数にわたり各年分の必要経費として算入されることになる(所令127、181)。
(3) 相続時精算課税制度の活用
相続時精算課税制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行う制度である。
適用対象者は、贈与年の1月1日現在において贈与者は65歳以上(平成27年1月1日以後の贈与は60歳以上)の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含む。なお、平成27年1月1日以後の贈与は、推定相続人であるかを問わず20歳以上の孫も含まれる)とされ、贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はなく、選択届出書の提出などの一定の手続きを行うことで、贈与者1人あたり最大2,500万円までの財産を贈与税が課されることなく移転することが認められている(相法21の9他)。
例えば、この2,500万円の非課税枠を活用して子や孫に贈与すれば、マンションの家賃収入は子・孫に付け替えることが可能となるため、相続税対策と同時に親のアパート収入に係る所得税を軽減させる効果が期待できる。
ただし、相続時精算課税制度を選択した場合の相続税計算上取り込まれる贈与財産の価額は、贈与時の価額(時価)となる。したがって、生前贈与したマンションが相続時に値下がりしていたような場合には、相続税負担が増える可能性があるため留意が必要である。
(4) 小規模宅地等の特例
相続の開始の直前において被相続人等が不動産賃貸業の用に供していた一定の貸付事業用宅地で200㎡までの部分は、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、その部分の50%を減額することができる(措法69の4)。
なお、区分所有のマンションを保有している場合の節税効果が限定的なものになる点に関しては、居住用の場合と同様である。
〔凡例〕
相法・・・相続税法
措法・・・租税特別措置法
所法・・・所得税法
(了)
次回は9/25(木)に掲載されます。