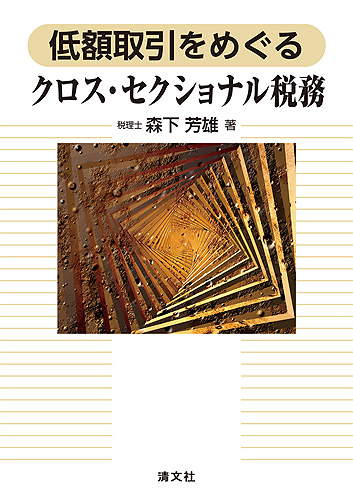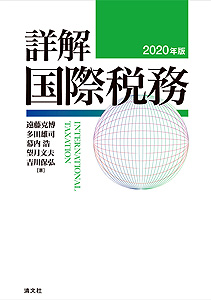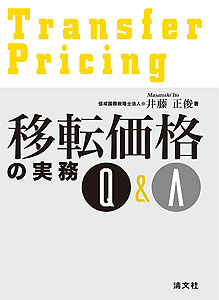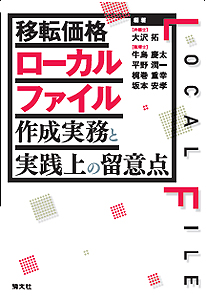移転価格文書化における
ローカルファイルの作成期限前チェックポイント
【第1回】
太陽グラントソントン税理士法人 マネジャー
税理士 川瀬 裕太
Ⅰ はじめに
平成28年度税制改正により、独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類(ローカルファイル)が平成29年4月1日以後開始する事業年度から同時文書化義務の対象となった。本稿では作成までの期限が差し迫っていることをふまえ、ローカルファイルの作成上の留意点について確認していきたい。
Ⅱ 作成義務のある企業の範囲等及び作成時期
まずはローカルファイルの作成義務のある企業の範囲等及び作成時期について、チェック方式で確認する。
1 作成義務のある企業の範囲等
国外関連者の範囲について確認しているか?
- 移転価格の対象となる国外関連者は、法人と「特殊の関係」を有する法人である。
- 「特殊の関係」には、発行済株式総数50%以上の直接又は間接保有関係及び同一の者による発行済株式総数50%以上の直接又は間接保有関係が含まれ、保有関係がなくても、役員派遣、取引依存、資金提供等により、法人が他方の法人の事業の全部又は一部につき実質的に決定できる関係も含まれる。
国外関連者との間で取引を行っているか?
- 国外関連取引を行った法人はローカルファイルの作成義務者に該当する。
作成期限について確認したか?
- 確定申告書の提出期限までに作成することが要求されている。
保存期間・保存場所について確認したか?
- 原則として、確定申告書の提出期限の翌日から7年間、国外関連取引を行った法人の国内事務所で保存することとされている。
同時文書化義務の免除基準について確認したか?
- 同時文書化義務とは、法人が国外関連者との取引を行う際に、又は法人が確定申告書を提出する際に利用可能である最新の情報に基づいてローカルファイルを作成し、又は取得し、これを保存しなければならないことをいう。
- 前期の一の国外関連者との取引金額が50億円以上、又は前期の一の国外関連者との無形資産取引金額が3億円以上である法人は、ローカルファイルを確定申告期限までに作成・保存しなければならないこととされている。
提出期限について確認したか?
- 同時文書化対象取引については、独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類(ローカルファイル)を45日以内の調査官の指定する日までに、独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類としてローカルファイルに記載された内容の基礎となる事項、関連する事項及びその他独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類を60日以内の調査官が指定する日までに提出することが義務付けられている。
- 同時文書化免除取引についても、独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類(ローカルファイルに相当する書類)、ローカルファイルに相当する書類に記載された内容の基礎となる事項、関連する事項及びその他独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類を60日以内の調査官が指定する日までに提出することが義務付けられている。
- 税務当局は、上記期日までに提出できない場合には、推定課税・同業者調査規定を適用することができることとされている。
2 作成時期
文書化のスケジュールの検討はできているか?
- 平成29(2017)年4月1日以後開始する事業年度から適用されることとなり、3月決算法人で同時文書化対象取引を有する法人の場合、平成30(2018)年5月末(延長の場合6月末)までに作成しておく必要がある。
- ローカルファイルの作成には数ヶ月かかるため、税務調査が入る時期を考えると、遅くとも決算終了後すみやかに作成を始めた方が望ましいと考えられる。
Ⅲ ローカルファイルの記載内容
ローカルファイルにおいては、租税特別措置法施行規則22条の10に記載されている内容を織り込む必要がある。以下では記載内容、準備書類、チェックポイントについて確認していくこととする。
1 「国外関連取引の内容を記載した書類」のチェックポイント
(1) 資産及び役務の内容(措規22の10①一イ)
① 記載内容
- 国外関連取引の対象となる資産の明細及び役務の内容を説明する。
- 取引の当事者、取引の流れ等を明らかにする必要がある。
② 準備書類
- 有価証券報告書、営業報告書又は会社案内
- 商品のパンフレット、カタログ又はプライスリスト
- 契約書
③ チェックポイント
取引対象が明確になっているかどうかを確認
- 取引の主たる対象だけでなく付随する役務提供等(据え付け、試運転)がないかどうかを確認した上で具体的な内容を漏れなく記載する必要がある。
ノウハウの移転がないかどうかを確認
- 海外生産拠点の利益率が高い場合には、ノウハウの移転があったとしてロイヤルティの請求漏れを指摘される可能性があるため、利益率が高い場合にはその原因について検討する必要がある。
第三者を経由する取引があるかどうかを確認
- 株式等の保有関係等のない第三者が介在している取引であっても、契約条件等により国外関連取引とみなされる場合があるため、留意が必要である。
(2) 機能及びリスク(措規22の10①一ロ)
① 記載内容
- 国外関連取引において、法人及び国外関連者がどのような機能を果たし、どのようなリスクを負担しているのかを説明する。
- 法人及び国外関連者の国外関連取引に係る機能を、誰がどこでどのように果たしているかを記載する。
- 機能を果たすための重要な判断や決定を誰がどこでどのように行っているか、また、費用の負担は誰がどのように行っているか、さらに、その機能が基本的活動のみを行う法人の機能とは異なる独自の機能である場合には、独自の機能と判断した理由を記載する必要がある。
② 準備書類
- 経営組織図、所属員数表、業務分掌表、業務フロー図、有価証券報告書、会社案内及びホームページをアウトプットしたもの
- 契約書
- 国外関連取引の取引フロー図
- 事業計画、事業計画に係る稟議書、出張稟議書及び出張報告書
- 事業再編等に係る計画書、稟議書、報告書及び会議資料
③ チェックポイント
事実関係が正確に把握できているかどうかを確認(形式的なリスク負担者ではなく、実質的なリスク負担者の確認等)
機能・リスクに前年と大きな変更があった場合には、変更前後の状況を記載できているかどうかを確認
- 機能とリスクが正確に把握できていないと、算定方法の選択や、比較対象企業の選定における判断を誤る恐れがあるため、正確かつ詳細な分析が必要となる。
事業再編があったかどうかを確認
- 事業再編がある場合には、租税回避が主たる目的ではなく、事業上の要請によるものであったかどうか、機能とリスクの変更が形式的なものではなく、実態を伴うものであったかどうかについても検討する必要がある。
〔凡例〕
措規・・・租税特別措置法施行規則
(例)措規22の10①一イ・・・租税特別措置法施行規則22の10条1項1号イ
(了)
この連載の公開日程は、下記の連載目次をご覧ください。