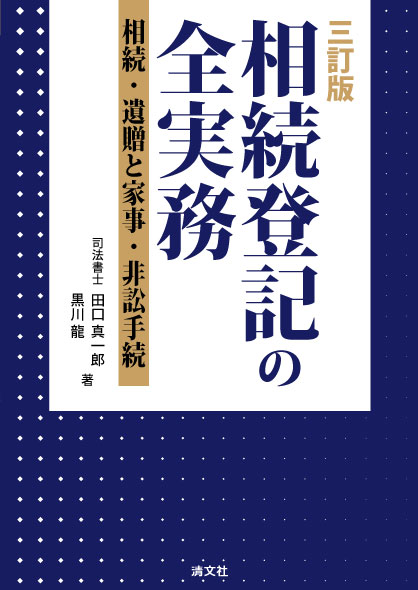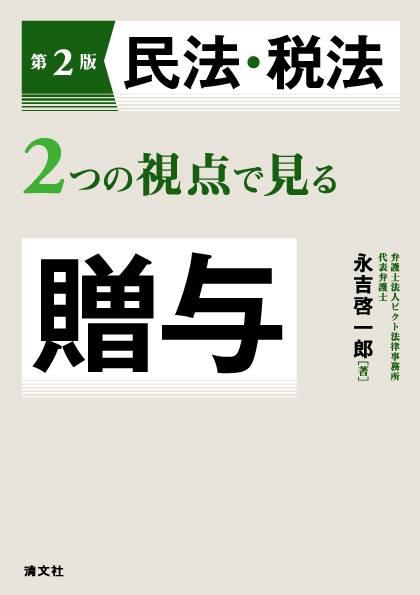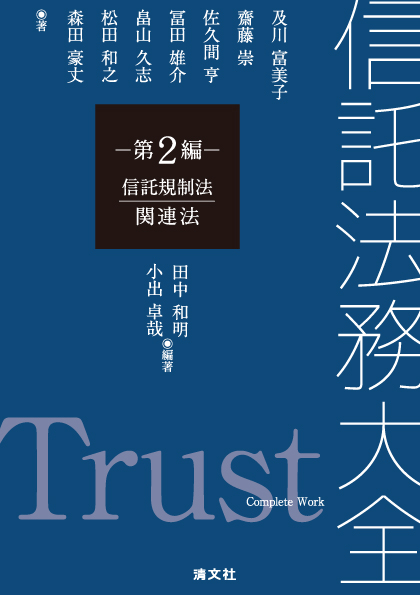改正法案からみた
民法(相続法制)のポイント
【第1回】
「「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案」における
改正内容の全体像」
弁護士 阪本 敬幸
-はじめに-
平成30年3月13日、民法の相続関係法の改正及びこれに伴う家事事件手続法の改正を内容とする「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案」が国会に提出され、本稿執筆現在、国会にて審議が行われている。本連載では、同法案のポイントを解説していく。
なお、法律案・法律案要綱全文は、下記ページから閲覧可能である。
「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案」
第1 改正法案の概要
法案における改正内容は、大きく分類すると以下の通りである。
① 配偶者の居住に関する権利の新設
② 遺産分割等に関する見直し
③ 遺言制度に関する見直し
④ 遺留分制度の見直し
⑤ 相続の効力等に関する見直し
⑥ 特別寄与料請求権の新設
⑦ 上記改正に伴う家事事件手続法の改正
⑧ 上記改正に伴う他の法律の改正
さらに分類すると以下の通りである。なお、改正法律案要綱に記載されている点であっても、内容的に現行法から変化のない点については記載していないものもある。
① 配偶者の居住に関する権利の新設
(ⅰ) 配偶者居住権
(ⅱ) 配偶者短期居住権
② 遺産分割等に関する見直し
(ⅰ) 配偶者に対する居住用不動産の遺贈・贈与についての、持ち戻し免除の意思の推定
(ⅱ) 遺産分割前の預貯金債権の行使を認める規定の明文化
(ⅲ) 遺産の一部分割の規定の明文化
(ⅳ) 遺産分割前に遺産の処分がされた場合の遺産の範囲
③ 遺言制度に関する見直し
(ⅰ) 自筆証書遺言の方式の緩和
(ⅱ) 遺贈義務者の引渡義務等
(ⅲ) 遺言執行者の権限の明確化
④ 遺留分制度の見直し
(ⅰ) 遺留分を算定するための財産の価額
(ⅱ) 遺留分を算定するための財産の価額に算入する贈与の範囲
(ⅲ) 負担付贈与がされた場合における遺留分を算定するための財産の価額に算入する贈与の価額等
(ⅳ) 遺留分侵害額の請求
(ⅴ) 受遺者又は受贈者の負担額
(ⅵ) 遺留分侵害額請求権の期間の制限
⑤ 相続の効力等に関する見直し
(ⅰ) 共同相続における権利の承継の対抗要件
(ⅱ) 相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使
(ⅲ) 遺言執行者がある場合における相続人の行為の効果等
⑥ 特別寄与料請求権の新設
・特別の寄与をした相続人以外の親族に、特別寄与料請求権を認める
⑦ 上記改正に伴う家事事件手続法の改正
・仮分割仮処分、特別寄与の審判
⑧ 上記改正に伴うその他の法律の改正
第2 各改正事項の概要
1 配偶者の居住に関する権利
(1) 配偶者の居住権の必要性
被相続人の配偶者(以下、単に「配偶者」という)は、被相続人と同居していたような場合、被相続人死亡後も住み慣れた家に住み続けたいと思うのが通常である。こうした配偶者を保護する必要性が存在することから、配偶者短期居住権及び配偶者居住権に関する条文が新設された。今回の法案における大きな改正点である。
(2) 配偶者居住権
配偶者居住権は、相続開始時に、配偶者が被相続人所有建物に無償で居住していた場合、以下のいずれかの場合に該当するときに、原則として終身、配偶者が無償で建物に居住することができる権利である。
① 遺産分割で配偶者が配偶者居住権を取得するものとされた場合
② 配偶者居住権が遺贈の目的とされた場合
③ 被相続人・配偶者間で死因贈与契約が成立した場合
〔追記:2018/6/8〕
上記の枠内において、法律上、死因贈与は遺贈の規定が準用されていることから、正確な表記とするため、③を追加し、下線部の表記を見直しました。
遺産分割審判により、他の相続人の意思に反して配偶者居住権が認められることもあり得るが、基本的には、被相続人の遺言による意思表示か、相続人全員の合意に基づき成立するものといえる。
(3) 配偶者短期居住権
配偶者短期居住権は、相続開始時に、配偶者が被相続人所有建物に無償で居住していた場合、
① 配偶者居住建物の遺産分割が必要な場合には、遺産分割により建物の帰属が確定する日か、相続開始の時から6ヶ月を経過する日のいずれか遅い日まで
② 遺産分割が不要な場合(遺言により遺贈・遺産分割方法の指定等が行われていた場合など)には、居住建物取得者による配偶者短期居住権の消滅の申し入れの日から6ヶ月を経過する日まで
すなわち、配偶者が被相続人所有建物に無償で居住していれば、原則として(例外はある)配偶者短期居住権が認められるということになる。
2 遺産分割等の見直し
(1) 配偶者に対する居住用不動産の遺贈・贈与についての、持ち戻し免除の意思の推定
婚姻期間20年以上の夫婦の一方が死亡した場合、死亡配偶者が他方配偶者に居住用不動産を遺贈・贈与していたときは、持ち戻し免除の意思を推定する旨が定められた。配偶者保護のための制度ということができる。
(2) 遺産分割前の預貯金債権の行使
最判平成28年12月19日により、預貯金債権も遺産分割の対象とされ、共同相続人が相続分に応じて当然に行使することはできなくなったが、生活費の支払や相続債務の弁済等、預貯金債権を行使すべき必要性も存在する。このため、相続開始時の預貯金債権額の3分の1に、共同相続人の法定相続分を乗じた額については、共同相続人が単独で行使することができるとされた。
(3) 遺産の一部分割の規定の明確化
遺産の一部分割は、現行法上も行われてきたところであるが、民法上、明文の規定がなかった。今回、一部分割の要件が明確化されることとなった。
(4) 遺産分割前に遺産の処分がされた場合の遺産の範囲
遺産分割前に遺産が処分された場合でも、共同相続人全員が同意すれば、処分された遺産があるものとみなして遺産分割することができるとされた。一部の共同相続人による遺産処分の場合には、共同相続人全員の同意は不要とされている。遺産分割前の遺産処分により、共同相続人間に不公平が生じることを防ぐ趣旨である。
3 遺言制度に関する見直し
(1) 自筆証書遺言の方式の緩和
現行法上、自筆証書遺言は、全文自筆であることが要件とされている。法案では、自筆証書遺言の遺産目録に限っては、自筆を要しないとされることとなった。ただし、目録の各ページに署名・押印が必要である。
(2) 遺贈義務者の引渡義務等
債権法改正を受けた改正である。債権法改正により、売買等有償契約の担保責任について法定責任説の考え方が否定され、特定物・不特定物を問わず、当事者の意思すなわち契約内容に適合する物を引き渡す義務があることとされた。
これを遺贈の場合に引き直すと、遺言者の意思からすれば、遺贈義務者には遺贈目的物を相続開始時の状態で引き渡す義務を負わせるべきであると考えられ、そのように規定された。
(3) 遺言執行者の権限の明確化
現行法上、遺言執行者の権限は必ずしも明確でないことから、原則的な権限が明確化されることとなった。
4 遺留分制度の見直し
(1) 遺留分を算定するための財産の価額
現行法と内容的に変わることはないと思われるが、「遺留分を算定するための財産の価額」という明確な文言で表現した。
(2) 遺留分を算定するための財産の価額に算入する贈与の範囲
相続人に対する生前贈与は、判例上、贈与の時期を問わず遺留分算定の基礎とされてきたが、法案では、相続開始前10年間に限って遺留分算定の基礎となる旨が定められた。
(3) 負担付贈与がされた場合における遺留分を算定するための財産の価額に算入する贈与の価額等
負担付贈与がされた場合における遺留分算定の基礎とされる部分については現行法と変わりはないが、不相当な対価をもってした有償行為(廉価での売買等)について、当事者双方が悪意の場合、対価を負担の価額とする負担付贈与とみなすこととされた。
(4) 遺留分侵害額の請求
現行法上は、遺留分減殺請求権の行使により、当然に物権的効果が発生すると考えられているが(例えば、遺留分侵害者が不動産の贈与を受けていた場合、不動産の所有権について減殺の効果が発生する。ただし、侵害者の側で価額弁償を行うことで義務を免れることは可能)、法案では、「遺留分減殺請求権」ではなく「遺留分侵害額請求権」と呼称を変え、遺留分侵害額請求権を行使する場合、金銭の支払いの請求(債権的請求)のみ行うことができることとされた。
(5) 受遺者又は受贈者の負担額
遺留分侵害者である受遺者又は受贈者が、遺留分権利者承継債務を消滅させる行為をしたときは、消滅した債務額を限度として、遺留分権利者に対する意思表示によって、遺留分権利者から受けた請求額を消滅させることができるとされた(実質的な相殺)。
(6) 遺留分侵害額請求権の期間の制限
遺留分侵害があったことを知ってから1年、相続開始時から10年で時効消滅する。現行法の遺留分減殺請求権の時効と同様である。
5 相続の効力等に関する見直し
(1) 共同相続における権利の承継の対抗要件
現行法上、判例により、遺贈による権利取得や、遺産分割により法定相続分を超えて権利取得した場合については、第三者対抗要件が必要とされている。他方、遺言で相続分の指定・遺産分割方法の指定があり、これにより法定相続分を超える権利取得がされたとしても、判例上、対抗要件は不要とされている。
法案では、相続の場合の法定相続分を超えた権利取得については、どのような場合であっても対抗要件を具備していなければ第三者に対抗できないとされた。また、取得する権利が債権である場合、債務者に対し、遺言・遺産分割の内容を明らかにした上で権利承継を通知することが、対抗要件となることが明記された。
(2) 相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使
相続分の指定があっても、被相続人の債権者は、相続人全員に対し相続分に応じて債権の請求が可能とされた。現行法の判例を反映したものといえる。
(3) 遺言執行者がある場合における相続人の行為の効果等
遺言執行者がいる場合、遺言執行は執行者のみが行い、これに反して相続人が行う行為は無効(ただし、善意の第三者には無効を対抗できない)であることが明記された。
6 特別寄与料請求権
被相続人の親族(相続人・相続放棄をした者・欠格や廃除により相続権喪失した者以外の者)で、無償で療養看護その他労務提供をしたことで被相続人の財産維持・増加に特別の寄与をした者に、特別寄与料請求権を認めることとされた。相続を知った時から6ヶ月以内か、相続開始後1年以内に、相続人に対して請求する必要がある。
相続人であれば寄与分の請求ができるところ、相続人以外の親族が特別の寄与をした場合に報いる趣旨である。
7 上記改正に伴う家事事件手続法の改正
仮分割仮処分制度(遺産分割前でも、生活費・葬儀費用・債務弁済等のために仮払を行うことを内容とする仮処分)、特別寄与の審判事件が定められることとなった。
8 上記改正に伴う他の法律の改正
刑法・抵当証券法・都市再開発法・不動産登記法・著作権法等。配偶者居住権の新設を反映させるための改正が多い。
(了)
この連載の公開日程は、下記の連載目次をご覧ください。