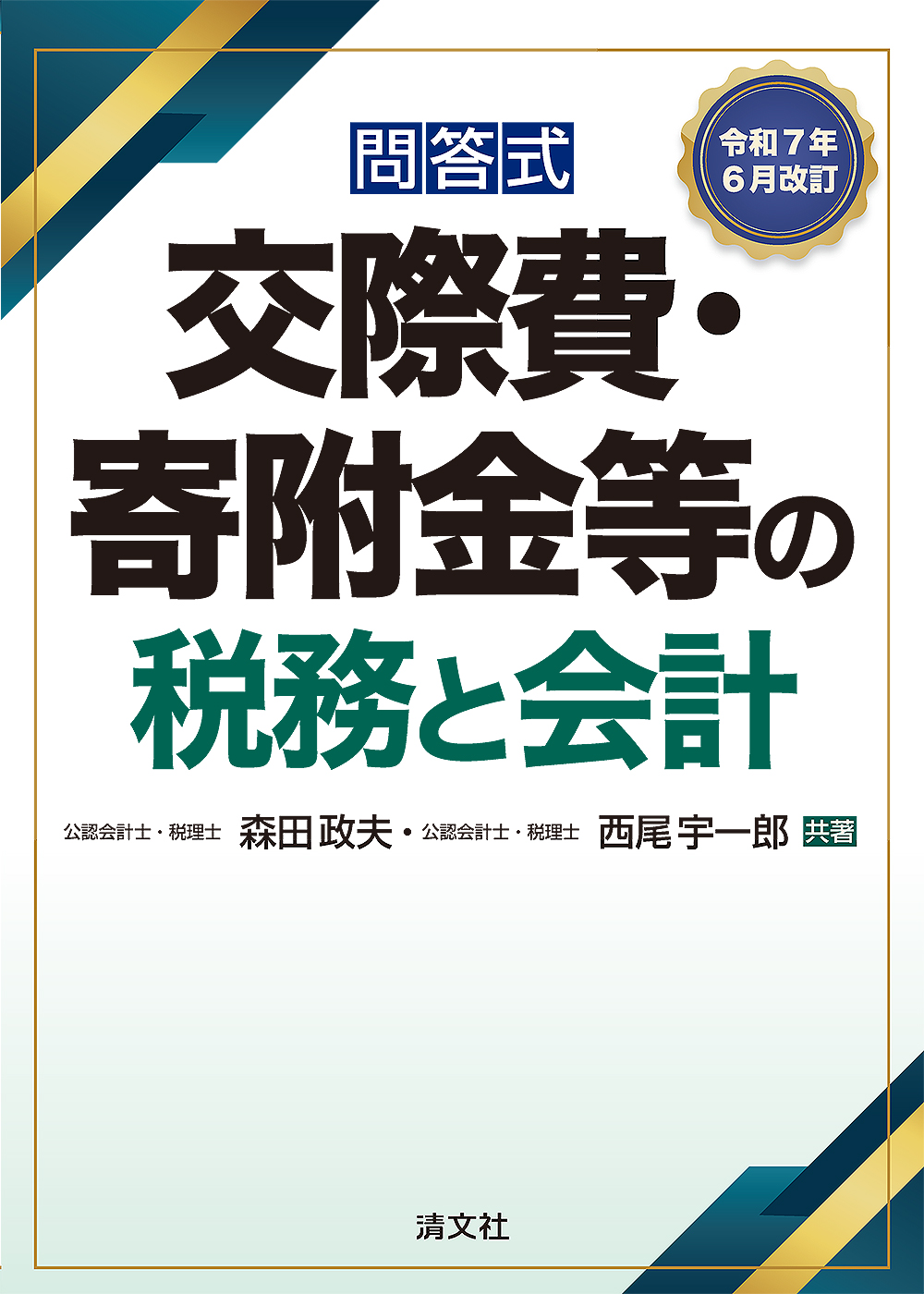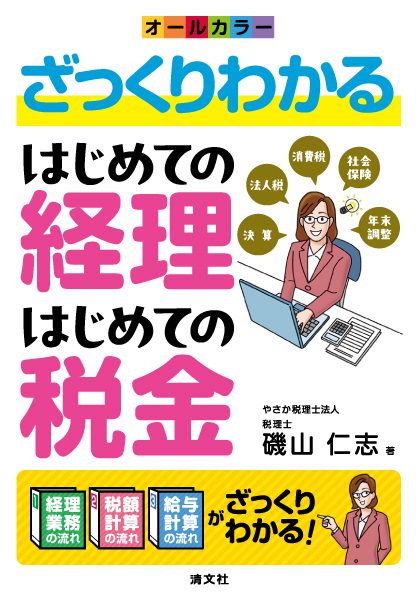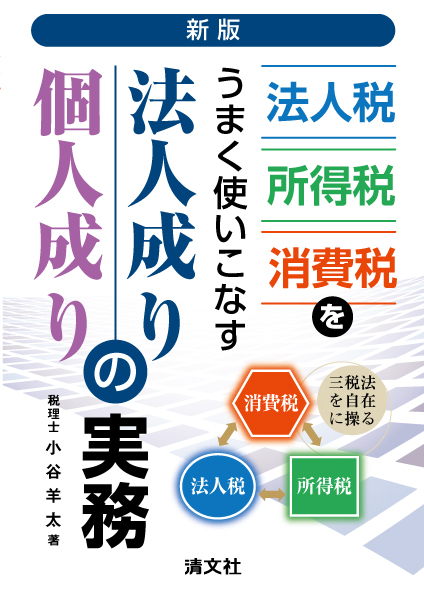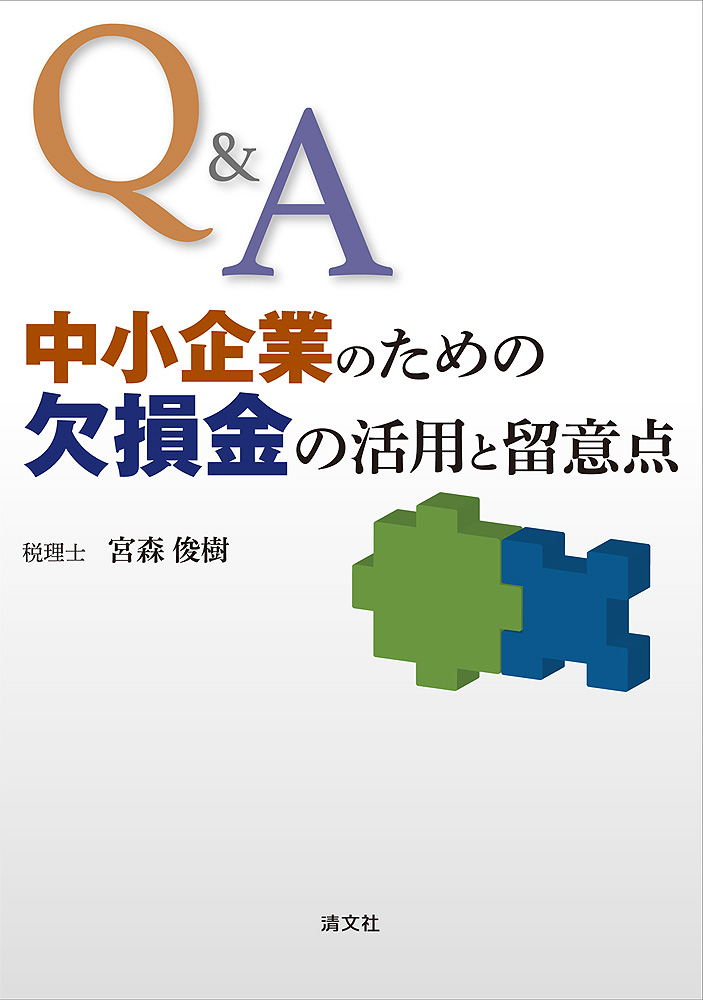中小法人の税制優遇措置を考慮した
『減資・増資』の活用と留意点
【第1回】
「中小法人の範囲の見直しと優遇税制」
公認会計士・税理士 石川 理一
1 はじめに
現在の税制上、中小法人についてはさまざまな優遇措置が施されている。
この「中小法人」として取り扱われる法人とは、
普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額・出資金の額が1億円以下であるもの又は資本・出資を有しないもの
とされている(法人税法66条2項)。
ただし、上記要件に該当した場合でも、相互会社や大法人の完全子法人等一部の法人については、中小法人とは扱われない(法人税法66条6項)。
平成27年度与党税制改正大綱において「中小法人の実態は、大法人並みの多額の所得を得ている法人から個人事業主に近い法人まで区々である」とし、「資本金1億円以下を中小法人として一律に扱い、同一の制度を適用していることの妥当性について検討を行う」と、中小法人の範囲を見直すことが言及された。
本稿では中小法人の範囲の見直しの方向性を検討し、中小法人に対する優遇措置を活用するための有効な施策である減資・増資について解説する。
2 現行の中小法人税制
中小法人に対する優遇措置として、主に以下の制度を挙げることができる。
① 軽減税率制度
② 欠損金の繰越控除制度
③ 貸倒引当金制度
④ 留保金課税制度
⑤ 交際費課税制度
⑥ 投資減税等の租税特別措置
⑦ 外形標準課税制度
これらの内容を大法人と比較すると、以下のとおりである。
① 軽減税率制度
- 軽減税率は適用されず、法人税率は23.4%
- 年800万円以下の所得については、19%の軽減税率が定められ、さらに、租税特別措置として平成29年3月31日までに開始する事業年度までは15%に軽減
② 欠損金の繰越控除制度
- 控除限度額が以下のように制限されている。
平成29年3月31日までに開始する事業年度:所得金額の60%
平成29年4月1日から平成30年3月31日までに開始する事業年度:所得金額の55%
平成30年4月1日以後開始する事業年度:所得金額の50%
- 所得金額の100%まで損金算入(控除)が可能
③ 貸倒引当金制度
- 貸倒引当金は損金算入不可
- 法定の繰入限度額まで損金算入が可能
④ 留保金課税制度
- 特別同族会社に対して特別税率による課税
- 資本金1億円以下の同族会社は特別同族会社から除外
⑤ 交際費課税制度
- 接待飲食費の50%相当額を超える交際費等の額が損金不算入
- 事業年度ごとに接待飲食費の50%相当額と800万円の定額控除限度額との選択が可能
⑥ 投資減税等の租税特別措置
- 以下の中小法人のような優遇措置なし
- 研究開発税制における税額控除割合の加算
- 所得拡大促進税制における適用要件の緩和及び税額控除割合の加算
- 中小企業投資促進税制において、資本金1億円以下の中小企業者等及び同3,000万円以下の特定中小企業者等について、特別償却又は税額控除を適用
- 取得価額30万円未満である減価償却資産について、年300万円まで損金算入可能
⑦ 外形標準課税制度
- 法人事業税の外形標準課税の適用あり
- 法人事業税の外形標準課税の適用なし
3 中小法人の範囲の見直し
法人税法上さまざまな優遇措置が施されている中小法人であるが、冒頭にも述べたようにその中には大法人並みの多額の所得を得ているなど、必ずしも担税力が乏しいとは認められない法人も含まれている。
会社法制の見直し等により資本金の性格が変わり、資本金の額が的確に企業の規模や経営実態を反映しているとは限らなくなっている。現行制度上、資本金基準のみで大法人と中小法人を区分しているため、大法人が減資を行って中小法人となり、外形標準課税を回避するなど恣意的な税負担の軽減が可能となってしまうという弊害がある。
日本税理士会連合会税制審議会では、これらの問題点への対処法を検討し2016年3月17日に「中小法人の範囲と税制のあり方について-平成27年度諮問に対する答申-」(以下、答申という)を取りまとめた。
答申では、中小法人の範囲の見直しの考え方として、以下の3つの方法が検討された。
① 現行の資本金基準の水準を見直す
② 資本金基準を廃止し、他の指標に置き換える
③ 資本金基準を維持した上で、他の指標と組み合わせる
検討の結果、現行の資本金基準は長年にわたって施行され、広く実務に定着していることなどの理由により、当面は同基準(1億円)を維持した上で、他の指標と組み合わせること(上記③の方法)によって中小法人の範囲を定めることが適当であると結論付けている。
一方、資本金と組み合わせる他の指標としては、事業年度開始時点において中小法人に該当するか否かが明確に判断できること(予見可能性)、適正な執行が担保されること、一定期間にわたって安定的であることという性格を有する必要がある。
答申では、この要件を満たす指標として、従業員数が中小法人の範囲を定めるのに適当な指標であると結論付けている。
従業員数基準には、従業員の範囲をどのように定めるか、業種ごとの差異をどのように考えるかなど、検討すべき課題が含まれているものの、企業の規模や経営実態を反映する指標として有力であり、中小企業基本法において、業種に応じた従業員数基準が定められている。
従業員数以外の指標として、所得金額又は売上高、純資産価額又は総資産価額、付加価値額などの指標も検討されたが、予見可能性等の観点からこれらの指標は問題が多いとして、答申ではこれらの指標を不適当と結論付けている。
4 税制優遇措置を適用するための減資・増資の活用
今後、中小法人の範囲については資本金基準と従業員数基準を組み合わせる方向で見直しが進められていくと考えられる。
従業員数の基準としては、業種ごとに異なる従業員数が設定される可能性があるが、現行の税制において、資本・出資を有しない法人の場合に従業員数1,000人以下を中小企業者等とする規定があることから、従業員数1,000人が1つのメルクマールとなろう。
従業員数基準として、従業員数1,000人以下であることが中小法人の範囲に含まれるための条件となることを前提とすると、資本金が1億円を超えており中小法人として扱われていない企業で、従業員数が1,000人を超えていない場合には、減資することにより税制優遇措置を適用することが可能となり、税金コストを抑えることができる。
逆に、資本金が1億円以下であったため、法人税法上、中小法人として扱われていたが、中小法人の範囲が見直された結果、従業員数が1,000人を超えるため中小法人に該当しなくなる企業も出てくるであろう。
それらの企業は資本金1億円以下にこだわる必要がなくなる。追加資本を投下することにより収益拡大が見込まれる場合には、増資による資金調達によって積極的な収益拡大戦略をとるという意思決定をする場面も出てくるであろう。
* * *
次回は減資・増資のメリット・デメリットについて解説する。
(了)
この連載の公開日程は、下記の連載目次をご覧ください。