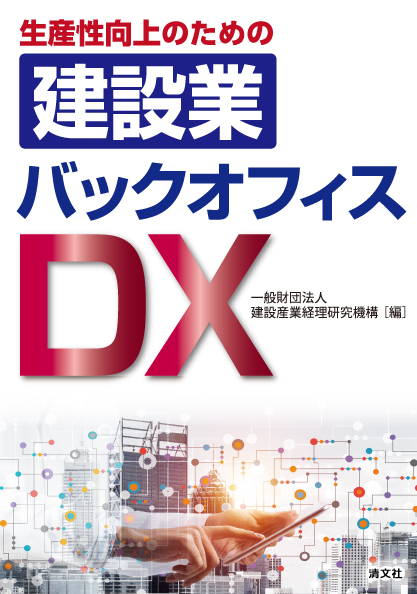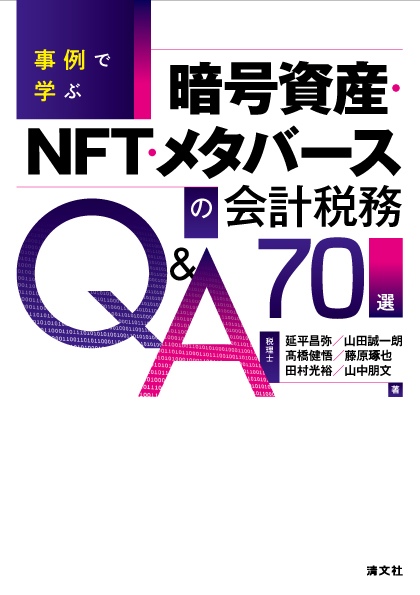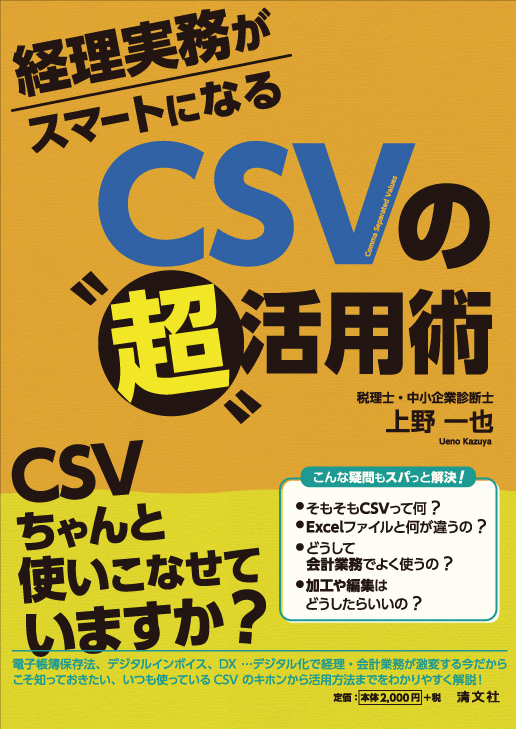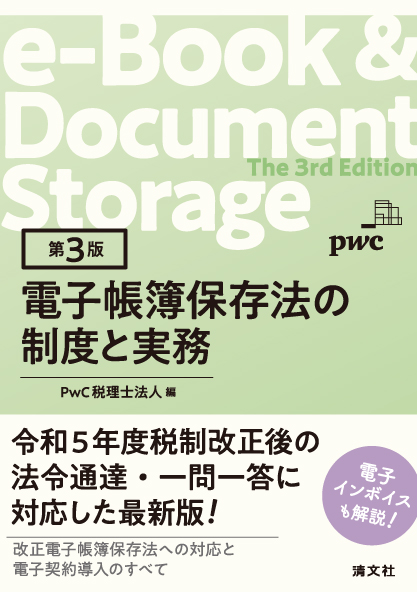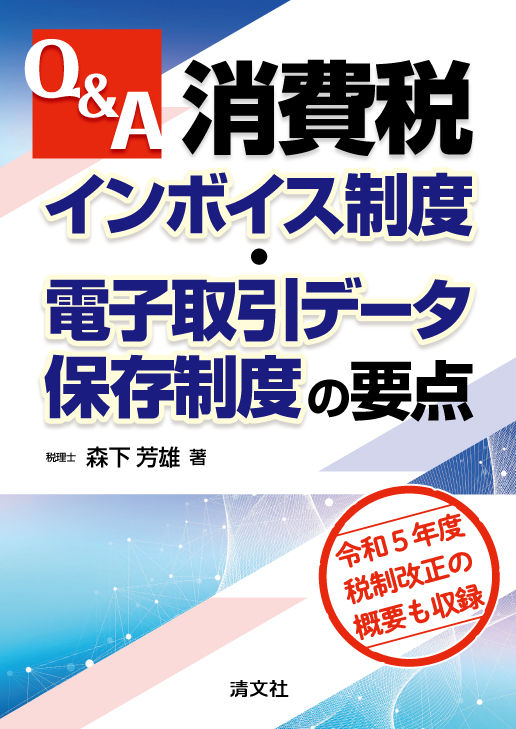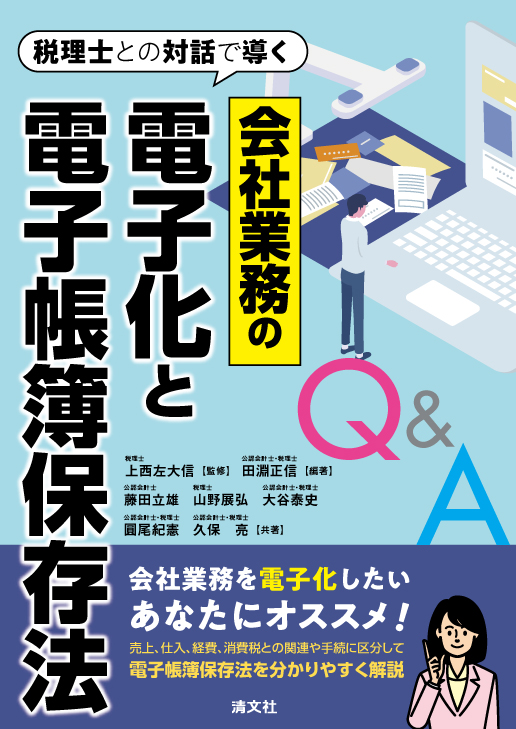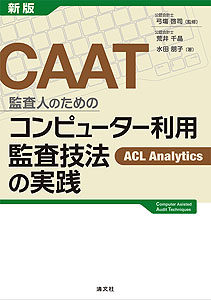〈知識ゼロからでもわかる〉
NFTとその利活用
【第1回】
「NFTの基礎知識」
東京ハッシュ株式会社 代表取締役 段 璽
公認会計士・公認不正検査士 松澤 公貴
1 はじめに
去る1月13日、国税庁のホームページにて「NFTに関する税務上の取扱いについて(FAQ)」が公表された。国内でもNFTが身近な概念として定着しつつある中で、税務・会計においても存在感が増していることを表しているといえるだろう。もとい、そもそもNFTとは何であるかを理解しておくことが重要である。
このような観点から、本連載では、3回に分けてNFTの入門知識を概説する。【第1回】では、NFTに関する最も基礎的な要素の理解を目指し、NFTの定義と性質、ブロックチェーンとの関係、長所と短所について述べるとともに、NFTを様々な面で拡張するユーティリティとNFTコレクションについても説明する。
2 NFTの定義と性質
NFTは「Non-Fungible Token」の略であり、「非代替性トークン」とも訳される。まず、ここでいうトークンとは、「所有と移転(譲渡)が可能なデジタルデータ」であると理解していただきたい。イメージとしては、オンラインゲームでプレイヤーがアイテムを収集し、通貨を介して他のプレイヤーと取引をする状況において、アイテムや通貨がトークンに当てはまる。
Fungibilityは「代替性」を意味する。通貨は普通、代替可能である。つまり、Aさんが持つ100円とBさんが持つ100円の間には価値の差がなく、両者が100円を交換することに何の問題もない。したがって、最小単位(1円)までの分割も可能である。一方で、代替不可能なものはこの世に唯一無二である。一点ものの絵画や不動産、あるいは個人的な思い入れが詰まった100円玉も非代替性を持つといえる(※)。非代替性を持つものは互いに識別可能であり、個別のIDが付与されていると考えても差し支えない。
(※) このように代替性の有無は文脈によって変わるが、NFTとして表されているものについては、それが非代替性を持つと主張していると捉えてもよいだろう。
3 ブロックチェーンとメタデータ
NFTの多くはブロックチェーン上でやりとりされる。この文脈におけるブロックチェーンの役割は、NFTの所有者の記録を台帳に収め続けることである。つまり、過去と現在において、「特定のNFTを誰が所有しているか」を記録し続けている。
通貨の役割を持つ一般的な暗号資産(俗にいう「トークン」)とNFTとの決定的な違いは、NFTは何かしらの唯一無二な概念に対する権利を表象するということである。その概念は、しばしば「メタデータ」という関連データとしてNFTに紐付けられている。例えば、芸術作品の画像データをメタデータに持つNFTがあれば、「対応する芸術作品の所有権をそのNFTの所有者が持つこと」がブロックチェーン上で示されていることになる。
4 NFTの長所と短所
(1) NFTの長所
ブロックチェーン上で管理されるNFTには、いくつかの長所がある。まず、ブロックチェーンで一度確定した取引は覆すことが非常に困難であり、NFTの所有権を高いレベルで保証することができる。また、ブロックチェーンが安全に存続する限り、利用者に落ち度がなければ、その所有権や存在は永続的である。利用者自身が所有に対して主権と責任を持つ様は「自己主権」とも表現され、特定の企業や政府に管理を委ねる必要がないことから、しばしば好まれる特性である。
そして、ブロックチェーンの規格に沿っていれば、NFTには互換性が保たれる。言い換えれば、特定のゲーム内で獲得したアイテムがNFTであれば、そのゲームの存続にかかわらず、NFTの所有権をブロックチェーンで示すことができる。デジタルデータであるため、証明や移転にかかる手間が実物より少ないことも長所である。
さらには、コンピュータプログラムとして様々なロジックを付与することが可能であり、これを利用すると、例えば著作権者のために、二次流通におけるロイヤリティ収入の機会を与えることができる。
(2) NFTの短所
一方で、NFTには短所もいくつかあり、主にリスクの高さが関連している。まず、ブロックチェーン上のデータであるがゆえに、ブロックチェーンやプログラムの安全性に問題がある場合にはNFTの所有権が危ぶまれる。管理体制の不備等、利用者の過失によってNFTを永遠に失う可能性もある。
さらに、プロジェクトという括りでNFTを新たに発行するビジネス形態が一般的になってきているが、これを模した投資詐欺は後を絶たず、被害に遭うリスクにも注意が必要である。
そして、NFTを資産として保有する場合、その価格変動リスクは暗号資産と関連が強く、比較的大きい。
5 NFTのユーティリティ
以上のように、NFT自体は特定のメタデータと繋がった単なるデータであり、ブロックチェーンにその存在と取引が記録されることに由来して、いくつかの基礎的な特性を持つものである。しかしながら、実態はこれにとどまらず、NFTをツールとして捉えることで、更なる利用価値(ユーティリティ)を取り決め、活用するケースも多い。
代表的なNFTユーティリティは、著作物の(商用)利用権、データへのアクセス権、会員制コミュニティへのアクセス権、イベント参加権などである。さらに、特定のNFT保有者に別のNFTや暗号資産等を配布したり、NFTを売却できないように一時的に預け入れることで、新たな投資機会を与えたりするスキームもある。こうしたNFTのユーティリティはビジネスにおいてインセンティブとして活用される。
注意点として、NFTのユーティリティは、ブロックチェーン上でコンピュータプログラム(スマートコントラクトと呼ばれる)に従って実現が約束されるものと、それ以外、つまり主に人間の裁量によって実現されるものがある。例を挙げると、前者はNFTの預け入れを条件とした投資機会、後者はオフラインイベントの参加権が当てはまる。リスクとして、スマートコントラクトの脆弱性や詐欺の可能性に気を付けなければいけない。
6 NFTコレクション
NFT自体は唯一無二であるが、1つの銘柄として「NFTコレクション」を作成し、その銘柄に属しながら互いに識別可能であるNFTを複数個設定することも可能であり、現在はこのパターンがむしろ標準的である。NFTコレクションを実現するための技術的なコントラクト規格があり、イーサリアム・ブロックチェーンのERC-721はその最も標準的な例である。これを初めて活用したNFTコレクション「CryptoKitties」は複数の子猫を表すNFTから構成されており、それぞれが唯一のNFTとして識別されるが、同時にその全てがCryptoKittiesに属している。
7 おわりに
本稿では、NFTの基礎的な観点を概説した。NFTは非代替性のトークンとしてブロックチェーン上でその存在と取引が記録され、確実性の高い形で唯一無二の概念に対する所有権を表す。またNFTにはユーティリティがしばしば付与され、ビジネス媒体としても活用されている。現在は、複数のNFTを1つの銘柄としてまとめたNFTコレクションが主流である。
【第2回】では、NFTの利用形態について、若干の技術的背景とともに解説する。
(了)
次回は5月18日に掲載します。