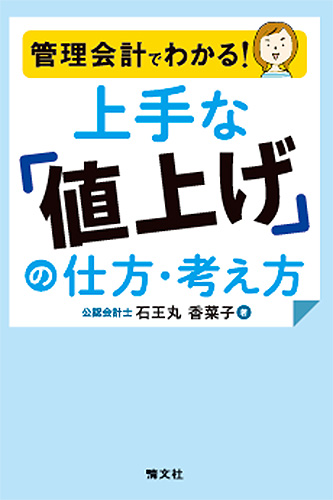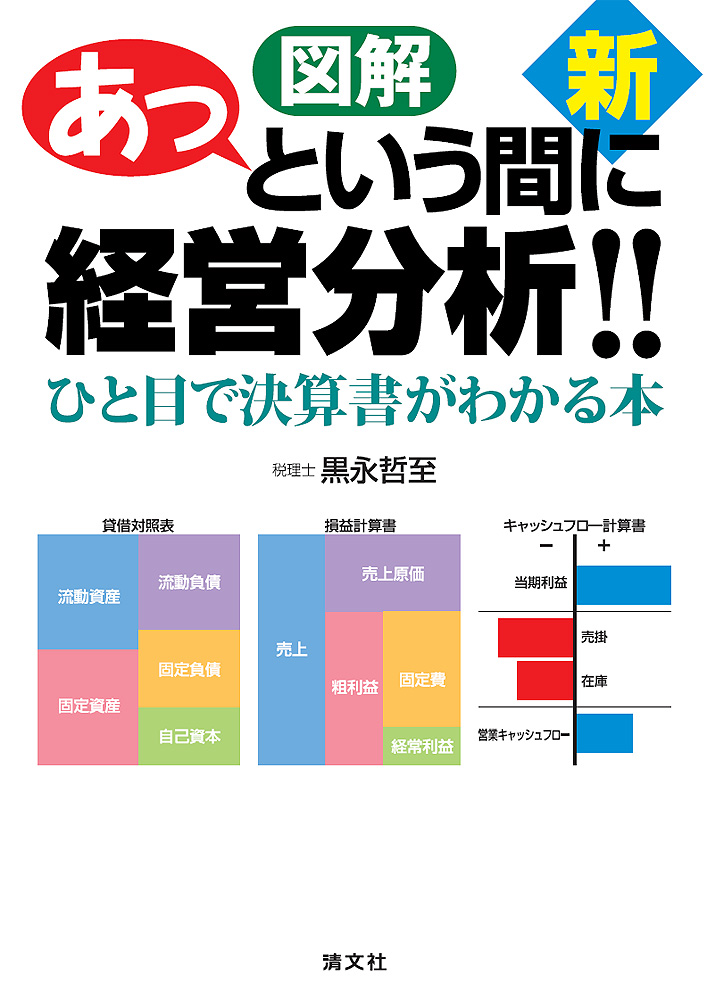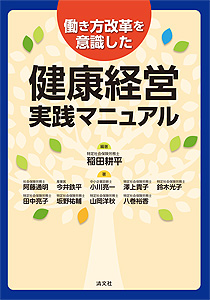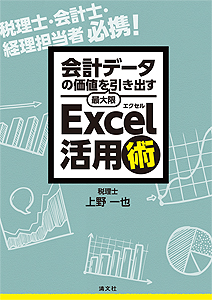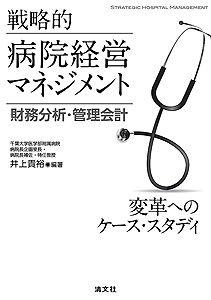企業予算編成上のポイント
【第1回】
「キャッシュ・フロー経営と予算の関係」
公認会計士 児玉 厚
大学卒業後、鉄鋼商社の経理、監査法人を経て、会社を起業して13年目になる。
たまたま「経理マン」「会計士・税理士」「経営者」という3つの立場を経験してきた。
それぞれの立場に対して、少なからず思い入れがある。
「経理マン」の時代には
- 「経営者はなぜ、管理部門を軽視するのか」
- 「数値に基づく経営が重要であり、経営者も会計を深く理解する必要があるはずだ」
と思っていた。
「会計士・税理士」の時代には
- 「(監査):経営者はなぜ、監査を軽視するのか。経営の姿をオープンにし、監査と正々堂々対峙していくべきではないか」
- 「(税務):経営者はなぜ、節税という幻想に目を奪われ、税引後利益をいかに最大化するかに向き合わないのか」
と思っていた。
今「経営者」の時代の中にいる。経営者の頭にあるのは次の2つの点だ。
- 「(お金):社員等の生活を守っていくために、いかに売上高を上げ、利益を上げていくべきか」
- 「(人):そのために、社員のベクトルをどう一本化して、オフバランスの人財価値をいかに最大化していくべきか」
経営者は、「過去」ではなく、99%「将来」の方向を向いている。
- 「なぜ、経理マンは、未来志向の経営の視点で行動し、サポートしてくれないのか」
- 「なぜ、会計士や税理士は、未来志向の経営の視点での良き相談相手になってくれないのか」
と多くの経営者が感じていると思う。
それだけ会社を継続させていくことが難しい時代に入っているのだ。
「経理マン」「会計士・税理士」「経営者」の間には、「大きな心の溝」がある。
お互いに信頼し合う「夢のトライアングル」の構築が、日本経済が復活していくために必要だと思う。
そのキーワードが「予算」である。
デフレの時代が長く続いている。物の価値は下がり、お金の価値が上がっていく時代だ。
「キャッシュ・フロー経営」の重要性を疑う経営者は誰もいないだろう。
ところが、目標としての「予算キャッシユ・フロー計算書」は作成されていない。
予算損益計算書の作成に留まっている。
実績財務諸表は、原則として過去の記録の積上げであるが、国際会計との整合性の観点から「予測概念」が多く入ってきている。たとえば、退職給付会計や減損評価や繰延税金資産の回収可能性や資産除却債務などである。時価評価も予測概念に入るだろう。
IFRSでは「将来キャッシュ・フローの予測に資する」という点が重視されるので、さらに予測主義が加速する。
実績財務諸表の適正性は、「予測の正確性」がなければ担保されない。
オリンパスなどの粉飾決算は跡をたたず、資本市場の発展に大きなブレーキがかけられている。
犯罪である粉飾決算は、なぜ起きるのだろうか?
上場会社は、決算短信で業績予想を発表している。(外部予算)
投資家はこの指標を重視して、「株を買う、保有し続ける、株を売る」という経済的意思決定をしている。
業績予想の売上高の10%以上、利益の30%以上、予想値からかい離すると判断した場合には、すみやかに業績予想の修正と修正理由を発表しなければならない。下方修正で合理的な理由がない場合、投資家の信頼を失い、株価が暴落する危険性がある。
経営者は、「何としても業績予想を実現する」という強いプレッシャーを受けているので、結果として経理操作による粉飾決算を誘発するリスクがある。
もし、業績予想が「営業キャッシュ・フロー」で示されるとしたら、経理操作しても意味がないので、粉飾決算の芽を実質的につむことができるはずだ。
内部予算が粉飾決算の引き金になる場合もある。
A事業は年率10%で成長しており、B事業は逆に年率10%で縮小しているとしよう。
A事業部門の目標売上高を当期比10%増加に設定することは合理的だが、B事業部門の目標売上高を同様に当期比10%増加に設定されたら、実現は限りなく不可能に近い。
B事業の営業マンは、予算達成により賞与査定が決まるとしたら、「何としても目標売上高を達成しなければ」という強いプレッシャーを感じ、与信上の危ない先にも販売したり、「経理操作してでも目標売上高を達成したい」という衝動にかられる危険性は常にあるだろう。
もし、営業部門の予算目標を「営業キャッシュ・フロー」に設定し、その目標達成により賞与等の人事評価がなされる仕組みに変わったら、「危ない先には売らない」し、「経理操作をしても意味がない」し、「できるだけ回収サイトを短くする努力をする」はずだろう。
連結経営において、連結子会社等をコントロールすることは難しいが、連結経営方針の予算目標を営業キャッシュ・フローに設定すれば、同様のリスクは大きく回避され、連結ベースのキャッシュ・フローの改善に繋がるだろう。与信管理や滞留債権の回収等の対応の管理コストも自動的に削減されていくはずだ。
営業キャッシュ・フローが改善されていけば、その資金を未来のために投資することができる。
それは社員にとっても大きな夢だ。
会社は「人」であり、「人の意識」が変わらなければ「会社」も変わらない。
つまり「キャッシュ・フロー予算制度の重要性を共に理解する教育基盤」が必要になる。
実績財務諸表を作成する理論が「会計」である。
しかし、予算財務諸表を作成する理論は世の中に存在していない。
そこで、「予算財務諸表を作成する理論」を「予算会計」に名付けることにした。
ここでいう予算財務諸表とは、「予算損益計算書、予算株主資本等変動計算書、予算貸借対照表および予算キャッシュ・フロー計算書並びに月次資金計画書」をいう。
さらに2011年7月より、ブログ&メルマガ「予算会計を学ぶ」を立ち上げた。
このサイトでは、2000年10月に発刊された『企業予算編成マニュアル』(清文社・共著)を解説し、予算作成の連関エクセルシート(製造業)を作成し、メルマガで配信している。「いつも楽しみにしています」というお言葉を多数いただき、感謝に堪えない。
素朴な気持ちとして、「会計業界をもっと夢のある世界にしたい」と思う。
多くの会計人の方のみなさんと「予算会計」という新たな世界を一緒に創造していけたらと願っている。
なお、株式会社プロフェッションネットワーク主催でセミナー「キャッシュ・フロー予算作成実践演習」を平成25年2月6日(水)に開催いたします。※当セミナーは終了しました。
また、上記のメルマガ「予算会計を学ぶ」も、ご登録いただければ幸いです。
(了)