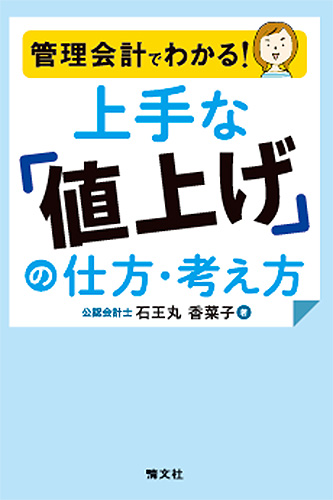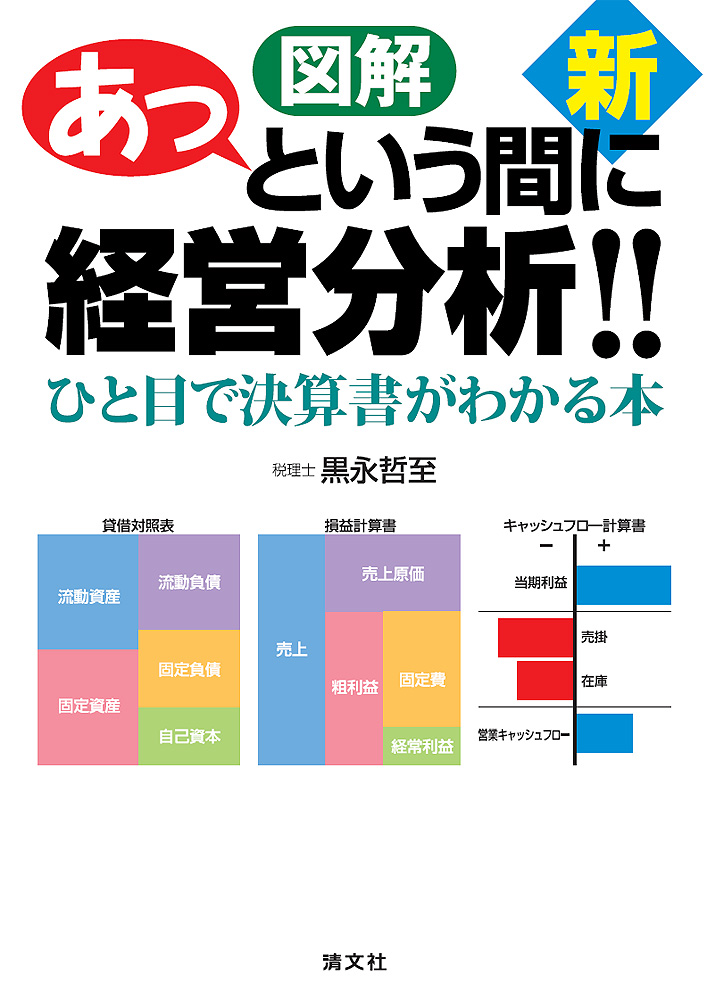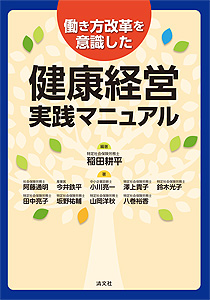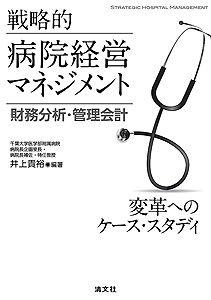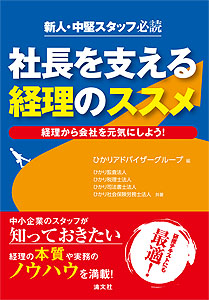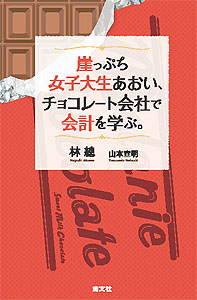◆◆◆ 対 談 ◆◆◆
◆◆◆ 対 談 ◆◆◆
管理会計を学ぶ
【第1回】

【発言者】
公認会計士 林 總 氏
公認会計士 秦 美佐子 氏
(対談日:2013年2月18日)
公認会計士を目指す受験生、また企業で会計・経理部門に配属された人にとって、管理会計はつかみどころがなく、難しいと言われる。
林總氏は、この管理会計をわかりやすく解説した書籍を執筆され、数多くのベストセラーを生み出してこられた。
秦美佐子氏もまた、女性会計士が活躍する書籍を執筆され、人気作家の仲間入りをされた。
今回は、会計士として、また作家として活躍されているお二人に、ご自身の経験から、会計の初学者がどのように管理会計を学べばいいかを対談していただいた。
なぜ、管理会計なのか?
秦
林先生は、女子大生がインターンシップで、管理会計を学んでいくというストーリーの『崖っぷち女子大生あおい、チョコレート会社で会計を学ぶ。』(林總・山本宣明著 清文社 2013年2月)を上梓されました。
なぜ、この本をお書きになろうと思ったのですか。先生の従来の本との違いは何ですか。

林
私は会計、特に管理会計を、専門知識から一般知識に落とし込みたいという気持ちがかなり強く、これまでに「餃子屋シリーズ」とか「会計物語、団達也がゆく」といった会計をテーマにした本を書いてきました。かれこれ15冊ぐらい書いた。ただ、私の本をアカデミックの視点から見たらどうなんだ、理論的に正しいのかという読者も、いないわけじゃないんですね。
言うまでもなく、業務システムというのは理論的に正しくないと動きません。私はもちろん、かなり厳密な理論で整合性を組み立てて本を書いていますが、どうしても危惧を持つ人がおられるようです(笑)。
それからもう一つ、実務的な話ばかりしていると、全体を俯瞰できなくなってしまう。要するに、会計理論のどこを使って実務作業をしているのかが分からなくなってしまう。まさに、『木を見て森を見ず』です。
そこで今回は、実務家の私と、それから研究者の山本宣明先生の2人で書いたわけです。
私はもともと管理会計が大好きで、会計士試験では得意科目でした。管理会計は好きになると難しくも何ともない。いい点がすぐとれるんです。ただ、嫌いな人には徹底的に嫌われる科目です。
なぜ嫌いかというと、全体のイメージがつかめない、だから自分は何を学んでいるのか分からない。逆に、好きな人は体系が単純だから、たいしたことはないと思う。
実は、両方とも正しくて両方とも間違っている。
体系そのものは単純であっても、その体系の裏側にある実際の人の動きとか、工場のモノの流れとかを考えていくと実はものすごく奥が深くて、管理会計理論だけでは、おそらく利益管理はできない。理解するには、会社のシステムや業務は当然、会社法もファイナンスも分からないといけない。総合力が必要なのです。
私は、この総合力というものを、何らかの形で、やさしく、ハードルを下げて伝えたかった。
「総合力」を難しく考えてしまい、そこに引っ掛かるとなかなか先に進めないところがあって、特に受験生や管理会計の実務に携わっている人にとって価値ある本にしようと思ったのです。

秦
体系をイメージできないから理解できないというところが、管理会計では非常に多いと思っていまして、特に会計士試験の受験生は、実務経験がない大学生から勉強を始める人がほとんどです。
実務経験がない中で、管理会計を理解するために必要なことは何でしょうか。
林
そのための仕掛けとして、主人公と、それから指南役が必要でした。『崖っぷち女子大生あおい』では指南役がたくさん出てきます。主人公は女子大生です。
企業とか会計の右も左も分からない女性がいて、その女性に感情移入することによって、同じ視線で問題を考え、解決策を考えていく。
秦
受験生の8割ぐらいが男性だと思うのですが、先生の本では、主人公の多くを女性にされています。理由はあるのですか。
林
本を読み進めてもらうためには、読者が登場人物のファンになるということが重要です。男性なら、主人公のあおいのファンになって一緒に考える。女性なら、あおいになりきるかあるいは友達としてか、いずれにしても、あおいの目線まで下りてきて考えるということです。
ファンになり感情移入できるかが、非常に大きなポイントです。
ファンになってもらうには主人公が魅力的でなくちゃいけないよね。だから、私の価値観で、魅力的な女性はこういう人かなと思ってやってる(笑)。
図式化とメタファーを駆使する
秦
林先生は、会社をオーケストラになぞらえ、社長は指揮者で社員は演奏者にたとえていらっしゃる。難しい学問とか知識を身近なものに置き換えることで非常にイメージしやすくなるのですが、先生なりの工夫はあるのですか。
林
私は記憶力がすごく悪いんです。おそらく、普通の人の2倍3倍努力しないと覚えられない。ただ、それをカバーするために、図表にして覚えてきました。
図表というのは、作り上げて頭の中にプリントすれば、それを思い浮かべることにより一覧で思い出せる。受験時代もそれをやりました。コンサルタントをやっているときは、会社からヒアリングしたことをA4用紙1枚か2枚の図にする。そうすると、何年たっても忘れません。
図にするのと同じことですけども、本を書くときはメタファーを使い、何かに置き換えることによっても全体が理解しやすくなるようにしています。一度読めば、後から内容や体系を思い出す。そのためには、ストーリーのあるたとえ話が一番有用だと思った。
ただし、かなり考え抜き、的を射たメタファーじゃなければ読者は読んでいて嫌になってしまうので、的確なメタファーを見つけ出すまでは、かなり時間がかかります。
秦
だから、先生の本はストーリー展開になっていますし、メタファーもたくさん使われているわけですね。
売上予測をどうやって立てる?
林
私から秦さんに質問したいのだけれど。私は昔の会計士試験を受けてきているので、管理会計といえば、すなわち原価計算でした。

秦
ええ、そうですね。
林
昔は、有名な管理会計学者の本の2~3冊を、ボロボロになるまで繰り返し読んで、問題を解いて試験に受かってきたわけです。ところが、どうも今は、受験範囲が広くなり、ある意味、とても難しくなったように思う。
受験生の立場からすると、どこをクリアすれば、管理会計が得意になるのですかね。
秦
管理会計を学んでいたときに気になったのですが、例えば、操業度を高めれば製品1個当たりのコストを下げられると学んでいく中で、売上予測が非常に大事だということを学びます。製造現場の工場長は受注予測した上で、それに合わせて材料を購入し、製品を生産していくわけですが、実務ではどうやって売上予測をしているのか。また、経営者は3年から5年の計画を立てて、それに基づいて原価に落とし込んでいくと本書にありますが、その3年、5年先をどうやって予測していくのかなど、実務ではどのように行われているのかが気になりました。
林
それは受験勉強をしているときですか。
秦
はい。理論はこう解説しているけれど、未来のことを予測するのに実際はどこまで通用するのか。実際はどうやって明日の売上予測しているのかですね。
林
ああ、そこね。受験生のとき疑問だったということですね。
秦
はい。教科書の中ではちゃんと予測できて、プランどおりにいけば利益が出ることになっているけれど、実務で本当に使えるのかどうかが気になりました。
林
将来というのは現在の延長ですから、現在の延長が予測になるんです。
例えば来月の売上予測は今月の受注がベースです。それから、3ヶ月後の売上予測は、今月の商談がベースになっている。1年後であれば、これまでの2年、3年のトレンドを見て、今現在の受注状況を勘案し予測する。
ですから、何だか分からないけども将来の売上はいくらになる、という予測はあり得ない。
テキストには、「予測」、「予測」と繰り返し書いてあるから分かりにくい。現時点における、あるいは過去から今に至る傾向とか勢いとか、商品それぞれの力とか、そういったものを総合して将来の売上を予測しているんです。
秦
なるほど。管理会計でよく標準原価というのが出てきて、例えば固定費を配分するときに、3,000個売れるから、その固定費を3,000個で按分して1個当たりの原価を出したりします。その3,000個が売れる見込みがあるというのを、過去の実績とか傾向を見て判断しているということですね。

林
そうです。今の商品力なら3,000個は堅い線で売れる。それを4,000個売る予測を立て、プラス1,000個をどう売るかというときに、マーケティングが絡んでくる。プラス1,000個を売るためには、今までの販売チャネルとは別のチャネル、例えば通販やインターネットで売ることを考える必要があります。また、売上を伸ばすためには、従来の若者向けだけでなくシニア向け商品を作って売り、積み増ししていくということを考えるわけです。
したがって、現在をベースにして、次にどのようなアクションをとるかによって、将来の売上予測が決まってくる。
秦
なるほど。で、何か差異が生じた際には、その都度変えていく。
林
そう。その差異というのは、実は金額の差異ではなくて、この販売チャネルではこう売っていこう、あるいはこういう新製品を作って売ろうとして、それがうまくいかなかったから予測と実際の売上の数量差が出るということなのです。
秦
はい。
林
会計というのは、金額で比較するから分からなくなる。お金の後ろ側には物や時間の流れがあり、人の動きがある。そこを比較しなくてはいけない。
秦
なるほど。
販売価格と原価管理
秦
あと、原価を論じる際に、セットとなるのが販売価格ですね。どれだけの利益を出したいかによって、その販売価格が決まると思うのです。販売価格の決め方で、原価プラス利益で設定する積上げ方式と、市場の相場から予め販売価格を決めた上で原価を設定する方式の2種類あると思うのですが、実際はどういったパターンが多いのですか。
林
販売価格というのはあくまでマーケットで決まる、つまり顧客によって決まるということです。マーケットもいろいろあって、裕福な層がマーケットなら販売価格が高くても売れるが、そうでない層には売れない。
一方、裕福ではないけれども、一番需要が多いボリュームゾーンがある。ボリュームゾーンを狙う場合、販売価格は低くなっても、量は売れるわけですから、一定の利益率を稼げれば利益の総額は増える。
どの層をマーケットにするかによって販売価格は決まってきます。どのマーケットであろうとも、利益が確保できなくてはならない。そこで目標原価水準を決めて、それ以内に製品コストを抑えるターゲット・コスティングです。たぶん、これが正しいやり方だと思う。

秦
なるほど。マーケットを想定した販売価格を設定して、その販売価格に合わせて何円以下に原価を抑えるという形で決めている。
林
『崖っぷち女子大生』でも書きましたが、トリュフチョコレートの販売価格が300円とした場合、ターゲット顧客というのは、普通にチョコレートが大好きな主婦ではなく、かといって、あまりチョコレートを食べない男性でもない。おいしければ高くても買おうという女性がターゲットです。でも、チョコレートの市場は競争が激しいから、そんなにたくさん売れるわけではない。販売価格も1個1,000円では売れないわけです。
カカオを選んできてカカオペーストを作り、多くの工程を経て職人が1個1個作るので、実はものすごくコストがかかっている。1個300円は高いようだけれど、そこから利益を稼ぐというのは結構大変なのです。どこのカカオを使いどのように調合するか、材料や作り方を全部考えないと2割、3割の利益率は稼げない。
それを事前にきちっと決めて、そのとおりに作っていきましょうというのが、いわゆる原価管理であり利益管理なのです。実際、原価計算を机上で勉強をしていても、そこが分からないよね。
秦
ええ、分からないですね。
林
受験生にとって、管理会計が分かりづらいのは、そこにある。実際に実務に就くと、ああ、こういうことなのかと分かりますけれどね。
秦
そうですね。

(次回へ続く)
おすすめ書籍のご案内
『崖っぷち女子大生あおい、チョコレート会社で会計を学ぶ。』
林 總、山本 宣明 著
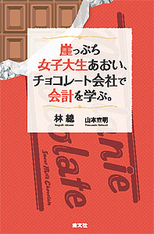
清文社・2013年2月発行・定価:1,575円(税込)
主人公の女子大生が、インターンシップの経験を通じ、管理会計がビジネスの現場でどのように考えられ、有機的につながっているかを学んでいく過程を、わかりやすい「ストーリー」と「解説」で完全詳解!
※プロフェッションネットワークの書籍販売ページでは、会員優待価格でご購入いただけます。