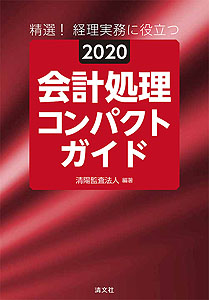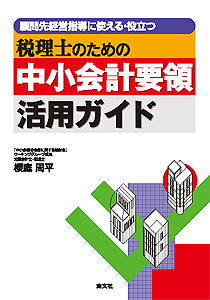「平成24年版
中小企業の会計に関する指針」の
主な改正点と留意点
【第1回】
「改正の経緯と指針の読み方」
税理士 永橋 利志
1 はじめに(改正までの経緯)
「平成24年版 中小企業の会計に関する指針(以下「中小会計指針」という)」が、本年2月に公表された。
中小会計指針は、平成17年8月に公表され、平成18年の会社法施行に伴う純資産の部に係る取扱いの変更をはじめ、その後のわが国の会計基準(以下「日本基準」という)の動向に呼応し、毎年改定されてきた。
ただし、その改定は、日本基準の改正等をすべて受け入れたものではなかった。それは、中小企業の規模や会計情報を必要とする利害関係者は、金融機関や取引先、そして、利害関係者とはいえないが、法人の申告内容の適否を調査する課税庁であるという実態を鑑み、精緻な日本基準を適用することが中小企業の実態に合わず、中小企業の会計の質を高め、財務体質の改善等に資すると考えられなかったからである。
このように、中小会計指針は、日本基準の動向に対応しつつ、中小企業の実態に合うように改正が行われてきたが、近年の国際会計基準(以下「IFRS」という)適用の影響を中小会計指針も受け、中小企業の経営者や経理担当者にとって、中小会計指針が複雑な処理を求めるようになり、利用しづらいものになるのではないかという議論がされるようになった。
また、以前から、中小会計指針の規定そのものが複雑で、中小企業にとって利用しづらいという指摘もあり、平成24年2月に「中小企業の会計に関する基本要領(以下「中小会計要領」という)」が公表された。
これは、中小会計指針より中小企業経営者にとって、理解しやすく、利用しやすい会計処理の基準という基本的考え方で導入されたものであるが、会計処理について、中小会計指針と大きく変わることなく、中小会計指針の簡易版というよりはむしろ、中小企業として最低限クリアすべき会計処理が規定されていると考えるべきである。
今回の中小会計指針の改正は、このような状況の下で、中小会計指針に対するこれまでの評価を受けて、水準を維持しつつ、中小企業経営者にとっても理解しやすく、利用しやすい基準とするよう、会計処理や計算書類への表示方法等について、大きく変えるのではなく、各規定の表現ぶりを理解しやすいようにし、必要に応じて脚注で解説を加える等の変更がなされた。
本連載では、今回の改正点をはじめ、中小会計指針を適用する場合の注意点を確認することとする。
2 中小会計指針における「重要性」
中小企業に限らず、企業が会計処理を検討する際に「重要性がないと認められる場合には、簡便的な方法が認められる。」という旨の規定を見ることがある。
この場合の「重要性」の判断基準は、画一的に決められるのものではなく、個々の事案ごとに金額的重要性や当該処理に係る取引が企業に与えるインパクト等を加味して判断することになる。
ただし、その判断は非常に難しく、中小会計指針においても、各論の該当する個々の規定ごとに「重要性」について触れていくべきであるが、そのような対応は、規定を増やすだけで実効性に欠けることから、中小会計指針の【総論】の「本指針の記載範囲及び適用に当たっての留意事項」第9項(2)に「重要性について」という項目を新たに設けた。
そこでは、「本指針の各論において記載の会計処理の中には、重要性の乏しいものについて、簡便な方法によることが認められているものがある。重要性が乏しいかどうかについては、金額的な面と質的な面の双方を考慮して判断することとなるが、具体的な判断基準は、企業の個々の状況によって異なり得ると考えられる。」としている。
さらに、重要性に関連して、「重要性が乏しいもの以外に、退職給付債務の計算方法等、中小企業の特性を考慮した簡便的な方法が認められている場合もある。」として、簡便法処理基準の具体例を紹介し、中小会計指針全体に共通するルールを示すこととした。
3 中小会計指針における「要点」と読み方
今回の改正により、本文が変更されたものではないが、中小会計指針を利用する上で認識しておかなければならないものとして掲げられるのは、各項目にある「要点」の位置づけについてである。
中小会計指針では、総論が第1項から第9項まで、金銭債権から始まる各論が第10項から第89項までの全89項の規定がある。
特に、日常の業務では、各論の該当項目を確認することが多くなるが、その際、中小会計指針の規定本体は、例えば、金銭債権であれば、第10項の金銭債権の定義「金銭債権とは、~(後略)~。」の本文であり、各論の冒頭にある枠組みの部分は、本文規定を要約したサマリー的位置づけのものであるという点について、これまでと同様であり、変更がない部分であるが、要点が規定であると見られていたような事実も散見された。
中小会計指針を利用するときは、各項の本文が規定であり、枠組み内の要点は、本文規定のポイントを要約したものであるという位置づけを認識しておく必要がある。
4 まとめに代えて
今回は、中小会計指針の今回の改正に至る経緯と、総論の改正点を確認した。
次回からは、各論での改正による変更点及び改正による変更点の有無にかかわらず会計処理を行う際の注意点、さらには、日本税理士会連合会が作成し公表している「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」を作成する際の注意点について確認することとしたい。
【参考】 日本税理士会連合会ホームページ
・「「中小企業の会計に関する指針(平成24年版)」の公表について」
・「中小企業の会計に関する基本要領」
(了)