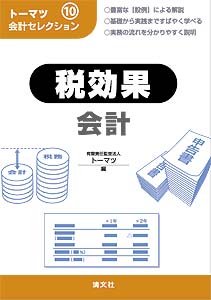『繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針』の
要点・留意点
【第1回】
「適用指針の読み方」
公認会計士 阿部 光成
平成27年12月28日、企業会計基準委員会は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号。以下「適用指針」という)を公表した。
適用指針は、「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」(日本公認会計士協会。以下「監査委員会報告第66号」という)などを基本的に引き継ぐものであるが、新たに規定された部分及び公開草案から変更された部分については、実務に大きく影響するものと考えられる。
「企業会計基準適用指針公開草案第54号『繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(案)』の主なコメントの概要とそれらに対する対応」が公表されているので、適用指針を読む際の参考になるものと思われる。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅰ 適用指針を読むときのポイント
前述のように、適用指針は、監査委員会報告第66号の内容を引き継ぐ部分と新たに規定する部分に分かれている。
適用指針を読む場合には、次の3つのことに注意するとその趣旨を理解しやすくなるものと思われる。
① 「踏襲している」と記載されている部分(監査委員会報告第66号を引き継いでいる部分の説明)
② 「企業が合理的な根拠をもって説明する場合」の規定(適用指針21項ただし書き、24項、28項、29項、77項~79項)
③ 「結論の背景に示された例示」(特に、新たに規定された部分に関する例示)
また、公開草案の審議では、次の事項が議論されていたので、これらの規定に関する実務への適用に際しても注意が必要と考えられる。
(a) 各分類の要件をいずれも満たさない場合の取扱い(適用指針16項)
(b) 「合理的な説明に関する取扱い」から「企業が合理的な根拠をもって説明する場合」への変更(上記②参照)
(c) 早期適用の取扱い(適用指針49項(1)(2))
(d) 適用初年度の期首の影響額の取扱い(適用指針49項(3))
Ⅱ 定義
定義では、「一時差異等加減算前課税所得」と「課税所得」がポイントになると考えられる(適用指針3項(7)(9)、58項。[設例1])。
「一時差異等加減算前課税所得」と「課税所得」については、これらを使用する場面の相違に注意する必要があると考えられる。
「一時差異等加減算前課税所得」
【定義】
将来の事業年度における課税所得の見積額から、当該事業年度において解消することが見込まれる当期末に存在する将来加算(減算)一時差異の額(及び該当する場合は、当該事業年度において控除することが見込まれる当期末に存在する税務上の繰越欠損金の額)を除いた額をいう。
【使用する場面】
将来に関する要件について、将来において当期末に存在する将来減算一時差異が解消する時に税金負担額を軽減する効果を有するかどうかを判断するために使用している。
「課税所得」
【定義】
法人税等に係る法令の規定に基づき算定した各事業年度の所得の金額の計算上、当該事業年度の益金の額が損金の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
【使用する場面】
過去に関する要件について、過去において将来減算一時差異が解消した時に税金負担額を軽減したかどうかに関する実績を把握するために使用している。
課税所得の見積りに、将来減算一時差異などを加減するのかどうかについては、「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第10号)21項において、次のように規定されている。
将来の課税所得の見積りに関して、本項で述べる課税所得とは、当期末に存在する将来加算(減算)一時差異のうち、解消が見込まれる各年度の解消額を加算(減算)する前及び当期末に存在する税務上の繰越欠損金を控除する前の繰越期間の各年度の所得見積額である。
Ⅲ 繰延税金資産の回収可能性の判断等
基本的に、従来の考え方を踏襲している。
① 繰延税金資産の回収可能性の判断における回収可能性の水準に関する基本的な考え方(一時差異等加減算前課税所得が生じる可能性が高いと見込まれるかどうかなど。適用指針6項、59項)
② 繰延税金資産の回収可能性の判断に関する手順(適用指針11項、61項)
③ スケジューリング不能な将来減算一時差異の取扱い(適用指針13項、62項)
適用指針の公表に際して、「【参考】企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」と監査委員会報告第66 号等の比較」が公表されている。
当該【参考】を読むと、多くの事項が改正されているように思われるが、上記のように、基本的には、監査委員会報告第66号などを踏襲していることが理解できると思われる。
このため、「踏襲している」や「見直さないこととした」などの説明が付されている事項については、実務に対して大きな影響は与えないものと思われる。
Ⅳ 企業の分類の枠組み
監査委員会報告第66号は、過去の業績等に基づいて、会社を例示区分に分類し、将来年度の課税所得の見積額による繰延税金資産の回収可能性を判断することとしている。
一方、適用指針は、次のように規定し、監査委員会報告第66号における企業の分類に応じた取扱いの枠組みを基本的に踏襲した上で、当該取扱いの一部について必要な見直しを行っている(適用指針15項、16項、64項)。
適用指針は、企業の分類に関する「要件」を定めており、「要件に基づき企業を分類し」と規定しているので、企業は(分類1)から(分類5)のいずれかに分類されることになる。
適用指針15項
収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得等に基づいて繰延税金資産の回収可能性を判断する際に(第6項参照)、第16項から第32項に従って、要件に基づき企業を分類し、当該分類に応じて、回収が見込まれる繰延税金資産の計上額を決定する。
適用指針16項
なお、第17項、第19項、第22項、第26項及び第30項に示された要件をいずれも満たさない企業は、過去の課税所得又は税務上の欠損金の推移、当期の課税所得又は税務上の欠損金の見込み、将来の一時差異等加減算前課税所得の見込み等を総合的に勘案し、各分類の要件からの乖離度合いが最も小さいと判断されるものに分類する。
監査委員会報告第66号では、例示区分に直接該当しない場合であっても、それぞれの例示区分の趣旨を斟酌し、会社の実態に応じて、それぞれの例示区分に準じた判断を行う必要があると規定している(5(1))。
前述のように、適用指針は、企業を分類する要件を規定したが、分類の実行可能性の観点から、必要と考えられる分類の要件を示しているので、各要件のいずれも満たさない企業が存在することが考えられる(適用指針65項)。
当該企業については、諸事情を総合的に勘案し、各分類の要件からの乖離度合いが最も小さいと判断されるものに分類することとなる(適用指針16項)。
ただし、適用指針16項における判断は、各分類の要件からの乖離度合いを定量的に検討することを意図するものではないと述べられている(適用指針65項なお書き)。
(了)