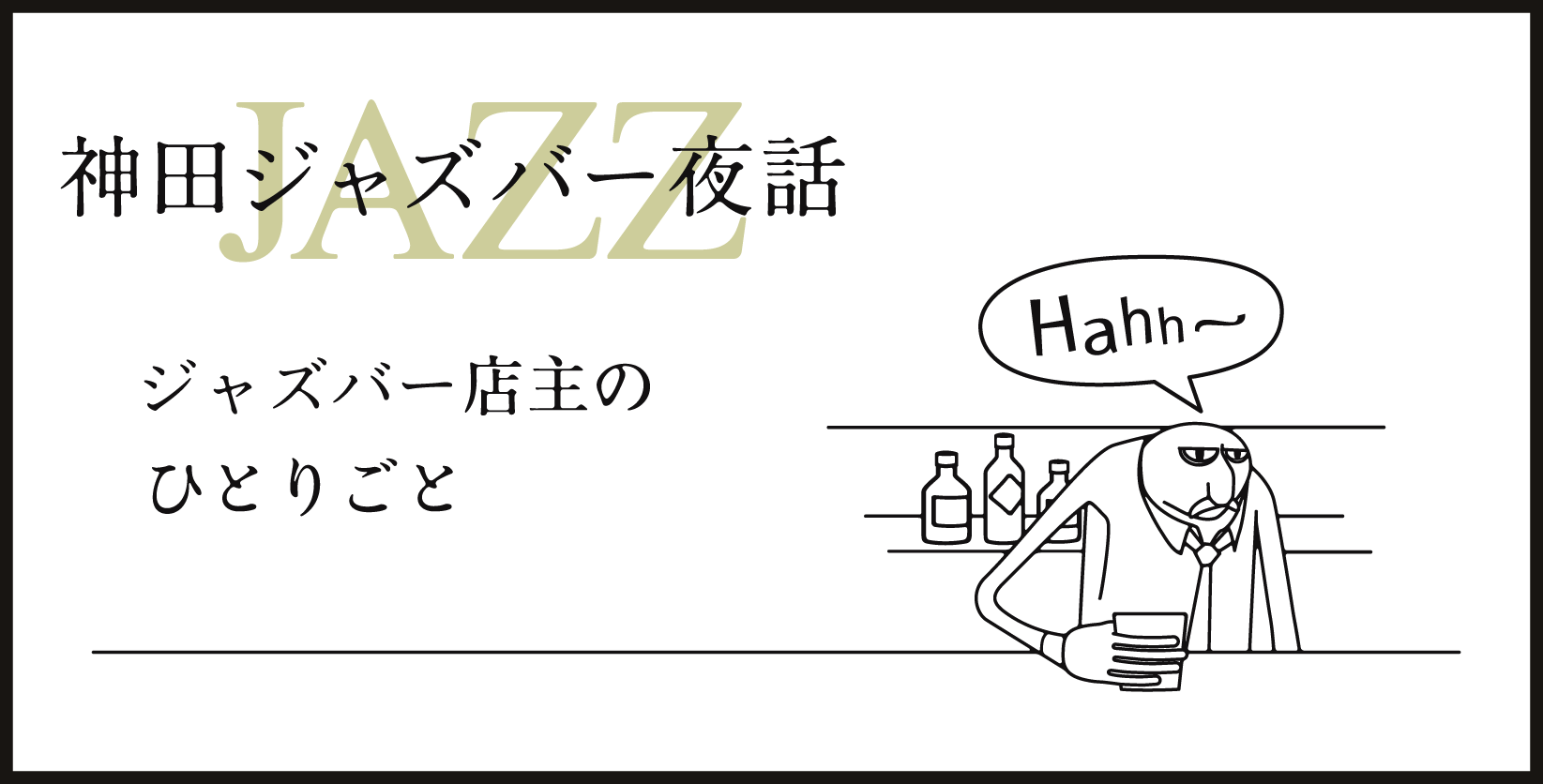
町名の頭に神田がくっついた、いくつもある町のひとつ。立ち飲み屋やもつ鍋屋の赤い提灯が灯る裏道の古い小さなビル。その地下へ途中で折れ曲がった階段を降り、黒い扉を開けると内側の真っ黒な箱がある。ここはジャズ・バー「G」。客のひとりもいない店内には、バド・パウエルが弾く半世紀前のピアノの音が流れている。
「来ないなあ」
ひとりごとは、ピアノの音と混ざって一旦店内に響くとすぐに消えたが、虚しい余韻はいつまでも漂っている。言わなきゃよかったと思う。
今夜はまだひとりも客が来ていない。閉店までもう1時間もない。
ボックス席のひとつで後悔している50代も後半になる小太りのおやじ。それが私で、ここでは「マスター」と呼ばれる。客が来ればだが。
私は本を読むのにも疲れ、トランプ占いにも飽き、ジンを飲み、たばこを吸っている。ジンはボトルの3分の1ぐらい、たばこは2箱空にした。
店主の一番の仕事は客を待つことだと気付いてからもう随分になる。
天井も壁も床も真っ黒な店内に、赤っぽいカリン材の重厚な5人掛けのカウンターと4人掛けのボックス席が2つあり、バックバーに並ぶ酒ビンは宝石のように輝いている。初めて訪れた客は一様に感嘆の声を上げるが、ここまで辿り着くには些か勇気がいる。
裏道にあり、ジャズで特化され、地下にあって中が見えないバー。隠れ家的でいいじゃないか。といったら聞こえはいいが、客が入り難い条件がみごとに揃っているという見方が正しい。客がいないのが常体と化し、客が来ると私はいつも驚いてしまう。
とはいえ、私は「私の時間」を楽しんでいる。悩んでたって客が来るわけじゃない。来るときは来る。こうして酒に酔い、バドのピアノに身を任せていられるのだからいいじゃないか。誰に煩わされることもなく私ひとりの貸切状態、なかなかの贅沢だ。もしかしたら私はこの時間を求めてジャズバーを始めたのかも知れない。などと酔っぱらった頭で考えている。
しかし、月末も近いのに家賃分も稼げていないってのは情けないね、どうも。
「来ないなあ」
またひとりごとが洩れてしまった。いや、泣きごとだなこれは。
電話が鳴って眼が醒めた。いつの間にか寝ていた。
「は、はい、Gです」私はあわてて受話器を取り、耳にあてたままアンプへ駆け寄り、音楽のボリュームを下げた。
「これから5人で行こうと思うんだけど、空いてます?」
飲んでいる店かららしく、背景音がうるさくて聴き取りづらい。
「ええ、今来れば貸し切りみたいなもんです」
「え、貸し切りなの?そうかあ、貸し切りじゃしょうがないね。うん、わかった」
「いえ、そうじゃなくて、来てくれれば貸し切りみたいなもんだって・・・」
言い終わらないうちに電話は切れてしまった。余計なこと言うんじゃなかった。
「まいったなあ」
思わず声が出ていた。
【今夜の一曲】
シー/バド・パウエル
She / Bud Powell [Swingin’ With Bud]

ジョージ・シアリングの曲で、ニュアンスを変化させて繰り返される情感のこもったテーマがいい。バド・パウエルの左手は、譜面では表せないニュアンスを含んで、アグレッシヴな右手と相まって独自の音を創り出している。ときにミス・トーン、不協和音、中途半端な音であったり、バド・パウエルはピアノという楽器のきれいに鳴らない音までも使用して、音楽を創っている。
まだ乾いていない絵具の隣に異なる色の絵具を塗り、2つの色の不規則に混色した境界。あるいは塗り重ねたときの混色具合。それは多分に偶然が関与しているが、それでよしとする絵描きの感性が生み出す色である。バド・パウエルの音には、それと似た色が確かに存在する。
(了)
「神田ジャズバー夜話」は、毎月最終週に掲載します。



