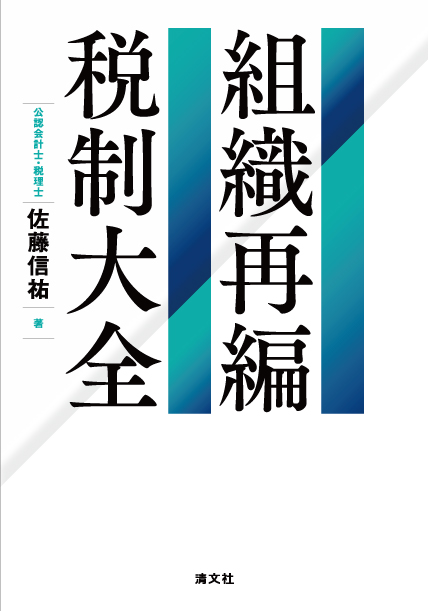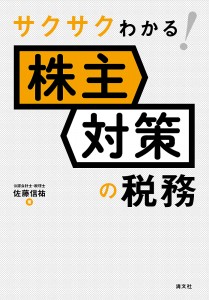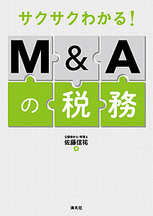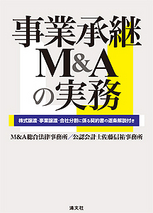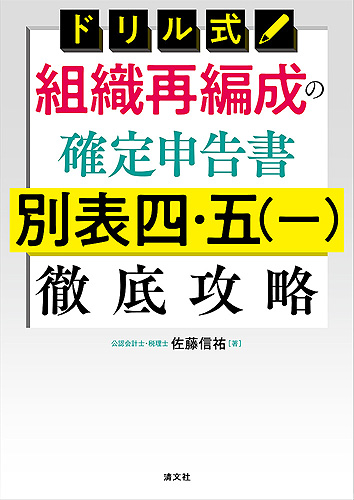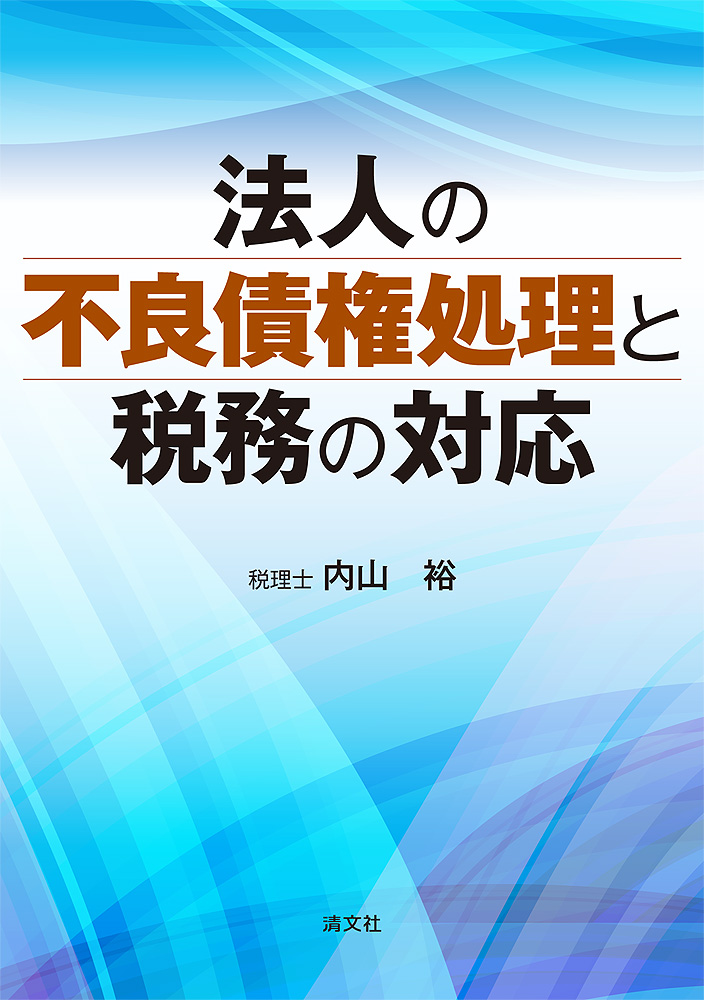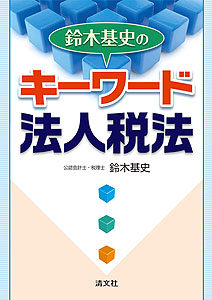貸倒損失における税務上の取扱い
【第1回】
「近年における税制改正の概要」
公認会計士 佐藤 信祐
平成23年度税制改正により、貸倒引当金制度は、銀行、保険会社その他これらに類する法人及び中小法人等に限定され、それ以外の法人は4年間の激変緩和措置を設けて廃止されることになった。
そのため、これらの業種に該当しない大法人においては、不良債権を貸倒損失として実現させる重要性が高まってきたと考えられる。
本稿では、近年における貸倒損失、貸倒引当金に係る税制改正の概要について解説を行う。
1 平成10年度税制改正
法人税法の抜本改正が行われたと言われているのが、平成10年度税制改正である。
平成10年度税制改正により、引当金制度が大幅に見直され、貸倒引当金の制度についても、
債権償却特別勘定を貸倒引当金制度に含めることとし、貸倒引当金の繰入限度額は、期末貸金を個別に評価する貸金(その一部につき回収が不能となった債権に限る。)と一括して評価するその他の貸金とに区分し、個別に評価する貸金については現行の債権償却特別勘定の繰入基準に相当する基準で回収不能見込額を計算し、一括して評価する貸金については過去3年間の貸倒実績率を乗じて貸倒見込額を計算し、両者を合計した金額による。(『平成10年度税制改正の要綱』より)
とされた。
このように、貸倒引当金の繰入限度額の計算が、個別評価金銭債権と一括評価金銭債権とに区分して計算する方式に改められた。
さらに、中小法人等を除き、一括評価金銭債権に対する貸倒引当金については、法定繰入率が廃止され、実績繰入率により貸倒引当金の計算を行うことになった。
2 平成12年度通達改正
平成12年6月28日に、法人税基本通達が改正され、法人税基本通達11-2-1の2(平成14年度の法人税基本通達の改正により、法人税基本通達11-2-2に変更)として、貸倒損失として計上したものについて、その後の自己監査や税務調査により否認された場合であっても、個別評価金銭債権に対する貸倒引当金の要件を満たしているのであれば、「個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書」を提出することにより、貸倒引当金の計上を認めることが明らかにされた。
しかしながら、平成23年度税制改正により、そもそも貸倒引当金制度は、銀行、保険会社その他これらに類する法人及び中小法人等に限定されてしまったため、それ以外の法人においては、意味のある制度ではなくなってしまった。
3 平成13年度税制改正
平成13年度税制改正により、組織再編税制が導入され、貸倒引当金の制度についても、期中損金経理の制度や、貸倒実績率の引継ぎ等が定められた。
また、平成13年度税制改正により、
個別評価金銭債権に係る貸倒引当金と一括評価金銭債権に係る貸倒引当金とを区分し、個別評価金銭債権に係る貸倒引当金については、その個別評価金銭債権に係る債務者ごとの繰入限度額に基づき損金算入額を計算する。(『平成13年度税制改正の要綱』より)
こととされた。
さらに、平成13年度税制改正前は、貸倒引当金の繰入限度額は、個別評価金銭債権に係る繰入限度額と一括評価金銭債権に係る繰入限度額の合計額とされていたため、個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入額に繰入限度超過額がある一方で、一括評価金銭債権に貸倒引当金の繰入額が繰入限度額に達していないような場合には、その通算が可能であったが、平成13年度税制改正により、個別評価金銭債権に係る繰入限度額と一括評価金銭債権に係る繰入限度額とをそれぞれ別に計算することとされたため、このような通算は認められなくなり、平成15年2月28日に改正された法人税基本通達11-2-1の2において、そのことが明らかにされている。
4 平成14年度税制改正
平成14年度税制改正により、連結納税制度が導入され、連結納税制度下においては、連結完全支配関係のある他の法人に対する金銭債権については、貸倒引当金を設定することが認められなくなった。
5 平成21年度税制改正
平成21年度税制改正により、企業再生税制が見直され、法的整理、私的整理における資産の評価損益を計上する対象資産として金銭債権が含められることになった。
それ以前においては、金銭債権に係る評価損益の計上は認められていなかったため、貸倒損失又は貸倒引当金の要件を満たさない限り、含み損部分について、損金の額に算入することは認められていなかった。
そのため、金銭債権に係る評価損益の計上が認められるようになったことについては、法的整理、私的整理という極めて限定された場面のみであるが、金銭債権における法人税法上の取扱いを大きく変更するものといえる。
なお、資産の評価損と貸倒損失は理論上も本質的な差異があることから、租税法の分析においても、両者は異なる検討をすべきであることはいうまでもない。この議論については、貸倒損失について、部分貸倒れを容認すべきか否かという議論にも繋がってくる点であるため、本連載において、いずれその点についても触れる予定である。
6 平成22年度税制改正
平成22年度税制改正により、グループ法人税制が導入された。その結果、資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上の法人又は相互会社等の100%子法人については、中小法人等の特例が適用されないことになった。
さらに、平成23年度税制改正により、中小法人等の特例の適用除外の範囲が、100%グループ内の複数の大法人に発行済株式の全部を保有されている法人にも拡充された。
7 平成23年度税制改正
平成23年度税制改正により、貸倒引当金制度は、銀行、保険会社その他これらに類する法人及び中小法人等に限定され、それ以外の法人は4年間の激変緩和措置を設けて廃止されることになった。
8 総括
このように、平成10年度税制改正から平成23年度税制改正までの流れについては、貸倒引当金の制度を大幅に見直すものであったといえる。
しかしながら、最終的に、銀行、保険会社その他これらに類する法人及び中小法人等を除いては、貸倒引当金が廃止されることになったということは、それ以外の法人については、不良債権を貸倒損失として実現させる重要性が高まってきていると考えることもできる。
一般論ではあるが、上記の業種を除く大法人においては、主要取引先、子会社、関連会社を除き、多額の不良債権が生じる可能性は少なく、子会社、関連会社に対する金銭債権についても、平成23年度税制改正前においても、貸倒引当金の計上が容認されにくかったということを考えると、平成23年度税制改正により大きな影響を受けるのは、外部取引先に対する金銭債権が不良債権化したケースであると考えられる。
また、アベノミクスの影響により、少しずつ景気が回復しているという考え方もあるが、日本経済、世界経済の動向は不透明であり、今後、産業構造の変化により、外部取引先や子会社、関連会社に対する不良債権が増えてくる可能性は否めない。
本連載においては、そのような状況を鑑み、貸倒損失についての税務上の取扱いについて理論的に分析した上で、実務上、どのように対応すべきなのかという点を模索していく予定である。
(了)
「貸倒損失における税務上の取扱い」は、毎月第2週・4週に掲載します。