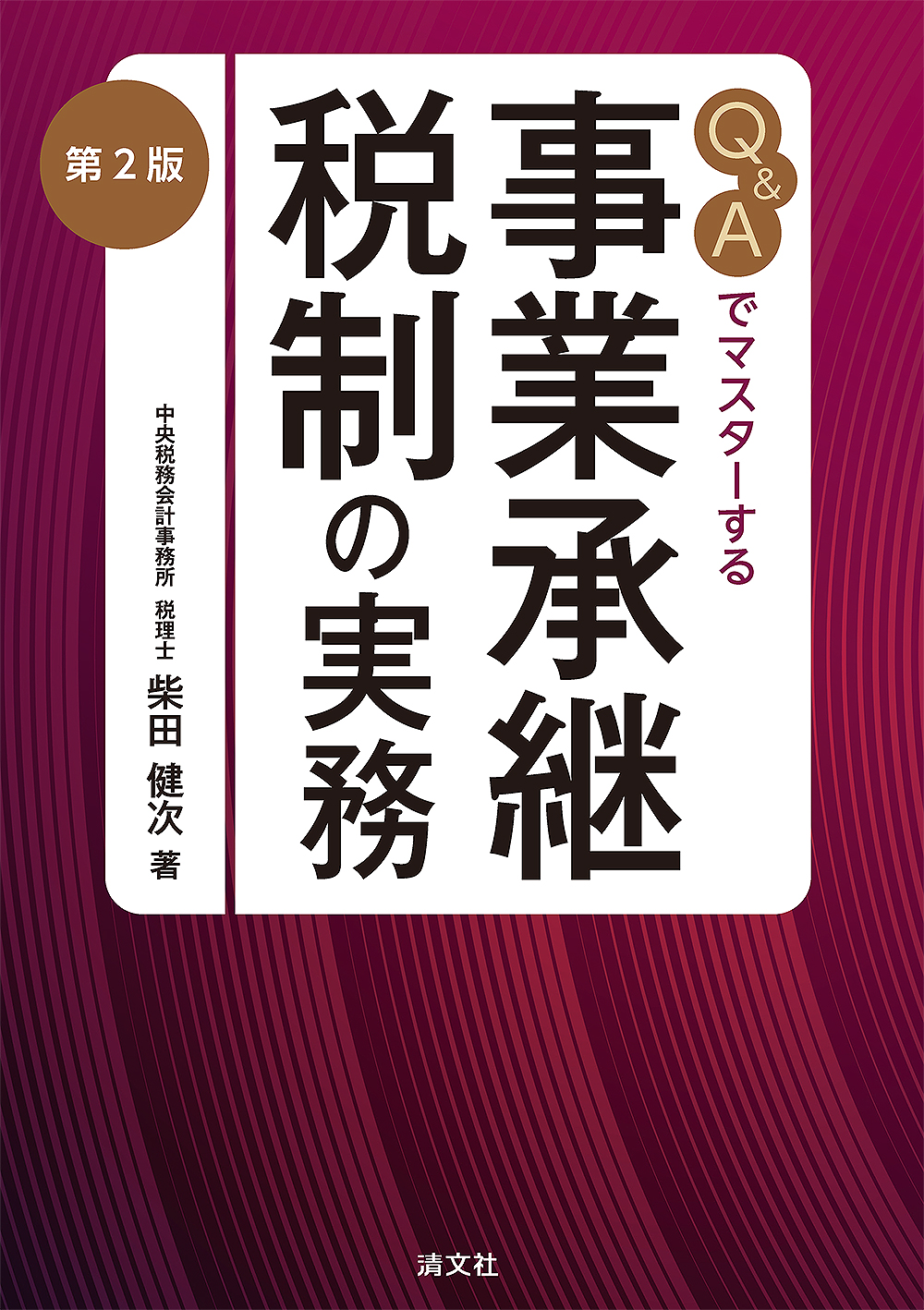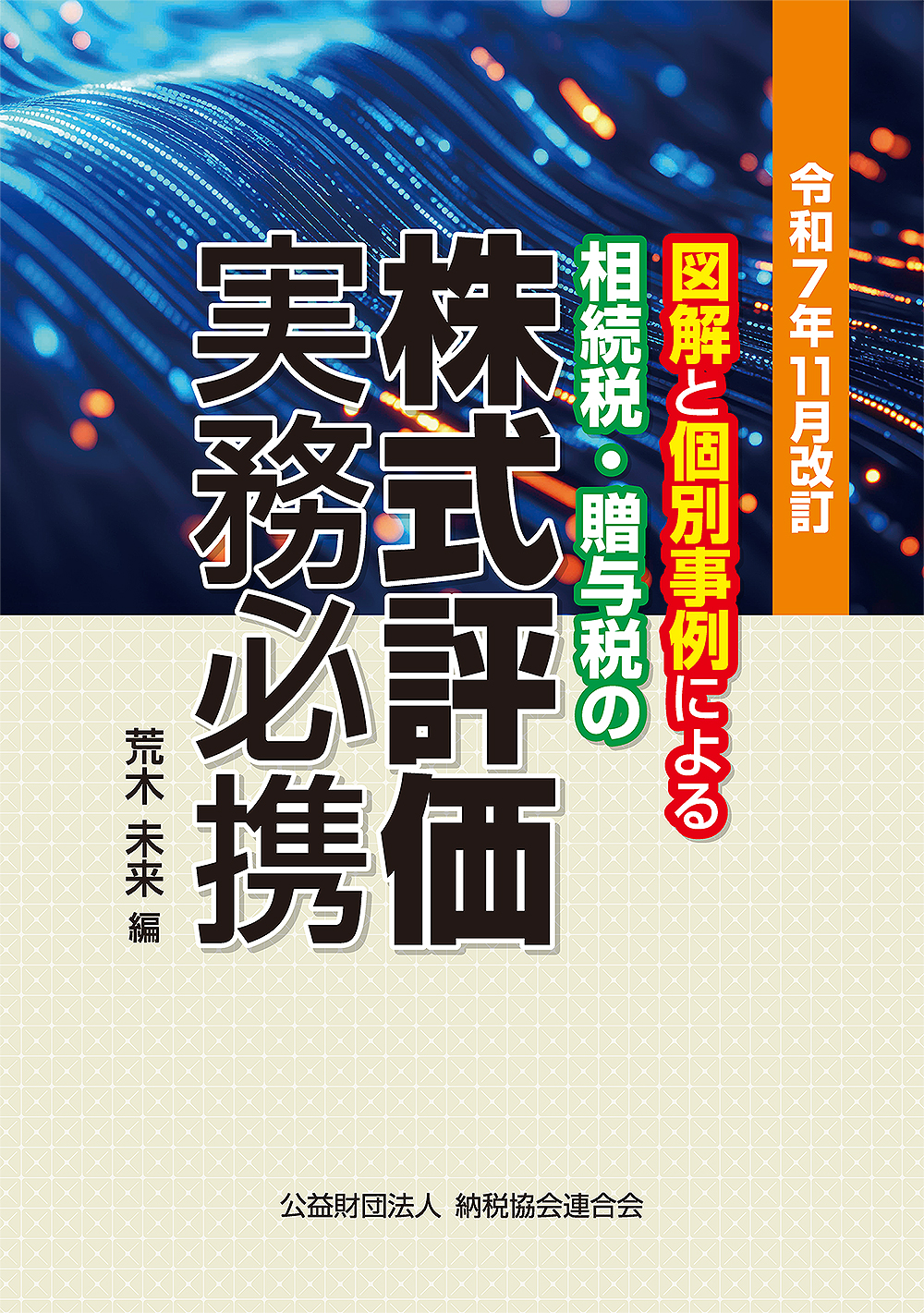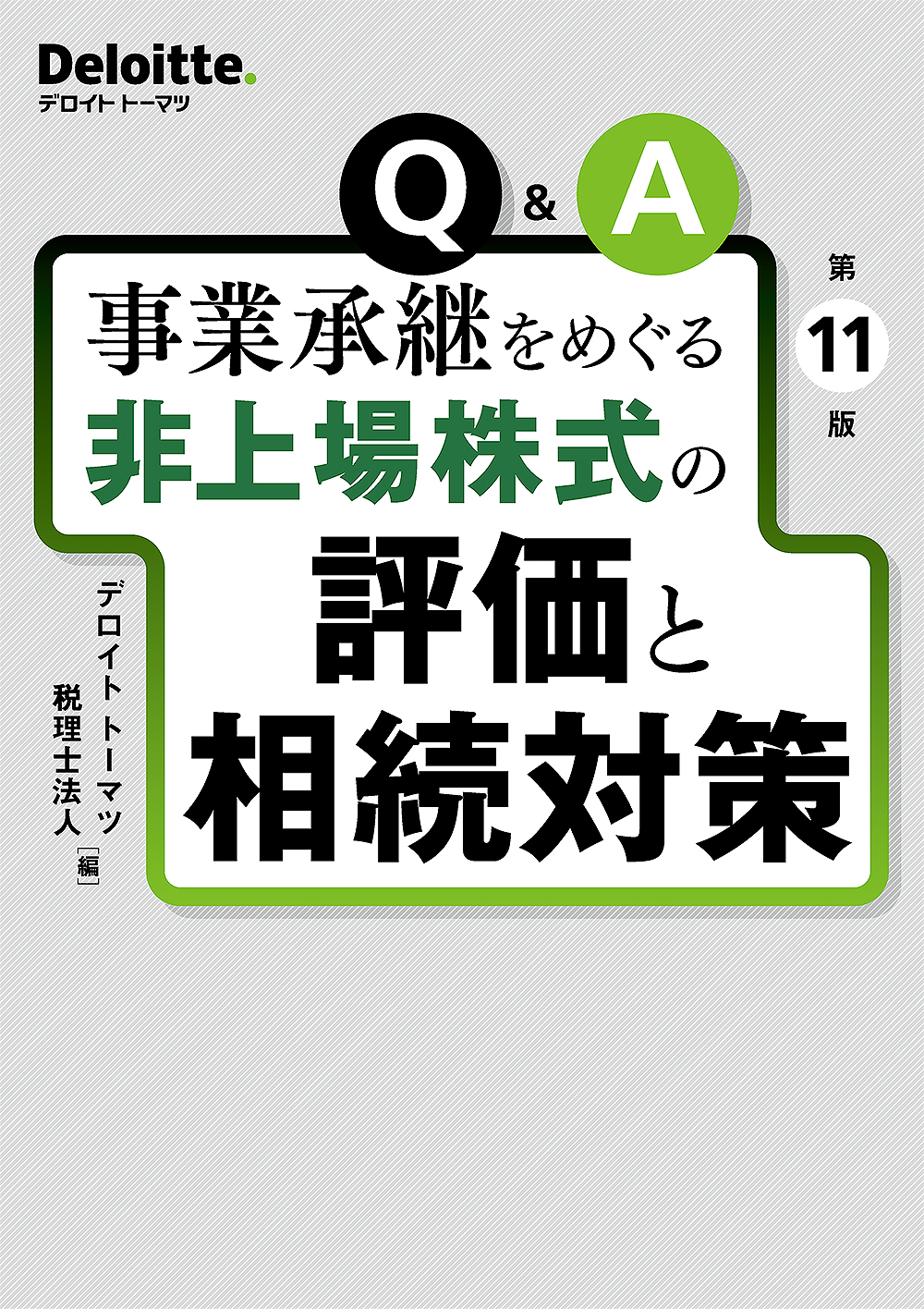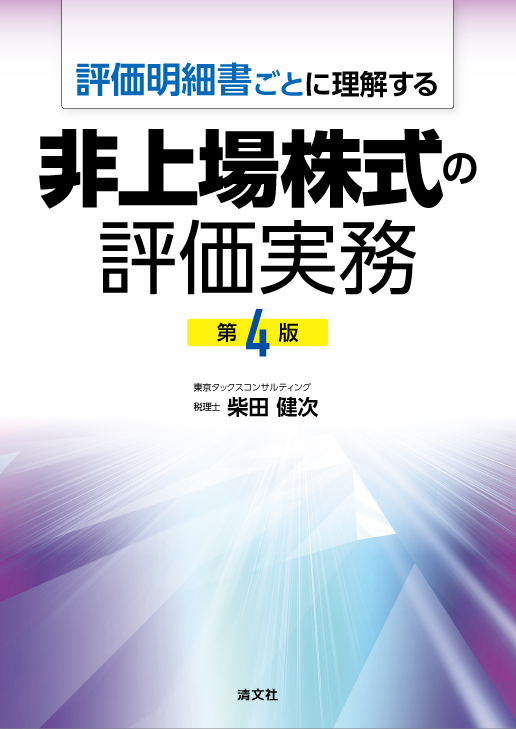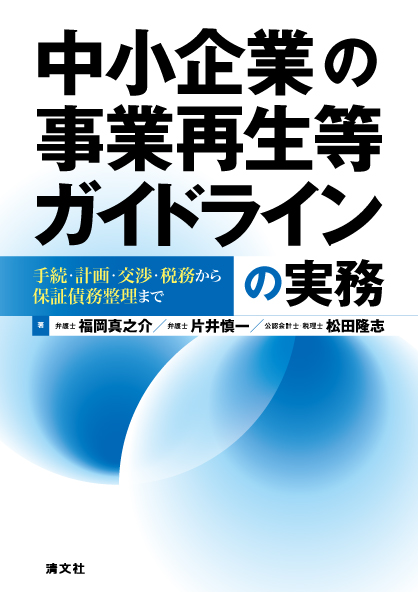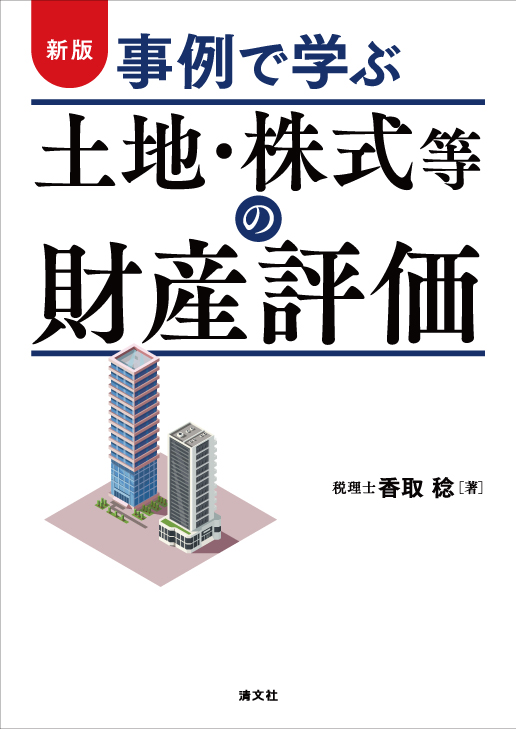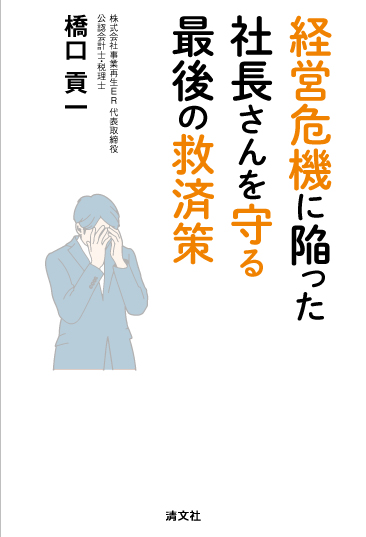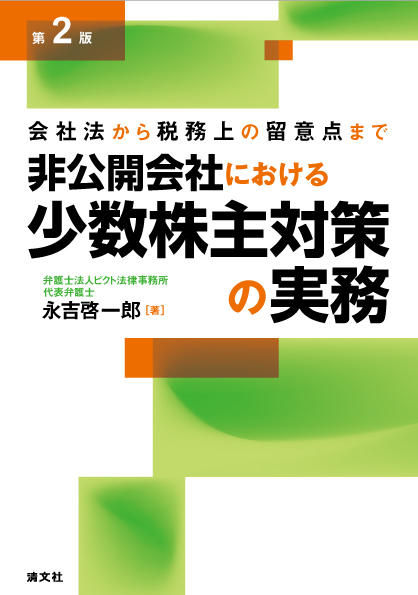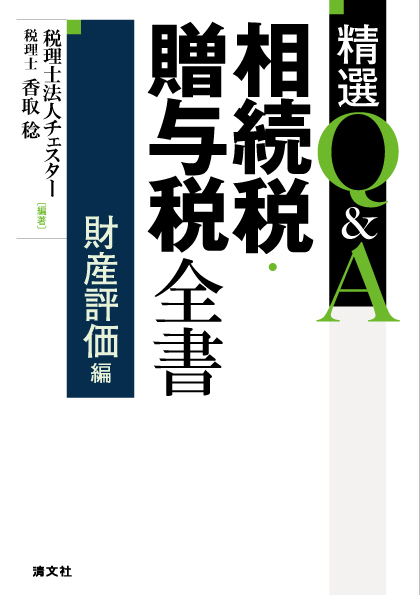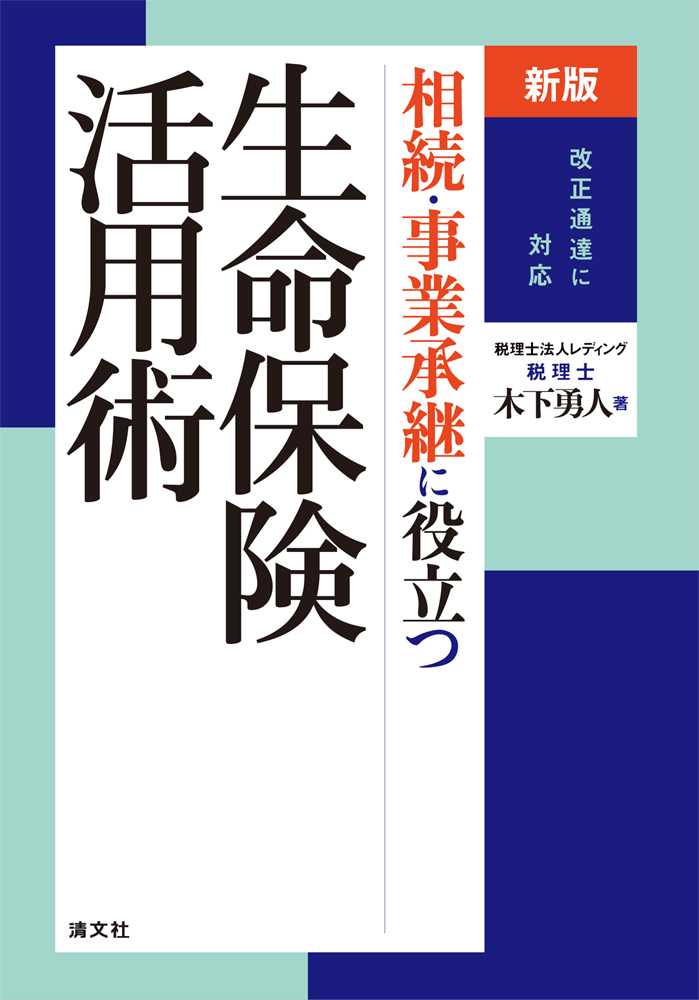船舶の評価を巡る贈与税決定処分等の
取消訴訟において全部取消が認められた事例
-東京地裁令和2年10月1日判決
(平成28年(行ウ)第413号:贈与税決定処分等取消請求事件)-
【第1回】
弁護士法人東町法律事務所
弁護士 木下 雅之
連載の目次はこちら
1 はじめに
相続税法第22条は、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、原則として、当該財産の取得の時における時価による旨規定する。そして、この財産の評価に関する基本的な取扱いを定める財産評価基本通達(以下「評価通達」という)は、船舶の価額について、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価するものとし、これが明らかでない船舶については、同種同型の船舶を課税時期において新造する場合の価額から償却費等を控除した価額によって評価するものとしている(評価通達136)。
かかる船舶の評価が争点となった贈与税決定処分等の取消訴訟において、東京地方裁判所は、令和2年10月1日、原告側の主張を認め、贈与税決定処分等の全部を取り消す判決を下したため、事例判断ではあるが、今後の実務の参考として紹介する(同月16日判決確定)。
2 事案の概要
海上運送業等を事業の目的とするA社の代表取締役であるX(原告)は、平成21年2月28日(以下「本件贈与日」という)、Xの母から、同じく海上運送業等を事業の目的とするB社の株式20株の贈与を受けたが、平成20年9月に発生したいわゆるリーマン・ショックの影響等により、B社株式の価額は0円であり、贈与税額は生じないと考えて、法定申告期限までに贈与税の納税申告書を提出しなかった。
なお、B社株式は、評価通達168(3)の「取引相場のない株式」で、かつ、評価通達189の「特定の評価会社の株式」のうち(4)「開業後3年未満の会社等の株式」に該当するものであったため、その価額は、評価通達185所定の「純資産価額方式」によって評価される。
一般的に、我が国の海運業においては、日本法人が海外子会社(多くはペーパーカンパニー)を設立し、当該海外子会社に船舶を所有させる仕組み(いわゆる便宜置籍船の仕組み)が広く採用されている。これにより、船舶は外国籍となるため、日本籍船と比べて、税負担や船舶の登録費用が安くなる等のメリットを享受することができる。
B社も便宜置籍船の仕組みを採用しており、本件贈与日当時、パナマ共和国を本店所在地とするM社の発行済み株式の全部を保有し、このM社が合計70隻の船舶(以下「本件各船舶」という)を所有していた。
したがって、純資産価額方式によってB社株式を評価するにあたっては、B社の海外子会社であるM社が所有する本件各船舶の評価がその算定の基礎となる。
処分行政庁(税務署長)は、本件各船舶の価額を約2,226億円と評価したうえで、M社株式の価額(純資産価額)を約374億円と評価し、更にこれに基づいて、B社株式の価額を評価したところ、B社株式の価額は約43億円となったことから、平成25年7月8日、Xに対し、贈与税約21億円の決定処分及びこれに伴う無申告加算税約4億円の賦課決定処分を行った。
Xは、上記各処分を不服として、不服申立手続を行ったところ、裁決により上記各処分の一部が取り消されたため、残部(贈与税額約5億円)の取消しを求め、平成28年9月9日、Y(国・被告)を相手に提起した取消訴訟が本件である。
本件の主たる争点は、本件各船舶の評価であった(全70隻の本件各船舶のうち3隻については当事者間に争いがなく、実際に争点となったのは、その余の67隻の価額である)。なお、本件各船舶には、本件贈与日当時、いずれも定期傭船契約(※1)が付されていた。
(※1) 船舶所有者が船員を乗船させ、備品等を備えた運航可能な状態にして船舶を傭船者に貸し渡し、傭船者がその対価として契約期間(傭船期間)につき定額の傭船料(定期傭船料)を支払う契約。
3 各当事者が依拠する本件各船舶の価格鑑定に用いられた鑑定方法
前述のとおり、船舶の評価は、「精通者意見価格」等を参酌して評価するものとされているところ(評価通達136)、X及びYは、それぞれ別の船価鑑定業者に鑑定を依頼し、かかる「精通者意見価格」を参酌して、本件各船舶の評価額を主張した。
(1) Y(被告)の依拠する価格鑑定に用いられた鑑定方法の概要
Yが船価鑑定を依頼した鑑定業者P社は、本件各船舶(全70隻)のうち34隻については「取引事例比較法」により価格鑑定を行い、その余の36隻については「建造船価償却法」によって価格鑑定を行った。
P社の採用する「取引事例比較法」は、本件贈与日に近接した平成21年1月から同年2月までの2ヶ月間の売買実例から、個別の評価対象船舶の比較対象となる売買実例を抽出し、その価格に、①船齢差による調整、②積載能力差による調整、③装備等(クレーン等の荷役装置の有無等)の差異による調整を行うほか、④定期傭船料に係る調整を行うことによって、本件各船舶の評価額を算定していた(※2)。
(※2) 中古船市場において定期傭船契約が付されたままの状態の船舶が取引されることはほとんどないため、抽出される売買実例は、いずれも定期傭船契約が付されていない船舶の価格である。しかし、評価対象船舶は、本件贈与日当時、いずれも定期傭船契約が付されていたことから、P社は、比較対象となる売買実例に①~③の調整を加えることによって、定期傭船契約が付されていない場合の評価対象船舶の価格を算定し、さらに、これに定期傭船料に係る調整を行うこととした。
このうち④について、P社は、具体的には、個別の評価対象船舶に付された定期傭船契約の契約傭船料と本件贈与日における定期傭船料の市場水準(市場傭船料)との差額に基づく調整額を加減算することで評価対象船舶の価格を算定したが、市場傭船料の指標となるデータが、傭船期間3年までのものしか公表されていなかったため、評価対象船舶に付された定期傭船契約の残存傭船期間が3年以下の場合はその全部を調整の対象とし、3年を超える場合には3年の限度で調整の対象とすることとしていた。
その結果、P社が取引事例比較法を用いて評価した本件各船舶(当事者間において価格に争いのない1隻を除く33隻)のうち、10隻は残存傭船期間が3年以下であったため、残存傭船期間の全部が調整の対象となったが、その余の23隻は残存傭船期間が3年を超えていたことから、残存傭船期間の全部についてではなく、いずれも3年の限度でのみ定期傭船料の調整が行われた。
P社の採用する「建造船価償却法」は、上記の「取引事例比較法」において価格算定の参考となり得る売買実例を収集することができなかった船型の船舶について、建造船価を基準に、建造時から本件贈与日までの経過年数に基づく減価修正(償却)を行うことで、本件各船舶(当事者間において価格に争いのない2隻を除く34隻)の評価額を算定していた。
(2) X(原告)の依拠する価格鑑定に用いられた鑑定方法の概要
Xが船価鑑定を依頼した鑑定業者Q社は、本件各船舶(全70隻)のうち当事者間に争いのある67隻すべてについて、「収益還元法(DCF法)」により価格鑑定を行った。
Q社の採用する「収益還元法(DCF法)」は、定期傭船契約の契約期間(傭船期間)中の収益価値に、契約終了時の船舶価値を加えることによって(いずれも現在価値に割り引いたもの)、本件各船舶の評価額を算定していた。
(続く)
この連載の公開日程は、下記の連載目次をご覧ください。