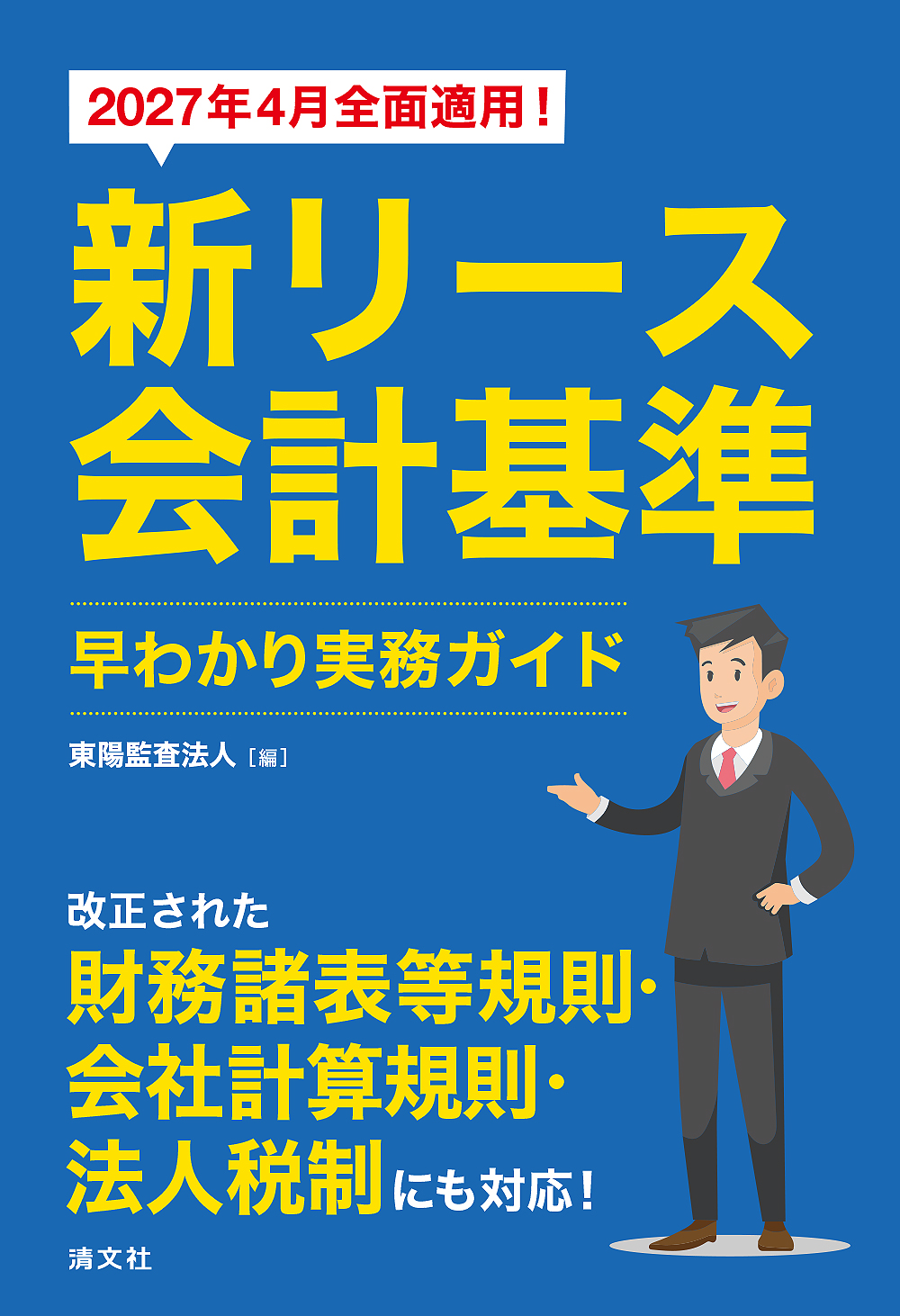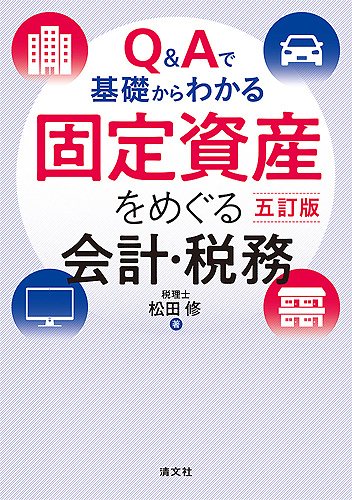〈一から学ぶ〉
リース取引の会計と税務
【第15回】
(最終回)
「リース取引の法律知識」
公認会計士・税理士
喜多 弘美
本連載では、これまで日本におけるリース取引の会計や税務上の取扱いを中心に解説し、前回、リースに係る国際的な動向を確認しました。最終回となる本稿では最後に、リース取引に係る法律知識について簡単に整理します。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。