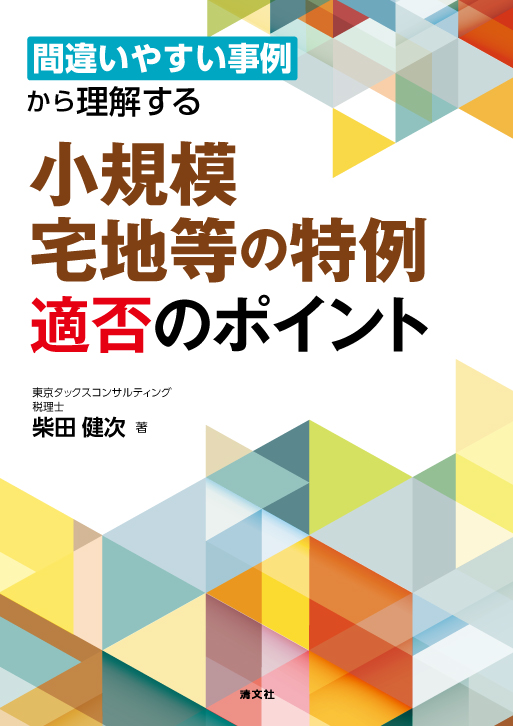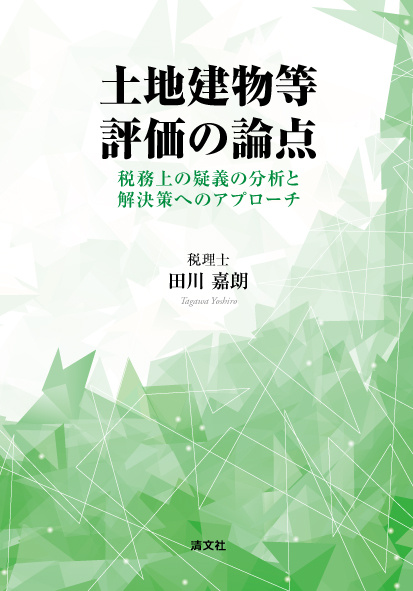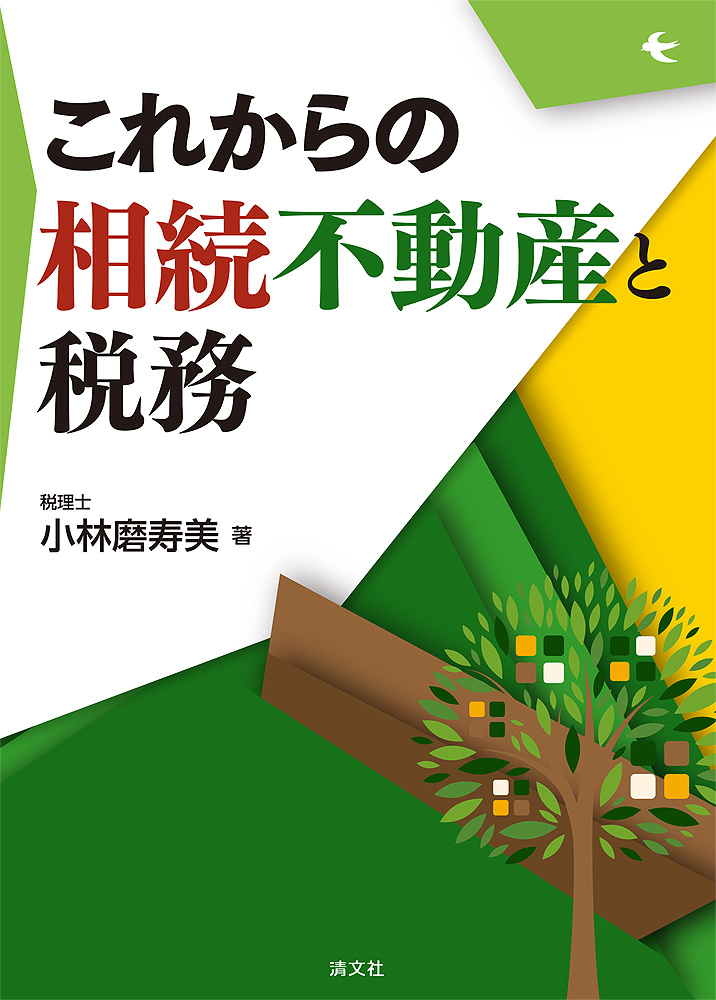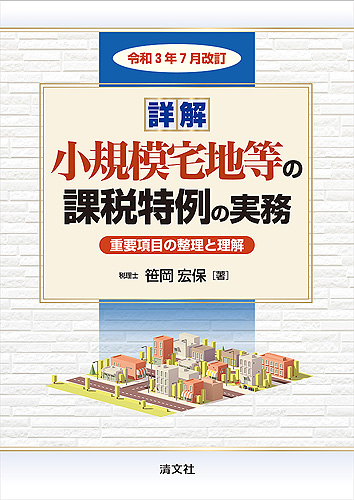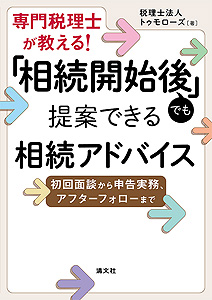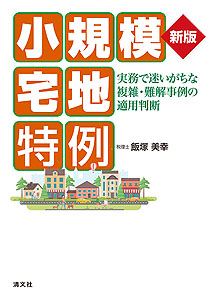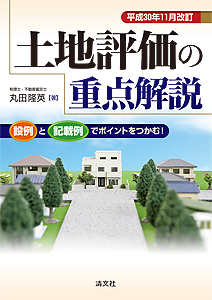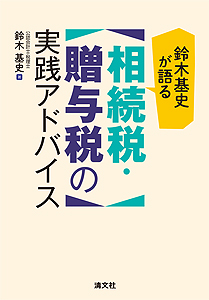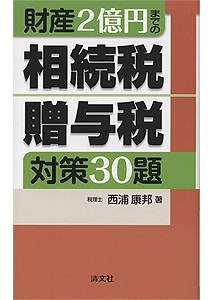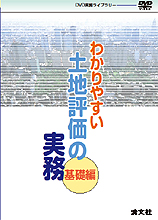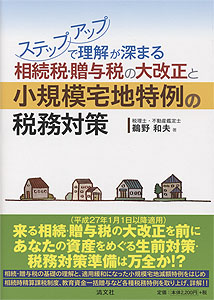区分所有登記要件をめぐる
小規模宅地評価減特例
【第1回】
「平成25年度の改正事項と論点の確認」
税理士法人ネクスト
公認会計士・税理士 根岸 二良
1 はじめに
平成25年度税制改正において、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(租税特別措置法第69条の4)(以下、小規模宅地評価減特例)に関する改正が行われたが、その改正点の一つとして、特定居住用宅地等(※1)の同居要件がある(措法69の4③二)。
(※1) 特定居住用宅地等とは
特定居住用宅地等は、相続人又は相続人と生計を一にする親族が居住していた土地(借地権を含む。以下、土地等)につき、一定の要件を満たす場合には、相続税の計算上、当該土地等評価にあたり240㎡を上限として80%評価減(平成27年1月1日以降に他界した場合の相続税申告については、330㎡を上限として80%評価減)される。
特定居住用宅地等として小規模宅地評価減特例が認められるケースとしては、以下のものがある。
【被相続人が居住していた土地等について】
(1) 被相続人の配偶者が相続する場合
(2) 被相続人の配偶者以外の、同居していた親族(子供など)が相続する場合
(3) 被相続人に配偶者・同居親族がともになく、相続前3年間、持ち家に居住したことがない親族が相続する場合
【被相続人と生計を一にする親族が居住していた土地等について】
(4) 被相続人の配偶者が相続する場合
(5) 当該生計を一にする親族が相続する場合
なお、本稿のテーマ「区分所有登記要件をめぐる小規模宅地評価減特例」は、上記(2)のケースの「同居していた親族(子供など)」(同居要件)に関する議論である。
2 平成25年度税制改正前の取扱い(*2)
二世帯住宅について、建物の構造上、内部で行き来ができるか否かにより、同居か否かが判定され、結果、小規模宅地評価減特例の適用が判断されていた(*3)。
つまり、建物の構造上、内部で行き来ができる場合には、被相続人と相続人とは同居していると判定され、他の要件を満たしていることを前提にすれば、特定居住用宅地等として、小規模宅地評価減特例が適用されていた。
(*2) 本稿の前提条件
被相続人が居住していた建物(二世帯住宅)に、相続人が居住し、かつ、当該相続人が当該建物の敷地を相続で取得することを前提とする。なお、被相続人の配偶者が当該敷地を相続する場合には、同居要件はないため、本稿の相続人とは、配偶者以外の相続人を意味する。
(*3) 構造上の区分とは
改正前の措置法通達69の4-21においては、以下のように規定されていた。
つまり、被相続人が居住していた建物について、構造上区分された数個の部分がある場合には、その構造上区分された部分で同一のものに、被相続人と相続人が同居しているか否かで判断することとなる。
この場合の「構造上区分された数個の部分」の解釈について、措置法通達で明記されたものはないが、「東京国税局資産税審理研修資料(平成23年8月)Ⅴ相続税・贈与税の審理上の留意点①二世帯住宅の敷地に係る小規模宅地等の特例(1)」に、一階二階が内部に階段が設置されており、家屋の内部で互いに行き来することができる構造のものを、構造上区分されていないものとする具体例が示されており、これを根拠に実務上は、構造上区分されているか否かは、内部で行き来できるか否かで判断されていると思われる。
なお、財務省主税局立法担当者の解説(「平成25年度税制改正の解説」p.588、財務省ホームページ)においても、構造上区分されているか否かは、構造上内部で行き来が可能か否かで判断する趣旨の記載がある。
3 平成25年度税制改正後の取扱い(*2)
二世帯住宅について、被相続人と相続人とが同一の建物に居住していれば(建物の構造上、内部で行き来ができるか否かには関係なく)、同居として取り扱われ、特定居住用宅地等として、小規模宅地評価減特例が適用される。
ただし、当該二世帯住宅が区分所有(*4)されている場合には、被相続人が居住していた専有部分(区分所有の対象となっている単位)において、相続人が居住(同居)しているか否かで、同居要件を判定する(*5)。
(*4) 区分所有とは
「区分所有」とは、建物全体を所有権の対象とするのではなく、建物の部屋(構造上区分された部分)毎に所有権を設定するものである。
わかりやすく言えば、分譲マンションをイメージすれば良い。
分譲マンションは、建物全体に対して所有権を設定しているわけでなく、部屋ごとに所有権が設定されており、そのような所有形態の区分所有という。筆者の経験からいうと、二世帯住宅のうち、1~2割程度は区分所有としているものと思われる。
なお、建物が区分所有であるか否かは、建物の登記簿を確認すればわかる。
区分所有されている建物の登記簿をみると、「表題部(一棟の建物の表示)」「表題部(専有部分の建物の表示)という記載がある一方、区分所有されていない(単独所有又は共有されている)建物の登記簿では「表題部(主たる建物の表示)」という記載になっている。
区分所有されている建物について、異なる取扱いとした趣旨については、財務省主税局立法担当者は以下のように解説している(「平成25年度税制改正の解説」p.589、財務省ホームページ)。
区分所有された建物を別の取扱いをした理由は、分譲マンションを想定して二世帯住宅と同一の取扱いにすることは好ましくないと判断したためであることが上記から読み取れる。
だが実際には、二世帯住宅にも区分所有とされているものが一定割合ある。
法令の適用上は、分譲マンション・二世帯住宅で取扱いを別にするという規定ではなく、区分所有されているか否かで異なる取扱いを行うこととなるため、結果として、二世帯住宅であっても区分所有されているものは、小規模宅地評価減特例の適用上は、区分所有ではない二世帯住宅と、異なる取扱いをせざるを得ないという解釈になる。
(*5) 同居要件の判定
この平成25年度税制改正(小規模宅地評価減特例における同居要件)は、平成26年1月1日以降に他界した相続税申告について適用されるが、被相続人等が居住していた建物が「(1)区分所有である場合」と「(2)区分所有でない場合(単独所有、または共有である場合)」とで、同居要件の判定が異なることになる。
4 適用判定のまとめ
上記で説明したとおり、平成25年度税制改正により、平成26年1月1日以降に他界した被相続人に関する相続税申告については、小規模宅地評価減特例(特定居住用宅地等)の同居要件については、以下のように判定が行われる(措法69の4③二、措令40の2⑩)。
【被相続人が居住していた建物が、区分所有されていた場合】
被相続人が居住していた部分(区分所有の対象となる専有部分)に、相続で当該土地等を取得する親族(子供など)が住んでいたか否かで、同居要件を判定する。
【被相続人が居住していた建物が、区分所有されていない(単独所有、または共有されている)場合】
被相続人が居住していた建物に、相続で当該土地等を取得する親族(子供など)が住んでいたか否かで、同居要件を判定する。この場合に、建物の構造上、内部で行き来できるか否かは考慮されず、あくまで同じ建物に居住しているか否かのみで、同居要件は判定される。
次回(4/17公開)は、上記で整理した論点をもとに、建物の所有権者、相続の発生時期から6パターンの事例を紹介し、小規模宅地評価減特例の適用を検討したい。
〔凡例〕
措法・・・租税特別措置法
措令・・・租税特別措置法施行令
(例)措法69の4③二・・・租税特別措置法第69条の4第3項第2号
(了)