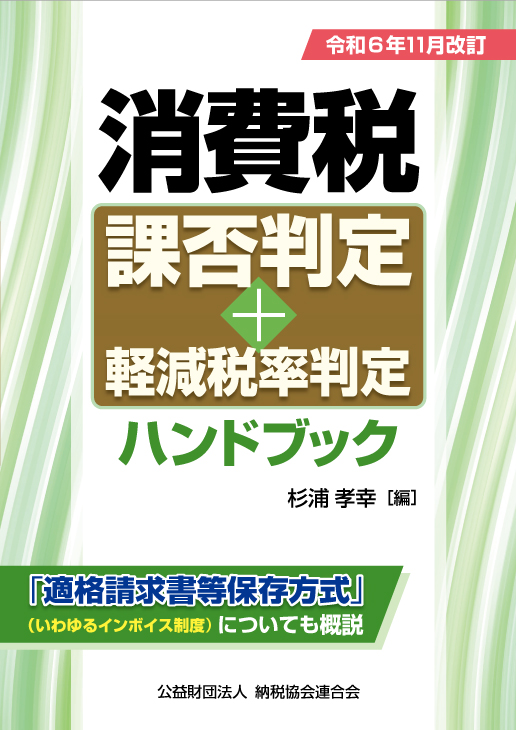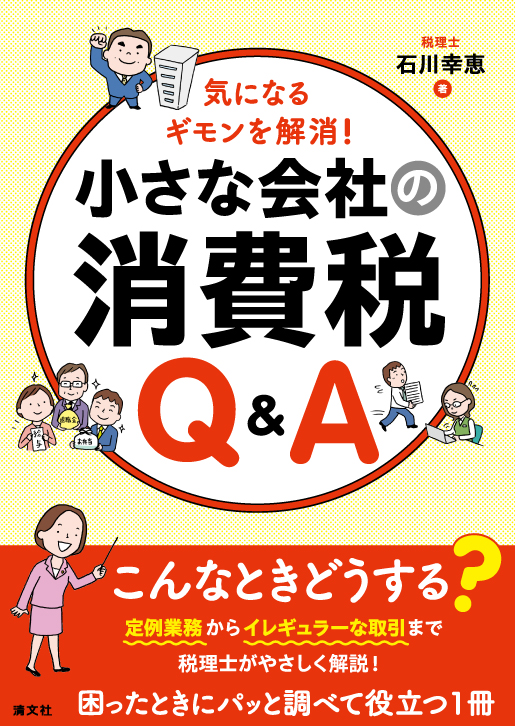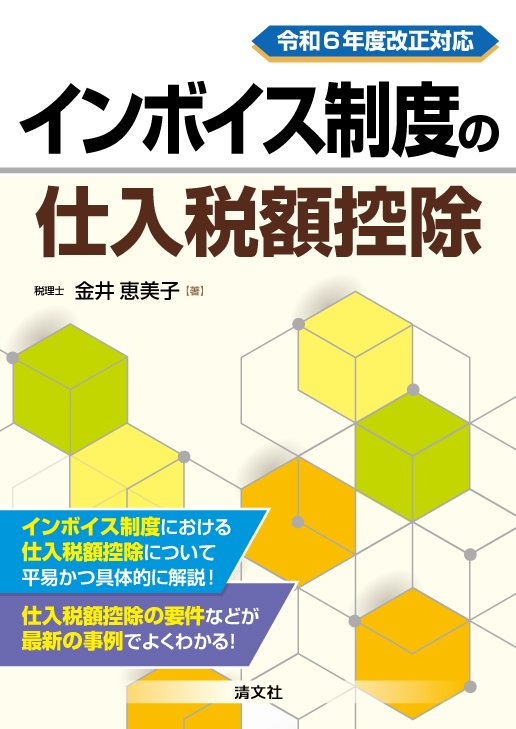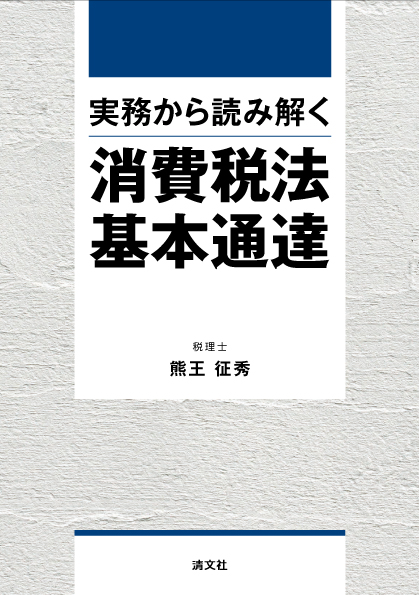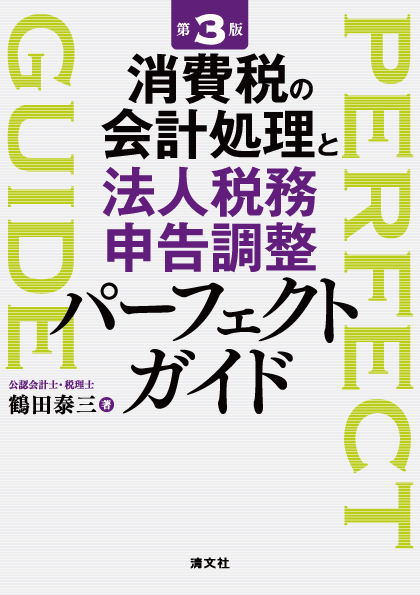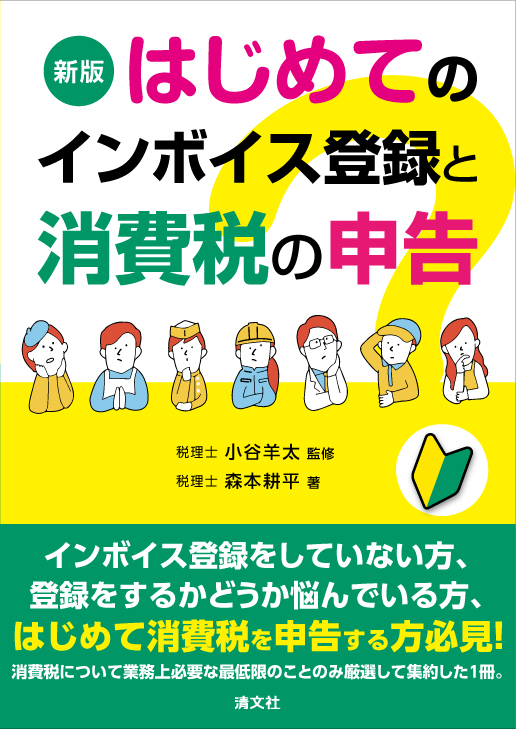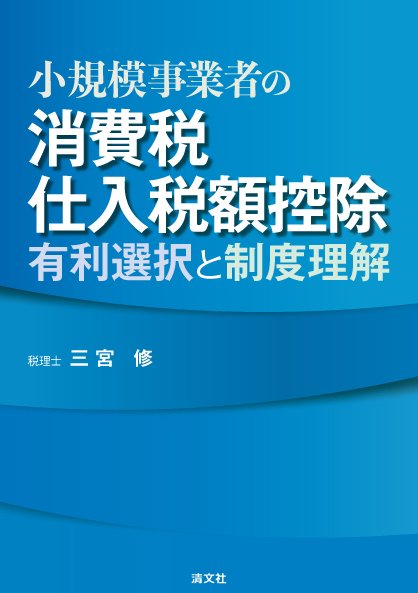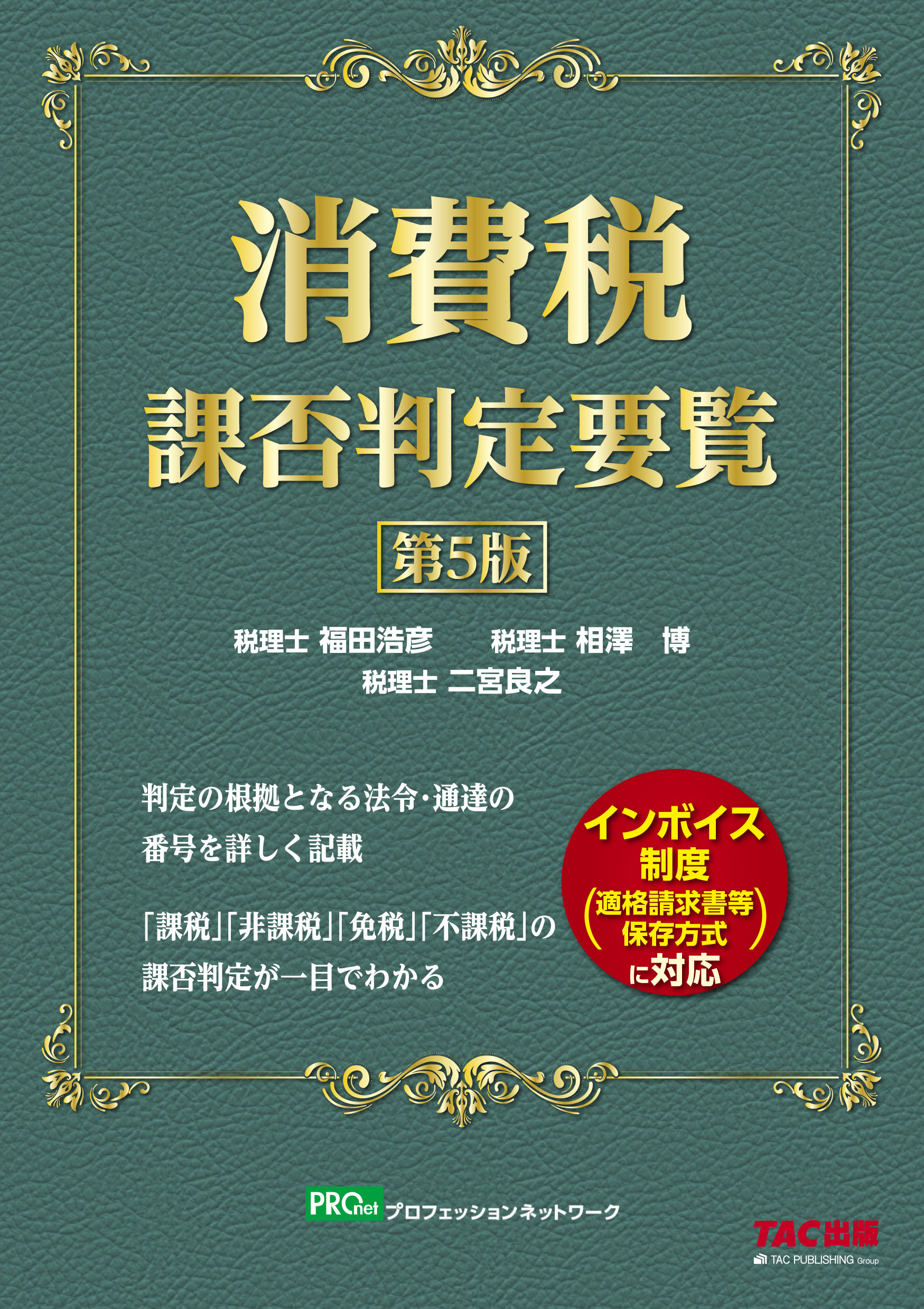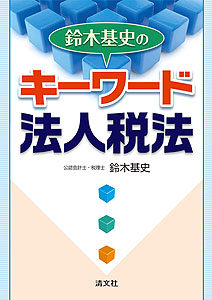会計検査院「平成29年度決算検査報告」で特定検査対象となった
税制上の論点整理
【前編】
「開廃業手続による事業の引継ぎを行って事業を開始した場合における個人事業者の消費税の納税義務の免除について」
税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝
はじめに
会計検査院は、日本国憲法第90条等の規定に基づく、国の平成29年度の収入支出の決算などを検査した結果を、「平成29年度決算検査報告(以下「検査報告」と略称する)」としてまとめ、昨年11月9日、内閣に送付したことを公表している。
本稿では、検査報告の中で、「平成29年度決算検査報告の特色」のうち、「特定検査対象」として取り上げられた下記5項目のうちから、赤字で記した税制に係る2つのテーマについて前後編にわたり、検査報告の内容をまとめるとともに、解説として若干の私見を述べたい。
・社会保障の動向と国の財政健全化に与える影響について
・競馬等の払戻金に係る所得に対する課税状況について(・・・後編で検証)
・開廃業手続による事業の引継ぎを行って事業を開始した場合における個人事業者の消費税の納税義務の免除について(・・・本稿で検証)
・量的・質的金融緩和等の日本銀行の財務への影響について
・独立行政法人国立病院機構が設置する病院の経営状況等について
なお、特定検査対象とは、「国民の関心が極めて高いテーマや検査上重要なテーマ」のことを表しており、特定検査対象については、「不適切な事態として指摘をするに至らない場合であっても、どのような検査を実施したかを明確にしておくために、その検査状況を記述」しているものであると説明されている。
* * *
1 検査報告の概要
(1) 検査の着眼点
会計検査院は、検査の着眼点として、高齢化社会の到来を踏まえて、「多くの個人が、引退する個人事業者から開廃業手続による事業の引継ぎを行って事業を開始することが見込まれる状況」にあることから、消費税の納税義務者であった旧経営者から開廃業手続による事業の引継ぎを行って事業を開始した新経営者が、事業者免税点制度によって、開廃業手続による事業を開始した年及びその翌年の消費税の納税義務が免除されている状況について検査を行うこととした。
検査に当たっては、①開廃業手続による引継ぎを行った新経営者の事業収入等は、納税義務を免除することが適切な状況となっているか否か、②旧経営者と新経営者の事業には、消費税に係る事務処理能力を含む事務処理の体制等に継続性があるか否か、などに着眼して検査を行ったということである。
(2) 検査方法
会計検査院は、全国58税務署において、平成26年中に開廃業手続による事業の引継ぎを行って事業を廃止した旧経営者のうち25、26両年課税期間分の消費税の納税義務者であった者と、開廃業手続による当該事業の引継ぎを行って事業を開始して事業者免税点制度の適用を受けている新経営者各312人に係る所得税及び消費税の確定申告書等、所得税青色申告決算書等、個人事業の開業・廃業等届出書により、事業者免税点制度の適用状況等について分析して会計実地検査を行った。
同時に、財務省及び国税庁において、事業者免税点制度等の趣旨を聴取するなどして会計実地検査を行った。
(3) 検査結果
上記の検査対象とした312人のうち、事業収入が把握できた旧経営者及び新経営者各212人の事業収入等について、旧経営者の25年分と新経営者の27年分との関係をみると、旧経営者と新経営者の双方の事業収入等が同じ規模となっている事業者数は以下の表のとおり、145人に及んでいた。
また、旧経営者の事業収入等が1億円超だった4人については、その新経営者の事業収入等も引き続き1億円超となっていた。
さらに、残りの新経営者67人のうち計43人に係る27年分の事業収入等は、旧経営者の25年分の事業収入等よりも高額の金額区分に属していた。
(4) 会計検査院による所見
検査の結果を、会計検査院は、以下のようにまとめている。
開廃業手続による事業の引継ぎを行って事業を開始した新経営者の事業収入等の状況は、(中略)多くの場合、新経営者に係る事業収入等は、消費税の納税義務者であった旧経営者と同程度となっていて、新経営者の推計課税標準額は旧経営者の課税標準額と同様に1,000万円を超えている状況であり、そして、新経営者における旧経営者から引継ぎを受けた業種の継続状況、事業の開始までの期間の状況及び消費税に係る事務処理能力を含む事務処理の体制の引継ぎの状況からみても、旧経営者と新経営者の事業には事業の継続性がある(以下略)
こうした検査結果を踏まえて、会計検査院は、次のように指摘している。
開廃業手続による事業の引継ぎを行って事業を開始した新経営者が、事業を開始した年及びその翌年に係る基準期間については、当該期間における課税売上高がないため、事業者免税点制度により免税事業者となっている現状は、小規模事業者の消費税に係る事務処理能力等を勘案して消費税の納税義務を免除する事業者免税点制度の趣旨に沿ったものとはなっていない
そして、財務省に対して、消費税に関わる幅広い議論が十分なされるよう、事業者免税点制度等の在り方について、引き続き、様々な観点から有効性及び公平性を高めるよう検討を行っていくことが肝要であると提言して、検査報告を締め括っている。
2 事業者免税点制度の概要
(1) 消費税の納税義務が免除される者の範囲
消費税については、小規模事業者の消費税に係る事務処理能力等を勘案して、原則として、個人事業者は課税期間の前々年、法人は課税期間の前々事業年度(以下、これらを「基準期間」という)における課税売上高が1,000万円以下の事業者について、消費税の納税義務を免除することとされている(事業者免税点制度)。
したがって、新規に事業を開始した事業者については、基準期間における課税売上高が存しないことから、事業者免税点制度により、原則として新規開業年及びその翌年の消費税の納税義務が免除されている。
(2) 免税事業者の問題点
会計検査院による検査報告で判明したように、新規に事業を開始した個人事業者であっても、旧経営者から事業の引継ぎを受けた者については、そのほとんどが消費税の課税事業者であった旧経営者と同じ規模の事業収入を開業初年度から稼得しており、小規模事業者の事務負担軽減を目的とする事業者免税点制度により、多額の消費税がいわゆる「益税」として事業者の収入となっている事実が明らかになった。
その一方で、中小企業庁は、消費税転嫁等対策として、取引先が免税事業者であっても、消費税額等を上乗せして下請業者に支払うよう、指導を強めている。
(3) 消費税法の改正
消費税導入当初、免税事業者に該当するかどうかの判断は基準期間における課税売上高が3,000万円以下というものであった。平成16年4月1日からはこの免税点が1,000万円に引き下げられているが、その後、免税点の引下げや免税事業者制度の見直しに関する議論は長く出ていないままである。
3 解説
消費税の免税事業者制度に関する筆者の個人的な見解は、少なくとも所得税に係る青色申告の承認を受けた事業者については、消費税の免税事業者から除外をすべきである、というものだ。
小規模事業者の事務負担の軽減が、消費税の免税事業者制度の目的であれば、青色決算書の作成が可能な事業者であれば、簡易課税制度の選択により、課税売上高の集計により、納付すべき消費税額等の計算が可能であることから、軽減すべき事務負担は存在しないように思われる。
むしろ、小規模事業者にとっては、軽減税率導入による複数税率への対応の方が、より事務負担を重くする結果につながる可能性が高いと考える。日本税理士会連合会も「平成31年度税制改正に関する建議書」の中で、消費税について、次のように述べている。
軽減税率(複数税率)制度は、区分経理等により事業者の事務負担が増加すること、逆進性対策として非効率であること、財政が毀損し社会保障給付の抑制が必要となること等の理由から、日本税理士会連合会では、単一税率制度の維持を強く主張している。
適格請求書等保存方式(いわゆる日本版インボイス制度)が導入される2023年度以降は、免税事業者からの課税仕入れについて、段階的に仕入税額控除が制限されることから、取引先として免税事業者を排除する動きが出ることも予想され、それに対応して、免税事業者から適格請求書発行事業者の要件である課税事業者への転換が進むこととなりそうだ。
とはいえ、免税事業者からの課税仕入れにつき、その全額の仕入税額控除が認められないこととなるのは、今から10年後であり、それまでの間は、会計検査院による特定検査の結果報告を注視したい。
(※) 詳細については、国税庁「よくわかる消費税軽減税率制度」を参照。
なお、会計検査院の検査報告に1つだけ苦言を呈するとすれば、検査結果に基づく税収減少額が試算されていない点にあるのではないだろうか。所得税の確定申告書や青色決算書から、課税事業者であれば本来納付することになる消費税額等を試算することはさほど困難な作業ではないと思料する。その結果、具体的な課税漏れの金額が試算されれば、会計検査院の提言もさらに重みが増すのではないかと思料する次第である。
* * *
【後編】では上記と同様に「特定検査対象」とされた「競馬等の払戻金に係る所得に対する課税状況について」の内容を検討したい。
(了)
後編は2019/3/14(No.310)に公開されます。