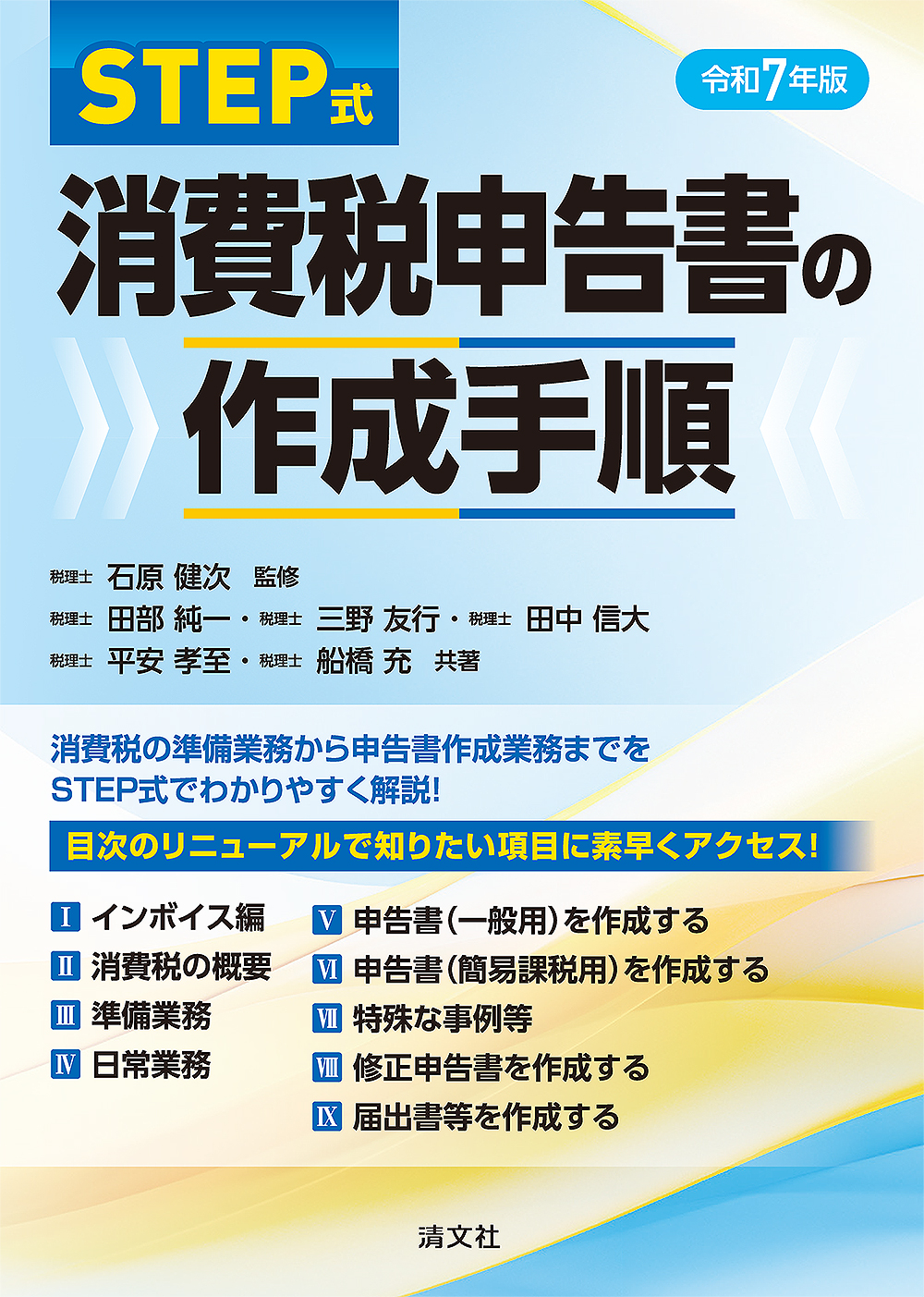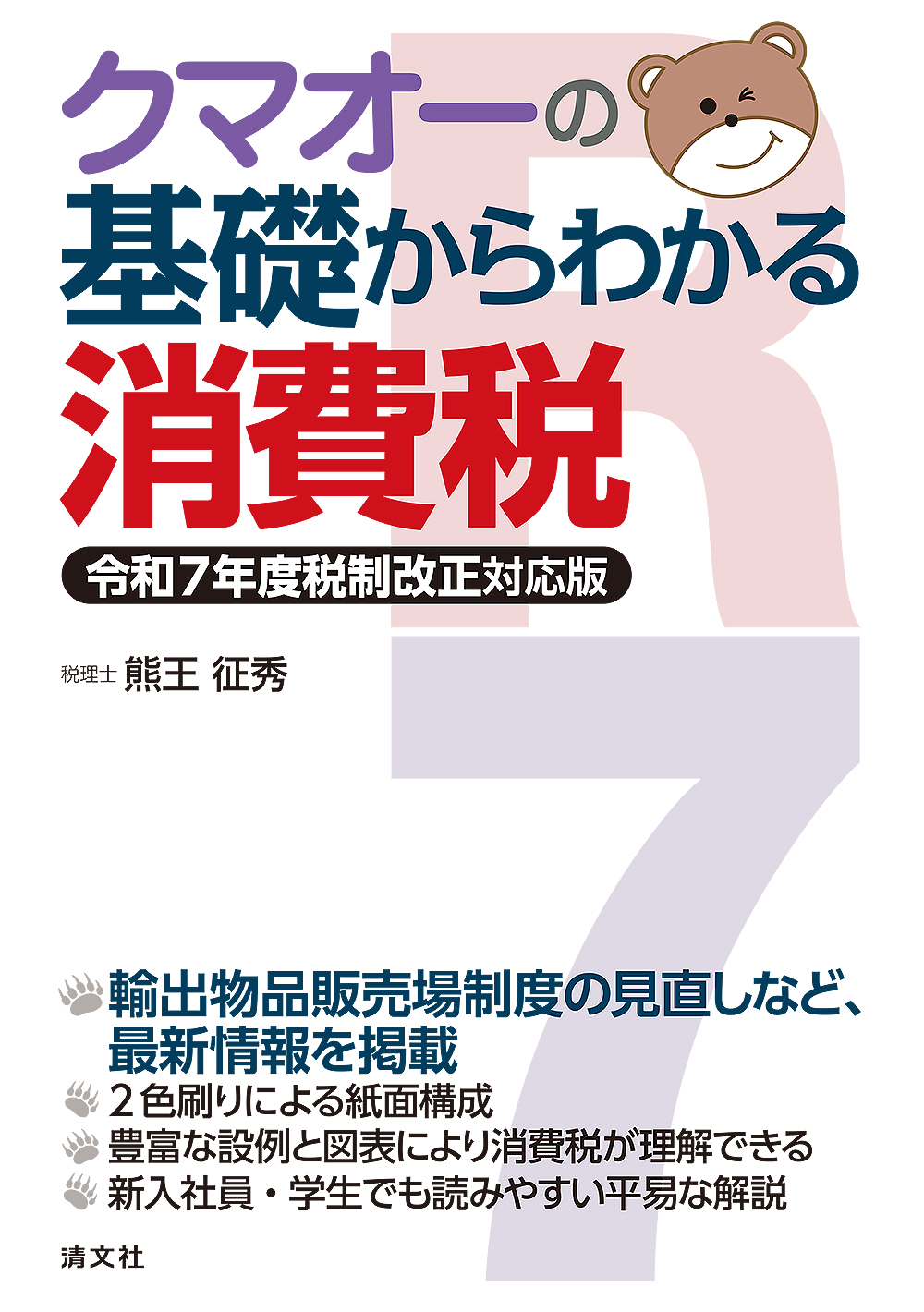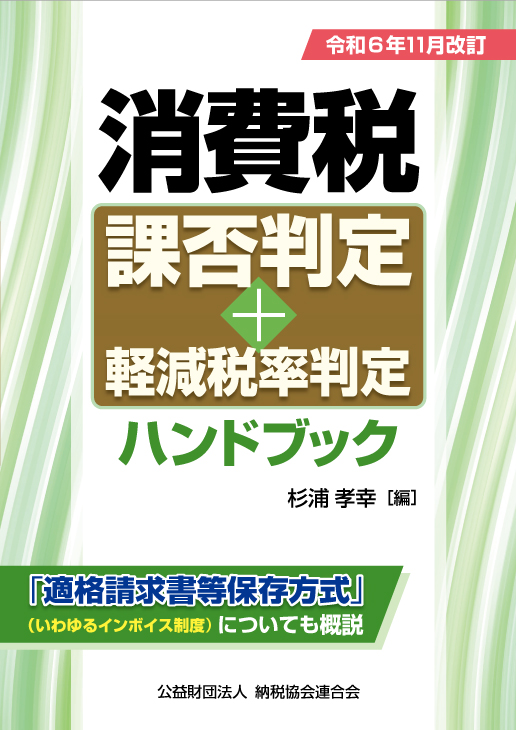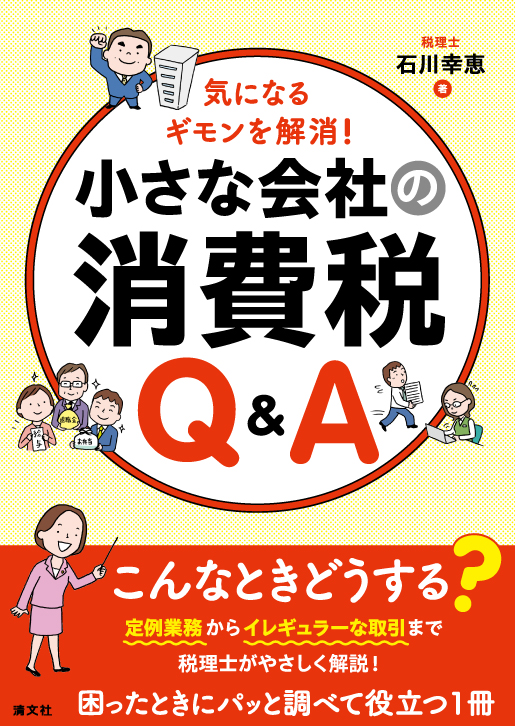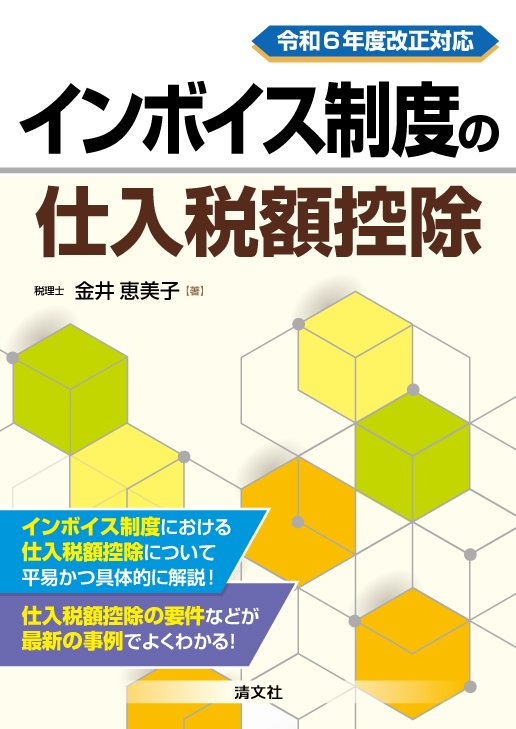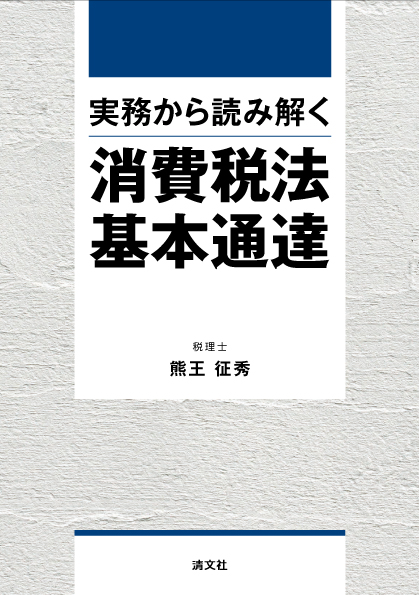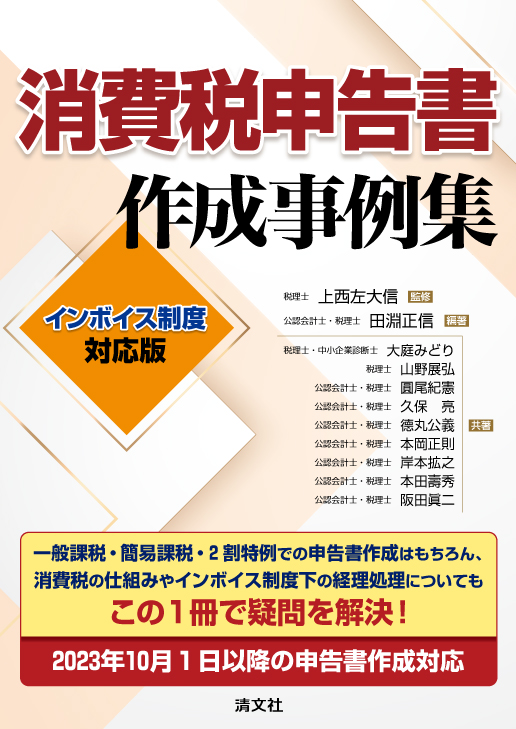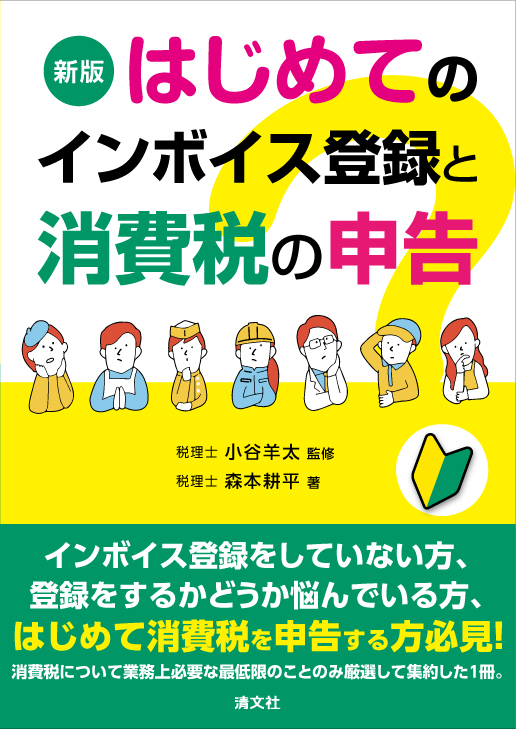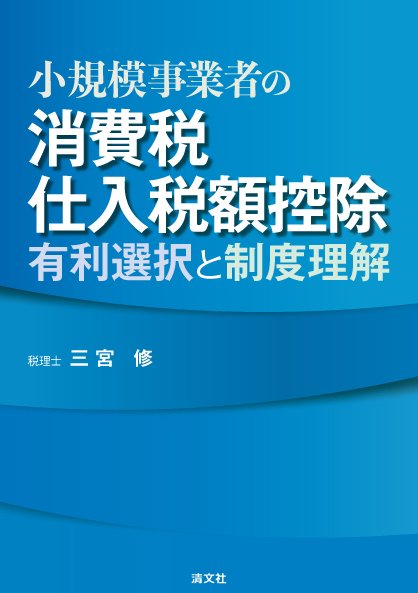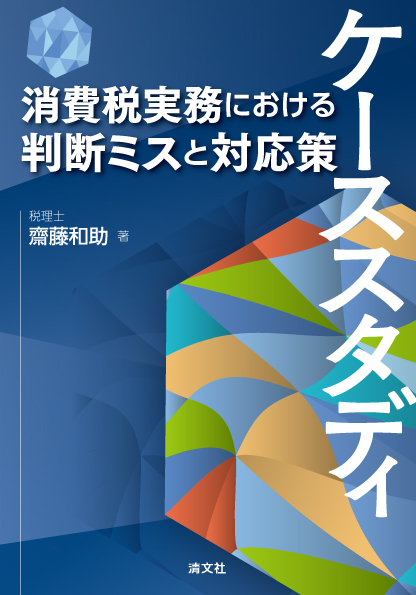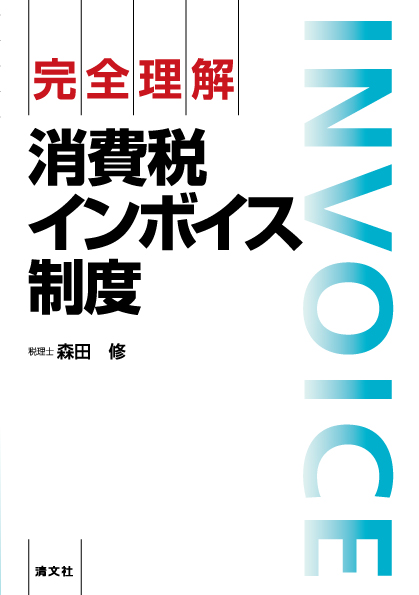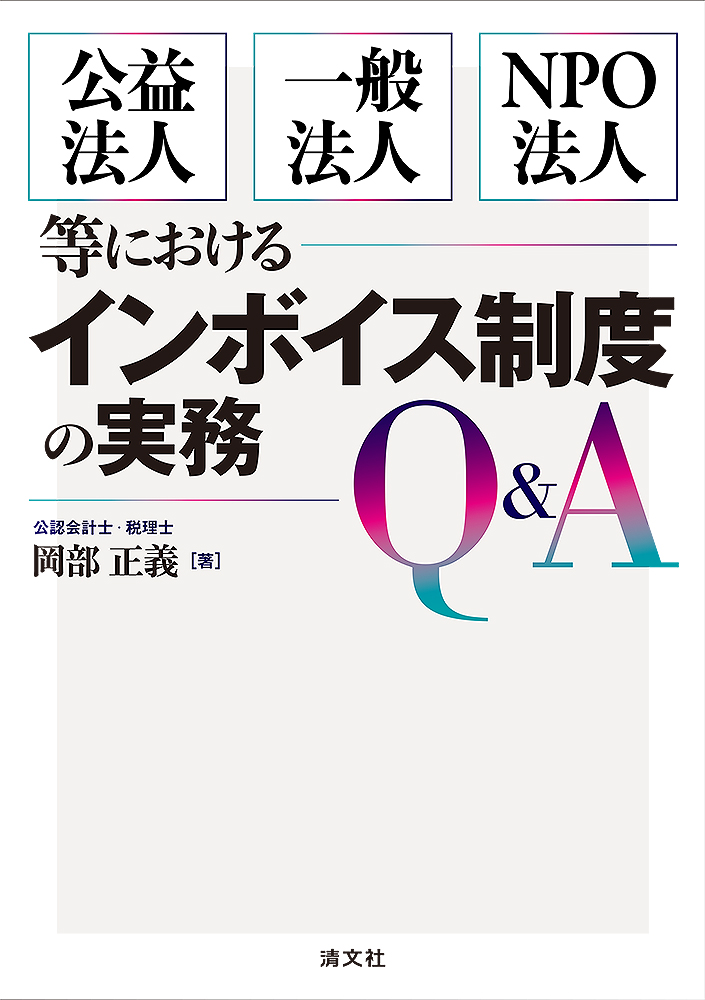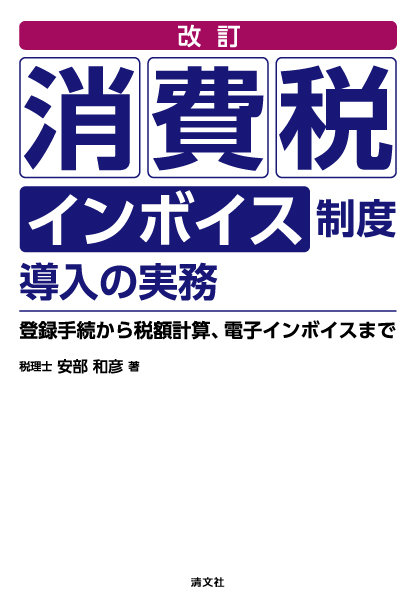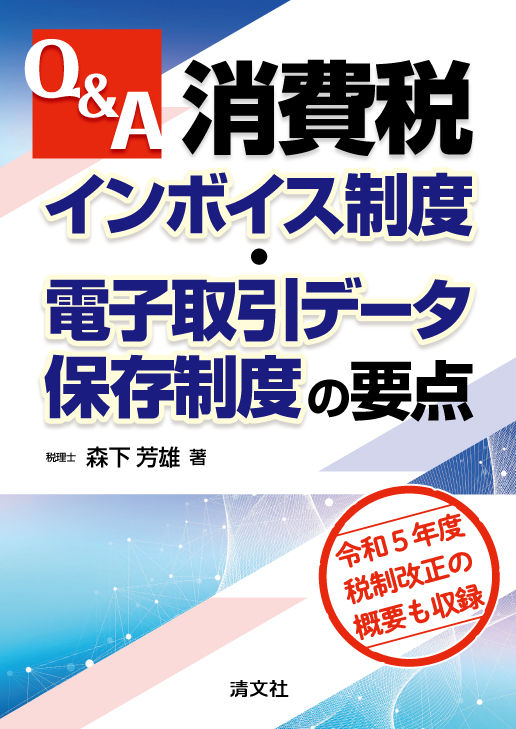消費税の軽減税率を検証する
【第1回】
「軽減税率の検討に至る経緯」
税理士 金井 恵美子
Ⅰ 消費税軽減税率制度検討委員会の設置
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」(以下「税制抜本改革法」という。)7条1号は、消費税率の引上げにより負担が増す低所得者に配慮する観点から、次の2つの施策について、様々な角度から総合的に検討するものとした。
(イ) 総合合算制度、給付付き税額控除等の施策の導入
(ロ) 複数税率の導入
「(イ)総合合算制度、給付付き税額控除等の施策の導入」は、税制抜本改革法成立当時の与党であった民主党が当初法案に掲げた施策であり、「(ロ)複数税率の導入」は、平成24年6月15日の民主党、自由民主党、公明の3党合意により加えられたものである。
両者は並列に扱われているが、法律制定後、平成24年12月の衆院選において3年余りの民主党政権は終了し、自由民主党、公明党が再び与党となって、具体的な検討が進められているのは、単一税率制度から複数税率制度への移行である。
すなわち、平成25年度与党大綱(※1)においては、「消費税率の10%引き上げ時に、軽減税率制度を導入することをめざす。」とされ、翌年の平成26年度与党大綱(※2)には、
消費税の軽減税率制度については、『社会保障と税の一体改革』の原点に立って必要な財源を確保しつつ、関係事業者を含む国民の理解を得た上で、税率10%時に導入する。
(※1) 平成25年度税制改正にあたっては、自由民主党と公明党が平成25年1月24日に公表した「平成25年度税制改正大綱」(平成25年度与党大綱)と平成25年1月29日に閣議決定された「平成25年度税制改正の大綱」とがある。平成25年度与党大綱は、「第一 平成25年度税制改正の基本的考え方」、「第二 平成25年度税制改正の具体的内容」、「第三 検討事項」からなり、このうち、「第二 平成25年度税制改正の具体的内容」の部分が「平成25年度税制改正の大綱」として閣議決定された。軽減税率に関する記述は、平成25年度与党大綱の「第一 平成25年度税制改正の基本的考え方」に見られる。平成26年度改正、平成27年度改正においても同様である。
(※2) 「平成26年度税制改正大綱」(自由民主党、公明党、平成25年12月12日)。
これを受け、与党税制協議会は、広く国民の意見を聞きながら検討していくための資料として、平成26年6月5日、「消費税の軽減税率に関する検討について」(以下「検討資料」という)を示した。
直近の平成27年度与党大綱(※3)においても、
消費税の軽減税率制度については、関係事業者を含む国民の理解を得た上で、税率10%時に導入する。平成29年度からの導入を目指して、対象品目、区分経理、安定財源等について、早急に具体的な検討を進める。
(※3) 「平成27年度税制改正大綱」(自由民主党、公明党、平成26年12月30日)。
Ⅱ 軽減税率と複数税率
読者は、上記において、税制抜本改革法で「複数税率」と呼んだものが、平成25年度与党大綱以後、「軽減税率制度」と呼び直されていることに気がつかれただろうか。
現状、割増税率を設定することは検討されていないので、「軽減税率制度」と呼んだ方が制度の内容をよりわかりやすく表現することになるのかもしれない。しかし、筆者は、「単一税率制度」に対する「複数税率制度」、「標準税率」(又は「普通税率」)に対する「軽減税率」という語を使用するべきではないかと考えている。
それは、「軽減税率制度」には、「日常生活への配慮」とか、「消費生活に優しい」とか、「経済的弱者への思いやり」とか、そういったイメージを連想させる心地良い語感があると感じられるからである。
消費税制度を大きく変える複数税率への移行は、税制全体における消費税の役割とこれまでの税制調査会での議論、複数税率を採用する国々の実態を踏まえ、制度構築上及び執行上の問題と消費者及び事業者が受ける影響等について、慎重かつ充分な議論を行ったうえで判断しなければならない。
意図したかどうかは別として、「複数税率」から「軽減税率」への言い換えが、制度に対する人々の期待感を煽り、その効果や影響についての冷静な議論の妨げになっているのではないかと考えられる。
Ⅲ 物品税から消費税へ
「検討資料」は、税率引上げ時の「痛税感を和らげる観点」から、軽減税率の適用範囲を検討するべきとしている。消費税は、もともと痛税感が大きい。それは為政者にとって決して好ましい特徴ではない。にもかかわらず、この税が導入された理由を考えてみよう。
消費税前の物品税は、いわゆる贅沢品に重く課税することにより間接税に累進課税の要素を求めるものであった。しかし、国民の消費態様の大きくかつ急激な変化に即応して的確に課税対象を選択しそれぞれに適切な税率を設定するということができず、税制の公平性、中立性の観点から問題が指摘されていた。
そこで、水平的公平を確保する観点から、すべての消費に広く薄く負担を求める一般消費税制度への転換が求められた。また、低い税率で多くの税収を確保する税収ポテンシャルの大きさが、個別消費税制度から一般消費税制度へ移行する力の源であったといえる。
税制改革法は、消費税創設の趣旨を
現行の個別間接税制度が直面している諸問題を根本的に解決し、税体系全体を通ずる税負担の公平を図るとともに、国民福祉の充実等に必要な歳入構造の安定化に資するため、消費に広く薄く負担を求める消費税を創設する。
としている(税制改革法10)。
Ⅳ 消費税による公平性の確保
(1) 水平的公平
消費税は、原則としてすべての消費を課税の対象としており、すべての課税取引に一律の税率を適用する単一税率である。
納税義務者である事業者や税の負担を予定する消費者の個別の事情には関係なく、すべての財とサービスに課税することを基本としており、したがって、制度は簡素であり、税務行政側と納税義務者側との両面でコストが少ないと評価される。
また、商品の価格が同一であれば同一の負担額となるので、商品やサービスの価格に中立であり、消費に対する選択にバイアスを生じさせる要因とならない。
(2) 世代間の公平
消費税は、「世代間の公平に優れた税」であると評価されている。
社会保障・税一体改革において消費税率の引上げを税制面における改革の柱に据える理由は、
今後、少子高齢化により、現役世代が急なスピードで減っていく一方で、高齢者は増えていくため、現役世代など特定の者に負担が集中せず、若者から高齢者まで国民全体で広く負担する消費税が、高齢化社会における社会保障の財源にふさわしいと考えられます。
と説明されている(『明日の安心 社会保障と税の一体改革を考える』(内閣官房、平成24年)17頁)。
ただし、世代間の不公平を是正するためには、税制のみならず、公的年金制度をいかにデザインするかという点が重要であろう。少子高齢化の中で、社会保険料の負担は、若い世代ほど大きく、世代間の受益と負担の収支の差は歴然としている。若者を搾取している、とまで表現されるこの状況に物価スライド制が拍車をかけている。
消費税率の引上げによる物価上昇は物価スライドに反映され、年金受給者の消費税率引上げによる負担増は、他に比べて相当程度減殺される。現行の物価スライド制においては、消費税の税率を引き上げることによって世代間の不公平を是正することは難しい。
(3) 消費税の逆進性
消費税には逆進性の批判がある。これについて、消費税創設当時の答申は、
税制の所得再分配機能は、一つの税目のみを取り上げて議論すべきものではなく、税制全体をみて論じられるべき性質のものであり、また、社会保障制度等の施策が国民生活の様々な分野で整備されてきている今日においては、所得再分配機能は財政全体で判断すべきもの
平成2年の東京地裁判決も、消費税の逆進性は憲法14条の平等原則に違反するという納税者の訴えに対し、所得の再分配等による実質的平等実現のための政策は、税制全体、ひいては、各種社会保障等をも含めた総合的な施策によって実現されるべきものであるとして(※4)、答申の考え方を首肯した。
(※4) 東京地判平2・3・26税資176-194。
また、所得税は垂直的公平の要請によく応えるが、暦年課税であるため、長期間安定的に所得を獲得する場合と、一時期に集中して所得を獲得する場合とでは、生涯の所得が同じであってもその税負担に差異が生じる。比例税にはこれを緩和する効果があると評価することもできる。
(4) 消費税の役割
消費税には、すべての消費に均一に課税するという性質によって暦年による累進課税を行う所得税の弱点を補い、税制全体の中で水平的公平、中立、簡素の要請に応えつつ多くの税収を確保するという機能を発揮することが期待される。
むしろ、累進的でないという特徴をもつ租税であるからこそ、その存在に意味があり、その役割を果たすことができると考えられる。
(了)
「消費税の軽減税率を検証する」は、隔週で掲載されます。