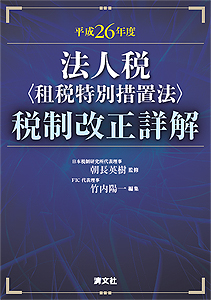〔理解を深める〕
研究開発税制のポイント整理
【第2回】
「各制度の計算方法を整理する」
税理士法人山田&パートナーズ
税理士 吉澤 大輔
1 はじめに
第1回は、研究開発税制の制度内容を制度の沿革と照らし合わせながら整理し、現行制度の概要を解説した。
第2回では、研究開発税制の具体的な計算方法を解説する。
2 研究開発税制の各制度の計算方法
前回述べたように、研究開発税制の適用事業年度における法人税額から控除する税額控除額は、「本体部分」と「上乗せ部分」のそれぞれの税額控除額の合計額である。
そこで、研究開発税制の各制度の計算方法を「本体部分」と「上乗せ部分」に分けて解説していく。
(1) 本体部分
① 試験研究費の総額に係る税額控除制度
【内容】
青色申告書を提出する法人(人格のない社団等を含む。以下、本稿において同じ)の各事業年度(解散(合併による解散を含む)の日を含む事業年度及び清算事業年度を除く)において、その事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額※1がある場合には、その事業年度の法人税額から次の金額を控除することができる。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。